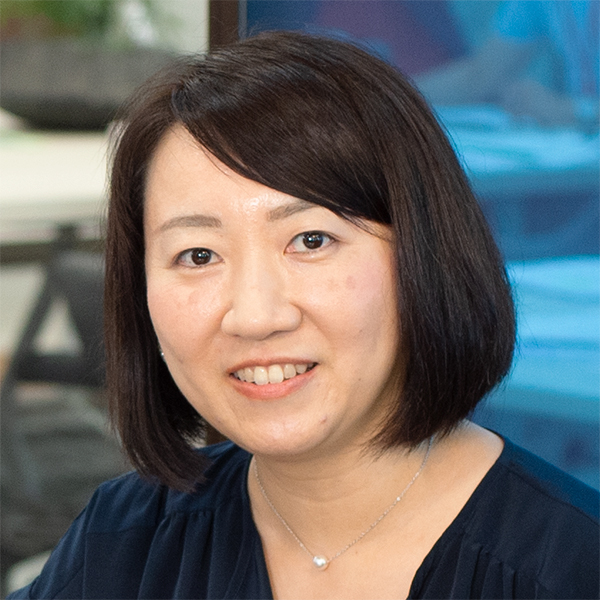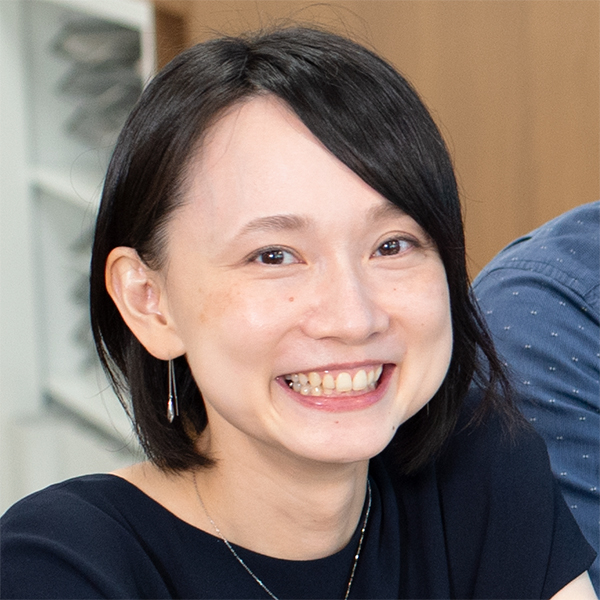オフィスは不要になるのか。ニューノーマルを「働く環境」のプロが語る

オフィス家具メーカーにとどまらず、人が集まる場に新しい価値を創るトータルソリューション企業への変革を進める、株式会社オカムラ。コロナ禍によるリモートワークの浸透によって、働き方や働く環境の変化が問われている今、同社はどんなことを思索しているのでしょうか。
これからの働き方の提唱や、社内の働き方改革プロジェクトなどを指揮する同社の大野嘉人氏(以下、大野氏)をはじめ、森田舞氏(以下、森田氏)、薄良子氏(以下、薄氏)、多田亮彦氏(以下、多田氏)の4名に、これからのオフィスの在り方、働き方に必要な考え方についてお話を伺いました。

オカムラが「働き方」を考える理由
大野氏:1980年代からオフィス研究所で働き方の研究を行ってきた弊社は、日本のオフィス家具トップメーカーとしてよりよい働き方を追求するため、海外の働き方なども調査し、さまざまな提言をしてきました。2011年の東日本大震災を経て、働き方改革の意識が強まり、2015年ごろからWORK MILL(ワークミル)として本格的に活動しています。
WORK MILL(ワークミル)というのは組織や部門の名称ではなく、活動の名前です。働き方について企業だけが考えるのではなく、働き手である社員が個人としてこれからの理想的な働き方を描く。そしてありたい姿を目指すために、「働き方」「働く環境」「生き方」について共に考える活動をしています。
大野氏:WORK MILL(ワークミル)のウェブサイトや一般のビジネス誌を通じて、「働き方」「働く環境」「生き方」に関する情報発信をしています。また、東京、名古屋、大阪、福岡にWORK MILL(ワークミル)のための共創空間を設けて、ゲストを招いた登壇イベントなどを展開しています。そのほかには共創プロジェクトという他社との共同案件もあります。例えば、スノーピーク社と「アウトドア」と「オフィス」を融合させた働き方として、アウトドアオフィスキャンプを企画しました。働き方に関する研究も進めており、オカムラにおける働き方改革の中核となる活動をしています。
森田氏:この数カ月で、多くの企業がリモートワークを取り入れました。初めてリモートワークをする人たちは、まず自宅で仕事をする環境を整える必要がありました。自宅の食卓にあるテーブルや椅子は、オフィスのように長時間仕事をするために設計されたものではありません。そのため、仕事の効率が落ちたり、体に痛みが出たりした人もいました。
そこで、リモートワーク用の家具が注目されるようになり、弊社サイトへのアクセスやeコマースサイトを通じてオフィス家具を購入される方が増えました。在宅で長時間仕事をするには、オフィスに近い環境で仕事ができるほうがよいと判断された結果ではないでしょうか。

多田氏:クライアント企業の中には、社員が健康的にリモートワークできるように自宅の環境改善をサポートする企業もいらっしゃいます。社員の方々がオフィスで使用している椅子を自宅用に購入するのに、費用の一部を会社が負担するといった支援をされています。今後、リモートワークをする人々が多い状況が長期化する場合、同じようにリモートワーク用の家具を福利厚生の一端として提供する企業も増えることが予想されます。
これからのオフィスには効率と「新しい」安全性が求められる
大野氏:これまでのオフィスは、いかに効率を上げるかが重視されてきましたが、現在は効率と安心・安全を両立することが求められるようになりました。これまでオフィスの安全と言えば、地震による転倒防止や入退室管理などのセキュリティーの分野でした。これからはウイルスという目に見えない敵への対策になるので、発想を大きく変える必要があります。

大野氏:例えば、ソーシャルディスタンスをとるためにオフィスの人口密度を下げ、出社率50%を前提にするオフィス設計などが必要になっています。これには、ホテリングという1990年代に欧米で話題になったシステムが活用できます。ホテリングとは、簡単に言えば予約式のフリーアドレスです。社員数より座席数が少ないので、複数の社員で1つの座席を共有します。レイアウト図を共有し、自分が希望するワークポイント(仕事をするための座席)がどこにあるかをシステム上でも把握できますし、予約制なのでいつ誰がどこを何時間使ったかが記録されます。万が一、感染者が出たとしても、行動履歴を追跡できますので、迅速な対応が可能です。
森田氏:座席を減らして距離を保つのは基本です。座る向きを変えたり、可動式のオフィス家具を増やしたりします。飛沫感染は、デスクトップパネルやスタンドパネル、ヘッドパネルなどで防止します。オフィス内の社員の動きを位置情報検知システムなどで把握し、密を防ぐことも可能です。ほかにも接触を減らすために顔認証システムの導入や出入口の自動化、収納スペースの個人化、ペーパーレスなどの対策が考えられます。

これからの働き方に「オフィス」がもたらす効果とは
大野氏:リモートワークが定着し、オフィス以外の自宅やサードプレイスなどで行う作業と、オフィスでしか行えないことが徐々に明らかになってきました。個々人の状況や目的に合った最適な場所でそれにふさわしい仕事ができることを体験したからです。ただし、オンラインではなかなか難しいイノベーションやインフォーマルなコミュニケーションなど、オフィスでないと生まれないことも多くあります。今までと同じ機能のオフィスが必要かどうかという点は議論が必要ですが、オフィスが無くなることはないと考えています。働き方も働く場もニューノーマルになっていきますね。
薄氏:オフィスを完全に無くす議論よりも、オフィスの規模を小さくするダウンサイジングの議論の方が多いのですが、単純に規模を小さくするダウンサイジングではなく、センターオフィスの機能を再定義し適切に配置した上で、適正なコストのオフィスを考えるライトサイジングをするべきです。結果的にオフィスの面積が小さくなる場合もありますが、社員数を基準にオフィスの広さを考えるのではなく、企業ごとにふさわしいサイズのオフィスを実現すべきだと考えています。
森田氏:オフィスのライトサイジングを進めるときには、オフィス以外で働くなど、働く場が分散するという考え方は欠かせません。これまでほとんどの企業はオフィスに機能を集約していました。集まっていたからこそのメリットは維持しつつ、離れていても成果を上げられるようにしていく必要があります。
薄氏:センターオフィスが小さくなっても、その分、サードプレイスの活用が増えることもあるでしょう。ニューノーマルでどんなオフィスを構築するかに関して、今まで以上に企業のニーズと要望は多岐にわたっています。

森田氏:オカムラでは、ニューノーマルの働き方を考えるときには、特に「自律性」「感情」「共通概念」の3つが重要になると考えています。働き方や働く場を柔軟にして自律的に働くことはもちろんですが、人とのつながりや感情、組織文化の醸成など、リアルなつながりも忘れてはいけません。こういった視点のもとで、オフィスの機能は再構成されるのではないでしょうか。
多田氏:リモートワークを含む柔軟な働き方に慣れている弊社の社員でも、同僚と実際に会って会話できることに喜びや安心を感じる人も多くいるようです。同僚を手伝えている、あるいは顧客が喜んでくれているなど、リアルなコミュニケーションを通して得られるリッチな情報とそれによって引き起こされる共感は、オンラインで得るのは難しいかもしれません。この「共感」は、働く人にとって大きなモチベーションであると考えられます。分業が進み、集まらなくても作業ができる時代に、実際に会って一緒に働くことの価値をいかに最大化できるかを、これまで以上に突き詰めて考えることが必要になると思います。
薄氏:弊社ではワークミルのほかに、「Work in Life Labo.」という研究会を2016年より産学協同で実施しています。オカムラが提唱している「Work in Life」という考え方のもと、関連したテーマを調査・分析・発信しているプロジェクトです。

Work in Life とは、「ワーク」と「ライフ」という2つの要素を同列にとらえるのではなく、「ライフ(人生)にはさまざまな要素があり、その中の一つとしてワーク(仕事)がある」という考え方のことです。ライフを構成する要素としてはワークのほかにファミリー(家族)、ホビー(趣味)、ラーニング(学び)、コミュニティ(組織・地域)などがあります。
大野氏:弊社の場合、コロナ禍以前より、この考え方をもとに「自分らしい生き方を想像し、自分らしい働き方を考え、その上で自分のライフを歩んでいく」、それを社員一人一人が実現することを目指してきました。それをサポートする目的で、働き方改革の取り組みとして「WiL-BE(ウィル・ビー)」を進めています。
薄氏:WiL-BEでは、社員一人一人がWork in Lifeを実現できる組織になるため、オカムラが提唱する働き方改革の3+1の要素(運用・制度、ICT・ツール、場・環境+ひと)にひもづけ、大きく4つのアクションで活動を推進しています。また、それぞれの要素で中心となって推進する部門を設定し、社長をリーダーとして、労働組合とも連携しながら進めています。
多田氏:弊社を含めた多くの企業で、コロナ禍でリモートワークが浸透しましたが、今後は仕事の内容・目的に合わせたさまざまな働き方が出てくるでしょう。オフィス、シェアオフィス、自宅、カフェなど働く場所もさまざまです。そこで使う家具だけでなく、どんな環境を実現し、どんな働き方をすべきか、社員自身が実践してお客さまにご提案できるよう、この活動を続けていきます。

取材後記
政府がいくら声を上げてもなかなか進まなかった働き方改革が、コロナ禍によって一気に進みました。 働き方が変われば働く環境も変わります。オフィス家具だけでなく働き方そのものまでも提言するオカムラ。リモート化によってオフィスの縮小化が注目されていますが、大事なことは「ライトサイジング(適正化)」だと言います。これからの世の中でビジネスを続けるために、オフィス機能を再構成しようと考えている企業にとって、これらのノウハウは参考になるのではないでしょうか。
取材・文/柴田雄大、編集/d’s JOURNAL編集部