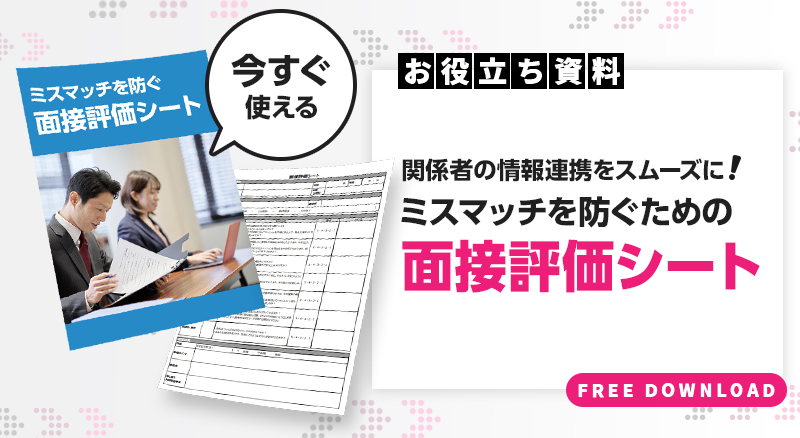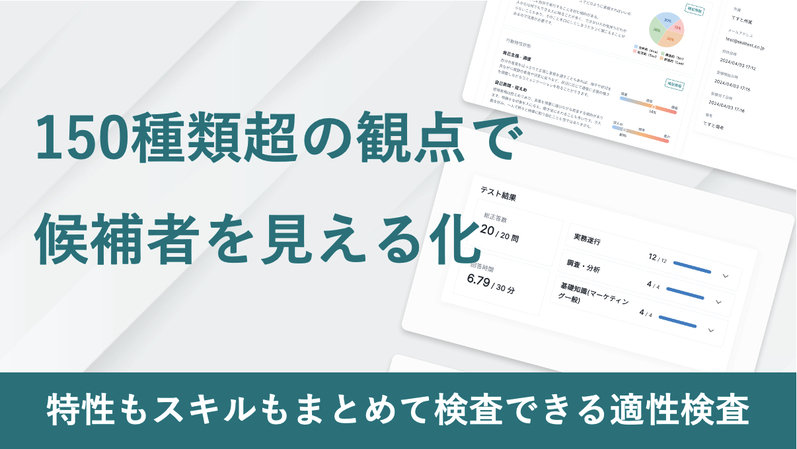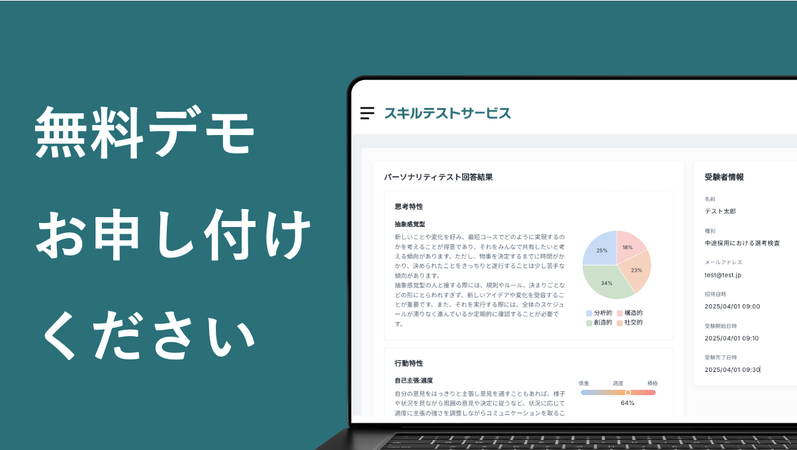「面接では良さそうに思えたのに…」採用ミスマッチを招く“3つの罠”と見極め術
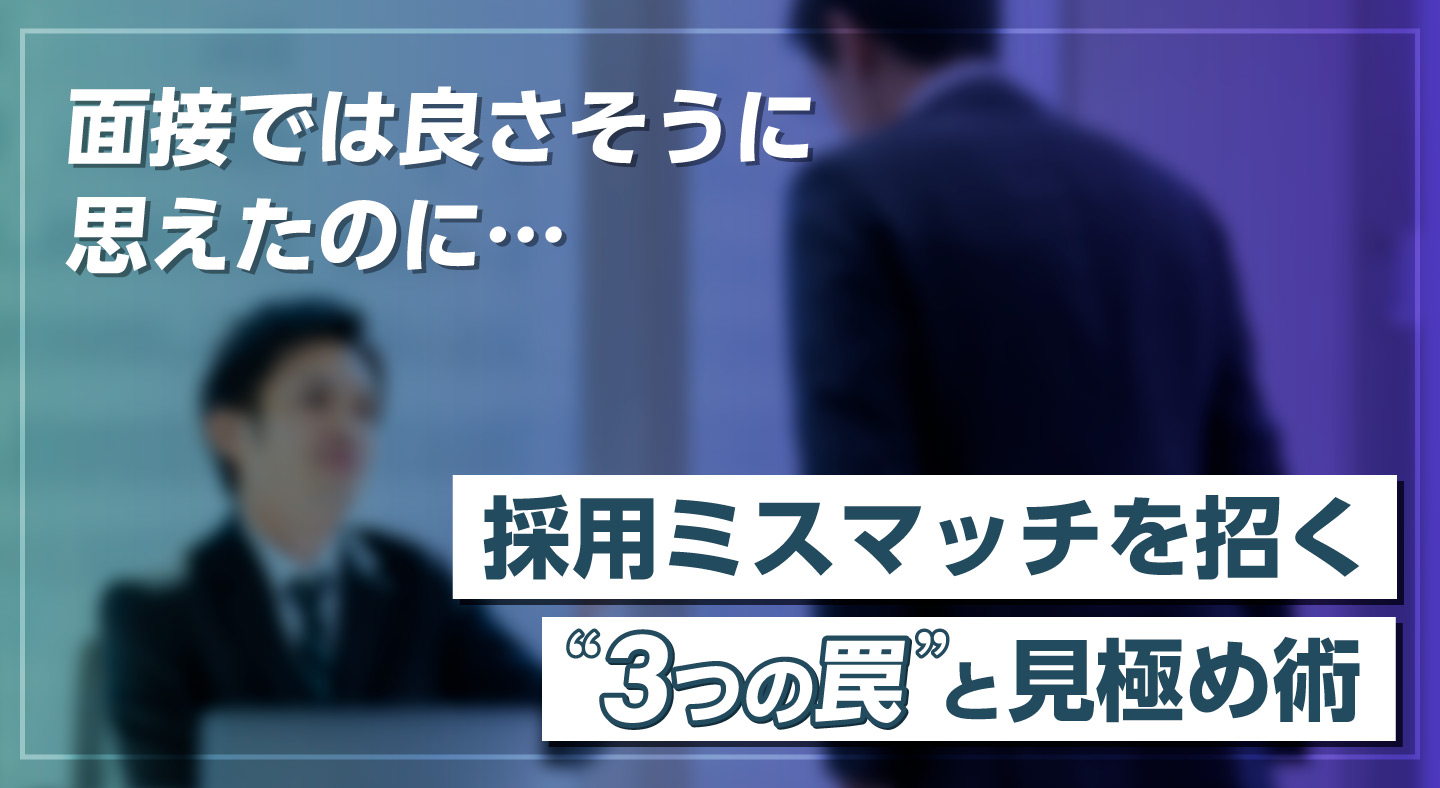

新規サービス開発本部 スキルテストサービス リードディレクター 梶岡俊樹
-
採用ミスマッチの構造的な3つの原因は「主観バイアス」「期待の罠」「認識の遅れ」
-
採用プロセスにおける問題点3つは「伝達不足による応募者のアピールのズレ」「応募者の実績やスキルの深掘り不足」「実務を想定した質問・やり取りの不足」
-
採用ミスマッチを防ぐ対応策「人材要件定義の明確化」「パーソナリティテストの活用」「スキルテストの実施」
選考を行う中で、「書類や面接だけで応募者を見極めるのは難しい」「結果判断に迷ってしまう」といった悩みを抱えることはありませんか?面接では良さそうに思えたのに、入社・配属後には活躍してもらえなかった…。そんな現実に直面することもあります。
こうしたミスマッチが発生してしまうのは、面接の“判断ミス”ではなく、選考プロセスの中にある“構造的なすれ違い”が原因かもしれません。
本記事では、採用ミスマッチの原因と対策、そして今注目される「判断の裏付け」手法まで、事例とともに解説します。
採用ミスマッチによる悪影響
採用ミスマッチが発生すると、組織にはさまざまな悪影響がもたらされます。
・チームのパフォーマンスが低下する
採用した人材が思うように業務をこなせず、周囲のメンバーがフォローに追われ、全体の生産性が徐々に下がってしまう。
・早期離職が増え、採用にかけた費用が無駄になる
採用しても「思っていた仕事と違う」と言われてすぐに辞めてしまう。採用費用やトレーニング費用、費やした時間が無駄になる。
・組織全体が停滞し、競争力を失う
人材の入れ替えが激しく、安定的な成長が難しくなる。戦略を実行する力が弱まり、市場内で後れを取る。
こうした悪影響を回避するためには、採用ミスマッチを起こさない仕組みづくりが重要なのです。
採用ミスマッチは、なぜ繰り返されるのか──構造的な3つの原因
人事・採用担当者の多くは応募者の業務スキルの見極めに課題を感じています。なぜミスマッチが起きてしまうのか。構造的な3つの原因から解説します。

原因①:主観バイアス──印象・相性・“なんとなく”
採用プロセスにおいて、面接官や人事・採用担当者の「直感」や「感覚」が応募者評価に大きく影響を与えることがあります。特に、経験が浅い面接官や、ミスマッチの経験が少ない面接官は、主観に引っ張られてしまう可能性があります。
<よくあるケース>
第一印象で「話しやすい」「自分と似ている」と感じた応募者を、好印象という理由だけで採用。応募者のスキルやパーソナリティを十分に評価できず、結果的に現場でのギャップが発生してしまいます。
<なぜ起きてしまうか>
第一印象で応募者の見た目や態度、最初の受け答えが良いと、全体的に「良い」と判断しがちな「ハロー効果」と呼ばれる現象があります。また、自分に似た価値観や経験を持つ人に対して好感を抱き、スキルやパーソナリティを過大評価する「類似性バイアス」が影響している可能性もあります。
面接そのものが構造化されていない場合は、面接官ごとに質問内容が異なり、評価基準も統一されていないケースがあります。これにより面接官の主観が大きく影響してしまうのです。
原因②:「期待」の罠──企業側の期待が事実をぼかす
採用活動を進める中で、「面接では最適な人材だと感じたのに、実際に入社してみたら期待していた活躍ができなかった」と感じたことはありませんか?この現象は、単なる評価ミスではなく、企業側の「期待」が採用の判断をあいまいにしてしまうことで発生することが多いのです。
<よくあるケース>
営業職のケースを紹介します。「前職で営業成績No.1のトップセールス」という実績を評価し、即戦力として採用したケースです。応募者は面接でも具体的な売上実績をアピールし、企業側も高い成果を期待していました。
しかし、前職では高いブランド力があり、顧客リストが整った環境での営業だったため、ゼロから新規開拓するスキルや経験が不足しており、入社後は思うように成果を出せませんでした。結果、期待と現実のギャップが生まれ、本人のモチベーション低下や早期離職につながってしまいました。
<なぜ起きてしまうか>
これは事実確認の不足が主な原因です。応募者の業務スキルを見極めるための事実確認が不足すると、入社後に期待する成果とのギャップが顕在化し、本人やチームに多大な負担をかけることになります。
原因③:認識の遅れ──ミスマッチと気付けない構造
応募者と企業の間でスキルの認識や価値観のズレがあっても、すぐには表面化せず、問題が見えにくくなってしまうことがあります。特に周囲のチームメンバーがフォローしやすい環境では、このようなミスマッチが潜伏しやすく、明確な問題として認識されるまでに時間がかかる傾向があります。
<よくあるケース>
新しく採用した営業担当者に本来は新規開拓のスキルを求めていたとします。しかし入社当初は一時的に既存顧客のフォロー業務が多い状況でした。こうした場合は、本来求めているスキルが不足していても、しばらくは問題なく業務を遂行できてしまうケースがあるのです。
<なぜ起きてしまうか>
原因は、こうしたミスマッチを「採用に起因する問題」として認識できないことです。たとえば、入社半年ほどして本来求めていたスキルが不足していたことに気付いた場合、ミスマッチを採用時の問題と認識できず、「部門の受け入れによる問題」と捉えてしまい、採用プロセスの見直しまでに時間を要してしまうことが少なくありません。
採用プロセスにおける問題点とは
上記でご紹介した原因は、部門側の受け入れに問題があるわけでも応募者によるものでもなく、採用プロセスに起因すると考えて対策を打つべきです。
具体的な問題点や解決の方向性を見ていきましょう。

・問題点1:企業の伝達不足が招く、応募者のアピールのズレ
企業が求めるスキルや成果を明確に伝えないと、応募者は「どのポイントを強調すればよいのか」がわからず、結果として、企業が本当に評価すべきスキルが適切にアピールされないまま選考が進んでしまいます。
・問題点2:応募者の実績やスキルの深掘り不足
面接で「この人は経験豊富だな」と感じても、その経験が「どんな環境で」「どのように発揮されたものなのか」を確認しないと、企業が求めるスキルとの適合性を正しく判断できません。「前職での営業手法はどのようなものでしたか?」「具体的には、どんな課題を抱える顧客に、どのようにアプローチしていましたか?」といった質問を行うことで、スキルの実態をより詳しく把握することができます。
・問題点3:実務を想定した質問、やり取りの不足
面接では過去の実績を中心に話を聞くことが多いと思います。しかしこれだけでは、実際に自社の業務にフィットするかどうかはわかりません。たとえば営業職であれば、実際の商談を想定したロールプレイを行う。エンジニアであれば、コーディング課題を出して実力を測る。このように実務に近い形でやり取りを行うことで、応募者のスキルをより正確に評価することができます。
ミスマッチを防ぐための具体的な対応策
ここまで見てきたように、採用において最も重要なのは、 企業が求める人材要件と応募者のスキルやパーソナリティが適切にマッチしていることです。この認識にズレがあると、入社後に「思っていた仕事と違う」「スキルが合わない」などのミスマッチが発生してしまいます。
とは言え、応募者を見極めるのは非常に難しいのも事実。書類や面接だけでは、どうしても主観的な評価が入りがちです。そのため昨今では、スキルやパーソナリティを客観的に可視化する仕組みを取り入れる企業が増えています。
スキルやパーソナリティの可視化には、いくつかの方法があります。
・面接官のトレーニングを強化する(構造化面接など)
・実務テストを導入する(ワークサンプル・業務シミュレーション)
・適性検査やスキルテストを活用する
これらを組み合わせることで、応募者のスキルやパーソナリティをより正確に見極め、ミスマッチを未然に防ぐことができます。その中でも、すぐ取り組める効率的な手法のひとつが、パーソナリティテストとスキルテストの実施です。
まずは「人材要件定義の明確化」を
取り組みを進めるうえで前提となるのは「人材要件定義の明確化」です。
選考プロセスの中で面接を進める際には、担当する面接官によって評価基準が異なり、人材要件定義がブレたまま選考が行われてしまうこともあります。ある面接官は「第一印象が良い」と高評価をつけ、別の面接官は「スキルが足りない」と判断する。こうしたブレが発生してしまうのです。
この原因は、面接官の主観的な評価に頼りすぎていることにあります。応募者を客観的に評価するためには、構造化面接を導入し、
・評価基準の統一
・面接での質問の標準化
・必要なスキルや経験の明確化
といった準備を整えることが重要です。
パーソナリティテストで応募者の考え方を見極める
こうした準備を整えたうえで、パーソナリティテストやスキルテストを活用しましょう。
応募者が業務に求められるスキルを十分に備えていたとしても、自社のカルチャーや働き方に合わなければミスマッチが生じてしまいます。そこで活用されているのがパーソナリティテストです。
パーソナリティテストでは、応募者の価値観やストレス耐性、仕事へのスタンスなど可視化することができます。たとえば「慎重な判断を好むタイプなのか」「自由な環境で力を発揮しやすいタイプなのか」といった傾向を把握することで、より適切なマッチングが可能となります。
スキルテストで応募者の能力を見極める
さらに、スキルテストを行うことによって、人事・採用担当者だけでは判断しきれない能力を見極めたり、人事と現場の認識のズレを埋めたりすることも可能です。
ここまで見てきたように、応募者のスキルを見極めるには
・書類や面接だけではスキルの粒度がわからない
・人事・採用担当者側にスキルや経験がなく、良し悪しが判断できない
・人事と現場で目線が異なり、認識の齟齬(そご)が生じてしまう
といったさまざまな壁が存在します。
こうした壁を乗り越え、採用ミスマッチをなくしていくためには、面接官個人の成長に頼るだけではなく採用プロセスにおける仕組み化が重要です。
【こんな方法もおすすめ】
ミスマッチを防ぐために設計されているのが、「doda」が提供する適性検査「スキルテストサービス」です。150種類以上の豊富なスキルテンプレートを活用し、「パーソナリティ」や「ビジネス基礎能力」、「思考力」、「業務適性」、「専門スキル」などを見極めることができます。
編集後記
応募者のスキルを適切に見抜き、採用ミスマッチをなくしていくためには、面接官個人の成長に頼るだけではなく採用プロセスにおける仕組み化が重要です。その打ち手のひとつとして、「特性もスキルもまとめて可視化できる適性検査『スキルテストサービス』」の導入を検討してみてはいかがでしょうか。
企画・編集/森田大樹(d’s JOURNAL編集部)、野村英之(プレスラボ)、文/多田慎介
ミスマッチを防ぐための「面接評価」シートテンプレート【無料】
資料をダウンロード