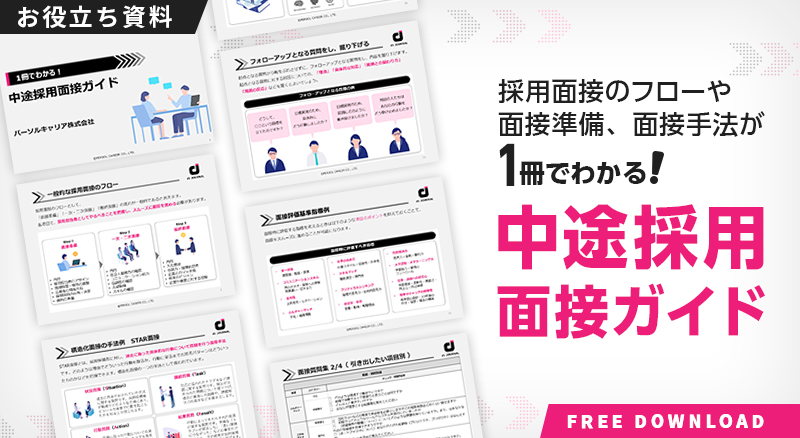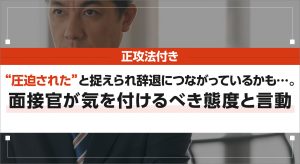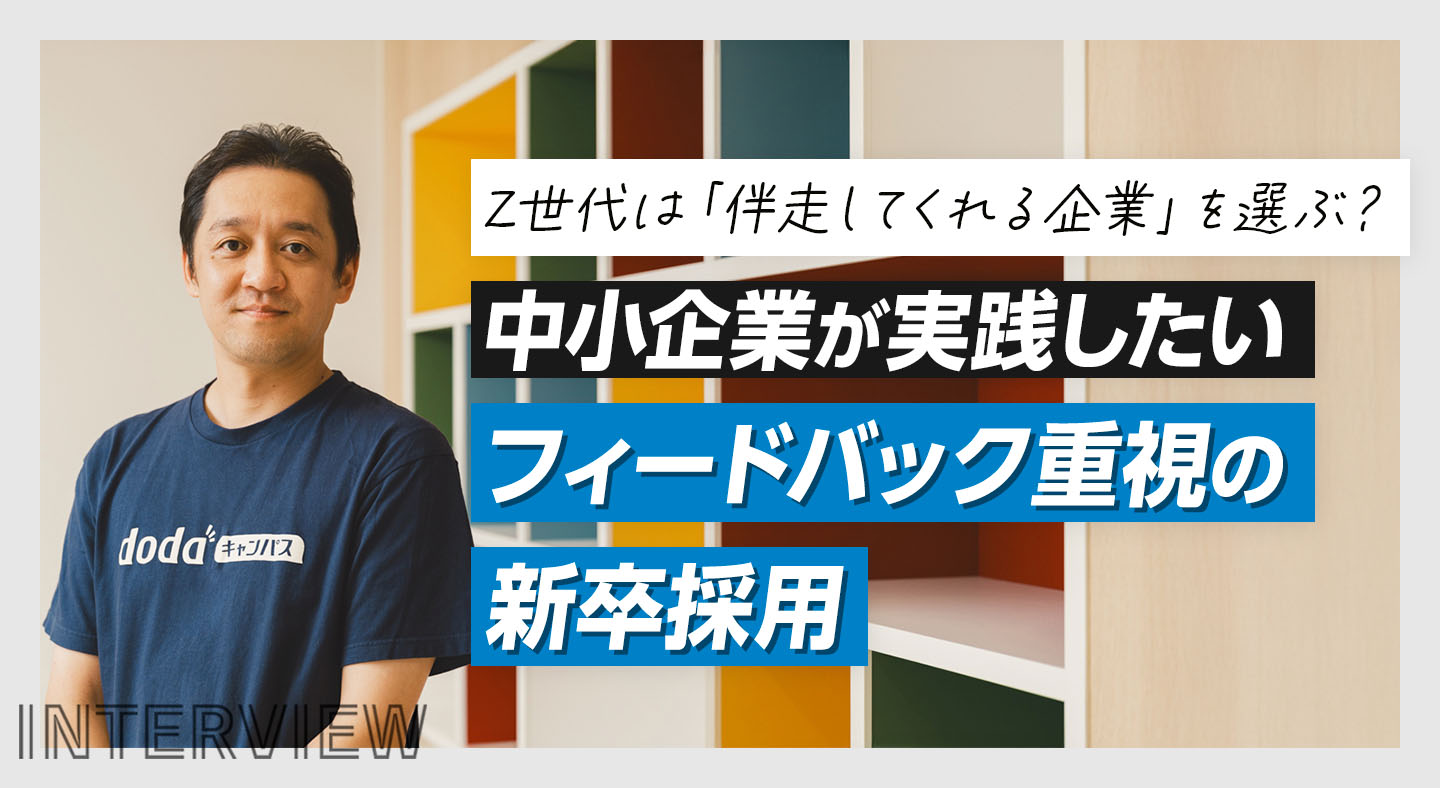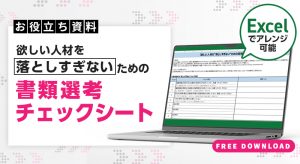表面的な情報に惑わされない!AI時代の職務経歴書の読み解き方
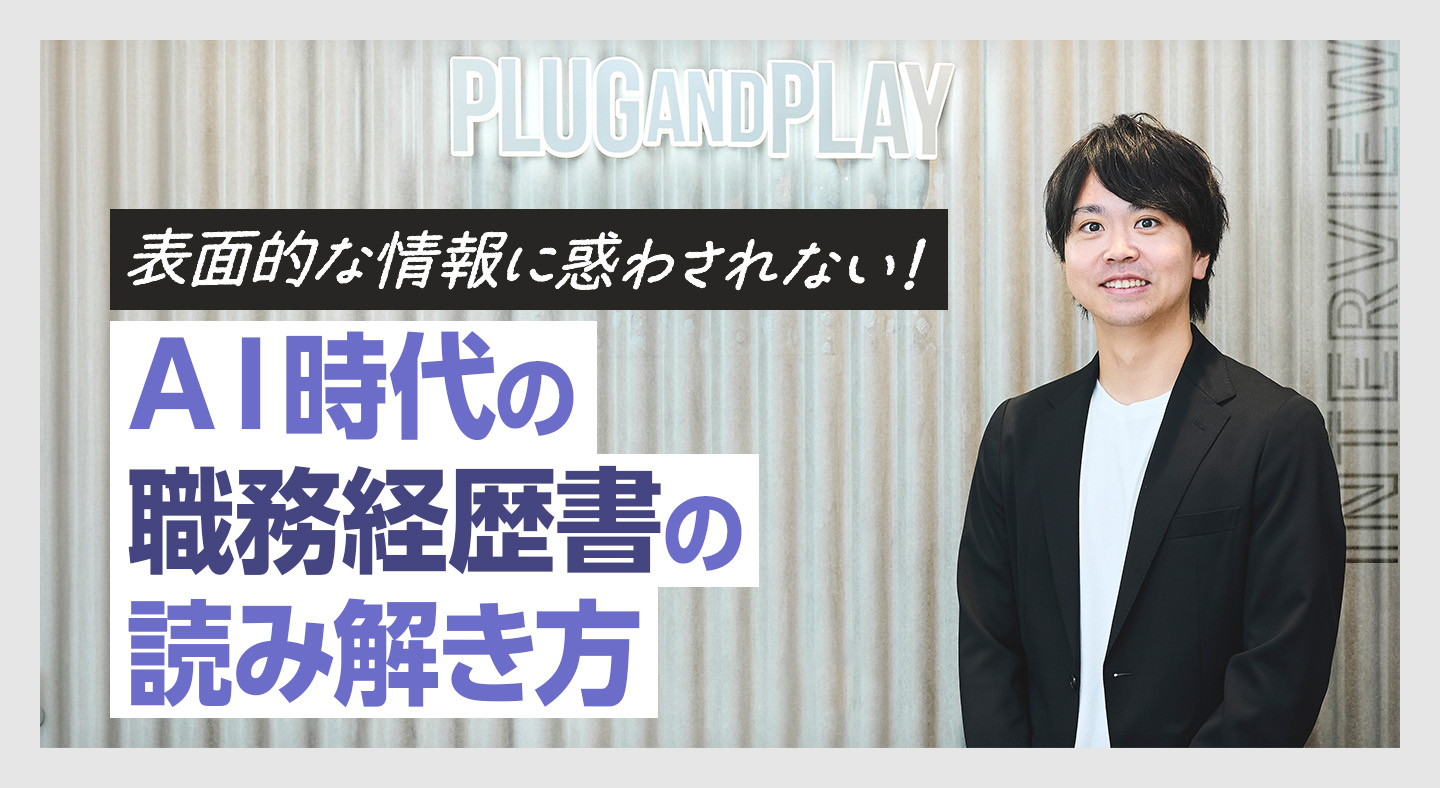
-
スクリーニングだけではない。書類選考は「仮説立ての材料」として、次の選考フローへの「重要な情報収集プロセス」
-
書類選考では数字や肩書をうのみにせず、「行間」を読むことが重要
-
判断に迷う転職希望者は極力書類選考を合格にして、スピードと候補者体験を重視することが採用成功につながる
職務経歴書の何を評価し、どう判断すべきか。自社に適した人材を見落とさないためには何をすべきか。多くの企業から「書類選考」についての悩みの声が聞かれます。さらに昨今では生成AIの普及によって、誰もが簡単に整った職務経歴書を作成できるようになりました。転職希望者の真の経験やスキルを見極める難度は確実に高まっていると言えるでしょう。
スタートアップから大手まで数多くの企業の採用支援に携わる佐伯叡一氏は、「書類選考を単なるスクリーニングにとどめず、面接で確認すべき点を設計する『情報収集のプロセス』として活かすことが重要」だと指摘します。AI時代に人事・採用担当者が取り組むべき、書類選考の実践ポイントを聞きました。
生成AIを活用した「職務経歴書」が当たり前の時代に
──現在の採用環境において、選考フローにおける「書類選考」の意義はどのように変化しているのでしょうか。
佐伯氏:生成AIの登場以前と以後で、書類選考の意義は大きく変わってきたと感じます。
かつては職務経歴書の内容は転職希望者によって大きくばらつきがあり、きれいに整った内容の職務経歴書を提出できる人はビジネスパーソンとして評価される傾向がありました。しかし現在では、生成AIを使うことで体裁そのものを簡単に整えられるようになっています。
生成AIによってきれいにまとめられた内容が本当かどうかを、書類だけで判断するのは難しいでしょう。書類選考は単なるスクリーニングとしてではなく、選考プロセスの次に向けた準備をするための重要なステップになったと感じます。

──中には、転職希望者が企業への提出書類作成にAIを活用すること自体、あまり評価したくないと感じている人事・採用担当者もいるかもしれません。
佐伯氏:気持ちはわかりますが、私自身は「職務経歴書を作るのにAIを使うなんて」と言っている時代ではないと思っています。
AIを活用すれば自分の経験を簡潔にまとめてくれますし、誤字脱字も整えてくれます。職務経歴書をうまくまとめるのが苦手な人でも自分の強みを伝えやすくなりました。それに、今は大学生もChatGPTなどの生成AIをフル活用する時代です。誰でも使えるツールを活用できていないほうが問題かもしれません。
文章自体はAIがまとめてくれていても、転職希望者にはそれぞれ独自の背景があるはずです。きれいな言葉でまとめられている経験やスキルについて、自分の言葉で語れるか、自分で思考できているかを人事・採用担当者は見るべきでしょう。企業側は転職希望者の書類を「仮説立ての材料」として、事実確認の入り口に過ぎないのだという前提で接するべきだと思います。
表面的な数字や肩書きを鵜呑みにせず、「行間」を読む
──佐伯さんが接している企業では、書類選考についてどんな悩みを抱えていますか。
佐伯氏:よく聞くのは、転職希望者によって情報の粒度が異なり、数字や再現性が見えづらい職務経歴書が多いことです。「売上に貢献しました」と書かれていても、転職希望者本人がどれくらい貢献したのか、その数字を実現するのは何がどれくらい大変なのかがわからないケースが多いのです。
たとえば「1年間で10億円売りました」といった実績が書かれていたとします。そうした大きな数字をそのまま鵜呑みにせず、本当にその人のスキルで実現したものなのか、会社のブランドや仕組みに頼って実現したものではないかを確認することが大切です。
また、肩書きとスキルのギャップもあります。肩書きに「マネジャー」と書いてあっても、実は配下メンバーがいないプレイングマネジャー、といったケースもあり得ます。表面的な肩書きの情報だけでマネジメント能力を判断することはできません。
──良さそうに見える内容でも注意すべきことがあるのですね。
佐伯氏:逆のケースもあるんですよ。
たとえば、過去の実績の数字にインパクトがなくても、ゼロから仕組みづくりや改善を進めた経験がある人はどんな業界でも活躍できる可能性があります。また、複数の部門や領域にまたがってプロジェクトを回してきた転職希望者は、それぞれの領域で書ける内容が少なくても、職種を超えて力を発揮できるスキルを持っているかもしれません。
書類に書いてあることだけを鵜呑みにしたり、行間にある転職希望者の強みが見えない状態のままでジャッジしていったりすると、自社に向いている人材をどんどん落としてしまうことになりかねない。この点は要注意だと思います。

高い解像度で転職希望者を見ている「現場の知見」を活かす
──書類選考で重点的に見るべきポイントを教えてください。
佐伯氏:転職希望者の職務経歴の解像度を高められるように書類選考を活かすべきだと考えています。
たとえば営業職なら、過去に扱っていた商材の特徴や単価、新規顧客と既存顧客の割合などから、売る難易度を類推できるでしょう。エンジニア職であればフロントエンドだけでなくインフラ周りもできるか、どんな種類の技術を扱ってきたかなど、担当領域の幅広さを見る必要もあります。
書類選考では、クリエイティブ職などのポートフォリオを見る機会もあるでしょう。過去のプロジェクトにおいてどんな工夫をしたか、作品のどんなところに力を入れたかなどを判断したいところです。
──人事・採用担当者だけでは判断しきれない内容もありそうですね。
佐伯氏:そうですね。人事・採用担当者は経験を通じてこうした視点を身に付けていくべきだと思いますが、より高い解像度で転職希望者を見ることができる現場の力を借りることも大切だと思います。
現場は、より短期的な視点で転職希望者の専門性やスキルを見ているはず。そのポジションに必要な知識やスキルはもちろん、「この業界でこの成果がどれくらいすごいものなのか」など、人事・採用担当者だけでは判断しきれないポイントにも知見があるでしょう。採用担当者は自社の現場を理解するために努力し、現場の関係者から得られる貴重なフィードバックを書類選考に活かしていくべきです。
──書類選考に不慣れな採用担当者でも、効率的に書類を見られるようになるコツがあれば教えてください。
佐伯氏:どこまでを書類選考に求めるかは企業によって異なりますが、なくてはならない知識やスキルなどの「MUST要件」をそろえておくことが大切だと思います。
MUST要件を重視し、「貢献しました」「尽力しました」などの表現だけでなく、定量的な情報が伴っているかを見る。そうした最低限のポイントをチェックリスト化していけば、1枚のレジュメを1分程度でチェックできるようになるのではないでしょうか。
採用成功企業は、書類選考でも「候補者体験」を重視している
──採用がうまくいっている企業の書類選考には、どのような特徴がありますか。
佐伯氏:採用成功企業は書類選考のスピードを重視しています。スピードは、企業が採用活動にどれだけ本気で向き合っているかを示すわかりやすい指標です。「応募書類が届いてから24時間以内に転職希望者へ返信する」などのルールを定め、そのためにSlackなどのツールを使いこなして人事・採用担当者と現場が連動するなど、オペレーション周りの体制を整えている企業が多いですね。
また、「判断に迷う転職希望者は極力合格にする」という方針で書類選考を進めている企業も多いと感じます。私が接している採用成功企業の人事・採用担当者は、「100%要件に合っていなくても、60~70%だったら合格にしている」という人がほとんどです。
特に書類選考ノウハウが乏しい段階では、判断に迷う場合は悩まずに選考を通していくほうがいいかもしれません。特に、人材紹介サービスで母集団形成をしている場合に、書類選考の段階でどんどん落としていると、エージェント側ではどんな転職希望者が望ましいのかわからなくなり、紹介数が減ってしまう可能性があります。その意味でも、「判断に迷う転職希望者はまず面接で判断する」のが正解だと思います。
最近では「候補者体験」という言葉をよく聞くようになりました。書類選考でも候補者体験を重視する企業が増えています。転職希望者やエージェントへのフィードバックにも手間を惜しまず、見送りの場合でも理由をわかりやすく伝えている企業もあります。こうした企業はファンが増えますし、良い口コミにもつながっていくのです。

【取材後記】
今回の取材で印象に残ったのは、書類選考はスクリーニングだけではなく、次の選考フローへ進むための情報収集の機会でもあるという視点です。佐伯さんは「レジュメの内容を基に面接での想定質問を考え、転職希望者への理解を深めるきっかけにすることが大切」だと話していました。生成AIの活用が進み、レジュメの表面的な内容だけでは転職希望者を判断しきれなくなった時代。これをポジティブに候補者体験の向上へつなげていく姿勢こそが、採用成功企業の条件なのではないかと感じました。
企画・編集/森田大樹(d’s JOURNAL編集部)、岩田悠里(プレスラボ)、取材・文/多田慎介、撮影/中澤真央
欲しい人材を“落としすぎない”ための書類選考チェックシート
資料をダウンロード