県内企業に新たな観点を提供し、採用力を高める。石川県が展開する独自の採用支援とは
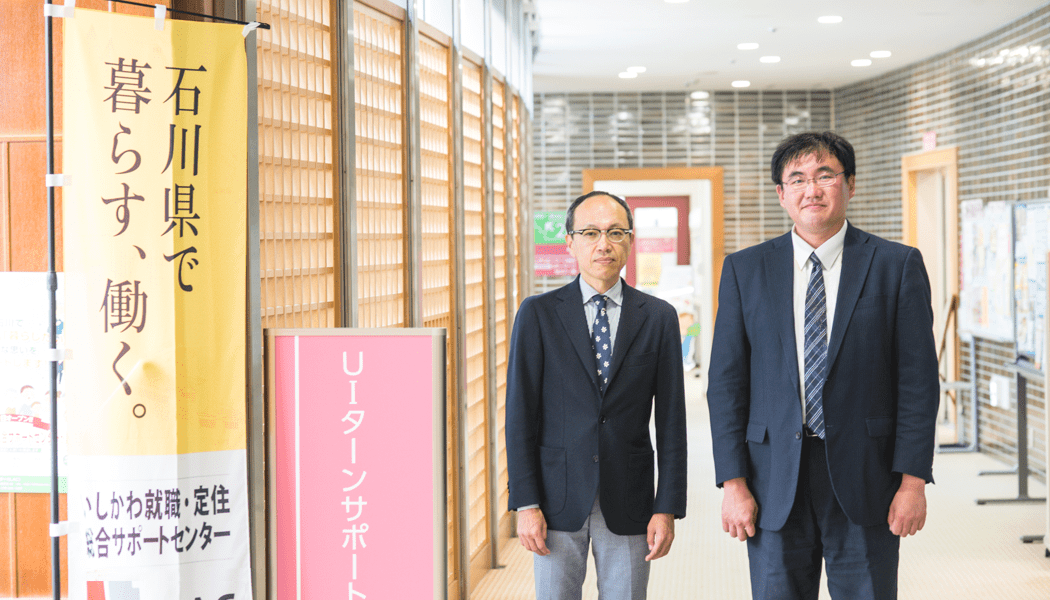
政府が進める「地方創生」の流れもあり、東京への一極集中や各地で加速度的に進んでいる人口減少への対策として、多くの地方自治体が自県への移住・定住やUIターンを促進する施策を打ち出しています。
そうした状況の中、石川県が人口の社会減少を食い止めるべく、移住・UIターン希望者をはじめとした、あらゆる人材と県内企業とのマッチングを一元的に行う組織として昨年4月に立ち上げたのが、いしかわ就職・定住総合サポートセンター、通称ILAC(アイラック)。今回は様々な側面から県内企業の人材確保をバックアップしているILACの高橋さんと矢部さんに、石川県とILACが行っている採用支援事例や県内企業の採用力強化に対する考え方についてお聞きしました。
「移住・UIターンはまず仕事から」というスタンスで企業の採用支援を推進
高橋:県内企業への採用支援については、ILAC設立以前より、「ジョブカフェ石川」を中心に、インターンシップの促進や合同企業説明会の開催などを通じて、主に新卒者をターゲットとして行っていました。
高橋:はい、国を挙げての地方創生という流れのなかで、石川県は2015年10月に「いしかわ創生総合戦略」を策定しました。この総合戦略の中に5つの基本目標があるのですが、そのひとつである「学生のUターン・県内就職と移住定住の促進」という目標を達成するための実行部隊として設立されたのがILACです。ILACはそれまでにあった「ジョブカフェ石川」や、ハローワークの窓口に加えて、移住・UIターンのための窓口等を加えた8つの窓口の総称であり、私と矢部を含む約90名の組織で活動しています。
高橋:他県の場合、移住・UIターンの取組は、人口減少対策として、県の政策を取りまとめる部局が担当することが一般的です。しかし石川県では「移住・UIターンはまず仕事から」という考えのもと、移住・UIターンの司令塔である「人材確保・定住政策推進室」が「商工労働部」の中に設置されています。ここが他県との決定的な違いですね。人口の社会減対策に取り組むとともに、県内企業の成長に資する人材を確保することが、ILACのミッションとなっています。

高橋:特徴的なものとして県内の企業向けに「いしかわ採強(さいきょう)道場」という道場形式のセミナーを開催しています。
高橋:県内の中小企業において採用や育成に携わる方を対象に、採用における実践的な力を身につけることを目的とした全5回のセミナーです。セミナーといっても採用ノウハウを提供するようなものではありません。ノウハウであれば、ネットを探せば出てきますからね。講師である千葉商科大学の常見陽平さんの言葉を借りるなら、「『わかる』だけでなく、『できる』ようになること、そして『やる』こと、『やりきる』こと」 を重視し、ひたすら「自社の魅力」と「求める人材像」を考えて、そして行動することに主眼をおいたセミナーです。
高橋:参加された皆さんが口を揃えて言われるのは、「これまでより優秀な人材にアプローチできるようになった」ということです。もちろん、優秀な人材になればなるほどライバル企業も増えるため、採用人数については一概に増えたとは言えないのですが、ある採用担当者は「業界屈指の有名企業からライバル視されるようになった」ということで、更に闘志を燃やしていると聞いています。それ以外にも、「採強道場」に参加した人事・採用担当者同士が自主的に集まって採用に関する勉強会が開かれるなど、総じて「採用活動」によって、会社が活性化していると感じています。
人口減少社会における採用に必要な観点とは
矢部:人口減少時代の今、学生や求職者に自分の会社のことを知って興味を持ってもらうためには、あらためて「自社は何者であるか」ということに、会社全体でしっかりと向き合うことが大切です。具体的には、会社の魅力、将来の方向性、求める人材像などといったことです。その過程で自分自身にいろんな発見や気づきが生まれます。そうして自社を腹落ちするくらい深く理解できたら、それを今度はどう相手に届く言葉で伝えていけばよいのかを考えます。良い会社だからと言って、そのまま「良い会社です」と伝えても相手に伝わりませんからね(笑)。
矢部:人口減少時代の人材採用には、非常にクリエイティブさが求められます。例えばハローワークの求人票は自社の「プレゼンテーションシート」といった捉え方です。石川県に限らず、多くの中小企業には「人事部」がなく、総務部の数ある業務の一つとして「人事・採用」を行っています。それではどうしても求人票作成一つとっても事務作業になってしまいます。

矢部:時代が加速度的に変化している中、人口減少で“永遠のテーマ”となった「人材採用」に対して、まずは長期的興味・関心を持ってもらうような考え方・観点を提供しています。特に経営者は人材採用に関しての知識を持っていないと思ったほうがよいと思います。なぜなら、社長自身は転職しないから(笑)。人口減少社会において、そしてインターネットであらゆる情報が入手できる社会においては、若者を中心として、ますます転職しやすい環境になり、求職者の立場が強くなっていきます。その中で経営者自身が求職者の気持ちを深く理解しなければ、選ばれる会社となるのは難しいと考えます。例えば求人票の仕事内容欄に「○○業務」とだけ。求職者は「もっとわかりやすく丁寧に教えてほしい」と壁を感じています。会社はごく当たり前に書いたつもりですが、それを気持ちが落ちている求職者からは脅威に感じるのかもしれません。このように、求人票は会社の化身として、求職者とコミュニケーションを図っているんですよ、といった観点など、どうしたら求職者が気持ちよく応募してもらえるかを検討してもらいます。
県内企業が採用に対して自ら考え、学んでいけるような支援を展開していく
高橋:もちろん、石川県においても、県外から移住される専門性をもった人材を採用した企業への補助制度や、理系大学院を修了し、県内ものづくり中小企業へ就職した方へ奨学金返還を助成する制度など、独自の補助制度が充実しています。しかし、「採用」が“永遠のテーマ”となった今、どのような状況になろうとも、自ら考え、行動しつづけられる採用担当者の育成、そしてそのようにしっかりと取り組む企業が、求職者と出会うための「場づくり」が重要だと考えています。
以前「いしかわ採強道場」に参加し、今年度、県の支援でdodaの転職フェアに出展した株式会社小松電業所の採用担当者からは、これまで会えなかったようなスキル・経験を持ったエンジニアと出会うことができ、採用にも成功したと聞いています。
矢部:doda転職フェアに関しても単純に出展を支援するだけでなく、事前研修にも参加してもらうようにしています。企業が、どのようなブースをつくり、どのように来場者にアピールするかはもちろん、来場者一人ひとりの欲求に応える形で応募につなげるようにアドバイスしています。

高橋:石川県の有効求人倍率は、全国3位という高水準で推移していることから、移住・UIターン者の採用はもちろんのこと、あらゆる人材の採用支援を行うこととしています。学生採用については、たとえば「年間を通じたインターンシップ支援」として、インターンシップで「仕事」をきっかけに知り合った企業担当者と学生が再び集まり、会社員の「暮らし」を知るための鍋パーティを開催するなど、企業と学生のより深い接点づくりを行うように工夫しています。また、本年9月からは、シニア人材や、再就職を希望される女性、外国人留学生などの潜在的な人材を掘り起こすとともに、企業に対してもマッチング交流会や「働きやすい職場づくり」をするための支援を行うなど、企業と求職者の双方へ支援を行うこととしています。また、内閣府が進めているプロフェッショナル人材事業(※)にも注力しており、実際、大手電子部品メーカーで工場マネジメントを行っていたプロフェッショナル人材を採用した石川樹脂工業株式会社など、成功事例もあります。
このように人手不足を、逆に多様な人材を採用する絶好の機会と捉え、多様な人材の採用が企業を成長させ、新たな産業や雇用が生み出される、そんな「いしかわ創生」を目指して引き続き取り組んでいきたいと思います。
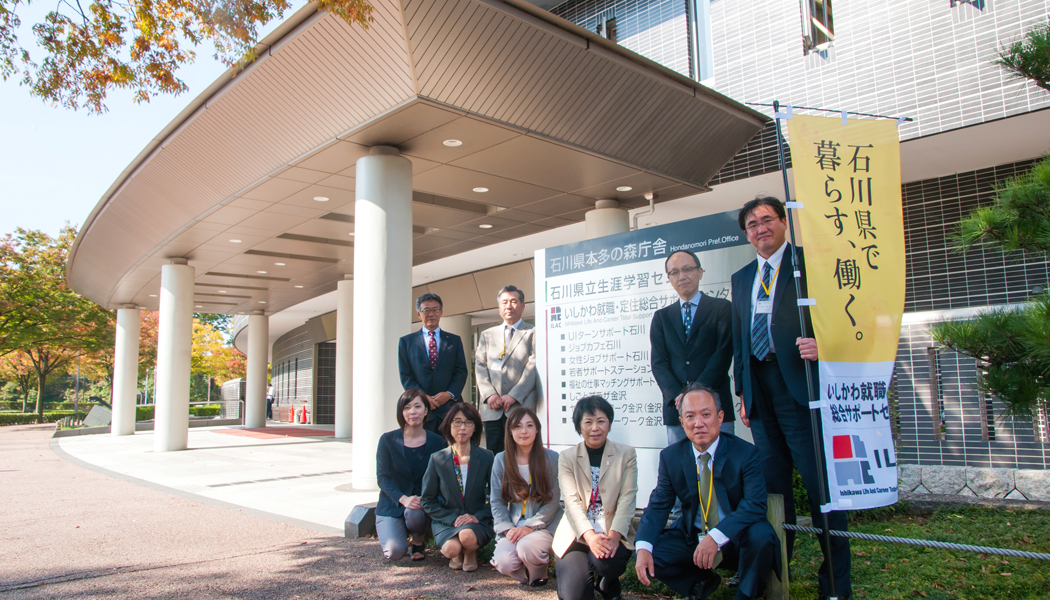
【取材後記】
地方自治体にありがちな制度や施設、資金の援助のみにとどまることなく、県内企業の人事・採用担当者に対して自立的・持続的に定着率の高い人材を採用するための意識改革を促す石川県とILACの取り組みは、マッチングに課題感を持つ多くの企業にとって参考になる施策ではないでしょうか。また、何よりも心に留めておきたいのは「採用するのは人員ではなく、会社にとって掛け替えのない人材であり、感情を持った人間である」という考え方です。日々の忙しさの中でついつい忘れがちですが、採用に関わるすべての人が常に意識しておかなければならない重要な視点であることは間違いありません。
(取材・文/佐藤 直己、撮影/中西 優・シナト・ビジュアルクリエーション、編集/齋藤 裕美子)













