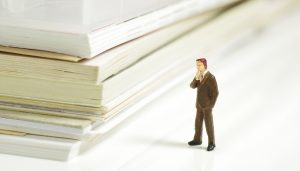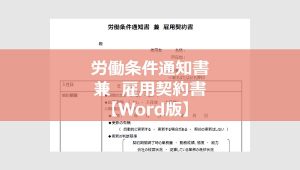【職業安定法 改正】採用担当者が押さえるべき4つの変更点と知っておきたいポイント


d's JOURNAL編集部
改正職業安定法が平成30年(2018年)1月1日より施行されました。今回の施行内容については、企業が人材募集を行う際に対応しなければならない事項が多く含まれており、注意が必要です。そこで、実際にどのように変更されるのか、主要な改正点/ポイントを紹介しますので、認識・理解しておきましょう。
職業安定法(職安法)の改正が行われた背景とは
職業安定法とは、国民の労働権利(労働する活動)を保障するために定められた法律です。職安法とも呼ばれており、労働者の募集・就業指導・職業紹介・労働者供給などについて規定されています。
今回の改定の背景として、東京労働局による『改正職業安定法 説明会』によると、“労働政策審議会 職業安定分科会 労働力需給制度部会において、以下の基本的考え方に基づく、報告書がまとめられた”とあります。その内容は下記の通りです。
社会経済の変化に伴い、職業紹介事業や募集情報等提供事業者等、求職者や求人者が利用する事業の多様化が進む中、求職者等が不利益を被るなどの不適切な事案に対して的確に対応していくことはもとより、求職と求人のより適切かつ円滑なマッチングを進めていくことも求められる。
現在、仕事を探す際にさまざまなサービスがある中で、求職者が不利な立場とならないよう、公正な情報を適切に提供することが求められています。求人詐欺などもニュースになる中で、人材サービス各社はもちろんのこと、募集企業自体にも責任を持って対応する必要があるとして、今回の法改正に至りました。
職業安定法(職安法)の改正で押さえておくべき変更点・ポイントとは
では、実際にどのような部分が追加・改正されたのか、具体的な要件を確認しましょう。求人募集を行うにあたって重要となるポイントは以下4点です。

1.最低限明示しなければならない労働条件の追加/明確化(明示事項の拡充)
往来よりある労働条件項目(業務内容、労働契約期間の定め有無、定めがあるときはその期間、就業場所、勤務時間、賃金、社会保険・労働保険)に加え、下記労働条件項目の明示が追加されました。
労働者を雇用しようとする者(雇用主)の氏名または名称
労働者を雇用しようとする者(雇用主)と、実際にその募集を行っている者が同じではないケースも少なからず発生します。例えば、子会社や関連会社の募集(親会社が求人広告を出している例、子会社に採用機能がある例、グループ会社募集など)、フランチャイズ募集(本部が募集を行うが実際はフランチャイズ経営者先が雇用主)などです。求職者/労働者は誰と労働契約を結ぶのか、きちんと把握・確認することが可能になります。
派遣労働者として雇用する場合は、その旨
労働者派遣について、きちんと明示する必要があります。例えば、正社員として働くつもりだったのに、実際は他企業に派遣労働者として働くケースです。無期雇用派遣などどういうケースで働くのかをきちんと明確にすることが求められています。
試用期間の有無、および、試用期間が発生する場合はその期間、期間中の労働条件
試用期間中は労働条件、特に賃金などが本採用に比べて低くなる場合が多いです。しかし、それをきちんと明記してないと、「金額がおかしいのではないか」と入社後トラブルになるおそれがあります。求職者が不測の損害を被ることがないようトラブル防止の目的で、試用期間について明示する義務が発生しました。
裁量労働制を採用している場合にその旨、他条件
裁量労働制の場合、終業時刻以降に仕事をしても原則残業代は支払われません。そのため、裁量労働制を採用していることをきちんと明示し、「終業時間を超えたら、残業代をもらえる」と思っている応募者との求人トラブルを回避することができます。
固定残業代制を採用している場合にその旨、他条件
例えば、「固定残業代を含めた月給が35万円」の場合でも、求人募集上では「月給35万円」と書かれていると、求職者は「月給35万円とは別に、残業代がもらえるのではないか」と思ってしまい、求人トラブルが発生してしまう可能性があります。賃金関係は特にセンシティブな部分なので具体的に明示することが求められているのです。
なお、固定残業代制を採用する場合は、下記内容を記載する必要があります。注意しましょう。
-
- (1) 固定残業代を除いた基本給の額
-
- (2) 固定残業代に関する労働時間数と計算方法
- (3) 固定残業時間を超える時間外労働と休日労働・深夜労働に対する超過分支給
2.労働条件に変更があった場合、変更内容を速やかに明示する(変更明示)
なお、募集要項・条件が変更・削除・追加になった場合は、求職者/応募者に労働条件の変更内容を明示し、その理由を説明する必要があります。以下を参照ください。
-
- (1) 「当初の明示」と異なる内容の労働条件を提示する場合
-
- 例)当初:基本給30万円/月 ⇒ 基本給28万円/月
-
- (2) 「当初の明示」の範囲内で特定された労働条件を提示する場合
-
- 例)当初:基本給25万円~30万円/月 ⇒ 基本給28万円/月
-
- (3) 「当初の明示」で明示していた労働条件を削除する場合
-
- 例)当初:基本給25万円/月、営業手当3万円/月 ⇒ 基本給25万円/月
-
- (4) 「当初の明示」で明示していなかった労働条件を新たに提示する場合
-
- 例)当初:基本給25万円/月 ⇒ 基本給25万円/月、営業手当3万円/月
(厚生労働省「○労働者を募集する企業の皆様へ」より抜粋)
求人情報が後から不利な条件に差し替わっている場合、企業と応募者とのトラブルが発生する可能性が高いためです。求職者に労働契約を締結するかどうかを考える時間がしっかり確保されるように、可能な限り速やかに知らせることが必要です。
なお、変更内容を明示する際は、変更前後の内容が分かるように示す必要があります。以下のいずれかを対応するようにしましょう。
-
- (1) 変更前後の労働条件を、「比較対照できる書面」にて提示
-
- (2)
-
- (※)において、変更部分に「アンダーライン」を引いて提示
-
- (3) 労働条件通知書において、変更部分を「着色」して提示
- (4) 労働条件通知書において、変更内容について「脚注を付けて」提示
3.募集情報を適切に保存しておく
労働者の募集を行う場合、当初明示された募集情報・労働条件を、「その募集が終了する日」もしくは「その募集内容で労働契約を締結する日」までの間、保存することが義務づけられました。なお、当初の内容と変更が合った場合は、その変更前後どちらの内容も保存しておく必要があります。履歴を残しておくことで求職者とのトラブル回避にもつながります。
4.労働条件明示にあたって、遵守すべき事項の制定
労働条件を明示する際に、職業安定法に基づく指針などを遵守することが必要になります。下記内容をしっかりと理解し覚えておきましょう。
●有期労働契約が試用期間としての性質を持つ場合、試用期間となる有期労働契約期間中の労働条件を明示しなければなりません。また、試用期間と本採用が一つの労働契約であっても、試用期間中の労働条件が本採用後の労働条件と異なる場合は、試用期間中と本採用後のそれぞれの労働条件を明示しなければなりません。
●労働条件の水準、範囲等を可能な限り限定するよう配慮が必要です。
●労働条件は、職場環境を含め可能な限り具体的かつ詳細に明示するよう配慮が必要です。
●明示する労働条件が変更される可能性がある場合はその旨を明示し、実際に変更された場合は速やかに知らせるよう、配慮が必要です。(厚生労働省「労働者を募集する企業の皆様へ」より抜粋)
職業安定法(職安法)を違反してしまった場合、罰則はどうなるの?

虚偽の求人に対する罰則はもちろんですが、今回の改正では指導監督の範囲が拡大されました。つまり、変更内容明示が適切に行われていないと、募集している企業自身が行政による指導監督(行政指導や改善命令、勧告、企業名公表)や罰則などの対象になる場合もあります。求人票や求人広告を作成するときは、労働条件を正確に記載するように徹底しましょう。
【まとめ】
求人詐欺がニュースで話題になったことは記憶に新しいですが、今回の改正では、勤務時間や残業など、より重要な部分にフォーカスされた印象です。採用を行う企業にとっては、「知らなかった」ではすまされない項目になっています。今回の改正の内容を理解しておけば、求人トラブル対策となり事前に防ぐことにもつながります。
厚生労働省のホームページ『平成29年職業安定法の改正について』やリーフレット『労働者を募集する企業の皆様へ』などをよく読み込んでおくようにしましょう。また人材サービス会社の担当営業に確認することもオススメです。
労働条件通知書 兼 雇用契約書テンプレート【Word版】
資料をダウンロード