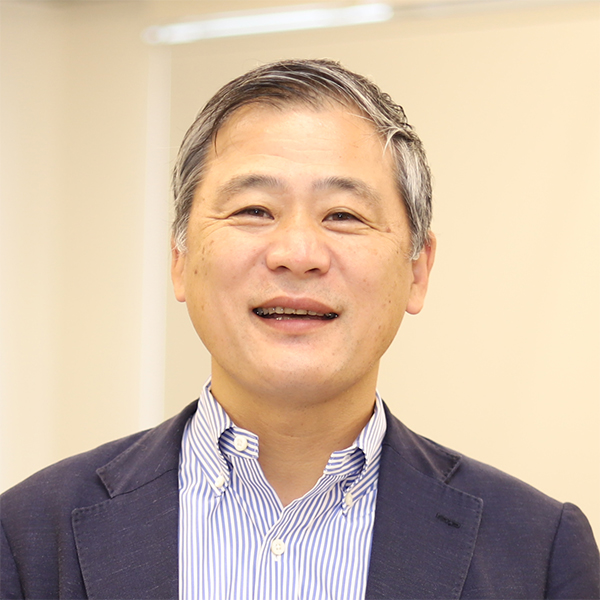就職率0%を目指す大学。世界でビジネス展開できる人材を育てるロジック

やりたい仕事に必要な知識や技術を学び、実践的なスキルも身に付けていく専門職大学。情報経営イノベーション専門職大学(以下、iU)では、それだけではなく起業にも取り組みます。学生は、連携企業や類いまれな社会的実績を持つ教員の支援を受けながら、サービスやプロダクトの開発、投資家へのプレゼンテーションも行います。なぜ、このような大学が必要だったのか。iUを立ち上げた学長・中村伊知哉氏(以下、中村氏)、イノベーションマネジメント局 局長・宮島徹雄氏(以下、宮島氏)、そしてアドミッションユニット長・稲岡克彦氏(以下、稲岡氏)に育てていきたい人材像や、それが今必要な背景について伺いました。

ICTを使ったビジネスを世界で展開できる人材を育てるために
中村氏:偉そうなことを言ってしまいますが、日本の産業界は平成の30年間で世界に負けました。特に、デジタル面で負けたのは大きかったと思います。
宮島氏:どれほど大きな負けだったかは、新型コロナウイルスのまん延で鮮明になりました。企業はテレワークにうまく移行できない、学校はIT対応で混乱する、国においても定額給付金のオンライン申請システムが不十分だった。これらの結果から、日本のデジタル化がいかに進んでいないかが浮き彫りになりました。
稲岡氏:いろいろなところでほころびが見えたのは事実ですが、昭和のころは全て世界に勝っていた分野です。
中村氏:平成元年の1989年、日本は世界1位の国際競争力を誇っていましたが、今年は34位。つまり、平成が始まってから1年ごとに1ランクずつ日本の国際競争力は落ちていったということです。それが日本の抱える大きな課題になっていきました。

宮島氏:昭和の大成功に引きずられて、イノベートを起こせなかったからじゃないでしょうか。変えなければいけないことを変えられない。変わるのが怖かったというか。もし、変えるべきことを的確に変えていたら、優勢を極めた日本企業がわずか30年で世界から大きな遅れを取ることはなかったはずです。
稲岡氏:国際競争力が高いころは、国内の戦いに勝てば世界でも上位に立てました。そのため、国内だけを見て、目の前のことを高い精度でやっていく。それが成功パターンでした。それが、安全運転で失敗しなければ役職も給与も上がって、定年まで勤められるという価値観をつくったのです。世界の国々ではそのパターンが通用しなくなっていたのに、そのまま続けてしまった30年間だったのかなと思います。
中村氏:デジタルの面ではICT(情報通信技術)を使って、もう一度競争力を付けていく以外に方法はないと思います。ただ、日本企業の力は全体的に落ちています。企業に力があれば、大学4年間をぼーっと過ごした僕のような学生を入社させても、鍛え上げて戦力にしながら勝つことができました。しかし、今の企業に自前で戦力を育てる時間も余裕もないので、そのスタイルを貫くのは厳しいでしょう。そうなると即戦力になる人材は大学で育てるしかない。だから、私たちはICTを駆使してワールドワイドにビジネスできる人材を育てる場として、iUを2020年4月に開学しました。

不確実なものにチャレンジし、失敗を重ねることでしか生まれない「真の変革」が必要
中村氏:iUのコンセプトは、『全員、起業にチャレンジする』。
宮島氏:学生は4年間のどこかで起業するでしょう。何度、失敗しても構いません。10回でも20回でも、iUでの4年間は何度でも起業にチャレンジできます。
稲岡氏:学長はよく、「iUは失敗大学」と言っています。だから、私も学生には失敗を気にしないでトライしてほしいと思っています。そうは言っても、起業家になることだけが目的ではなく、卒業後に企業で働くのも一つの選択肢です。ただ、企業の看板を自慢するのではなく、「僕は○○ができるので、この企業で働いています」と言ってほしい。そのためにも、学生時代は不確実なものにチャレンジして失敗を重ねていく。それを今までの日本の大学や企業はやってこなかったと言えるでしょう。
宮島氏:もちろん、ゼロやマイナス評価の社員が逆転ホームランで社長になれる企業もありますが、日本の普通の企業、特に歴史のある企業では1回の失敗で出世のラインから外れると聞きます。決まったルールの中で110、120%頑張っている人が評価され、不確実なものにチャレンジする人は評価されないという話も聞きました。しかし、企業も社会も、変革は待ったなしの状況です。

稲岡氏:ビジネスでICTを使うのは、ゲームのルールが変わったのと同じです。それでも古いルールに固執して戦おうとしたのがこれまでの日本でした。僕は、それが世界に遅れを取った一番の要因だと思います。
中村氏:僕の目から見れば、デジタルに関して彼らの方が先を進んでいて、仕事に対する向き合い方でも「つつがなく定年を迎えました」と花束をもらう姿を思い描いている人は誰もいないと思います。二足、三足のわらじを履くのは当たり前。いろいろなキャリアを重ねていくのが普通の考え方というか。当然、起業も選択肢に入っています。iUに入学する学生はその考えをもっと鋭くしたような人たちが多いようです。
宮島氏:iUの学生たちはいい意味で「変わって」います。高校時代に起業しようと意思決定している方や、明確に何かをしたい方もいれば、まだやりたいことが決まっていないけれど、「何かをやりたい」「何かを見つけたい」という意欲の高い方も入学しています。これまでの大学とは違い、枠を超えたチャレンジができるiUと、それが当たり前になりつつある時代は彼らにとって好機と言えるでしょう。
稲岡氏:専門職大学の特長は、社会で素晴らしい経験・実績を持つ教員が40%以上在籍していて、4年間で640時間(約5カ月)のインターンシップがあることです。それに加えて、iUには起業にチャレンジするカリキュラム「イノベーションプロジェクト」があります。アイデアからサービスやプロダクトを開発して、プレゼンテーションして起業する。それが必須になっているので、入学を決意する時点において、4年間で何かをしようという意識は強いと思います。

「世界に誇れるものを生み出す人材」を育成する大学
宮島氏:まず1つ目として、起業資金を用意するために、VC(ベンチャーキャピタル)機能を持つi株式会社を設立しました。優秀なビジネスプランに資金を援助します。2つ目は、キャンパス内にインキュベーションセンターを設け、オフィスとして無償で貸し出しします。最後3つ目は、起業経験のある教職員が起業をサポートすることです。学生たちにとって、この「経験」だけは得ることが難しい。しかしiUは経験を余すことなく学生に伝えることができる教職員がいる。そこが強みだと考えています。
中村氏:最初に産業界について偉そうなことを言いましたが、日本で一番問題を抱えているのは大学だと考えていました。GoogleやFacebookは大学生がつくったものです。そういう意味でも、大学でそのようなイノベーションを起こすことができる人材を育てていきたい。この部分をどうにかしない限り、日本の再生はないと思っていました。その考えを伝えてみたら、共感するトップ級の実績を持つ教員がたくさん集まりました。今では200名を超えて、学生よりも多い状態です。つまり、本当はもっと教える側のポテンシャルはあるのに、そういう方々が多く集まる大学がなかっただけです。

宮島氏:何かを教えたい、教育で日本を変えたい、今までとは違う教育に関わりたいという方が多く、心強く感じています。みなさん多忙を極めている方ばかりですが、吉本興業ホールディングス株式会社の大﨑(洋)会長、株式会社コナカの湖中(謙介)社長は、客員教員から学生へオンラインで学びを提供する「バーチャル研究室」を持ち、定期的に講義を行っていただいております。
稲岡氏:社会で卓抜した実績を残している方ほど、外の声を聞くことが自然だと思っているのかもしれません。ほかにもVC、会社をつくる際に必要な財務、マーケティングなど必要な専門知識があります。そのような知識を実学として持つ人たちが教員として学生に教えています。
中村氏:だからこそ、今の目標は就職率0%。全員が起業に成功にしたら、就職率0%達成ですから。ただ、起業してもほとんどが失敗すると思います。それも必ずいい経験になるでしょう。iUの学生には、3つぐらい掛け持ちで異なる仕事ができる人材に育ってほしいと考えています。そのときは、就職率0%から就職率300%に方針転換します。
中村氏:一方で、大学はもっと速いスピードで変わらざるを得なくなるでしょう。たとえば、世界の大学がつながれば、講義は全てオンラインで視聴できるようになります。そうなると、これからは大学の卒業証書よりもオンラインでそれぞれの講義を修了した記録の方に価値が出てきます。それは大学に別の魅力が求められるということです。今のiUで言えば、イノベーションプロジェクトがその一つ。そういう既存の概念にとらわれない「新しい魅力」を生み出していく能力も大学には求められるでしょう。「iUには世界中の起業家が集まっている」「iUではいつも突拍子もない変わったことが起きている」というような。もちろん、iUだけで大きな変化は起きないので、いろいろなことのハブになったり、台風の目になったりする存在を目指したいと考えています。

取材後記
すぐ近くに東京スカイツリーが見えるiUの墨田キャンパス。4月に開学されたばかりの新しい建造物を囲うものはありませんでした。そのボーダーレスな佇まいは、必要に応じて自在に世界中とつながることができるICTの一端を見るようです。このキャンパスに集う学生たちが世界を舞台に何を生み出していくのか。そのとき、日本の国際競争力はどうなっているのか。まったく想像できませんが、中村氏らの話を聞いていくうちに、将来への楽しみが大きくなっていった取材でした。

取材・文/洗川広二、編集/d’s JOURNAL編集部