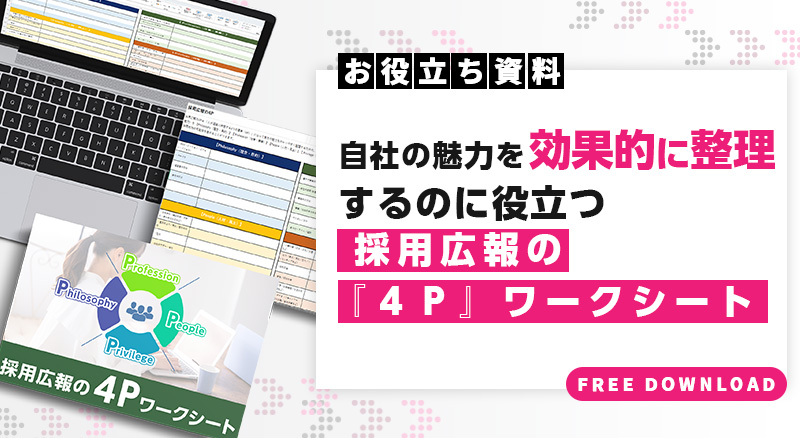採用活動がうまくいかないのはなぜ?母集団形成・面接前・面接後の各フェーズにある「採用課題の見つけ方」と「対策」
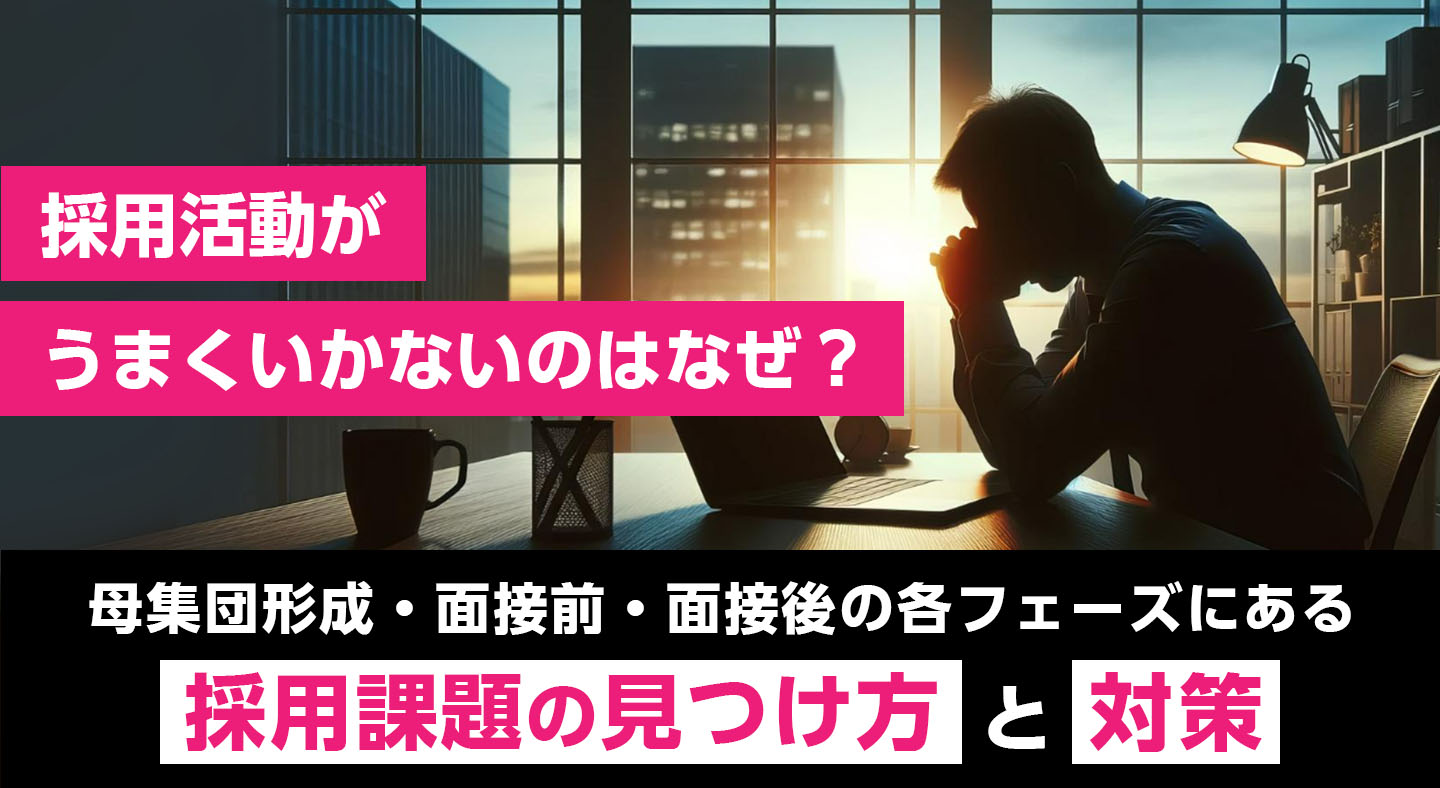
d’s JOURNAL編集部
-
採用課題は「母集団形成ができない」「面接実施に至らない」「入社承諾に至らない」といったフェーズに大別できる
-
母集団形成フェーズでは「応募率を高めるための魅力訴求」「アプローチ対象・方法を見直す」に分けて対策を考える
-
選考フェーズの課題解決のために、場合によっては採用要件の再定義や訴求ポイントの打ち出しに立ち戻ることも必要
多くの企業で人手不足の状況が続き、採用活動を積極的に行っているものの、最適な人材獲得に苦戦している人事・採用担当者も多いのではないでしょうか。さまざまな採用手法を試みるもうまくいかず、自社の採用活動の見直しを進めている企業も少なくないでしょう。
採用がなかなかうまくいかない場合には、まずどのフェーズで歩留まりが発生しているかを整理し、自社の採用課題を特定することが重要です。この記事では歩留まりが発生する場面を「母集団形成ができない」「面接実施に至らない」「入社承諾に至らない」といったフェーズに大別し、それぞれのフェーズで対応するべき課題と対策について解説します。
母集団形成フェーズで発生する課題 ~応募者が集まらない原因を解決するために
求人に対して応募者が集まらないという課題を持つ人事・採用担当者は多いのではないでしょうか。この段階では、「応募率を高める」「アプローチすべき対象・方法を見直す」という課題ごとに分けて対策に取り組む必要があります。具体的なアクションプランを見ていきましょう。
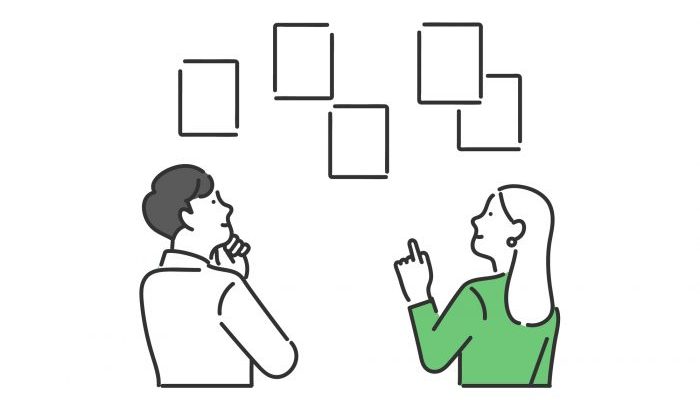
■アプローチしている対象者からの応募率を高める
応募率が低い原因は、単純に転職希望者が自社に興味を持ってくれていないからです。そのため、まずは自社の魅力の棚卸しを行い、転職希望者が何を求めているのかをイメージして情報を訴求することが大切です。
採用活動における自社の魅力とは「転職希望者にとっての魅力」です。求めている人材は何を重視して転職を希望しているのでしょうか。「働き方を変えたい」「やりがいのある仕事がしたい」「さらなる高待遇を実現したい」など、転職希望者の転職理由や要望を知った上で自社の魅力を訴求する必要があります。
なお、自社の魅力を訴求する上では、以下の4つに分類して考えることで、転職希望者の意向に合致したポイントを打ち出しやすくなります。
・会社や事業そのものの強み
・仕事の面白さ
・働き方の魅力(残業なし、休みが多いなど)
・組織文化(企業風土、どんな人と働くのかなど)
■求める人物像を定義し直す
自社の魅力が十分訴求できているのにもかかわらず応募が集まらない場合は、求める人材と転職市場の現状に乖離(かいり)があるのかもしれません。自社の募集条件・魅力に対して、求めているスキル・経験が高すぎる場合はなかなか応募に至りません。転職市場に合わせて募集条件を見直すか、求める人材の要件を再定義する必要があります。
どのような人材であれば採用背景をかなえられるかを見直すことで、求める人物像を再定義しましょう。たとえば営業職募集で営業経験者を求めているとして、「営業職から営業職」への転職を希望する人は市場にどれくらいいるでしょうか。もしかしたら、営業という仕事にしんどさを覚え、他職種へ転職したいと考える人も多いかもしれません。市場にどんな人材がいるのか、その人材は何を求めているのか、どんな理由で転職をするのかを踏まえて、自社に来てもらえそうな人材像を設計するべきです。
同時に「どんな人材なら自社で活躍できるか」という視点でも考えることが重要です。自社で活躍できる人材要件を再定義することで、同業界や同職種の経験ではなく、異業界や異職種の経験・スキルが活かせるかもしれません。
【こんな方法もおすすめ】
自社で行う「転職市場の調査」や「現場への情報収集」には限界を感じることも少なくありません。「HR forecaster」では、dodaが蓄積した200万件以上の市場データを活用し、平均年収などの多様なデータを可視化。「採用のものさし」として求める人物像の設定などに活用できます。
■アプローチ方法を変える
自社の魅力を訴求し、求める人物像を再定義しても応募が集まらない場合は、アプローチ先の変更も検討してみましょう。自社のリソースのみで採用活動をしていた場合は、たとえば人材紹介サービスを活用する、もしくは人材紹介サービスをすでに活用している場合は、データベースの特性が異なる他社のサービスも追加検討したり、転職潜在層にもアプローチできる求人広告に掲載したり、自社で直接アプローチできるダイレクト・ソーシングサービスを導入したりといった手法が考えられます。
面接前フェーズで発生する課題 ~面接実施にまで至らない原因を特定する
応募は集まるものの、社内での書類選考通過数が少なく面接実施までに至らなかったり、面接直前で選考辞退が多く発生したりする企業も多いのでは。こうした場合には「選考プロセス・スケジュールの見直し」を検討し、場合によっては採用要件の再定義や訴求ポイントの打ち出しに立ち戻ることも必要です。
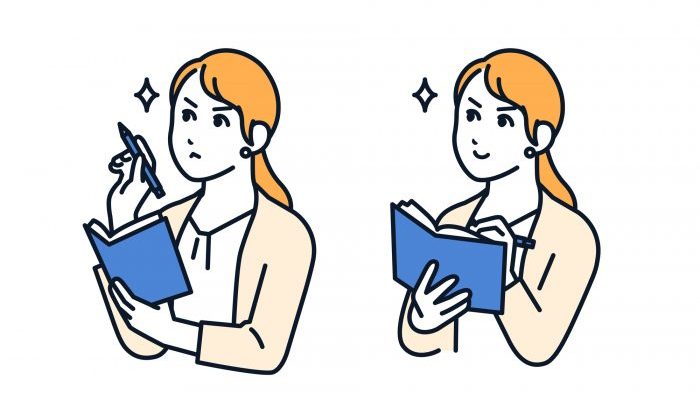
■選考スケジュールを見直す
面接前の選考途中で辞退が多く発生してしまう背景としては、自社の選考スケジュールが長期化することで、応募者が他社の選考を先に進めてしまっていることも考えられます。そのため選考スケジュールの短縮化を図り、早期に応募者との接点をつくる必要があります。
普段は何気なく進めている選考プロセスにも無駄が潜んでいるもの。たとえば書類選考ではまず人事・採用担当者が確認し、現場に回覧して判断してもらうケースも多いのではないでしょうか。人事・採用担当者を経由せず、現場のみで書類選考を完結させるだけでも選考スピードアップにつながります。昨今ではオンライン面接を行う企業も多く、これも選考スピードアップに寄与しています。
■選考の前段階から意向を高めるために情報訴求を行う
ほとんどの転職希望者は複数企業の選考を並行して受けています。面接前の段階では、会社の情報を伝える機会が少なく、転職希望者の優先度によっては面接前に辞退されてしまうことも。応募者の面接意欲を高めるためには、届けるべき情報が伝わっているか、手前の訴求段階に立ち戻ることも大切です。
応募者は求人広告やスカウトメールの文面だけでなく、企業サイトや採用サイトで発信している情報も見ています。その意味では更新頻度や掲載内容などにも気を配るべきでしょう。最近では転職口コミサイトを見て選考に進むのをためらう人もいます。ネガティブな口コミが書かれている場合は、それを払い去るための情報発信もしておきたいところです。
■求める人物像と転職市場の現状とのギャップを埋める
社内での書類選考で不合格が頻発し、面接に進む応募者が少ない場合は、求める人物像と転職市場の現状に乖離(かいり)があるのかもしれません。人事・採用担当者と現場との間で、求めている人物像に相違があることも考えられます。改めて、募集段階での求める人物像の設定に立ち返り、求めるスキルや経験などの要件を見直すことも必要でしょう。
面接後フェーズで発生する課題 ~入社承諾に至らない理由と対策
面接までは実施するものの最終選考で不合格になったり、選考通過したものの他社との比較の上で辞退になったりする場合など、面接実施後のフェーズで入社承諾に至らないという課題を抱える企業も多いはず。ここでも、「不合格が多い」「辞退が多い」など、どこで歩留まりが発生しているかを踏まえた上で対策を進める必要があります。具体的なアクションを見ていきましょう。

■辞退理由から採用競合との差別化ポイントを考える
最終面接実施後に選考を辞退され、入社承諾に至らなかった…という経験がある企業も多いのではないでしょうか。辞退が多い場合は、面接の問題点を洗い出すために応募者から率直な辞退理由を聞きたいところです。
条件なのか仕事の魅力なのか、他社との比較により辞退となった場合は、その理由によって対応策が異なります。競合他社が提示する年収と自社が提示する年収に100万円の差がついていたら優位に立つのは難しいかもしれませんが、応募者が担当する仕事の魅力を高めることはできるかもしれません。辞退されてしまう理由を理解し、その上で対策を考える必要があるのです。
人材紹介サービスなどを経由する場合はこうした情報を聞けるケースが多いです。自社で応募者と直接やり取りしている場合でも、できる限り辞退理由を聞き、可能であれば他の検討先企業についても教えてもらえるようコミュニケーションを図りましょう。加えて、採用競合の選考スケジュールも把握できれば、自社が先回りして対応することができます。
■面接を通じて入社意向を醸成する
前述の通り、転職希望者は複数企業の選考を受けて優先順位を決めていきます。自社の優先順位が低い状態では選んでもらえません。面接を通じて応募者の入社意向を高めていく必要があります。しかし、実態として面接を見極めの場として考え、面接官が聞きたいことを聞く場となっている企業が少なくありません。
昨今では面接におけるアトラクト(自社の魅力づけ)を重視する企業も増えています。応募者が実現したいことに合わせて、自社であればどんなことがかなえられるかなど、面接では相手が求めている潜在的ニーズを想像しながら情報提供することを心がけましょう。
【こんな方法もおすすめ】
パーソルキャリアが提供する「HR analyst」では、応募者へのアンケート発行や分析、適切な面接官アサイン、面接官同士の申し送りなどをサポート。転職希望者一人ひとりについて志望順位を高めるポイントを把握し、情報提供することで入社意向の醸成につなげています。お伝えすることで、理解の深まる面接が重要です。
■一次や最終など各面接のスケジュールの短縮化・判断基準を統一する
選考途中での辞退が多く発生する企業では、社長・役員など最終意思決定者との最終面接までの期間が開いてしまっているケースも珍しくありません。せっかく書類選考や一次面接を素早く行っているのに、最終面接が2週間後などになってしまうケースも。辞退を防ぐためには、最終意思決定者のスケジュールを事前に押さえた上で選考を進めるべきでしょう。採用数が多い企業では、毎週定例の「面接対応時間」を設けてあらかじめスケジュールを押さえる取り組みも進められています。
また、選考不合格によって、面接後の歩留まりが発生するケースもあります。たとえば、一次面接では高評価でも、最終面接で不合格者が多く発生している場合などが考えられます。その場合、人事・採用担当者と現場、最終意思決定者などの間で判断基準に乖離(かいり)があるのかもしれません。どんな人材を採用すべきか、どんなところを重視しているのかなど、判断基準を改めて擦り合わせる必要があります。もちろん、それぞれの立場で見ているポイントが異なることも多いですが、人事・採用担当者としては、それぞれが何を重視して判断しているかの基準を認識しておくべきでしょう。
社長など最終意思決定者の判断基準を確認するためには、まず「NG理由」をヒアリングすることが大切。フォーマットのような形で明文化し、NG理由を共有するフローを設けておけば、人事・採用担当者がストレスなくデータを蓄積できるのではないでしょうか。
現状の厳しい転職市場においては、経営トップが本気にならなければ採用成功は難しいと言えます。給与・待遇などの条件を見直すのも経営トップが納得しなければ難しいでしょう。一朝一夕で変わるものではないからこそ、人事・採用担当者は粘り強いコミュニケーションを重ねていくべきなのです。
【こんな方法もおすすめ】
doda人材紹介サービスは、採用決定時に費用が発生する“完全成功報酬型”の採用支援サービスです。専任担当がお預かりした求人情報をもとに、募集ポジションにマッチした転職希望者を厳選しご紹介。採用手法や年収相場、選考フローの歩留まり改善など、採用全般についてのアドバイスも可能です。
編集後記
自社のどのフェーズで、どんな採用課題があるのか。取り組むべきことを明らかにした上で、適切なアクションを実施していくことがますます重要となっています。人事・採用担当者、現場、経営層のコミュニケーションでは、人材紹介サービスなどの外部リソースをうまく活用することもおすすめです。話者を変え、第三者の視点から転職市場について伝えることで、「経営トップや現場も採用にコミットするべき」という認識が広がっていくはずです。
企画・編集/森田大樹(d’s JOURNAL編集部)、野村英之(プレスラボ)、文/多田慎介
【マンガで解説】doda人材紹介サービス資料
資料をダウンロード