「面接=万能な選考ツールではない」採用学から学ぶ募集・選考・面接でとるべき行動

成功する採用活動を行う企業の人事・採用担当者は、どのような取り組みを行っているのか? 様々な企業が直面する、採用・選考時の問題とは? そうした情報や事例を通して学べることは数多くあります。
そこで横浜国立大学大学院で「採用学」を研究する服部泰宏先生に、人事・採用担当者が覚えておきたい基本的な資質に加えて、「募集」「選考」「面接」の各フェーズで考えておきたいポイントについてお話を伺いました。
はじめに取り組みたいのは、基礎リテラシーの復習と社内の人脈作り
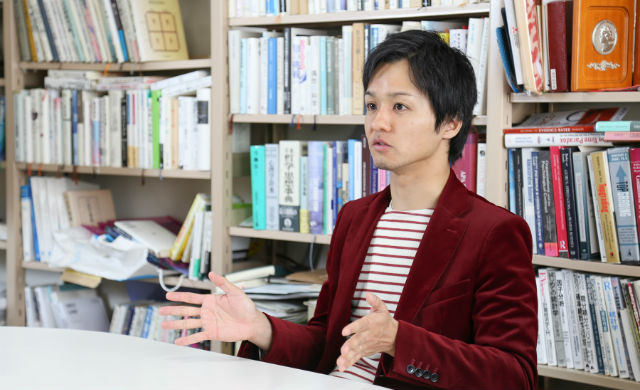
服部先生:これは採用活動を刷新したいと考えるベテランでも、困るところでしょうね。採用活動は各企業の状況や課題ありきですので、一概にこうすればいいという明確なハウツーはありません。ただし、基本となる考え方はご紹介できると思います。例えば、前回「採用力のベースになるのは、人事・採用担当者自身の力」とお話ししました。
服部先生:そうです。ここでいう“知識”とは、新卒・転職市場に関するものと、自社に関するものがあります。特に自社の知識に関しては、私が学生に対して行った調査で「採用担当者にがっかりした瞬間」というアンケートを取ったところ、「会社に関する基礎知識が足りないと感じた時」という回答が非常に多かったのです。
服部先生:「人事担当者が、社長のフルネームを漢字で書けなかったことに驚いた」と回答した学生もいれば、「アニュアルレポートで読んだ、中期経営計画の進捗について質問した際、回答してもらえなかった」という声もありました。細かな知識や情報のすべてを押さえる、というのは酷ですが、細かな知識によって尊敬や信頼が形成されると考えると、まず最低限の基礎リテラシーは復習すべきであろうと思います。
服部先生:土台の2階の部分になるのは、社内に人脈を築き、採用に協力してくれる仲間を見つけることです。実際、新卒分野などで革新的な活動を成功させている人事・採用担当者の方に話を聞くと、会社の中に味方を作っている場合が非常に多いです。
服部先生:とはいえ、革新的な採用活動を成功させている人事・採用担当者の方々も何か特別なことをしているわけではありません。社内の研修や勉強会で会った別部署の方に実務の状況をヒアリングしたり、同期飲み会に出席した際に、どんな人材が欲しいのか、どんなタイプが活躍しているのか、意見を交わしてみたり。カジュアルな情報収集を日々行うことで、採用に向かう一体感も育んでいる印象です。
服部先生:それに、経営者に採用活動の刷新を提案する場合にも、採用ポジションの担当者と一緒になって「本当に人材が必要なんです」と発信することが有効なケースもあり得ます。ですから、社内の協力体制がどれだけ整えられるかは、様々な面で非常に重要ではないかなと思います。
採用活動の選択肢はひとつではない。各フェーズで自社に合う施策を練るべき

服部先生:それぞれのポイントをお話しします。まず募集の段階では説明会などを含めた「メディア」を複数持つこと、そしてその全てで一貫した情報発信を行うことが重要です。
服部先生:求職者は一般的に、説明会や見学会など実際に見聞きするメディアと、求人サイトやコーポレートサイトなどのウェブ系のメディア、両方から情報を得たいと考えています。そして、求人情報で見た情報と同様のテーマが説明会でプレゼンされていれば、説得力が約1.5倍になるといった調査結果も出ており、異なるアプローチ方法で統一した情報を提供することは欠かせません。
もちろん、ある種の逆張りと言いますか、今までのオールドイメージを刷新するために、あえて採用だけは雰囲気をガラリと変える戦略もありますが、基本は一貫性を持たせるべきでしょうね。
服部先生:私が以前調査を行った際、自社の採用活動に満足している企業の多くが、選考段階での絞り込み方が非常に巧みだったんですね。最初の認知の段階では非常に広範囲にアプローチしつつ、情報をしっかり提供することで、実際に“エントリーしようかな”というタイミングでは、合う人・合わない人という点を求職者自身が判断できるようにして、一定の絞り込みをかけている。
例えば、カフェテリア採用などの独自の採用手法を行う三幸製菓や、一次選考で「重い課題」を提示するライフネット生命は、その代表例と言えるでしょうね。
服部先生:エントリーシートで落とすのか、Weサイトの時点で「自分には合わないな」と求職者が判断するのか。これは微妙な違いですが、ここが変化すると、膨大なエントリーシートをチェックしていた時間を、面接で採用候補者をしっかり見極めることに費やせるようになる。人事・採用担当者の希少な時間の使い方が大きく変わるため、生産性が格段に高まります。
服部先生:ダイレクト・ソーシングは、欲しい人材にピンポイントに近い形で接点をつくっていく手法ですからね。まずは、「求める人材がどこにいるのか?」という情報収集が重要でしょう。それもできれば求人が発生するタイミングだけでなく、常に自社にマッチしそうな人材の情報にアンテナを張り、リサーチし続けることです。
また、社内でも、どの部署にどんな人材が必要なのか?自社で活躍しているのはどういったタイプなのかをリサーチして、スキルマッチだけでなく「自社に本当にマッチする人材とは?」という物差しを自ら創り出し、常にアップデートしていくことが不可欠です。
服部先生:採用候補者の立場になって考えてみると、「机を挟んで複数の人間と話すのが得意」という人は少ないと思います。そのため当たり前のように行っている面接も、実はコミュニケーション力の一部だけを見ているだけにすぎません。ですから、選考のツールを複数用意し、「どんなスキルを見たいのか?」「どんな尺度で見極めるのか?」というバリエーションを採用担当者が持つことが重要です。
また大切なのは、「面接の担当者は、感覚的に物事を判断する」という前提を、面接を担当する人自身が認識しておくことだと思います。私が以前に調査した際、大半の方が、面接が始まって数分で「彼は気難しいタイプだな」「この子は面白いな」といったおおよその印象を決めていました。そして、最後まで第一印象を引きずりがちです。採用候補者の本質は違うかもしれないのにです。
そのため、それを理解しておけば面接に臨む姿勢も変化するはずです。もちろん人を見る目がずば抜けている方や、あえて俗人的な判断に任せることで多様性に富んだ採用を行いたいという場合もあるので、ケースバイケースではありますが。
服部先生:これまでの採用は、母集団をとにかく集めて、誰が自社にマッチしているか分からないから相対的な物差しで見極めようとするメジャーメント型が一般的でした。しかし、これからの時代は、その物差しや採用手法自体を自分で選択し、創造することが問われてきます。メジャーメントからクリエーション型へと変化することは、かなり大変ですが、同時にやりがいも格段に高まるはずです。
【取材後記】
まず採用マーケットの情報や自社の情報を日頃からチェックする。次に、社内でのカジュアルなコミュニケーションで「採用の仲間」を増やす。そして、採用活動の各フェーズごとに考えを巡らせ、戦略を立てて進めていく。
積極的に知識を身に付け、それをもとに戦略を練り、新たな採用手法を積極的に導入すれば、採用成功の確度が格段に増していくはず。服部先生のインタビューからは、その可能性を強く感じられました。今後もd’s JOURNALでは、人事・採用担当者のレベルアップに役立つ情報を発信し、採用力向上を応援していきます。












