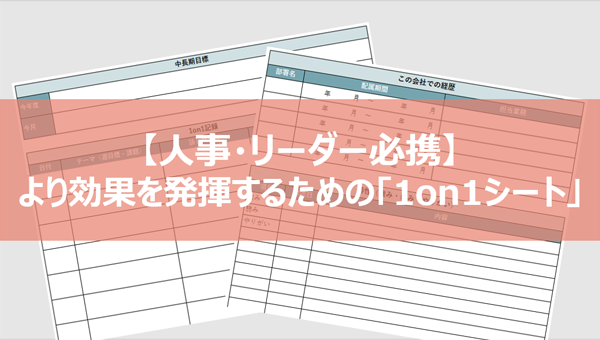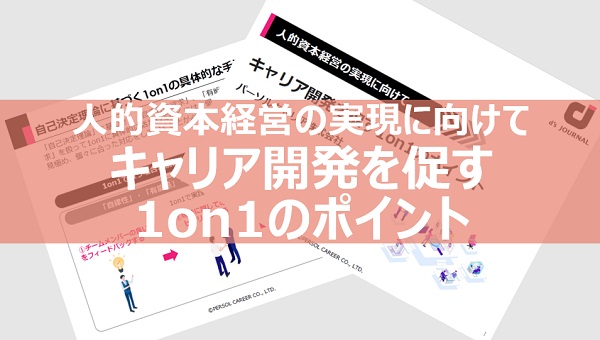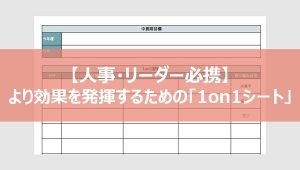【具体例あり】1on1で話す内容や考え方や目的に沿ったテーマ例を解説


d's JOURNAL
編集部
上司と部下がマンツーマンで行う定期的なミーティングを意味する「1on1」。「部下と何を話せばよいかわからない」「部下の成長を促すには、どのようなテーマや質問が効果的なのか」といった悩みを抱えている方も多いでしょう。
この記事では、1on1で話すことや、目的に沿ったテーマ例、実施する際に意識することなどをご紹介します。
1on1で話すことは目的から考える
1on1とは、上司と部下が1対1で行う定期的なミーティングのことです。「1on1ミーティング」と呼ばれることもあります。多くの企業で導入されていますが、1on1の場を設ける理由は「各企業がどのような目的で1on1を実施しているのか」によって異なります。そのため、1on1で話す内容は目的によって考える必要があるでしょう。1on1の主な目的として、次の3つが挙げられます。
<1on1の主な目的>
●部下の成長促進
●組織・チーム力の向上
●離職防止(モチベーション向上)
1on1でどのようなことを部下から聞いたらよいのかを、実施目的ごとに見ていきましょう。
部下の成長促進が目的の場合
部下の成長促進が目的の場合、部下の担当業務の話題を中心に話を聞き、助言やサポートを行います。部下は、業務での失敗体験や成功体験を上司に話すことで自身を振り返ったり、上司と一緒に考えることで取り組むべき課題を明確化したりできます。
上司としては、部下の話をしっかり傾聴した上で、部下の能力を引き出すためのフィードバックを行い、成長促進につなげましょう。
組織・チーム力の向上が目的の場合
組織・チーム力の向上が目的の場合、「チームメンバーとの関係で不和はないか」「様子が気になるメンバーはいないか」などを複数の部下にヒアリングし、組織・チームの状況を確認します。
上司自身が気づかなかった職場環境の問題点を聞き出すことで、チームの課題が把握できるだけでなく、職場環境の改善ポイントも見えてくるでしょう。
離職防止(モチベーション向上)が目的の場合
離職防止(モチベーション向上)が目的の場合、会社からの好評価を伝えたり、業務内外問わず不安や悩みを尋ねたりといった形で、部下のフォローアップを行います。
1on1は、部下のモチベーションの低下を早期に察知するための重要な機会の一つです。部下の変化や課題を把握した場合、できるだけ早く対応することでモチベーションの低下を防ぎ、離職防止につながるでしょう。
1on1で扱うテーマ(話題)の例
1on1は部下の話を上司が聞くことを目的としていますが、限られた時間を有効に活用するにはいくつかテーマを押さえておくとよいでしょう。1on1で取り扱うテーマとしては、次の7つが挙げられます。
1on1で扱う7つのテーマ
・体調やメンタルの状態
・モチベーション
・将来のキャリア
・業務や組織の課題
・目標設定と自己評価
・企業の戦略・方針の共有
・プライベート
それぞれのテーマについて、ポイントを解説します。
体調やメンタルの状態
体調やメンタルの状態は、業務を遂行するうえで基礎となる部分です。普段から気配りを行っておく必要がありますが、必ずしも見た目で判断できるものばかりではないので、1on1の機会に話を聞いてみるとよいでしょう。
普段はなかなか話しづらいことであっても、1on1の場であれば心身に感じていることを話してくれるかもしれません。心身の健康状態について確認しておきたい点として、次のようなものが挙げられます。
健康状態に関する質問事項
・業務量の負担はないか
・業務外の時間はきちんと休めているか
・睡眠時間をしっかり確保できているか
・体調やメンタルに変化を感じる部分はないか
・健康について、周囲に相談できる人はいるか
特に相談できる相手がいない場合は、突然心身の不調が生じてしまう恐れがあります。離職につながる原因にもなるので、早期発見を行うためにも1on1の機会を活かしてみましょう。
モチベーション
部下のモチベーションについては、1on1向きのテーマともいえます。モチベーションの低下などの悩みを部下が抱えているときは、本人自身も何が原因となっているのか把握できていないことがあるからです。
モチベーションの低下を防ぐための話をする一方で、モチベーションを高めるための話題も振り向けてみることが大切です。特に次のようなアプローチを行ってみると、部下のモチベーションを向上させることにつながります。
モチベーションを高めるための話題
・業務に対する普段の取り組みを褒める
・業務の成果にたどり着くまでのプロセスを評価する
・チームによい影響を与えていることを伝える
・社内での評価が高まっていることを知らせる
本人の意欲を引き出すには、できるだけポジティブな評価を伝えることが大切です。逆に、モチベーションの低下を防ぐための話題としては、業務でストレスに感じることや人間関係で悩んでいることなどを聞いてみましょう。
部下自身が自分の言葉で語ることで、新たな気づきを発見するきっかけになるはずです。
将来のキャリア
1on1はじっくりと話を聞ける機会でもあるため、部下がこれから積んでいきたいと思えるキャリアについてもテーマとして取り上げてみましょう。1on1では、本人の強みと弱みを踏まえたうえで、どのような業務であれば力を発揮できるのかを一緒に考えていくことが大事です。
また、普段の業務でやりがいを感じている点やこれから挑戦したいと思っている仕事などを尋ねてみましょう。将来のキャリアがまだ漠然としているときは、部下自身が大切にしている価値観や生き方などについて話し、キャリアを支援していくことが重要です。
業務や組織の課題
日々の業務や組織の課題に関するテーマは、1on1でも取り上げられる機会が多いものとなるでしょう。現在関わっている業務のことや、何か業務で困っていることがないかなど丁寧に話を聞くことが大切です。
また、メンバーとの人間関係やチームが抱えている課題、どのような取り組みを会社に行ってもらいたいかなど、その時々の状況に応じて質問する内容にも変化をつけてみましょう。
特に人間関係で抱えている悩みや上司・会社に対する不満は、普段は聞きづらいものでもあるため、1on1の機会を通じて話を聞いてみることが重要です。きめ細かく話を聞くことによって、部下のモチベーションを高め、仕事の生産性をアップさせることにつながります。
目標設定と自己評価
部下の目標設定や自己評価についても、1on1のテーマとして取り上げてみましょう。会社やチームが掲げる目標と、部下が目標とする部分をうまく擦り合わせていくことが大切です。
一緒に考えて設定した目標は、定期的に部下に自己評価を行ってもらいましょう。テーマとしては、以下のものが挙げられます。
目標設定・自己評価のテーマ
・現在の業務に対する感想
・これから関わってみたい業務について
・どのような目標を目指したいか
・目標を達成して得られたこと
・自身の業務に対する取り組みへの評価
部下が会社やチームが掲げる目標をきちんと認識しながら、自分の目標を設定できているかを確認しておきましょう。
企業の戦略・方針の共有
1on1は、普段は思うように時間が取れずに話せないことであっても、じっくりと話をする機会として活用できます。経営戦略や事業方針などは、部下の立場からではわかりづらい点もあるので、上司から改めて説明していくことも必要です。
会社の方針に対する疑問点を尋ねたり、部下の立場でどのような貢献ができたりするのかを話し合ってみましょう。会社に対する帰属意識が強くなれば、離職を予防することになり、仕事に対するモチベーションを高められるはずです。
プライベート
1on1では、部下とざっくばらんに話をして、信頼関係を深めることも大事なポイントだといえます。業務に関する話だけでなく、プライベートな話題も取り入れることで部下の緊張が和らぎ、穏やかな雰囲気で話ができます。
何か特別なことを話すというより、休日の過ごし方や趣味といった何気ない話題を振ってみましょう。部下があまり話したがらないことは、話題をすぐに切り替えて興味のありそうなことを尋ねてみてください。
部下の本音を引き出す4つの質問例
1on1では、部下側の本音を引き出すことが重要です。「Yes」「No」で答えるしかない質問ではなく、自由に答えられる「オープンクエスチョン」をするとよいでしょう。
ここでは、1on1を成功させる4つの質問について解説します。具体的な会話例もご紹介しますので、参考にしてください。
質問①:「最近あったうれしかったことは?」
部下の人となりをある程度知っていた方が話は弾み、本音を引き出しやすくなります。価値観や性格を知るため、まずは「最近あったうれしかったことは?」といった、本人がどういったことに喜びを感じるのかがわかる質問をしましょう。
「何を重視しているか」を知るために話を掘り下げ、相手を知ろうとすることが大切です。しかし、プライベートに関わる可能性がある質問をする場合は、相手との「信頼関係」が築けているかが重要なポイントです。
信頼関係が築けていない段階でこうした質問をすると、「少し警戒・萎縮してしまう」など逆効果になる可能性があるので注意しましょう。
会話例
上司:<最近のうれしかった出来事についての質問>最近、どんなことがうれしかった?仕事のことでも、それ以外でも差し支えない範囲で教えてくれる?
部下:家族で、最近オープンした●●に出かけました!
上司:<詳細を確認する質問>へー、●●に行ったんだね!どうだった?
部下:子どもが「▲▲ができてよかった!」と大喜びで。子どもが楽しんでいる姿を見ることができました。
上司:<価値観を探る質問>それはよかった。他にはどんなときが楽しい?
部下:家族でご飯を食べたり、のんびりしたりしている時間です。
質問②:「最近、何か困っていることはない?」
通常の「報・連・相」では、「業務に直結する緊急の事柄について話をする」ということも多いでしょう。しかし、部下は「緊急性は低いけれど、実は重要な課題」を抱えていることもあります。1on1では、そうした部下の抱える悩み・課題を聞き出す質問をすることが大切です。
会話例
上司:<課題を聞き出すための質問>最近、何か困っていることはない?
部下:新入社員Aさんへの業務の教え方が正しいのかわからず、悩んでいます…。
上司:<詳細を確認する質問>どの辺に不安を感じているの?
部下:人に何かを教えるのは、私にとって初めての経験です。自問自答しながらAさんに教えていますが、今の教え方でAさんがちゃんと理解できるのか、自信がないんです。
質問③:「どうして成功/失敗したと思う?成功/失敗から何を得たの?」
業務を進めていくと、誰でも何かに成功したり、逆に失敗してしまったりということがあるでしょう。成功/失敗の事実だけでなく、成功/失敗の理由やそこから何を得たのかに気付いてもらうことで、部下の成長につなげることができます。
会話例
上司:<成功体験についての質問>最近、「うまくいったな」と思ったのはどんなこと?
部下:3社が競合した●●のコンペで、我が社を選んでいただけました!
上司:<成功の理由についての質問>頑張ったね!どうしてうちの会社を選んでくれたんだと思う?
部下:B社が現在抱えている▲▲の課題を理解した上で、コンペに臨めたからだと思います。
上司:<成功から得たものについての質問>なるほど。今回、コンペに勝ったことで、今後の業務につながるヒントは見つかった?
部下:クライアントが抱える潜在的な課題を顕在化することが大切だと気付きました。
質問④:「どんなことにやりがいを感じる?」
部下が「どういったキャリアを目指しているのか」がわからなければ、キャリア形成をサポートするのは困難です。そのため、1on1では一人一人が将来どのように活躍したいのかを明確にする必要があります。まず「どんなことにやりがいを感じているのか」を聞き、そこから徐々に話を掘り下げましょう。
会話例
上司:<仕事のやりがいについての質問>仕事では、どんなことにやりがいを感じている?
部下:自分の考えた企画が成功したときに、やりがいを感じます!
上司:<大切にしていることについての質問>なるほど。新しい企画に携わるときは、どんなことを大切にしている?
部下:そうですね。クライアントの希望をいかに引き出し、それに合った企画を考えることでしょうか。
上司:<今後のキャリアについての質問>さすがだね。そういう経験を、今後どういう業務に活かしていきたいかな?
部下:要望を引き出すのが得意なので、個人のお客さまに関わる仕事にも挑戦してみたいです。
【無料ダウンロード】1on1シートの活用
確認事項や話した内容などを記録する「1on1シート」を用意しておくと、より1on1が実施しやすくなります。1on1シートに記入した方がよい項目を簡単にご紹介します。
項目①1on1の記録
本人の中長期目標をベースに、毎回の1on1のテーマや実際に話した内容などを記録します。次回に向けたToDoが見つかった場合は併せて記入し、進捗状況も管理しましょう。
項目②キャリア形成
これまで社内でどのような業務を担当してきたか、1on1を通じてわかった部下の「特性」や「キャリアビジョン」を記録します。1on1記録を付けた後に、キャリアに関する情報だけを整理し直すことで、本人のキャリア形成につなげることができます。
※このほかにも、部下の基本情報や日ごろの様子をメモしていくのも有効です。フィードバックが必要な内容は、次回の1on1の際に伝えるようにしましょう。
1on1で話すことがない要因
1on1では、「話すことがない」という状況がしばしば発生します。1on1でこうした状況に陥る原因として、どのようなことが考えられるのでしょうか。1on1で話すことがない要因について、上司側・部下側それぞれの視点で解説します。
上司側の要因
上司側が1on1で話すことがない状態というと、次のような状況が想定されます。
●会話のスキルが低く、思うように相手の話を引き出せない
●普段から部下との会話が少なく、適当な話題が思いつかない
●そもそも部下とカジュアルな会話をするのに抵抗がある など
これらの状況から、上司側の要因として、会話のスキル不足や部下とのコミュニケーション不足、1on1に対するモチベーションの低さが考えられます。それぞれ異なるアプローチで対策を講じる必要がありますが、例えば1on1の意義・目的を確認したり、傾聴や質問力などマネジメントスキルの向上を図ったり、上司を対象とした研修を実施したりするとよいでしょう。
部下側の要因
一方、部下側が1on1で話すことがない状態というと、次のような状況が考えられます。
●上司に心を開いておらず、悩みを打ち明けられない
●毎回違う話をしなければならないと思い、ネタ切れ状態になっている
●そもそも自分の話をするのが苦手 など
部下側の要因としても、1on1に対するモチベーションの低さが伺えます。加えて、上司との信頼関係が構築できていないことも大きな要因の一つです。上司と部下という立場の違い(上下関係)があるため、心理的安全性が確保されていない状態では、自分の状況を話すことに抵抗を感じたり、話したいことがあっても思うように話せなかったりするでしょう。
1on1で話すことがないと感じた際には、自身の会話スキルや双方の1on1へのモチベーション、上司と部下との信頼関係に問題がないかをまず確認しましょう。
1on1を意味のある場にするために意識すべきこと
1on1を意味のある場にするためには、工夫が必要です。1on1を実施する際に意識すべき3つのポイントを見ていきましょう。
話すテーマは事前に決定しておく
1on1を意味のある場にするために、話すテーマは事前に決定しておくことが望ましいです。1on1の目的やテーマ(話題)が不明確だと、部下は何を話せばよいかわからないという事態になってしまいます。そうなると、部下は「この時間を使って別の仕事ができるのに」と集中できなくなり、1on1の時間が無駄なものと感じてしまうでしょう。
「最近仕事で困っていること」や「サポートしてほしいこと」など、1on1の目的やアジェンダを事前に決定し、部下に共有しておくことが重要です。
上司の話よりも部下の話を引き出すことが重要
1on1では上司の話よりも部下の話を引き出すことが重要です。上司の考えやアドバイスが話の中心になってしまうと、一方的に言葉を浴びせられた部下は内省する機会を失い、成長につながりません。まずは部下の話をしっかり傾聴しましょう。その上でフィードバックしたり、気づきを得られるような質問を投げかけたりするなど、部下の内にあるものを引き出せるようにファシリテーションしていく必要があります。
部下の話にしっかり耳を傾けることで、日頃どのようなことを考えているのか、どのような思いで業務に臨んでいるのかが把握できるようになるでしょう。
普段から部下と信頼関係を築く
1on1の成功の鍵は、「上司と部下との良好な信頼関係の構築」にあると言っても過言ではありません。信頼関係を築けていると、部下は1on1で要望や悩みを正直に話してくれるでしょう。1on1という短い時間だけでは信頼関係を築くのは難しいため、普段からコミュニケーションを取り、部下が話しやすい職場環境を整えることが大切です。
加えて、上司は部下の信頼を得るために「日頃から、部下の意見を尊重する」「よほどの理由がない限り、一度決定した1on1の日時を一方的に変更しない」など、行動でも示せるとよいでしょう。
まとめ
多くの企業で導入されている1on1ですが、場合によっては上司・部下ともに「話すことがない」状態になる可能性があります。1on1は上司と部下の信頼関係があってこそ成立するため、普段からコミュニケーションを取り、部下の話にしっかり耳を傾けることが重要です。
また、部下の1on1へのモチベーションを高められるよう、事前に話すテーマ(話題)を決定し、部下に共有した上で実施しましょう。
今回の記事でご紹介しているテーマ(話題)例や、部下の本音を引き出す質問例などを参考に1on1を実施し、「部下の成長促進」「組織・チーム力の向上」「離職防止(モチベーション向上)」につなげてみてはいかがでしょうか。
(制作協力/株式会社はたらクリエイト、編集/d’s JOURNAL編集部)
【人事・リーダー必携】より効果を発揮するための「1on1シート」
資料をダウンロード