博士と企業のマッチングイベント「赤い糸会」。15年の変化が物語る、博士人材に対する企業ニーズの高まり

博士課程を修了し、努力の末に学位を取得した。ところが大学教員などアカデミアポストには限りがあるため、その先のキャリアパスを描けない。才能ある博士たちが、そんな不遇をかこっている国は、世界でも日本だけです。欧米でドクターと言えば、明らかに一目置かれる存在であり、研究職に就くための前提条件です。日本企業でもグローバル展開の進行につれ、博士人材の重要性がようやく認識されるようになってきました。
その変化を象徴するのが、博士人材と企業のマッチングイベント『赤い糸会』の盛況ぶりです。北海道大学在籍中から企画を推進してきた樋口直樹特任教授(現・新潟大学経営戦略本部。)(以下、樋口氏)によれば、イベント参加を希望する企業は増える一方であり、博士たちの意識も大きく変わってきたとのこと。博士号を取ればアカポスに進むのが当たり前だった時代に、あえて民間企業を選んで活躍してきた、樋口氏のキャリアそのものも博士人材の価値を示唆しています。
博士人材と企業を結ぶ『赤い糸会』
樋口氏:『赤い糸会』は、博士人材と企業のマッチングを図るイベントで、2006年に北大でスタートしました。この手のイベントを全国の国立大学で行う所は、当時はまだ北大以外にありませんでした。あふれ返っていたポストドクターたちに、何とか将来の希望を見出してあげたい。そんな思いからスタートした企画です。
樋口氏:あの計画の結果、1985年には約7万人だった大学院生の数が、2005年には24万人にまで膨れ上がっています。博士課程に在籍する学生数も85年の2万人強から7万5千人にまで増えました。博士たちの就職先となる大学の数も増えてはいたものの、理工系アカポスが大幅に増加したわけではなく、多くが行き場を失っていたのです。計画を主導したのは国ですから、中央官庁で博士たちを採用してくれるのかと思えば、そんなそぶりは一向に見せません。出口もつくらずに一体国は何をやっているのか。こんな状況を黙って見過ごすことはできないと立ち上げられたのが『赤い糸会』だったのです。
樋口氏:私が関わりだしたのは2010年からですが、当時は年2回の開催で、企業よりも学生の参加者の方が少ないぐらいでした。なにしろ研究室の教授たちが「そんなイベントに参加する暇があるなら、少しでも実験を進めなさい」という時代ですから、学生も参加しづらかったと思います。それが徐々に変わってきたのは、『赤い糸会』から企業に就職した先輩たちの多くが幸せになっていると、後輩たちに知れ渡るようになってきたからです。その結果、今では全国の12大学がコンソーシアムを形成して参加するようになり、北大でのイベントは年4回の開催です。参加企業数は1回当たり上限の20社がすぐに埋まり、学生も毎回50人が参加しています。
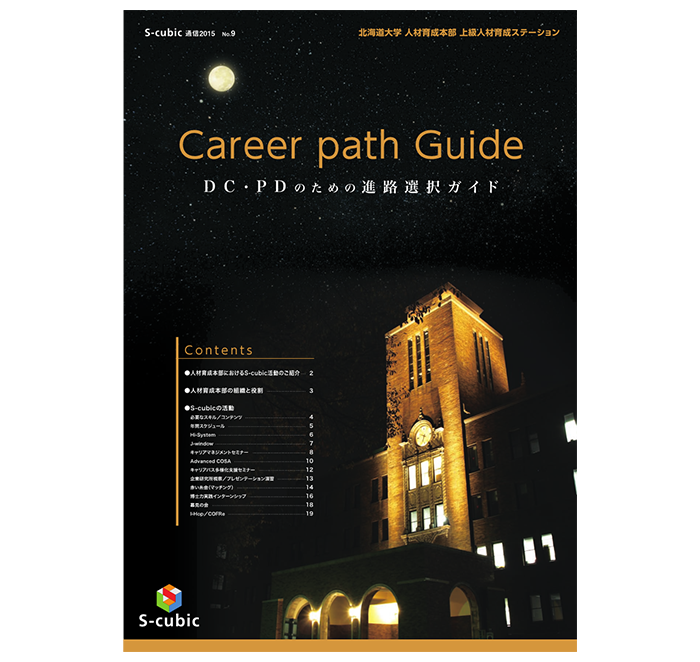
大きく変わってきた企業のスタンス
樋口氏:何より大きいのは、日本企業のグローバル化が進んだことでしょう。まず通年採用や中長期インターンシップが日本でも導入されるようになりました。海外では、研究職を名乗りながら博士号を持っていないような人は相手にされません。この厳然たる現実に、多くの日本企業が気づき始めたのです。その結果、グローバル企業ほど博士採用に乗り出すようになってきました。
樋口氏:たとえば海外企業と提携などの話をするシーンを想定してください。日本企業でいくら部長だとか取締役だと肩書がついていても、名刺にPh.D.と記されていなければ、議論に参加できないのです。研究に携わる人間が一つの土俵で話をするためには、同じレベルの知的訓練を受けていない限り話が噛み合うはずがない。だから「研究職は博士」が世界の常識なのです。となるとグローバル展開を推進する日本企業としては、博士を抱えていなければ土俵にさえ上がれない。メンバーシップ型雇用を続けてきた日本企業が、欧米中のジョブ型雇用とのギャップに気づき、そこに危機感を覚えたのでしょう。
樋口氏:もちろん、そうした企業も多く参加していますが、化学や電気、さらにはいわゆる重厚長大系の参加も増えています。某総合電機メーカーなどでは、事業部管轄の研究所ならマスター採用でもよいけれど、中央研究所に採用するのはドクターだけで十分といった雰囲気もあるようです。『赤い糸会』を15年続けてきた結果、立ち上げ当初に就職したドクターたちが40代に入り管理職に就き始めています。その結果、企業サイドにもドクターの上司が増えつつあります。一方ではドクターの進路はアカポスしかない、などと考える学生も減ってきました。研究職としての就職が、もはやごく普通の選択肢となっているのではないでしょうか。

ドクターとマスターの決定的な違い
樋口氏:非常に視野が狭く、深掘りはいくらでもできるけれど、人の話など聴くことなく、一人で研究に没頭している。彼らには、そんな都市伝説のようなイメージもあるようですね。北大の数学部門の就職担当スタッフと話したときも「純粋数学の研究者を企業が欲しがるだろうか?」などと言っていましたが、実態はまったく異なります。最近の『赤い糸会』では、数学系のドクターが1人で複数社の内定を取っています。なぜだか、おわかりになりますか。
樋口氏:AIやディープラーニング、あるいはデータサイエンス、さらには最先端の金融工学などでも必須となるロジカルな思考力を持っているのは誰でしょうか。カリキュラムとしては工学部の情報系が最も近いのでしょうが、そうした学生たちは引く手あまたでたいてい修士卒で就職してしまいます。そこで純粋数学や理論物理の博士たちを採用してみると、これが想像以上に適した人材だったのです。少し訓練すれば、期待をはるかに超える成果を出してくれる。そんな話が浸透してきたからでしょう、『赤い糸会』でも数学や理論物理出身の学生の参加が増えています。
樋口氏:時間にすれば3年ですが、その間に受ける訓練の質が「ケタ違い」なのです。同じ大学院で学ぶとは言え、修士の研究テーマは教授から与えられるケースが多いでしょう。ところが、ドクターは自力での課題発見がスタートです。テーマを与えられるのか、それとも自ら見つけるのか。この違いは決定的です。現状に対する問題点を自ら見つけて、その解決法を考え出す。これこそが企業が最も求めている能力でしょう。
常に成果を出し続けてきた企業人として
樋口氏:私が大学院を修了したのは1981年、ポスドク一万人計画の始まるずっと前のことでした。当時はまだアカポスに余裕があったので、努力すればたいていは大学に残れた時代です。ただ私は少し変わり者だったようで、学部は阪大、修士は北大、そして博士ではまた阪大に戻っています。そして博士号を取ってもアカポスに行きたいと思えなかったので、自分で就職先を探してサントリーに入りました。私が所属していた研究室では、初めて民間企業に就職したコース博士となったのです。
樋口氏:それはまったく考えていませんでした。専門は物理化学でしたから、企業の業務内容とはあまり関係がありません。とは言え一応、研究職として採用されたので、何でもやってやろうぐらいの意気込みでした。当時は景気も良かったので好きにやらせてもらったのですが、ある時期から的を絞って事業化に取り組むことになり、私は健康食品事業の配属となりました。といっても今のサントリーの健康食品事業ではなく、素材開発です。そして開発した素材を食品メーカーなどに売り込むBtoBビジネスの担当となります。
樋口氏:とは言え、技術屋としてみれば、優れた技術が売れるのはわかりやすい話です。ただ素材ビジネスは利益率が高いものの、なにしろ売上の額が小さ過ぎました。サントリーぐらいの規模になると、年商1億ぐらいでは何をやっているんだという話になるわけです。そこで素材を生かしてBtoCの製品を開発し、その販売に取り組みました。試行錯誤を繰り返す中で通信販売に行き着き、それが今では1000億近いビジネスに育っています。
樋口氏:健康食品事業の部長、知的財産部のプロジェクトリーダーを経て部長を任され、その次は水科学研究所の研究所長を任されました。第三者から見れば多彩なキャリアなのかもしれませんが、本人としては特別なことをやってきた意識はないのです。ただ、いつも何が問題なのかを突き詰めて考えることと、その解決策を見出してはトライしてみる。その繰り返しでした。
樋口氏:結果的にはそう言えるのかもしれませんが、やっていたときにはそんな意識はありませんでした。水科学研究所の所長時代に九州大学と共同研究を始めて大学との接点ができ、その後「あんた、面白いキャリアだね。その経歴を博士人材のキャリア開発支援に活かしてほしい」と北海道大学に誘われたのです。
視野は可能な限り広く、博士の未来は海外にも開けている
樋口氏:『赤い糸会』が発足してから15年が経過し、先輩博士たちの活躍ぶりが広く知られるようになってきました。さらに企業を取り巻く環境も大きく変わってきたため、博士を必要とする企業はこれからも増えていくでしょう。これまでの日本が特殊だっただけで、博士号を取得した人たちは、自分に自信を持ってほしい。
樋口氏:博士号の価値は世界共通であり、就職先を日本国内に限る必要などまったくないわけです。むしろ、海外の方が日本の博士採用に熱心なケースもあるのではないでしょうか。日本の大学も外国人博士人材を留学生として受け入れるばかりでなく、日本人博士人材を海外に押し出す施策が必要です。視野を広げる意味では、博士課程に進む段階で海外の研究室に出るのも有意義な選択肢だと思います。自ら積極的に動けば、見えてくる世界が変わってくるでしょう。
樋口氏:現役人生80年がこれからは当たり前になるとしましょう。すると27歳で博士号を取ってから、まだ50年以上残っているわけです。5年間かけて博士号を取った人なら、別の専門分野でも5年ぐらいをかければ、博士を取れるぐらいのレベルに到達できるはずです。そのための訓練を博士課程で受けているのですから。自分の可能性を信じて、とんでもない仕事を、とてつもなく多く実現してほしい。そんな博士たちが、これからの日本を支えてくれるよう、心からエールを送ります。

取材後記
人材関係の企業取材、特にBtoBメーカーに話を聞くと、新規採用で博士の獲得に力を入れていると語る企業が増えています。その理由は、グローバル企業の海外展開のためだけではなく、博士人材の可能性に企業が気づき始めたからでしょう。博士が本来もつ異才ぶりを、サントリーで遺憾なく発揮されたのが今回お話を伺った樋口氏です。そして、そんな樋口氏だからこそ、博士の力を活かしてほしいと「赤い糸会」の運営に尽力されたのだと思います。その「赤い糸会」は現在、国公立私立大学合わせて12大学がコンソーシアムを形成して参加する組織となりました。博士たちの活躍の場がどんどん広がること、それが日本の希望につながるはずです。
取材・文/竹林 篤実、編集/竹林 篤実












