「働きがいのある会社」3年連続1位。経営陣も含めたメンバー同士がフィードバックして成長し合うコンカーの企業文化とは?

出張・経費管理クラウドの国内売上No.1を誇る株式会社コンカー。業界を牽引するリーダーであるとともに、「働きがいのある会社」ランキングで3年連続1位(従業員100〜999人部門)と、企業文化を重視する姿勢も注目されています。そのコンカーを率いるのが代表取締役社長を務める三村真宗氏。実は、企業文化重視の社風は起業当初の苦戦から導き出されたのだとか。働きがいに関する著書もある三村氏に、特徴的な経営姿勢の背景や狙い、今後の展望について、オンライン会議システムを通じて伺いました。
文化よりも、明日の数字を追い求めて苦戦した設立当初
三村氏:当社は米国シアトルに本社を置くConcur Technologies Incの日本法人として2010年に設立し、私は2011年に社長に就任しました。当初は、まったくといっていいほど企業文化について考えることができず、私はその失敗から学んでいきました。ゼロから組織をつくるときのセオリーはまずリーダーシップチームをつくることです。少数精鋭のチームでビジョンや戦略を固め、ゼロから1にする。そこからスタッフを増やし、1から10、10から20と大きくしていく。ところが、そのコアメンバーの採用から苦戦しました。さまざまな職種のコアメンバーの採用について、本社からことごとくストップがかかったんです。
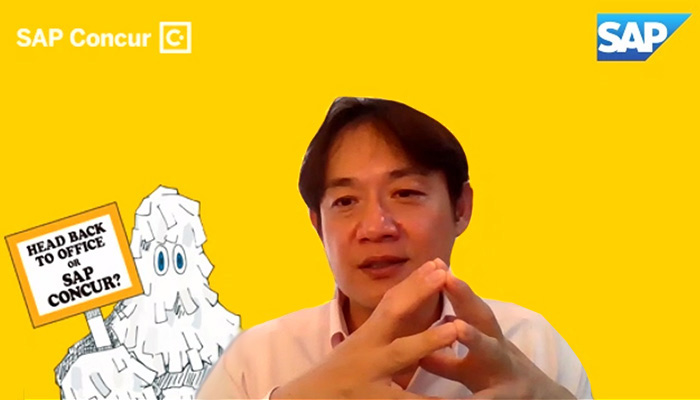
私は外資系ソフトウェア企業の社長としては珍しく、営業畑の出身ではありません。そこで、ぜひとも営業のトップとなる人物が欲しかった。しかし、本社から「社長であるあなたが営業も見るべきだ」と言われて却下されました。ほかにもマーケティングや、管理部門の責任者なども採用できず、営業は私がやって、管理部門はアシスタントがやるというような状況がしばらく続いたのです。
三村氏:当時本社では、日本市場に対して懐疑的な見方がありました。日本は品質に対して厳しい国であり、その要求水準に応えられるのか。また欧米との商習慣の違いもあり経費精算の分野はマーケットとして難しいのではないかと。本社による採用ストップにはそうした慎重さが背景にありました。
もっとも、たとえ本社の却下がなかったとしても採用自体が難しいという事情もありました。米国においてコンカーは、フォーチュン100に選ばれた企業のうち75%に採用されており、経費精算を中心とした間接業務クラウドサービスのデファクトスタンダードだと言えます。しかし、当時の日本では、知名度は全くと言っていいほどなく、募集をかけても応募が少なかったんです。そんなこともあって企業文化なんてことは考えていられない状況でした。
三村氏:外資系は結果を出さないとすぐにクビというイメージがあります。実際にはそんなこともないのですが、当時の私もそんなイメージを抱いていて、戦々恐々としていました。とにかく実績を出したいと焦っていましたね。文化なんてとりあえず横に置いて、明日の数字をつくってくれる人、今日、成果を出せる人という基準で人を採用していました。
内発的な動機づけのため、“働きがい”という目標を定める
三村氏:なかなかうまくいかなかったので、出直そうということで社員を集めてオフサイトミーティングを行いました。そこで私は2つのビジョンを掲げました。1つは、日本市場を国別でアメリカに次ぐ2番目のマーケットにすること。これは外的かつ定量的な目標です。これだけだと「お腹に力が入らないな」と思ったので、もう1つ目標を掲げました。それが、業務アプリケーション業界で働きがいナンバーワンになるということです。
外的・定量的な目標はあくまで結果論でしかない。そこに向かっていくためには内発的な動機が必要です。内面的かつ定性的な目標は何だろうと考えたときに、“働きがい”というキーワードが出てきたのです。
三村氏:はい。この目標を掲げた当時は、そういったランキングがあることを知りませんでしたが、働きがいを高めれば結果として事業は成功するという仮説を立てて取り組みました。振り返ると、9年間にわたる壮大な実験だったと思いますが、成功した今では、この仮説が正しかったという確証を得ています。ですから、ほかの企業、経営者にも、もっと働きがいに目を向けてほしいと思い、講演やほかの企業に招かれてお話するなどの活動もしています。
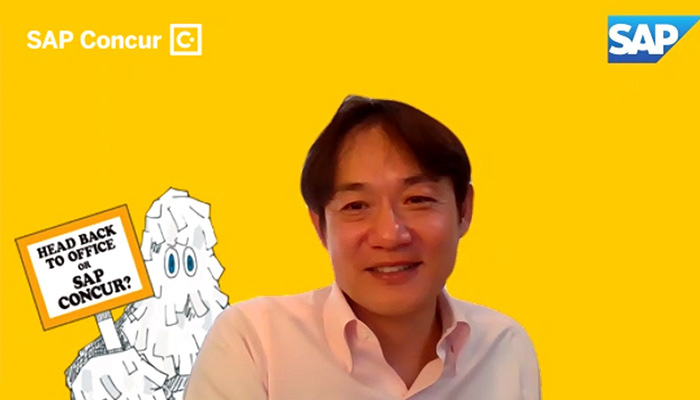
三村氏:本質的に、業績を伸ばすために必要なことは、社員が内発的動機から働きたいと思えることです。このことは外資も日本企業も関係ありません。最近、日本の会社にあまり元気がないように見えるのは、このあたりに原因があるのではないでしょうか。
松下幸之助さんに代表されるように、昔の日本の経営者の多くは家族主義という観点を持っていて、そのことが日本的経営の特徴と言われました。それが次第に失われていった。しかし一方で日本のビジネスパーソンは昔と同じように、あまり会社を辞めません。今でも“勤め上げる”という感覚を持っている人は少なくないのではないでしょうか。そのことが経営側の甘えを生んでいると思います。俗っぽい言い方をするなら“釣った魚に餌はやらない”というような状況になっているのではと思います。社員の忠誠心に甘えているのです。
三村氏:いかに優秀な社員を採用し、定着させるかが重要です。経営資源を“ヒト・モノ・カネ”と言いますが、外資系企業は「モノ」をつくっていません。「カネ」も大抵は困っていません。資金が足らなくなるような事業なら本社が融資するなり撤退するなりします。ということは、外資系の日本法人の社長は「モノ」も「カネ」のレバーも握っていません。自由になるレバーは「ヒト」だけです。「モノ」や「カネ」の部分で創造力を加速できない分、「ヒト」の面に徹底的に注力する。つまり、外資系のトップは働きがいのある環境を整え、優秀な社員を採用し、定着させなければならないのです。

三村氏:多様性や個人の価値観は最大限尊重すべきだと思います。しかし、絶対に譲ってはいけない部分というのはあります。それは、社会で言えば基本的人権といったような憲法で定められた部分であり、私たちの会社においてのそれは「Concur Japan Belief – 私たちの信念」です。社員の価値観は尊重しますが、社員にもConcur Japan Beliefを尊重してもらうことでバランスを取っています。
連帯感を高めるフィードバックの仕組みと企業文化の共有
三村氏:毎年必ず行っています。オフィスを離れて、みんなで1日、会社の未来を語らい合うという機会は非常に大切です。現在、社員数は300人近くおりますが、今も全社員が集まって実施しています。今年は7月に行いますが、コロナウイルス感染拡大防止の影響もありますのでオンラインでの開催を予定しています。どのスタッフも日々の仕事で忙しいですが、一度仕事の手を止めて、会社の将来のことや、普段だったら我慢して溜め込んでしまっているような話題についてもみんなで議論する。オンライン開催になったとしてもそういう1日は必要です。
三村氏:社員の働きがいにはさまざまな観点がありますが、1つは成長できることだと思います。成長は会社から与えられるものや仕事を通じてだけではなくて、社員同士がお互いに刺激しあって成長する、高め合うという部分もあるはず。そのためには何か問題意識があったら指摘する、すなわちオープンにフィードバックし合うことが必要です。
三村氏:フィードバックを可能にするにはまず雰囲気・文化づくりが必要ですね。「フィードバックしてもいいんだ」という環境をつくる。問題というのは裏を返せば、それを指摘された人にとって成長の機会なのです。ですから、問題に気づいているのに、それを相手に伝えないことに対して罪悪感を持つくらいになってほしい。フィードバックされる側は、相手が成長を願って言ってくれていることを理解して心を開くべきです。
三村氏:フィードバックについてはオフサイトミーティングなどでもよく話しています。また、私が講師になって、新入社員向けのフィードバック講習を実施しています。先ほど説明したのは精神論ですが、もちろん、フィードバックをするときには手順を踏むこと、すなわちプロトコルが重要です。まず、“フィードバックしていいですか?”と宣言してから会話を始める。第三者がいる前ではしない。事実と人間性を分けて話す。改善策を相手に考えてもらう。そういった、さまざまな実践的方法論があります。プロトコルを社員全員が共有することで会話が噛み合ってくる。指摘した問題の内容が正しかったとしても伝え方を間違うとフィードバックにはならないんです。
三村氏:毎年、アンケートでフィードバックの実行状況をモニタリングしています。質問は4つ。「上司からフィードバックを受けていますか」「上司にフィードバックしていますか」「同僚からフィードバックがありますか」「同僚にフィードバックしていますか」です。現状で、上司から部下へのフィードバック率が約75%。同僚同士が約60%。これはまだ低いと思いますが、上司へのフィードバック率がおよそ40%あります。これは他社ではあり得ないほど高い数字だと考えています。

部下から上司へのフィードバックは心理的安全性の保証がないとできません。当社では管理職に対して、部下からのフィードバックを求めるようにガイドしています。年次評価のセッションがあるときには、上司から部下にフィードバックがないか聞いてもらうようにしていますし、私も本部長とその部下、合わせて50人くらいと話す機会がありますが、全員に「いい機会だから私や会社へのフィードバックをください」と必ず聞きます。
三村氏:そうです。権限委譲されていないと仕事に“やらされている感”を抱きがちですし、成功したら「言われた通りにやったから」と感じてしまいます。失敗しても「言われた通りにやっただけ」という言い訳ができてしまう。ですから権限委譲は進めるべきです。ただ、注意しなければならないのは、権限移譲は視座を高めることと一対だということです。それなしでは、あらぬ方向に突っ走ってしまう危険性があります。
会社のビジョンや戦略、課題を、きちんと社員と共有する。まず、ここが重要です。そうして現場の視座を経営陣に近づけた上で権限移譲すると、各自が会社の方向に沿った形で動く。お客さまの実情やお悩み、課題を最もリアルに知っているのは、経営者ではなく現場の社員です。経営者が大きな方向性は示せても、一定以上のきめ細かなサービスを打ち出すことはできません。そこは現場で仕事に対峙している一人一人が、最適な判断をしなければならないのです。
三村氏:文化的に適合した人のみを採用すると、どうしても採用率は下がってしまうため、現在、当社の採用率は3%ほどです。そうすると必要な人材を採るためには、母数を増やす努力も必要になってきます。そのために、エージェント向けの戦略説明会を年2回設けるなどの取り組みをしています。エージェント向けの説明会とは、エージェントにもコンカーの経営者目線になってもらうという取り組みです。これにはコンカーのビジョンや戦略を、エージェント自らの言葉で外部の応募者にいきいきと話せるようになってもらいたいという狙いがあります。
当社では「コンカーを職場に選ぶ理由」という173ページの資料もインターネット上に公開しています。

(スライド『コンカーを職場に選ぶ理由」 https://www.slideshare.net/ConcurJapan/201812-124325968 )
これは、言ってみれば外部の応募者に向けて私の想いを込めたラブレターのようなもの。ここには良いことも悪いことも実態を正直に書いています。なんだか狭き門のような言い方になってしまいましたが……。もし、転職希望者がこれを読んでいたら、構えずにどんどん応募してほしいですね。
リモートワーク前提の採用文化を実現し、事業で大きな社会的要請に応える
三村氏:これについては、2つ観点があります。1つは社員の働き方という観点です。私は以前、在宅勤務に慎重な考えを持っていました。それは社員の絆が、日々同じ場所で働いて、同じ空気を吸うことに多くを負っていると思っていたからです。ですから、今回の在宅勤務が始まったときに、私たちの文化が維持できるかのチャレンジになると感じました。
そのため、オンライン会議にて朝礼のようなミーティングをしたり、社歴の浅い社員とは私が個別に1on1ミーティングをしたり。またビデオ会議システムを介して社員とランチをしたり、お茶をしたり。これは“みむティー”と呼んでいて、その名の通り、私とお茶をする感覚のくだけた雰囲気のものです。
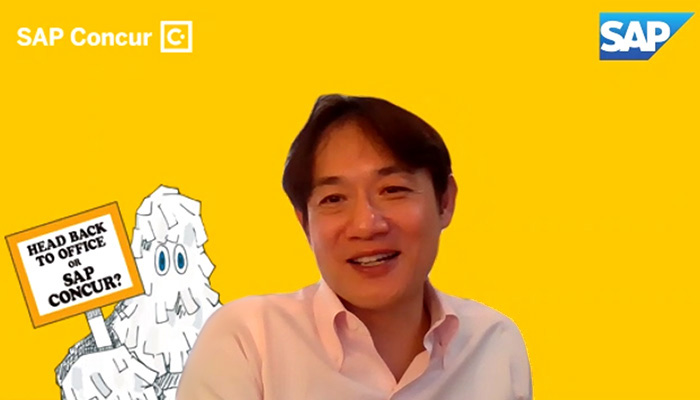
こうして、さまざまな工夫をすることによって在宅であっても社員の絆は維持できるというのが、ここ2か月の私の実感です。この結果を踏まえ、今後の出社方針については今までの慎重論から一気に舵を振って、「在宅か出社かは会社が定めず、社員個人に委ねる」という方針としました。働きがいとは何なのかということを、リモートワークを前提にして突き詰めていきたい。
そして、それに伴って、地方支社の採用も各県内だけにとどまらず、より広い地域で募集していきます。ゆくゆくは地域にまったく関係なく採用できるようにしたいですね。例えば東京でIT関連の仕事をしていたけれど、配偶者の転勤に伴って地方に移住したといった方も採用できるので、人材の有効活用になります。採用のための新たな文化づくりをしています。
三村氏:私のTwitterアカウントで在宅インターン募集についてツイートをしたら、それが学生さんを中心に拡散されて、135名もの応募があったんです。
大学生の皆さんへ
「在宅でインターンは無理」と思い込んでいせんか?
こんな状況だからこそConcurは在宅インターンも募集します
・SaaSビジネスを学べる
・全社員会議等で経営戦略を聞ける
・働きがい日本一と評された文化を体感
・戦力とみなし時給1500円✨事態が収束した暁にオフィスで会える https://t.co/3buQyaHuZ7
— 三村 真宗|Masa Mimura (@Masa_Mimura) April 23, 2020
採用におけるTwitterの訴求力に驚かされました。この在宅の状況を逆手に取って、ソーシャルメディアも活用しながら、新しい採用の形を見いだしていきたいと思っています。他社に先駆けて、私たちがそのお手本になれればと思っています。
三村氏:事業面です。今回の自粛要請時に、ハンコを押すためだけに出社しなければならない“ハンコ出社”が問題になりました。しかし、実はハンコ出社をしなければならない人はそれほど多くはないんです。もっと深刻なのが、経費精算のために出社する“領収書出社”。経費精算は、実務でハンコを使う立場でない社員でも誰もが必要ですから。これは「リモートワークのラストワンマイル」だと言えます。
そして、これこそが私たちコンカーがお役に立てる場面です。私たちは、経済産業省をはじめとした関連省庁に対して、制度改正に向けた働きかけをしてきた実績があります。現在は、QRコードや交通系ICカードといった電子決済における領収書をデジタルデータで代用できるというところまで実現しました。将来的には、電子決済で経費を払ったらそのデータが当社のシステムに自動連携され、そのまま経費が振り込まれるような、経費精算業務自体が要らなくなる世界を構築しようとしています。ここには大きな社会的ニーズがあると思っていますので、会社としてぜひともしっかり応えていきたいですね。
取材後記
社員の働きがい重視を標榜する企業は少なくないと思います。しかし、三村氏のように、働きがいとは何かを突き詰めて考え、それを実現するための「高め合う文化」という社風づくりに、さまざまな具体的な対策を持って取り組んでいるリーダーは逆に多くはないとも感じます。
問題を指摘するフィードバックは大切ですが、それを実行するには意識の共有と、手順を踏むことが重要になってきます。その中での同社の実践的な企業文化創造の方法論は、非常に参考になるのではないでしょうか。
取材・文/宇田川しい 編集/森 英信(アンジー)・d’s JOUNAL編集部












