「こんなマネジメントは失敗する」。反面教師に学ぶ、次世代マネジメント術4選
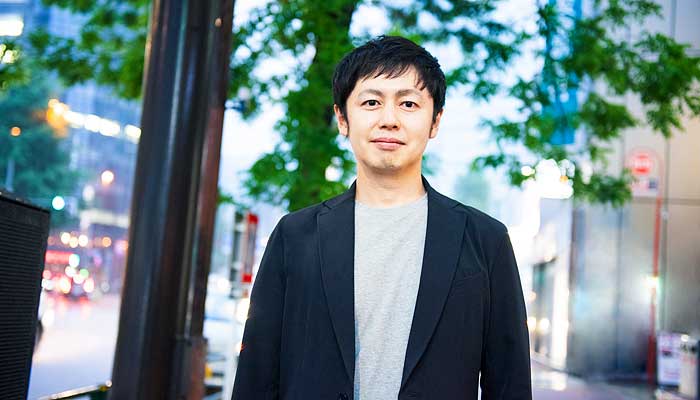
新年度になって約2カ月。春から初めて管理職になった人、異動して新たな組織の中で上司になった人にとって、組織のマネジメントに悩みを持ち始める時期ではないでしょうか。
システム開発を行う株式会社アクシアは、2006年の設立以降、長時間労働が常態化していましたが、2012年に残業ゼロを断行。長時間労働が多いイメージのIT業界で、「残業ゼロ」の組織づくりに成功しました。
今回は、同社代表取締役社長の米村歩氏にインタビュー。ホワイト企業への改革、残業ゼロの成功に至るまでには、さまざまなトライ&エラーがありました。その過程で米村氏が得た、マネジメントの教訓やノウハウを、上司が陥りやすい失敗事例とともにご紹介します。
【教訓1】結果につながらない指摘は、ただの自己満足でしかない
──米村さんは、ブログで「相手の間違いを指摘する難しさ」について書かれていますが、これまでの経験を通じて学ばれたマネジメント面の教訓をお聞かせください。

米村氏:間違ったことが行われているとき、「波風を立ててはいけない」と見て見ぬふりをすれば被害が拡大するばかりです。たとえば「遠慮」と「配慮」の違いについて。間違いを指摘するのに「遠慮」があってはいけません。ただし、その際に「配慮」がなくていいかと言えばそうではない。相手に対して敬意を払わず、人格をおとしめるような言い方をするのは、コミュニケーションを拒否しているのと同じことです。かつては私も「正しいことをストレートに言って何が悪い」と思っていました。「遠慮」と「配慮」の区別がついていなかったのです。
伝える「内容」が正しければ、「言い方」はどうでもいいと思う人もいるでしょう。しかし、人に何かを伝えるときに一番重要なのは「結果」です。自分の発した言葉によって相手の行動が改善され、望んだ結果が得られなければ、自己満足だけの言いっぱなしで終わってしまいます。
上司が部下の間違いを指摘する場合も、「内容」とともに「言い方」にも気を付けるべきで、もし部下をこき下ろすような言い方しかできていないなら、いじめをしているのと変わりありません。それでは部下のモチベーションを下げるだけの「結果」しか得られないでしょう。
【教訓2】上司が部下に寄り添う1on1は、必ずしも有効ではない
──貴社では1on1ミーティングを採用されていないというお話をお聞きしました。
米村氏:1on1を取り入れようと思った時期もありますが、当社の文化に合わないと判断し、見送りました。上司が部下に寄り添ってコミュニケーションを取る1on1を採用すると、当社における上司の役割から外れることになるからです。
当社では、「上司と部下は友達ではない」という考え方をしています。上司は感情面で部下に寄り添うのではなく、部下が成果を上げるための育成を第一義としてコーチングを行っています。その根底にあるのは、上司は全ての部下に対して公平に接するべきだという思想です。
よくある話ですが、部下と接する際に感情が入り込んでくると、どうしても「かわいい部下」「かわいくない部下」という区分けが発生してしまいます。すると、かわいい部下と飲みに行ったり食事に行ったりする機会が増えていきますので、連れて行ってもらえない部下は疎外感を持つようになります。実際、当社でも過去にそういうケースがあり、弊害が大きいと感じたんです。今は管理職が部下と個別に食事などに行くことを禁じ、チーム全体での食事会や飲み会だけに限るようにしています。
【教訓3】部下の仕事に口出しするのは、自分(上司)の指示があいまいだから
──部下を成長させるためには、どのような取り組みが必要でしょうか?
米村氏:教育もコーチングももちろん必要ですが、部下が成長したと明らかに実感できるのは、権限委譲がきちんとできたときです。「部下を育てるためには権限委譲が必要だ」という話はよく聞きますし、それを実践している企業も多いと思いますが、権限委譲が本当にできているかと言えばそうではない。当社も初めはそこを見誤りました。

ある仕事を部下に任せることにして、その仕事に関して権限委譲をしたはずなのに、実際には途中で「あれはどうなっている」「いやそれでは駄目だからこうやって」と上司が口出ししていたんですね。それでどうなるかというと、結局部下は上司の手足になっているだけで、自分の頭で考えることをやめてしまうため、成長することもできない。さらに、その仕事がうまくいかなかったとき、部下は上司に言われた通りにやっただけだからと考えるので、責任感を持つこともありません。
そういうプロセスが見えてきたので、当社では、長期にわたる仕事については何度か中間ポイントでチェックはするものの、上司は基本的に口出しせず、本人の裁量に任せるということを徹底しています。
──仕事のプランニングが間違っていたりすると、部下が途中で迷ってゴールにたどり着けないという危険性はありませんか?
米村氏:それを避けるために必要なのが、上司が最初に明確な指示と期待する成果の提示を行うことです。当社でも初期にはそれができていなくて、上司があいまいな指示をしたために部下が勘違いし、成果物が期待した内容とは全然違っていたというケースがありました。当社だけでなく、上司の指示の仕方が悪いためにトラブルになる事例は、多いのではないでしょうか。
的確な指示を最初に出すためには相当なスキルが必要ですが、当社では管理職の責務としてそのスキルを身に付け、部下に成果を出させ、成長させることを求めています。
──部下のモチベーションを高めるために、何か工夫されていることはありますか?
米村氏:以前はモチベーションを高めようとして、いろいろ言葉を掛けたりしたこともありますが、結論から言うと私には無理でした(笑)。ですので、少なくともやる気をそぐことだけはしないように心掛けています。途中で口出ししないというルールもその一つですし、副業をしたい人はしてもいいということにしています。
【教訓4】上司は組織図を意識したマネジメントを行うべき
──マネジメント層の育成に関して、心掛けていることはありますか?
米村氏:先ほどお話しした、部下に対して明確な指示を出すことのほかに、組織図を意識するように伝えています。組織図を意識するというのは、要するに指示系統を明確にして、直属の上司以外が勝手に部下に指示をしないようにするということです。上司の上役などが直接指示を出してしまうと、部下はどちらの言うことを聞けばいいのかわからなくなります。特に、上司と上役の指示内容が食い違っていると最悪です。また、「上役が部下の面倒を見てくれるから任せておけばいい」という思考回路になり、直属の上司が責任を持たなくなってしまうという弊害もあったため、今は階層を飛び越えて指示を出すことを禁じています。
私は、「仕事の質が高い」状態とは、上司が部下に対して何を期待しているのかを明確に伝え、それに応えてくれたかどうかの評価をきちんとできる体制になっていることだと考えています。ところが、複数の上司がいて、それぞれ期待することが違うと、部下は何を目指してどう頑張ればいいのかわかりません。ですから当社では、部下にとって上司は常に一人という関係性をつくるように気を付けています。
──部下が仕事のことで悩んでいる場合は、どのように対処すればいいのでしょうか?
米村氏:部下から相談を受けたとき、上司の立場にある者は、まずその相談内容が部下の権限や裁量の範囲内で解決できるものかどうかを見極めることが必要です。そして、それが部下の権限・裁量の範囲を超えたものであれば、上司が対処策を考え、改めて部下に指示やコメントを出しますが、範囲内のものであれば指示は出さず、再度自分で考えて問題解決を図るように差し戻します。部下が悩んでいるときに、安易に手助けをするのではなく、自分で答えを探してもらうようにした方が本人の成長につながるのではないでしょうか。
【アクシア 残業ゼロの取り組み】業務の「見える化」「廃止」「自動化」「標準化」
──ここからは、貴社の残業ゼロの取り組みについて伺います。システムの受託開発業務というと、「長時間労働」というイメージを抱きがちですが、貴社ではどのようなきっかけで残業時間の削減に取り組まれたのですか?

米村氏:当社も他のIT企業と同じように長時間労働が常態化していたのですが、そういう状態のままだと離職率が高くなり、入社した社員がなかなか定着しないという問題が起きていました。そこで、2009年から業務効率化に取り組み始め、仕組みもいろいろつくったのですが、その後も残業が減らない状況が続いたんです。当社ビジネスの傾向として、金曜日に依頼が来て、「月曜日までに完成させてほしい」と言われるようなケースも多々ありました。その依頼に応えるために「どうしても間に合わなければ残業や休日出勤でこなせばいい」といった気持ちがまだ残っていたため、残業が減らない状況が続いたのだと思います。
そのため、一時は残業時間削減への取り組みに挫折しかけましたが、そんな折に、事業の要となっている社員から「もうこの労働環境に耐えられないので辞めさせてほしい」という申し出を受けました。当時社員は10人ほどで、その社員に辞められたら仕事が本当に回らなくなってしまうので、何としてでも引き止めなければなりません。窮地に立たされ、背水の陣で「残業ゼロ」に挑むことになったのです。
──2012年に「残業ゼロ」を実現されていますが、どのような手法を用いられたのですか?
米村氏:「業務の見える化」「業務の廃止」「業務の自動化」「業務の標準化」の4施策に取り組みました。
「業務の見える化」では、タスク管理システムを作り、そこに社員が日々の進捗状況を入力することでタスクの進捗率やスケジュールが一目でわかり、いつまでに誰が何をすればいいのかを把握できるようにしました。
情報が見える化されると、今まで慣習的にやっていた業務の中で、実際はやらなくてもいいものが見えてきます。それが2つ目の「業務の廃止」につながります。たとえば、当社では定例会議などで進捗確認をしていましたが、タスク管理システムを導入したことで、会議や会議のための資料作りも不要になったわけです。
3つ目の「業務の自動化」では、システムやプログラムを作って、自動化できることは徹底的に自動化しました。そして、自動化が難しい業務に関しては、4つ目の「業務の標準化」を実施。業務を属人化させず、複数の社員で肩代わりできるよう、マニュアルの整備や教育の充実を図ってきました。また、当社では「業務改善部」という部署も設けて、業務に非効率な部分があれば改善を行っています。
【アクシア 残業ゼロの取り組み】離職者が激減し、採用面にも好影響
──タイトな納期を要求する顧客に対して、残業で対応しなくていいようにスケジュールの再考をお願いするのは難しい面がありそうですね。
米村氏:契約締結の前に、当社のスタンスについてお客さまにご説明し、納得いただいた上で契約を結ぶようにしたので、無理なスケジュールで依頼を受けることはなくなりました。逆に、今お付き合いしているお客さまは、「アクシアさんは残業ゼロだから、この案件は今週中で大丈夫だよ」と言ってくれるんですよ。もちろん、最初は「無理を聞いてもらえないのは困る」ということで、成約につながらない案件もありましたが、当社ではそれは仕方ないというスタンスです。しかし、ほとんどのお客さまは、こちらがきちんと説明すると納得されて、「そういう取り組みは必要だね」と理解を示してくださいました。
──予想外に仕事が難航して、契約時に設定した納期を守るのが難しくなったような場合、社員に残業させずにどのように対応するのですか?
米村氏:確かに、仕事がいつもスケジュール通りに進むわけではありません。ですので、スケジュールを組むときは、想定外の事態が起きることを前提として、何重にもバッファを設けるようにしています。バッファは、個人のスケジュールの中で設けるのに加えて、チームとしてのバッファも入れておきますし、それでも足りないときは、業務改善部が応援に回りますので、納期に間に合わないということはまずありません。残業ゼロを始めた当初はバッファが少なかったので、最後は役員まで出動して作業をしていましたが、今では効率化も進み、役員の手を借りなくても済むようになっています。
──残業ゼロになったことで、どのようなメリットが生まれましたか?
米村氏:残業が常態化していたころは入社した人が半年で辞めていくような状態でしたが、残業ゼロになってから離職率が大幅に下がりましたね。ここ2年ほどは離職者ゼロで、最後に辞めた社員も自分のやりたいことのために転職しただけで、当社が嫌になって辞めたわけではありません。

また、採用面でも大きな変化がありました。以前は求人媒体を使って募集していたのですが、残業ゼロの評判が広まるにつれて広告費をかけなくても応募がありますし、当社にとって最適な人材が応募してくれるようになりました。残業ゼロの効果は絶大でしたね。
──ここまでのお話で、残業ゼロの取り組みはマネジメント層の役割が重要だと感じました。貴社では、マネジメントに求められる役割やスキル、評価基準などについて、明文化したものをつくっていますか?
米村氏:痛いところを突かれましたね(笑)。実はそこがまだできていなくて、各ポジションの役割や権限などを明文化することを今年の課題にしています。いろいろ教訓めいたことをお話ししてきましたが、当社もまだまだ発展途上ですので、今後も試行錯誤を重ねながら、さらなるレベルアップを図っていきたいです。
取材後記
業務効率化や残業削減、部下への権限委譲など、日本企業は生産性向上のためにさまざまな取り組みを行っているものの、その成果がなかなか見えてこないのも事実です。そこには、制度が形だけのものになっていたり、取り組みが中途半端だったりという要因があるようです。
米村さんもその壁に何度もぶつかりましたが、失敗を重ねる中で制度がうまく機能しない根本原因を探求し、改善を図っていきました。
その結果、独創的な業務体制やマネジメント手法が生み出され、アクシアは「残業ゼロ」を貫きながら業績を拡大し続けるホワイトIT企業に変貌しました。組織系統とフラットなマネジメントを重視するその姿勢は、働き方改革を成功に導く参考となるでしょう。
取材・文/森 英信(アンジー)、撮影/中澤真央、編集/野村英之(プレスラボ)・d’s JOURNAL編集部












