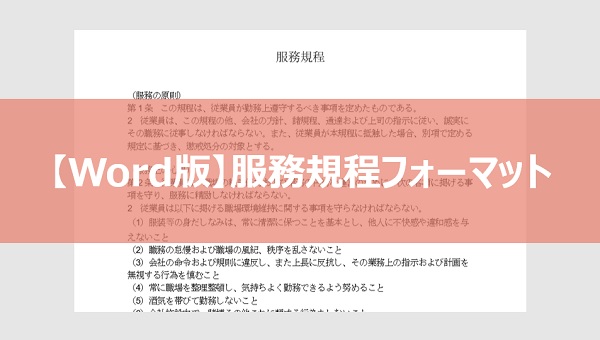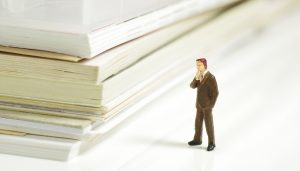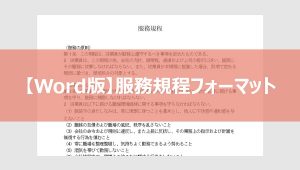服務規律とは?就業規則との違いや定めるべき内容と記載例を解説

企業内で守るべきルールや行動規範を記載した「服務規律」。「服務規律を見直したい」「服務規律に違反している従業員に対し、トラブルにならないよう正しく対処したい」といったケースもあるでしょう。そこで今回は、服務規律に記載しておくべき項目や、違反時の正しい対処について判例を交えてご紹介します。
下記より「服務規律サンプルフォーマット」を無料でダウンロードいただけます。自社規程の見直しやトラブル防止のために、ぜひご活用ください。
服務規律とは
服務規律とは、従業員が業務を遂行するに当たって遵守すべき義務やルールのことです。企業の一員としてはたらく上で取るべき行動を定めた行動規範といってもよいでしょう。
服務規律の規定は法律で義務付けられているものではありませんが、企業秩序を維持する上では必要不可欠な対応であり、作成しておくことが一般的です。
詳細な内容は企業ごとに異なりますが、多くの場合は以下の3つの内容に関する事項を記載することとなります。
| 内容 | 該当する例 |
|---|---|
| 労務提供そのものや、提供の在り方 | ●無断での職場離脱の禁止 ●パワハラ・セクハラの禁止 ●遅刻・早退・欠勤などの勤怠ルールの制定 |
| 企業施設の管理方法や職場環境の維持 | ●無許可での施設利用の禁止 ●喫煙の禁止 |
| 業務外活動に関する留意点 | ●秘密保持に関するルールの制定 ●副業(兼業)の可否 ●自社に対する誹謗中傷の禁止 |
なお、細かな記載内容は各企業の判断で決めて問題ありませんが、労働基準法や自社の就業規則に相反する内容となってはなりません。
就業規則との違い
就業規則は、従業員が守るべきルールのほか、労働条件などについても定めた規則です。賃金や労働時間など記載が必須である「絶対的必要記載事項」と、賞与や表彰など記載の義務がない「相対的必要記載事項」の2種類が記載内容に含まれます。
服務規律は、就業規則の一部として定められるのが一般的です。
つまり「服務規律だけが独立したルール」というより、就業規則の中に服務規律という章や項目が含まれているイメージです。
しかし就業規則に関しては、従業員を常時10人以上雇用する事業所であれば作成および労基署への提出が義務付けられています。
なお、服務規律を就業規則には含めず、「服務規程」や「誓約書」といった別の書類にまとめても問題ありません。
ただし、この場合でも法律上は就業規則の一部とみなされます。
そのため、変更するときには就業規則の改定と同じ手続きが必要です。
具体的には、「従業員代表から意見書をもらう」また「労働基準監督署へ就業規則の変更を届け出る」などの対応が求められます。
服務規律で定める内容と記載例
服務規律の内容は各企業である程度は自由に定められますが、一般的には以下のような事項を定めるケースが多いでしょう。
●労働者が遵守すべき事項
●身だしなみ
●勤務態度
●勤怠
●備品・施設利用
●秘密保持・個人情報の保護
●ハラスメント
●副業
●SNSの利用
●在宅勤務
●競業避止義務
それぞれの詳細を記載例とともに解説します。
労働者が遵守すべき事項
労働者が遵守すべき事項とは、企業の一員としての責任感や、業務を遂行する上での義務などをまとめたものです。
以下に示したとおり、これらは誠実労働義務・職務専念義務・企業秩序遵守義務の3種類に分けられます。
| 分類 | 該当する例 |
|---|---|
| 誠実労働義務 | ●会社の指揮命令に従って業務に従事すること ●会社の設備や物品を私的な目的で使用しないこと ●会社の機密情報を外部に持ち出さないこと |
| 職務専念義務 | ●勤務時間中は許可なく職場を離れないこと ●勤務時間中は私語や居眠りをしないこと |
| 企業秩序遵守義務 | ●ほかの従業員や会社を誹謗中傷しないこと ●ほかの従業員の業務を妨害しないこと |
上記は服務規律のベースとなる内容ともいえるため、自社の業務内容に照らし合わせて可能な限り詳細に定めることが大切です。
(参照:厚生労働省『第3章 服務規律』)
身だしなみ
髪色や服装は個人の自由で決められる事項ではありますが、業務に支障を来す場合は服務規律による制限が可能です。
身だしなみの服務規律の例としては以下が挙げられます。
●指定された制服を着用すること
●華美な衣類やアクセサリーを着用しないこと
●髪や爪、ひげなどを清潔に保ち、職場の衛生環境を損なわないこと
例えば接客業の場合は、お客さまに不快感を与えないように頭髪の色や服装を制限することが望ましいでしょう。
また、食品衛生に関連する業種であれば、身体を清潔に保つことは必須の対応だといえます。
勤務態度
職場での過ごし方や勤務中の私的な行動にルールがないと、社内の秩序が乱れてしまいます。そのため、勤務態度についても服務規律で明確に定めておく必要があります。
【勤務態度に関する服務規律の例】
●整理整頓を行い常に職場を清潔に保つこと
●勤務時間中に私用の端末(携帯電話やパソコン)を利用しないこと
●会社が指定した場所以外で喫煙しないこと
●勤務中に飲酒しないこと
業務の性質上、個人の携帯電話やパソコンを使う場面がある場合は「正当な理由がある場合に限る」といった条件を付けて、業務に影響を与えない範囲で規定を設けましょう。
勤怠
遅刻や早退、欠勤など勤怠に関する事項も、服務規律で定めることが一般的です。
勤怠に関する主なルールとしては、以下が挙げられます。
●遅刻や早退、欠勤、また勤務時間中に私用で外出する際は、原則として上長から事前に承認を得ること
●遅刻や早退、欠勤があった場合は、不就労分に対する賃金を控除すること
●傷病のために継続して〇日以上欠勤するときは、医師の診断書を提出すること
●遅刻や早退、欠勤を無断で行った場合は懲戒処分の対象となる可能性があること
特に不就労分の賃金控除については、服務規律に記載することが非常に重要となります。
「ノーワーク・ノーペイの原則」により、遅刻・早退・欠勤時には、明文化していなくとも賃金を控除して問題ありません。
しかし、明文化されていないことが原因で従業員とトラブルになる可能性もあるため、服務規律に明記する必要があるのです。
備品・施設利用
自社の備品や設備を自由に使われては業務に支障が出てしまうため、服務規律として利用に関するルールを設けましょう。
【備品・施設利用に関する服務規律の例】
●会社の備品を許可なく持ち出さないこと
●貸与された備品を紛失しない、あるいは破損させないこと
●会社の施設を本来の目的以外で使用しないこと
このほか、火器の取り扱いや、刃物などの危険物の持ち込みに関する事項も、必要に応じて規定する必要があります。
秘密保持・個人情報の保護
自社のビジネスに関わる機密情報や、お客さまの個人情報などが漏洩しないように対策することは、社会的な信用を得る上で必要不可欠な対応です。服務規律にも、機密情報や個人情報は適切に取り扱わなくてはならない、という旨を記載しましょう。
【秘密保持・個人情報の保護に関する服務規律の例】
●在職中・退職後を問わず、業務上で知り得た自社あるいは取引先の情報を持ち出さないこと
●自らの業務に関係のない情報を不当に取得しないこと
●異動時や退職時は、自らが管理していた機密情報を速やかに返却すること
上記のほか、従業員が不正に機密情報を漏洩させた場合に備えて、損害賠償責任に関する事項も整備しておくことを推奨します。
ハラスメント
2022年4月1日より、「パワーハラスメント防止措置」に基づきパワハラ・セクハラ・マタハラの防止対策を講じることが、中小企業も含む全ての事業主の義務となりました。
この義務に違反するような事態が社内で起きないように、服務規律にもハラスメントに関する以下のような規定を設けましょう。
●職場内の優位性を背景に、ほかの従業員に精神的・身体的な苦痛を与えないこと
●性的言動によりほかの従業員に不利益や不快感を与えないこと
●妊娠・出産に関する言動、および関連する制度または措置の利用に関する言動により、ほかの従業員の就業環境に損害を与えないこと
また、服務規律を定めるだけではなく、ハラスメントを目撃した場合の報告、あるいはハラスメントを受けた際の相談窓口をつくることも大切です。
(参照:厚生労働省『労働施策総合推進法に基づく「パワーハラスメント防止措置」が中小企業の事業主にも義務化されます!』)
副業
職業選択の自由の観点から、従業員の副業や兼業を企業側が制限することは認められていません。
ただし、自社業務がおろそかになることを防ぐ目的であれば、以下のような内容を服務規律に設けられます。
【副業に関する服務規律の例】
●自社以外の企業や団体に勤続する、あるいは営利を目的とする事業を営む場合は、事前に許可を得ること
●自社の業務に関わる事項について著作物を出すあるいは講演を行う、または特許を出願する場合も会社の許可を得ること
●自社の業務ならびに心身の健康に支障を来さない範囲で活動すること
なお、以前と比較して遅刻や欠勤が増えたなど、副業による自社業務への明確な悪影響が認められた場合には、副業を禁止できる可能性もあります。
SNSの利用
近年は、従業員がSNSに投稿した内容が大きな社会問題に発展する場合があるため、SNSの利用に関する規定を設ける必要もあります。「しかし、SNSの利用をどのように制限すれば良いかわからない…」という人事・採用担当者は、以下の内容を参考にしてください。
【SNSの利用に関する服務規律の例】
●SNS等で会社の取引先情報や従業員の個人情報を投稿しないこと
●SNS等でほかの従業員または外部の第三者などを誹謗中傷しないこと
●会社のSNSアカウントで私的な投稿を行わないこと
従業員のプライベートまで完全に制限することは不可能ですが、上記のようなルールを設けておけば、トラブルが発生するリスクをある程度は軽減できるでしょう。
在宅勤務
はたらき方改革や新型コロナウイルスの流行などの影響から、在宅勤務を取り入れ始めた企業もあるでしょう。在宅勤務とオフィスでの就労ではいろいろと業務の進め方が異なるため、服務規律に独立した項目設けてルールを定めることをお勧めします。
【在宅勤務に関する服務規律の例】
●在宅勤務のために持ち出した会社の情報および作成した成果物を、第三者が閲覧・コピーしないように注意を払うこと
●自宅以外の場所で在宅勤務を行わないこと
●在宅勤務中に許可なく外出する、また業務に関係のない作業を行わないこと
在宅勤務では特に情報漏洩のリスクが高まるため、セキュリティに関する内容で抜け漏れが出ないように注意してください。
競業避止義務
競業避止義務とは、競合他社への転職を制限するための規定です。顧客リストなどの機密情報や、業務に関するノウハウの流出を防ぐことを目的に設けられています。
【競業避止義務に関する服務規律の例】
●新商品の企画・立案や研究開発業務に従事していた従業員は、退職または解雇されてから1年間は同業種に携わる企業に就職しないこと
●退職または解雇後に、自社に隣接した地域で開業しないこと
一点、副業に関する規定と同様に、職業選択の自由により競合他社への転職、または独立を完全には制限できないことに注意しましょう。競業を禁止する期間や地域については、一般的な観点で問題ない範囲にとどめる必要があります。
下記より「服務規律サンプルフォーマット」を無料でダウンロードいただけます。自社規程の見直しやトラブル防止のために、ぜひご活用ください。
服務規律を作成する手続きの流れ
先述した通り、服務規律は就業規則の一部と見なされるため、作成時には就業規則の変更手続きと同じ手順を踏む必要があります。具体的な手順は以下の通りです。
●労働者の過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数を代表する者の意見を聴取し、意見書を作成する
●就業規則変更届を作成する
●服務規律を作成し就業規則に組み込む
●労働基準監督署に意見書と就業規則変更届、変更後の就業規則の3点を提出する
上記の流れは労働基準法で定められたものであるため、いずれの対応も欠けることがないように注意してください。
(参照:e-gov法令検索『労働基準法』)
服務規律を新設・変更する際の注意点
服務規律を新しく作成する、あるいは変更する場合は、その内容が「不利益変更」になる可能性も考慮しなくてはなりません。
不利益変更とは、賃金の減額や所定休日の削減など、従業員が不利益を被る形で就業規則を変更することを指し、原則としてその内容は無効となります。
ただし、変更に合理性があり従業員からも同意を得ている場合は、その限りではありません。服務規律の作成・変更が不利益変更になると考えられる場合は、変更に合理性があることを示した上で、従業員の理解を得られるように説明を行いましょう。
また、服務規律の作成・変更により就業規則も変更となる場合は、その旨を従業員に周知することが義務付けられています。これを怠ると服務規律が無効となるだけではなく、30万円以下の罰金を科される恐れもあります。
事務所や休憩室などに掲示する、また冊子にまとめて配布するなどして、従業員全員が服務規律および就業規則を確認できる状態にしておけば問題ないでしょう。
(参照:e-gov法令検索『労働基準法』)
(参考:『就業規則の不利益変更とは?実施する場合の対応方法とこんな時どうする?16の事例』)
従業員が服務規律に違反した場合の対処法
服務規律違反が懲戒事由として就業規則に規定されていれば、違反した従業員を懲戒処分の対象にできる可能性があります。
また、就業時間外に服務規律に反する行動を取った場合にも、その行動が企業に不利益をもたらす可能性がある場合は処分の対象となりえます。
ただし、違反者に対しては企業が好きに懲戒処分を下せる、というわけではありません。以下の対応を行った上で、懲戒権の濫用とならない範囲で処分を決める必要があります。
【従業員が服務規律に違反した場合の対処法】
●事実確認を行う
●懲戒処分の有効性を判断する
●違反内容に応じた懲戒処分を決定する
●派遣社員は派遣元の服務規律を適用する
事実確認を行う
まず、対象の従業員が本当に服務規律に違反したかどうかを、以下の流れで確認します。
1.関係者への聞き取り
2.証拠品の収集
3.対象者の周囲の人間への聞き取り
4.当事者への聞き取り
この際「対象者は服務規律に違反したはずだ」という先入観を持つと、客観的な事実を収集できなくなるため、中立的な立場を保つことを徹底しましょう。
懲戒処分の有効性を判断する
服務規律に違反した事実が確認できた後は、それに対して懲戒処分を下すことの有効性を判断します。その際は、以下の要件を満たしていることを確認しましょう。
●服務規律違反が懲戒事由になると就業規則に規定されていること
●懲戒処分が相当であること
●懲戒事由に対する懲戒処分の内容が妥当であること
●過去の類似した事例と処分の内容が同程度であり、公平性を保っていること
●同一の事実に対して処分が重複していないこと
●懲戒処分の手続きが遵守されていること
上記の要件を満たせている場合は、対象者に懲戒処分を下して問題ありません。
違反内容に応じた懲戒処分を決定する
先の要件にも記載があるとおり、処分内容は違反内容に対して相応なものでなくてはなりません。各所へのヒアリングを踏まえた上で違反の程度を検討し、以下の7種類のうちから最も適当と思われる処分を行います。
※下に行くほど処分の程度が重いです
| 懲戒処分の種類 | 具体例 |
|---|---|
| 戒告 | 対象者の過失や非行などを口頭で注意する |
| 譴責(けんせき) | 始末書を提出させる |
| 減給 | 賃金から一定額を控除する |
| 出勤停止 | 就労を一定期間にわたり禁止する |
| 降格 | 役職や職位を引き下げる |
| 諭旨解雇(ゆしかいこ) | 退職届の提出を勧告した上で、対象者がそれに応じれば退職扱いとし、応じなければ懲戒解雇する |
| 懲戒解雇 | 制裁として解雇する |
処分が違反内容に相応ではない場合には懲戒権の濫用と見なされて、処分が無効となる可能性もあります。社内の過去の事例や裁判例などを参照した上で、妥当な処分を決めることが大切です。
派遣社員は派遣元の服務規律を適用する
派遣社員には派遣元の服務規律が適用されるため、自社の服務規律に違反したとしても処分できません。口頭での注意喚起を行った上で、実際の処分は派遣元に要請する必要があります。それでも事態が改善されなかった場合には、代わりの派遣社員を要請する、または派遣契約を解除するなどで対応しましょう。
なお、派遣社員に対して自社から処分は下せませんが、服務規律を守ってほしいと伝えることは可能です。服務規律の内容を事前に伝えて理解を得ておけば、認識の齟齬によるトラブルを防ぐことができるでしょう。
服務規律違反の判例
最後に、服務規律に違反した従業員に対する処分が無効とされた例と、有効とされた例のそれぞれを紹介します。
【従業員が服務規律に違反した場合の対処法】
●「解雇」処分が無効とされた例
●「解雇」処分が有効とされた例
(参照:厚生労働省『裁判例14-1 会社物品の私的使用』)
「解雇」処分が無効とされた例
採用後22年間にわたり秘書業務や翻訳業務等に従事し、勤務実績も良好だったXは、業務用パソコンから私用メールを送受信したなどの事由から、無期限の出勤停止処分を受けました。そしてその3カ月後、企業側はXに「解雇」を通告。
これに対しXは「メールの送受信などは就業規則上の解雇事由には該当しないため、解雇権の濫用にあたり無効である」として、地位の確認と賃金・賞与等の支払いを求めて企業側を提訴します。
裁判の結果、東京地裁は「就業規則所定の解雇事由に該当する行為もあるが、約22年間の非違行為もなく良好な勤務実績を考慮すると、解雇が客観的合理性・社会的相当性を備えているとは評価し難い」と判断を下し、解雇処分を無効としました。
「解雇」処分が有効とされた例
Z専門学校は、同校に勤務する教師Yが、就業時間内に職場のパソコンを利用して出会い系サイトに登録し、大量の私用メールを送受信したことを確認。これを理由に「懲戒解雇」処分を下しました。
処分を受けたYは「懲戒事由に該当する事実はなく、解雇権の濫用である」として、地位の確認および未払賃金等の支払いを求めて学校側を提訴します。
これを受けて、まず福岡地裁久留米支部は「懲戒解雇事由に一応は該当するものの、その内容や程度、影響等を考慮すると解雇権の濫用にあたる」と判断しましたが、福岡高裁は「Yの行為は著しく軽率かつ不謹慎であり、学校の品位や名誉を傷付けるものである上に、職務専念義務にも違反する」とし、懲戒解雇は適法であると結論付けました。
自社内の秩序を守る上で服務規律は欠かせない
服務規律の作成は義務ではありませんが、自社内の秩序を守る上では必要不可欠な対応だといえます。自社の業務内容や文化、企業風土を考慮した上で、労働者が遵守すべき事項や勤務態度、またハラスメントに関わる規定などを詳細に設定しましょう。
また、服務規律違反が懲戒事由になり得ると定められていれば、違反した従業員に懲戒処分を下すことも可能です。ただし、その際は過去の事例や裁判例などを調査し、違反の内容に対して妥当な処分を決めることを心がけてください。
下記より「服務規律サンプルフォーマット」を無料でダウンロードいただけます。自社規程の見直しやトラブル防止のために、ぜひご活用ください。
(制作協力/株式会社eclore、監修協力/弁護士 藥師寺正典、編集/d’s JOURNAL編集部)
服務規程サンプルフォーマット【Word版】
資料をダウンロード