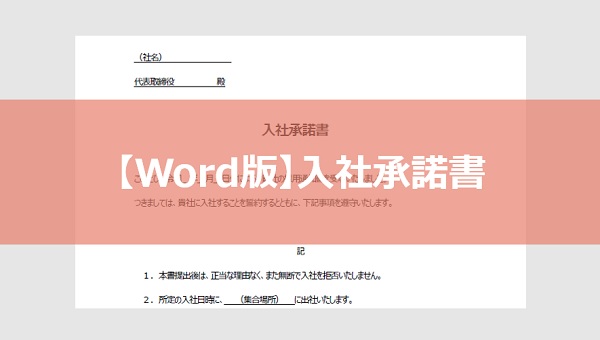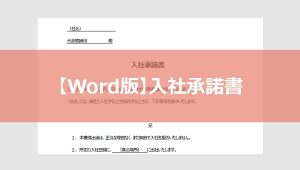【テンプレート付】入社承諾書とは?採用担当者が知っておくべき記載内容や注意すべきポイント
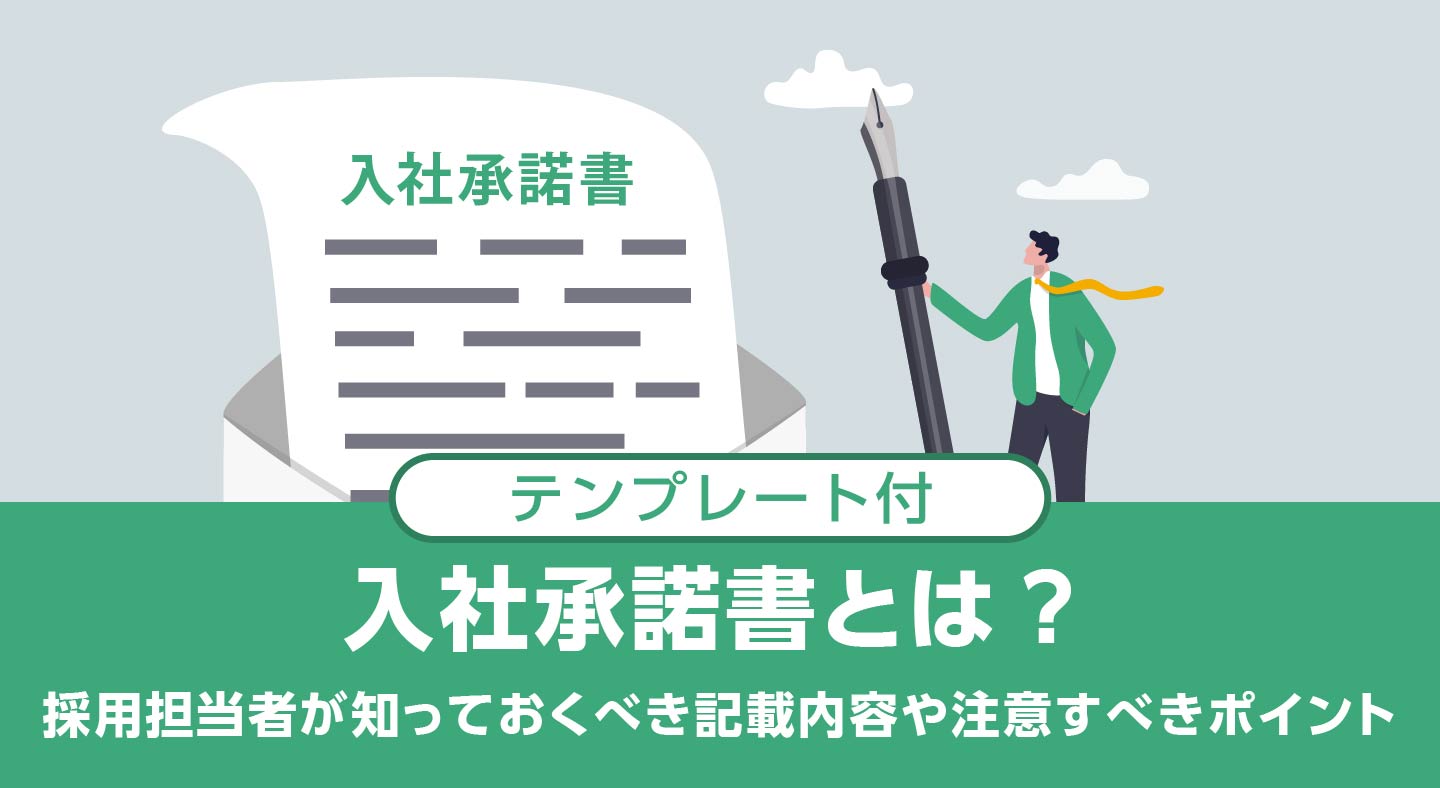
採用予定者の入社意思を確認するための書類である、入社承諾書。「入社承諾書にはどのような内容を記載すればよいのか」「作成する際に注意すべき点は何か」を知りたい人事・採用担当者もいるのではないでしょうか。
この記事では社労士監修のもと、入社承諾書に記載すべき内容や注意すべきポイントなどについて解説します。入社承諾書のテンプレートもダウンロードできますので、ご活用ください。
入社承諾書(内定承諾書)とは
入社承諾書とは、採用予定者が企業に入社の意思を伝え、入社を誓約するための書類のこと。内定承諾書と呼ばれることも多い書類です。法的な作成義務はなく、作成・発行の有無は企業に一任されます。
企業からの採用意思の通知後、採用予定者は「特別な理由がない限り入社する」という意思を示すために、入社承諾書の用紙に署名・捺印などをして企業へ返送します。
入社承諾書の目的
入社承諾書を作成する目的は、主に「採用辞退を防ぐため」と「不要なトラブルを避けるため」の2つです。
万が一採用予定者に入社を辞退されてしまうと、欠員を補充するために採用コストがかさむ可能性があります。誓約内容を書面化した入社承諾書を提出してもらうことで、入社の意思を固め、入社辞退を防ぐ効果が期待できます。
また、採用時の約束事を書面化し、内容を確認した上で誓約してもらうことで、双方の認識の相違による不要なトラブルを避ける効果もあるでしょう。
入社承諾書に関する注意点
入社承諾書の提出により、企業と採用予定者には「始期付解約権留保付労働契約」が成立します。難しい言葉ですが、簡単にいえば「応募者と企業の間で入社までに一定の期間があり、その入社までにやむを得ない事情があれば内定を取り消すことがある、という条件付きの労働契約が結ばれている状態を指します。
そのため、会社側からの内定の取り消しは解雇同等の要件が求められてくることに注意が必要です。ただし、民法第627条第1項には「雇用期間に定めのないときは、解約(辞退)の申入れから2週間で雇用契約が終了する」と定められているため、採用予定者がこの内定を辞退することは可能であり、企業としては入社承諾書が提出されても採用予定者から辞退される可能性があることに注意が必要です。
また、近年は企業が採用予定者に対し、他社の選考を辞退させ就職・転職活動を終わらせるよう迫る「オワハラ」が問題視されています。入社承諾書を提出するよう求めること自体は問題ありません。
ただし、入社承諾書を提出した採用予定者に対し、自社以外の選考を辞退するように求める行為はオワハラおよび職業選択の事由を侵害する行為とみなされる可能性があるため、注意しましょう。
入社承諾書とともに送付する書類
入社承諾書は、内定の意思を通知する「内定通知書」および、労働契約を結ぶ際に必ず取り交わす義務のある「労働条件通知書」とともに送付するのが一般的です。併せて、返信用封筒も同封しておくとよいでしょう。
なお、企業と採用予定者双方の合意があれば、必ずしも紙媒体で書面を用意する必要はありません。電子メールや電子契約で承諾を交わすことも可能です。
(参照:『【テンプレあり】採用通知書とは|書き方や送付方法・法的効力を解説』『【記入例・雛型付】労働条件通知書とは?雇用契約書との違いや書き方をサクッと解説』)
中途採用と新卒採用における入社承諾書の違い
労務リスク低減の観点から、入社承諾書には、万が一の場合、例えば大学を卒業できなかったとき、健康状態が相当に悪化したとき、入社日前に犯罪行為等の非行を犯した場合などには内定を取り消すことがあるという旨を入社承諾書に盛り込む企業もあります。中途採用と新卒採用では、こうした「企業側がやむを得ず採用を取り消す事由」についての記載にも若干の違いが見られます。
新卒採用の場合は上述の通り「卒業すること」が入社の条件になるため、やむを得ず採用を取り消す事由として「学校を卒業できなかった場合」と記載されている一方中途採用の場合には「入社日までに前職を退職できなかった場合」などが入っています。
それ以外の記載内容や作成の目的は、中途採用、新卒採用にかかわらずほぼ同じです。
入社承諾書の記載内容
入社承諾書には法的な発行義務がないため、書式や記載項目についての決まりもありません。ただし、「入社意思の確認」「トラブルの防止」という目的を達成するには、押さえておくべき項目がいくつかあります。
ここでは、入社承諾書に「必ず記載すべき項目」と「必要に応じて記載する項目」をそれぞれ紹介します。
記載必須の項目
企業によってフォーマットは異なるものの、入社承諾書に記載すべき項目は以下の通りです。
記載必須項目
●社名、社長(代表取締役)名
●表題
●採用通知を受理した旨
●入社を誓約する旨
●入社を誓約した日付
●採用予定者の住所、氏名、捺印欄
採用予定者が入社を誓約したことが明確にわかる文章や、署名と捺印欄を設けることが一般的です。
必要に応じて記載する項目
必要に応じて、以下の項目も記載しましょう。
必要に応じて記載する項目
●今後のスケジュール
●内定取り消し事由
●同封書類を遅滞なく返送する旨、返送期日
●提出書類の記載内容(住所・連絡先など)に変更があった場合は速やかに連絡する旨
など
「内定取り消し事由」とは、やむを得ない理由で採用を見送る際の条件です。こちらについては、後ほど詳しく解説します。
その他、「同封書類の返送期日」や「記載内容に変更があった場合は連絡する旨」などを記載しておくと、採用予定者との入社日までのやり取りがスムーズになるでしょう。
入社承諾書の作成ポイント
入社承諾書を作成する際に押さえておくべきポイントを解説します。
承諾条件を明確に記載する
入社の承諾条件をあいまいな表現にしてしまうと、入社辞退などの際にトラブルに発展するリスクがあります。承諾条件を定める際は、以下のようにわかりやすく明確に記載するようにしましょう。
承諾条件の記載例
●入社承諾書の提出後は無断で入社を拒否しない
●提出書類に不実な記載をしない
●健康上の理由により入社ができない場合は、速やかに連絡する など
内定取り消し事由を記載する
採用通知書の発行と入社承諾書の提出により、企業と採用労働者の間には「始期付解約権留保付労働契約」が成立し、いわば労働契約と同等の契約が成立します。成立した労働契約を正当な理由なく解約することは「解雇」に相当し、労働契約法第16条に示されている「解雇権の乱用」にあたるため、注意が必要です。
ただし、入社承諾書に採用が取り消しとなる条件である「内定取り消し事由」を明記し、かつその事由が過去の裁判例等に照らして客観的・合理的であり、採用予定者がこれを了承して署名・捺印していれば、その条件に抵触した場合に採用を取り消す根拠を強めることができます。内定取り消し事由として認められうる例は以下の通りです。
内定取り消し事由として考えられる事由
●学校を卒業できなかった場合
●就労までに必要とした免許・資格が取得できなかった場合
●健康を著しく害し勤務に重大な支障がでる場合
●履歴書や誓約書などに重大な虚偽記載がある場合
●犯罪行為を犯した場合
など、客観的に合理的で、社会通念上相当であると認められるもの。
(参考:日本労働組合総連合会『労働相談 2.採用内定取消・延期』)
採用予定者との不要なトラブル防止のため、取消事由となるケースを事前に定めておき、入社承諾書にも明確に記載しましょう。
課税文書になりうるかを法務に確認する
入社承諾書は、印紙税がかかる「課税文書」に該当する場合もあります。課税文書に該当するか否かは、文書の表題にかかわらず実質的な内容で判断することになっているため、事前に税理士などの専門家や法務担当者などに確認をしておくとよいでしょう。
まとめ
入社承諾書は、採用予定者の入社意思を確認するために、「入社を誓約する旨」や「採用予定者の氏名・捺印欄」などを記載した書類です。企業に入社承諾書の作成義務はありませんが、採用予定者の誓約を得ることは入社辞退の抑制や労務トラブルの防止といった効果が期待できます。
作成する際は承諾条件や内定取り消し事由を明確に記載し、スムーズな入社につながるよう心掛けましょう。
(制作協力/株式会社mojiwows、監修協力/社会保険労務士 寺島有紀、編集/d’s JOURNAL編集部)
【Word版】入社承諾書
資料をダウンロード