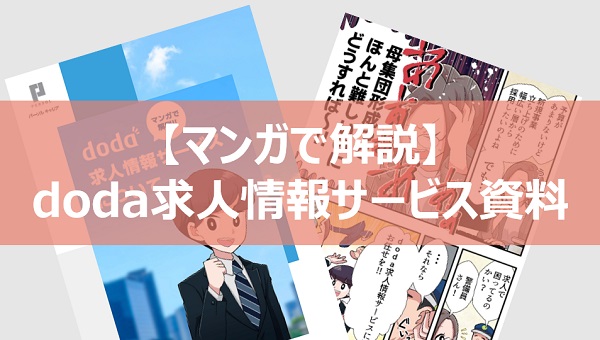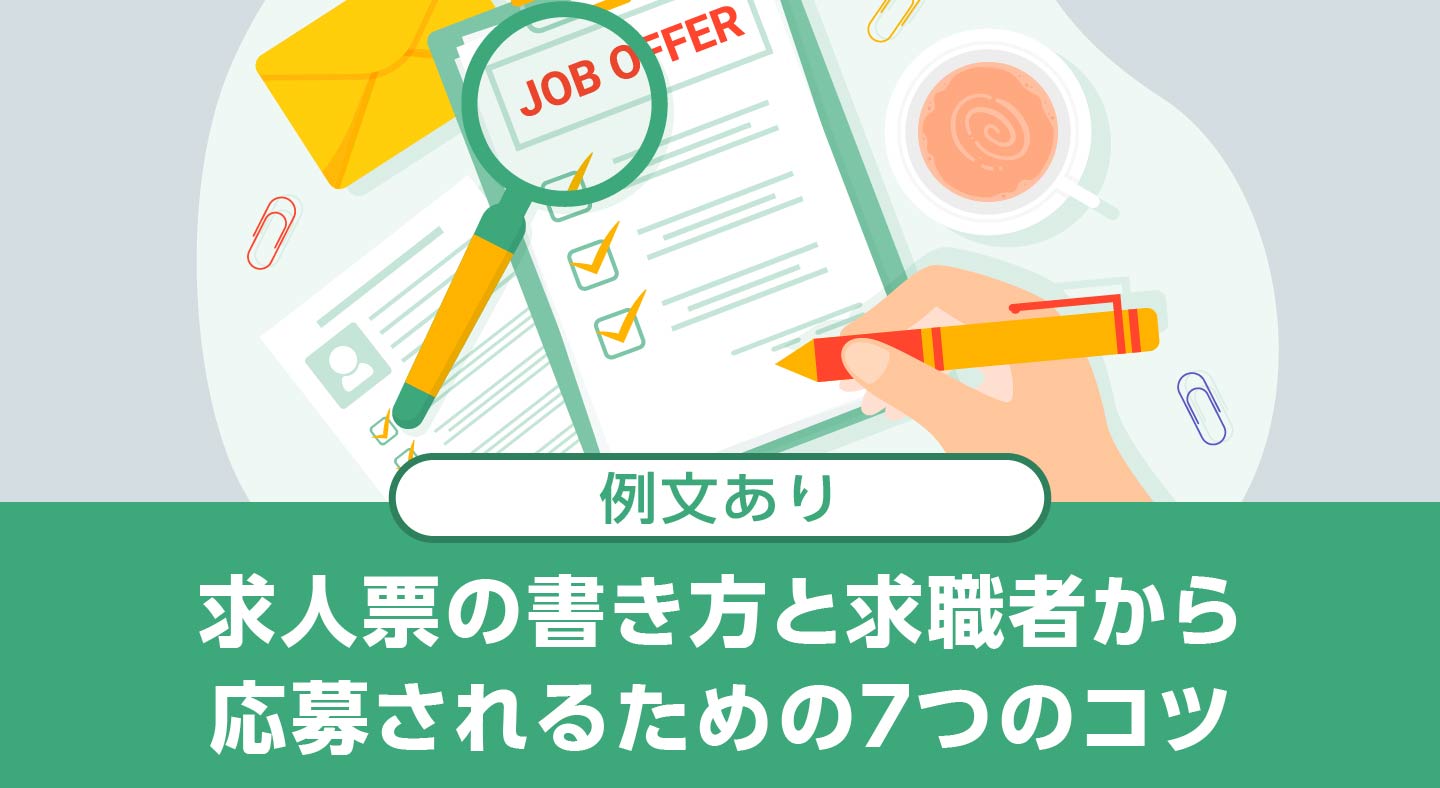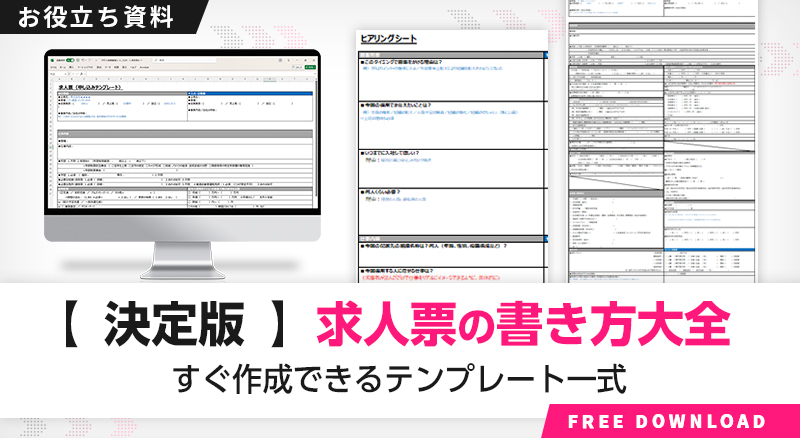その求人票やスカウトメールは大丈夫?採用決定のために無料で今すぐできる5つの対策
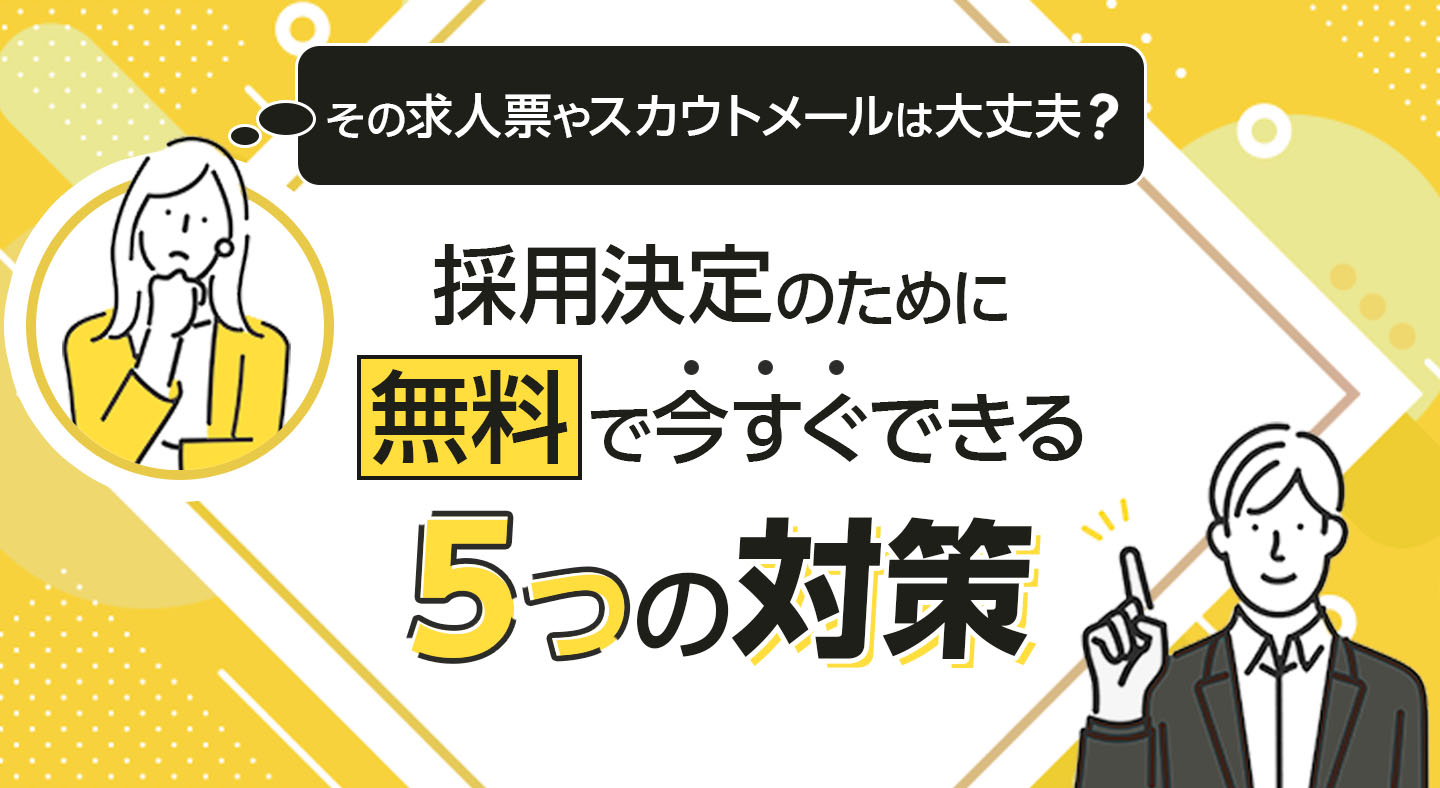

d’s JOURNAL編集部
-
中途採用市場は売り手市場。転職希望者に自社の求人を見つけてもらう工夫が必要になる。
-
検索キーワードランキングや求人特集と自社を照らし合わせて、合致する情報を記載することが、転職希望者に気づいてもらう第一歩。
-
求人情報閲覧後の応募促進のために、具体的な業務内容や定性情報を記載することと、常に更新することが重要。
採用活動に取り組む上で、「予算が限られている」「応募がなかなか来ない」「母集団を形成できない」といったお悩みを抱えている人事・採用担当者の方も多いのではないでしょうか。
売り手市場となっている現在の転職市場においては、求人票やスカウトメールといった求人情報の記載内容に工夫が必要です。今回は、転職市場の状況を踏まえつつ、採用決定のために無料でできることを5つご紹介します。この機会に、自社の採用情報の書き方を見直してみましょう。
データで見る転職市場の状況と転職希望者の動向
まずは、転職市場の現状を押さえましょう。転職・求人サイトdodaの「転職求人倍率レポート」によると、2024年11月時点の転職求人倍率は2.82倍となっており、依然として売り手市場といえる状況です。
そこで、転職活動の方法を厚生労働省の「令和2年転職者実態調査の概況」と5年前の「平成27年転職者実態調査の概況」で比較すると、以下のようになりました。2020年で最も使用されているのは「求人サイト・求人情報専門誌・新聞・チラシ等」の39.4%で、年齢や学歴別に見ても、若手や最終学歴が大卒以上であるほど求人サイトの利用が増加傾向にあるという結果が出ています。
| 2020年(令和2年) | 2015年(平成27年) | |
|---|---|---|
| 1位 | 求人情報専門誌・新聞・チラシ等 :39.4% |
公共職業安定所(ハローワーク)等の公的機関 :41.3% |
| 2位 | ハローワークなどの公的機関 :34.3% |
縁故(知人、友人等) :27.7% |
| 3位 | 縁故(知人、友人等) :26.8% |
求人情報専門誌・新聞・チラシ等 :24.2% |
ハローワークよりも民間の求人サイトが利用されている状況において、求人広告件数もまた多い状況にあります。公益社団法人全国求人情報協会の「求人広告掲載件数」では、2024年10月時点の職種別求人広告件数が全体で2,071,229件となっており、求人広告件数の多さからも、自社の求人情報を見つけてもらうことへのハードルの高さがうかがえます。
そのため、母集団を形成し自社の求める人材を採用するには、「数ある情報の中から自社の求人を見つけてもらう工夫」や「求人情報を見た後に応募したくなる工夫」が必要になるといえるでしょう。
採用決定のために無料でできる5つの対策
それでは、採用決定のために無料でできる5つの対策を具体的にご紹介します。
①人気の検索キーワードを入れ込む

まずは、求人サイトで人気の検索キーワードを入れ込むことが大切です。検索キーワードは、いわば「転職希望者が現在転職活動において重視している情報」そのものです。「検索キーワードランキングで上位にあるキーワードが自社求人の中に織り込まれているか」「言い換えられる言葉がないか」を確認してみましょう。
転職・求人サイトdodaの「人気の検索キーワードランキング」を見ると、2024年12月更新時点では、1位「在宅勤務」、2位「フルリモート」となっています。例えば現状「テレワーク」という言葉を求人票に使用している場合、検索でヒットせず求人票を見つけてもらえていない可能性があります。検索上位にある「在宅勤務」や「フルリモート」などに書き換えてみると、検索画面で自社の求人票が表示される見込みが高まるでしょう。また、これらの上位文言を、スカウトメールのタイトルに入れることも有効です。
ランキングにあるワードが業務内容に関わる場合は、追記が必要です。例として、ランキングに入っている「英語」を業務で使う機会があるにもかかわらず、現状記載していない場合は、きちんと求人票に記載しましょう。業務内容とランキングを照らし合わせて、記載内容を見直すことも重要です。
さらに、検索キーワードだけでなく求人サイト内の求人特集を参考にしてみるのもおすすめです。「語学力を活かす特集」「面接1回特集」「副業OK企業特集」など、求人サイト内での特集内容は、それだけ転職希望者のニーズがあるとも言えます。転職希望者の目線に立ち、キーワードやニーズを意識した求人情報を作成しましょう。
(参考:転職・求人サイトdoda『doda求人特集』)
②自社ならではの情報を記載する

意外と見落としがちなのが、自社ならではの情報です。例えば、「この商品は日本で数社しか取り扱っていない」「ニッチな部品『●●』を製造している」などの情報が該当します。このような情報があるにもかかわらず、よくあるのが、求人票にそこまで詳細に記載していないケースです。ニッチだからこそ、ピンポイントでその技術や情報を求めている転職希望者がいるかもしれません。上記の例では、商品名や部品名などを求人情報に盛り込むことで、転職希望者に見つけてもらえる可能性が高まるでしょう。
また、商材のみならず、福利厚生やユニークな取り組みといった制度も、自社の強み情報になりえます。自社ならではのアピールポイントは何か、一歩引いた視点から見つめ直してみましょう。
③業務内容を具体的に記す
上記2つのステップで自社の求人を見つけてもらえた後は、転職希望者が応募したくなる工夫をすることが重要です。まずは、業務内容を具体的に記すことです。当たり前に感じられるかもしれませんが、例えば、営業職であれば「法人に対して●社程度の営業活動を行う」といった文言で終わらせていないでしょうか。この表現では、転職希望者は働くイメージをもつことができません。
・どのような規模・業界向けの法人に営業をするのか
・新規開拓なのか既存顧客向けの営業なのか、複数の場合の割合は
・顧客への営業方法は電話・訪問・オンラインなのか、複数の場合の割合は
・1カ月で何件程度営業活動を実施するのか、何社の担当を持つのか
・一人当たりの受注平均金額はどの程度か
・評価はどのように決まるのか
というように、具体的に働くイメージ内容を記載することをおすすめします。
他にも、エンジニアであれば「Java」や「Swift」といった使用する言語を、設計であれば使用するツールとして「3DCAD」、事務であれば「Word」や「Excel」というように、どのようなツールや言語を用いて、どの程度の頻度で、何のためにどのような業務を行うのかについても記載しましょう。細かく情報を載せることで、転職希望者は「自分のスキルが活かせるかどうか」や「希望する業務なのか」を判断しやすくなります。
④定性情報を載せ、入社後をイメージできるようにする

数値では表せないような定性情報も、自社のアピールポイントになります。採用においては、「今後の展望」や「担う役割」「一緒に働くメンバーの人数」といったことが挙げられます。
「今後企業としてどのような方向性を目指していくのか」「企業方針に対して入社後の自分は何を求められるのか」「どのような人とどう関わり一緒に働くのか」「どのようなキャリアアップが望めるのか」といった、自社で働く未来のイメージが湧くような文章を掲載することは、求人への応募につながるといえるでしょう。
(参考:『求人票で「アットホームな社風」はNG?求職者が知りたい社風を伝えるコツとは』)
⑤求人情報を定期的に見直す
求人情報は一度書いたら終わりではなく、定期的に見直すことが大切です。転職希望者のニーズは常に変化します。定期的に検索キーワードをチェックし、求人票を見直したり、スカウトメールをつくり直したり、時流に合わせて言い換えられる言葉がないかを確認したりして、内容をブラッシュアップしていきましょう。
まとめ
採用決定に向けて無料でできる5つの対策をご紹介しました。現在、転職希望者の多くが民間の求人サイトを利用しているという調査結果が出ています。人事・採用担当者には、自社の求人情報が転職希望者にしっかりと届くような工夫が求められるため、この機会に自社の求人票やスカウトメールを見直してみてはいかがでしょうか。
上記を試してもなかなか採用決定に結びつかない場合は、人材サービス会社に相談・問い合わせをしてみることもおすすめです。
(企画・編集/田村裕美(d’sJOURNAL編集部)、制作協力/株式会社mojiwows)
<決定版>求人票の書き方大全【すぐ作成できるテンプレート一式】
資料をダウンロード