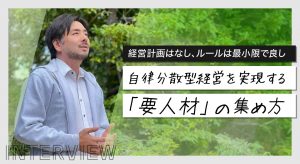企業文化の醸成と浸透が採用力を高める。人事・広報…バックオフィス横断型組織とは

昨今では、企業における採用広報・採用ブランディングの重要性が高まり続けています。しかし、人事部門と広報部門の連携がスムーズに進まないという課題を抱えている企業も少なくないようです。そうした中、ソーシャルゲーム事業で成長を続けている株式会社オルトプラスは約2年前に人事、広報、総務というバックオフィス横断型のブランディングチームであるCB部(コーポレートブランディング部)を立ち上げました。同部門は採用ブランディングや社員のエンゲージメント向上を目指した幅広い活動を推進し、大きな成果を上げていると言います。
今回は同社におけるCB部発足の背景やCB部の具体的なミッション、推進しているさまざまな施策、得られた成果などについて、同部門のマネージャーである柳さん、広報担当の内田さんのお二人に詳しくお聞きしました。
離職率50%以上。採用コストが経営を圧迫するハードな状況の中、CB部が誕生

柳氏:CB部は創業者でもあるCOOの直轄組織であり、2017年に立ち上げられました。人事、広報、総務といった職種の垣根を超え、企業文化の醸成と社内外への周知、採用PR、社員エンゲージメントの向上などを目的とし、幅広い施策の企画・立案・運用を推進しています。また、最近ではインナーブランディングや採用広報に加えて、メディアとのリレーションなども含めた社外広報や採用以外のPR活動にも力を入れ始めています。現在はCOOが部長を兼任し、マネージャーの私と広報担当の内田、そのほかに採用担当、労務担当、総務担当、アートディレクターがそれぞれ1名ずつ、合計7名で構成された部署となっています。
柳氏:はい。CB部ができる前は人事部、総務部があり、PRはマーケティング部門の中に含まれているという状況でした。一般的な企業のバックオフィスと同じような体制だったと思います。
柳氏:ゲーム業界そのものの課題に加えて、オルトプラスの急激な成長から生じている課題もありました。当社のメイン事業はゲーム開発ですが、そもそもゲーム業界は非常に離職率が高い業界であると言われています。プロジェクトが終わるたびに転職をする人も多く、1〜2年で会社を変えてしまう人も珍しくありません。
柳氏:当社は2010年に設立し、2013年には東証一部に上場しています。5人程度でスタートした会社が3、4年後には200名ほどの組織に急拡大していました。とにかく短期間で急激に人を増やしていたので、企業文化やビジョン、ミッションに共感して入社した方ばかりではなく、スキルだけがマッチしているという方もたくさん採用していました。その結果、「会社が何を考えているのかわからない」「企業文化に合わない」という人が大量発生し、酷い時期には離職率が50%を超えたこともありました。1年で社員200名のうち半分の100名が辞めていくというイメージです。

柳氏:そうは言っても事業を伸ばしていかなければならないので、「100人辞めたら100人採用しよう」と、その当時は社員の入れ替わりが非常に激しかったですね。また、それだけの人数を採用しなければならないのに会社の知名度が低く、候補者から認知されていないという問題もありました。当社はかなり有名なゲームも開発しているのですが、パブリッシャーではないので社名が出せないのです。
柳氏:その通りです。当時は採用の9割が人材紹介経由だったので、年間の採用コストも数億円に達しており、採用コストが経営を圧迫するという状況も生まれていました。この状況を改善しようと、COOの発案によってCB部が立ち上がったのです。そうした経緯があるので、立ち上げ当初のCB部のミッションは採用コストの削減と社員定着率の向上に重きが置かれており、採用・インナーブランディングの推進に注力していました。その後、徐々に業務範囲を広げていき、現在は総務や労務もインクルードされているという状態です。
柳氏:採用してもすぐに人が辞めていく状況だったので、採用担当としてはザルに水を流しているような感覚でしたね。また、年間で100人も採用していたので採用以外の仕事が手につかず、社員のフォローアップにも意識が回りませんでした。
柳氏:経営の意図を反映させるようなプロジェクトなどでは、どうしてもスピードが落ちてしまうと感じていました。ちょっとした社内イベントを開催するにしても他部署であった総務部と連携する必要があったので、今よりもコミュニケーションの手間と時間が掛かっていたことは確かです。
コーポレート部門は、「経営の思いを汲み取り、社員に伝達すること」がミッション

柳氏:コーポレートブランディングというと、社外向けのPRを思い浮かべる方も多いと思いますが、CB部では「企業文化を作ることがコーポレートブランディングにつながっていく」と考えているので、コーポレートブランディングにしても採用広報にしても、まずは社内から進めていくことを徹底しています。
柳氏:コーポレートブランディングを進めるステップとしては、何よりも先に価値観の共有を行うことを大事にしています。具体的には会社のビジョンやミッション、バリューといった部分になるのですが、全体会議や社内ポスター、人事面談、会社のイベントなどを活用して「こういう人が活躍する会社にしたい」というメッセージングを徹底して行います。そうした価値観の共有・発信を行ったあとに飲み会や交流会といったコミュニケーション施策を進めていく。価値観の共有によって同じ共通言語を持った状態でコミュニケーションの活性化を行い、そのあとに社員を巻き込んでいくという流れですね。
柳氏:会社の情報を社員がSNSでシェアすることを推奨しています。もちろん強要はしていないのですが、会社のリリース、募集記事、社員インタビューなどを作ったときは、「ぜひシェアしてください」と社員に周知をしています。シェア数が増えることよってリリースや記事のPVが伸びることもありますし、CB部で力を入れているリファラル採用などにも波及効果があります。
内田氏:最初はSNSでシェアしてくれる社員がほぼ0という状況でしたが、CB部が社員交流会などのコミュニケーション施策を積極的に増やしていったことで、最近では多いときには20パーセントぐらいの社員がシェアしてくれるようになりました。
柳氏:「CBplus」というブログを運営しています。バックオフィスで働いている方やバックオフィスを統括する経営者の方々に対して、コーポレートブランディングに関するノウハウやバックオフィス系の話題を発信しているのですが、現在はブログからオウンドメディアに進化させている最中です。また、バックオフィスの活動は事業部門の社員からは見えにくい部分もあるので、社内の社員たちに向けて、私たちCB部が「どのような意図を持って、どのような活動を行っているのか」を知ってもらうためのメディアとしても機能しています。
柳氏:以前からWantedly を細々と運用していたのですが、CB部立ち上げ以降に本格的な運用をスタートしました。現在では社員のインタビュー記事なども頻繁にアップしており、それを社員にシェアしてもらうことでリファラルにつなげていくという取り組みを積極的に行っています。
内田氏:昨年の10月は入社者全員がリファラル採用でしたよね。5名ぐらいだったと思いますが。

内田氏:CB部では毎日朝会がありますし、週一の定例会でも互いの取り組みや結果、数値などに関する情報共有を欠かさずに行っているので、広報担当だから人事や総務が何をしているかわからないということはないですね。
柳氏:職種によって繁忙期が異なるので、互いに業務を補完し合うことも珍しくありません。採用が忙しいときには内田にスカウトメールの配信を手伝ってもらうこともありますし、年末などは人事担当や広報担当も含めてみんなで年末調整をしていました。
内田氏:先ほどご紹介した「CBplus」の運用は基本的に広報セクションで行っているのですが、CB部のメンバー全員が毎月2本ずつ記事を更新するローテション制で回しています。
柳氏:ファシリティもインナーブランディングの一環ですから、CB部の業務に含まれています。当社は昨年夏にオフィスを移転したのですが、オフィスのレイアウトや配色もすべてCB部が担当しました。たとえばリフレッシュスペース一つにしても、「社員間のコミュニケーションを活性化させるためにはどこに配置するべきか」ということを何度も検討しながらレイアウトを決めていきました。
柳氏:経営から降りてきたものをCB部が具現化することもありますし、CB部内で行っているブレストの場を中心に、自分たちでアイデアを出し合って実現していくものもあります。割合としては半々ぐらいでしょうか。

柳氏:社員の声に耳を傾けることも大切にしていますが、どちらかと言えば経営サイドの「こういう会社にしていきたい」という思いを汲み取り、それを社員に伝えていくことを重視しています。社員の話だけを細かく聞きすぎてしまうと、会社が向かいたい方向性や掲げているビジョン、ミッションとのズレが生じてしまうこともありますからね。
柳氏:もちろん、会社は社員で成り立ちますし、社員に向き合う必要はあります。しかし、私たちは経営と密にコミュニケーションを取り、その経営方針や理念をどのように社員に浸透させるかが重要なミッションです。そこはぶらさないようにCB部一同心がけています。
会社で働く意味を作り出し、発信していくことで社会全体を活性化させたい

柳氏:CB部立ち上げ前に52パーセントだった離職率ですが、現在では34パーセントまで低減しています。また、採用コストは180万円から50万円に下がっています。一人当たり130万円も削減できていることになるので、これは本当に大きな成果だと考えています。採用にかける工数やコストが削減された分だけ、PRに注力できるようになったことも私たちにとっては大きいですね。
柳氏:CB部立ち上げ以降は、採用時にもビジョン、ミッションをしっかり伝えてきましたし、そこに共感してくれた方が入社していることもあって、以前と比べると協力的な社員が増えたと思います。社内イベントなどのコミュニケーション施策も進めやすくなりましたし、採用インタビューやリファラル採用なども同様です。多くの社員が進んで手を挙げてくれるようになりました。
内田氏:みんながオルトプラスという環境を大事にしていて、自分たちが何をすべきか、どうしていきたいかを考えられている状況が生まれていることは私たちによって大きなやりがいですね。

柳氏:フリーランスで働いている方が10万人を超えたという話もあるなど、人が企業に属して働く意味が希薄になりつつあるご時世ですが、だからこそ「どうして会社で働くのか」という意味を作っていきたいと思いますし、作った意味を広く発信していきたいとも考えています。若干大げさな話になってしまいますが、オルトプラスに限らず会社で働く多くの人たちを幸せにすることによって、社会全体を活性化させていきたいという思いがあります。
柳氏:CB部では実際に成果報酬型採用代行「HRsync」、さらにはソーシャルメディアPR代行「PRsync」という2つの新規事業を立ち上げています。バックオフィスの私たちが事業を手がけるなどとは想像もしていませんでしたが、離職率や採用単価を大幅に下げたという実績を活かし、CB部のノウハウをパッケージ化することで多くの企業の方々のお役に立ちたいと考えています。
柳氏:「兼務すると業務が多くて大変だ」と兼務をネガティブに捉える人も多いのですが、私自身は「何をするか」よりも、「何のためにするか」ということを大切にしているので、さまざまな業務を兼務できることはラッキーだと考えています。部署や職種の垣根にとらわれることなく、本質的な課題を見つけ出して解決していくというアクションに意義を見出せるようになれば、どんな環境であっても楽しく働けると思います。

【取材後記】
インナーブランディングや社員のエンゲージメント向上となると、どうしても新しい施策や制度の構築・運用ばかりに目が向きがちになります。しかし、オルトプラスのCB部は、ビジョンやミッション、バリューといった価値観の発信を最優先で行い、社員に価値観や共通言語が十分に浸透した段階でコミュニケーション施策を行うことによって、施策・制度の効果をより一層高めることに成功しているようです。
さらにはインナーブランディングによって社員のエンゲージメントが高まることにより離職率が下がり、リファラルが促進され、採用コスト自体も大幅に下がるといった好循環が生まれているのが現在の同社です。人事、広報、総務、それぞれの担当者が同じ部署内で協業しているからこそ得られる効果も大きいとは思いますが、社外に対するコーポレートブランディングや採用ブランディングに苦戦しているようであれば、柳さんが語っていたように「まずは社内から作っていく」という発送の転換が必要なのかもしれません。
(取材・文/佐藤 直己、撮影/石山 慎治、編集/齋藤 裕美子)