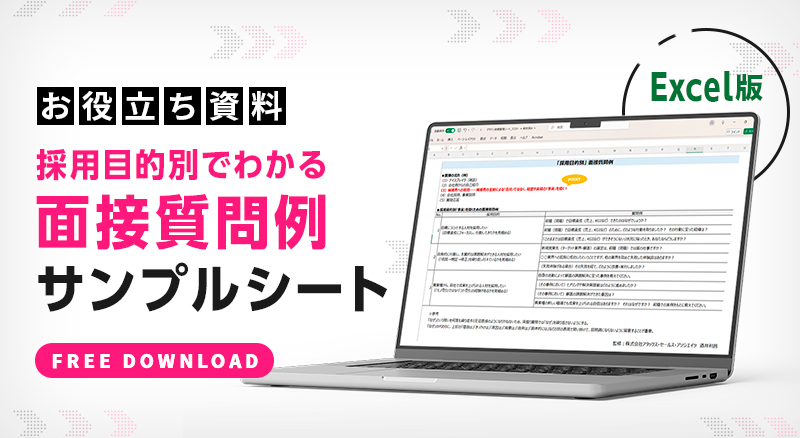採用稟議書とは?承認される稟議書の書き方を解説【フォーマット&例文付】


d's JOURNAL
編集部
企業が採用活動を行うには、採用稟議書という書類を作成して、関係部門や上長の承認・決裁を受ける必要があります。採用活動を予定通りに行うためにも、承認がスムーズに進められる採用稟議書を作成したいところです。
本記事でお伝えする必要項目や作成のポイントを把握し、隙のない採用稟議書を作成しましょう。
採用稟議書とは
企業が採用活動を行うに当たり、社内で必要な決裁を得るための書類を「採用稟議書」といいます。
新たな人員の募集や採用は、社内担当者の一存では決められないため、決裁権のある関係部門や上長の承認を得る必要があります。その承認を得るために、採用稟議書を作成・提出するのです。
また採用稟議書は、単に承諾を得るだけでなく、その後の採用業務を円滑に進めるという役割もあります。例えば、求人募集の内容や採用の予算などの採用計画を稟議書に明記することで、採用活動の方針が社内で共有され、必要な業務を効率的に進められるようになるでしょう。
採用活動で採用稟議書が必要な2つのケース
人事・採用担当者が採用稟議書を作成する必要のある、2つのケースについて解説します。
1.求人募集を開始するとき(募集のための稟議書)
2.採用したい人材が決まったとき(入社のための稟議書)
1.求人募集を開始するとき(募集のための稟議書)
新たに人員を募集することが決まったら、募集を開始する前に採用稟議書を作成します。詳細は後述しますが、採用稟議書の作成に当たっては採用予定人数や職種、予算やスケジュールなどを記載しましょう。
採用稟議書の内容に対して承認・決裁を得ることで募集を開始できます。
この後の採用活動では、求人広告の作成を目的とした取材対応や、選考のための面接など、社内で協力を仰ぐ場面も出てくるでしょう。そのようなときに協力を得られるよう、事前に情報を共有して合意を得るという意味でも、採用稟議書に詳細な情報を記載して決裁を得る必要があります。
2.採用したい人材が決まったとき(入社のための稟議書)
採用したい候補者が決まったタイミングでも改めて採用稟議書を作成して承認・決裁を得ます。こちらも詳細は後ほど解説しますが、採用決定後の採用稟議書には「どのような候補者を、なぜ採用するのか」を記載します。
ここで関係部門や上長に情報を共有することで、採用後の教育体制の構築をはじめとする受け入れの準備を進められるのです。
【求人募集開始時】採用稟議書に必要な項目と書き方
求人募集を開始する際、人事・採用担当者が稟議書に記載する項目とその書き方を紹介します。また、求人募集開始時に使える稟議書のフォーマットもダウンロード可能ですので、ぜひ活用してください。
【求人募集開始時】採用稟議書に必要な項目
●採用予定人数・配属先・職種・雇用形態
●募集理由
●募集期間・入社予定日
●応募資格(応募要件)
●募集方法・費用
採用予定人数・配属先・職種・雇用形態
求人募集を開始する際には、「どこのポジションで何人採用する必要があるのか」を明確にしておく必要があります。「1人」「2~3人」「10人程度」といった採用予定人数、「●●事業部●●グループ」のような具体的な配属先、「営業職」「SE」「コールセンター業務」「接客業務」といった職種、「正社員」「契約社員」「パート」などの雇用形態を稟議書に記載しましょう。
募集理由
求人募集開始時には「どうして今、求人募集をする必要があるのか」という情報が必要になります。意思決定者に求人募集の必要性を認識してもらうため、稟議書には具体的な募集理由も記載します。
募集理由の例文
| 新規事業に伴い、 新たな人材が必要な場合 |
今後、●●部で新たに●●の事業を展開する予定です。それに当たり、●●のスキルを持った人材が必要になるため、求人募集を希望します。 |
|---|---|
| 退職者が出たことにより、 新たな人材が必要な場合 |
●●月に●●部で▲▲人が退職しました。退職者が担当していた業務を引き継ぐ際に、現在の従業員では補いきれないため、新たに人材の募集を希望します。 | 業績向上により、 新たな人材が必要な場合 |
先月から●●の売上が好調です。顧客対応に伴う残業が増え、社員の疲労が蓄積しているため、●●担当を増員する必要があると判断し、求人募集を希望します。 |
募集期間・入社予定日
事業拡大や欠員補充が目的で人材を募集する際は、「いつまでに入社してもらいたいのか」を考えた上で、それに間に合うように「いつからいつまで募集をかけるか」を決める必要があります。
募集方法によって採用までの期間が異なるほか、まとまった人数を採用したい場合や特別なスキルのある人材を採用したい場合に、なかなか候補者が集まらないことも想定されます。入社予定日から逆算して計画的な募集期間を設定し、採用稟議書に記載しましょう。
応募資格(応募要件)
人材を募集する際、「どのようなスキル・経験がある転職希望者を採用したいのか」を明確にする必要があります。
選考基準があまりにも高いと、「候補者が見つからない」「入社予定日までに採用が決まらない」といった可能性もあるため、採用する際の最低基準について、関係者の合意を得ておくことが重要です。「業務経験」「保有資格」「未経験可」といった応募資格を採用稟議書に記載しましょう。
募集方法・費用
求人広告や人材紹介サービスなどの中から、どのような募集方法を用いるのかを採用稟議書に記載します。
また、募集に伴ってどれくらいの費用が発生するのかも、意思決定者が判断する上での重要事項となります。そのため、募集にかかる費用も事前に確認しておきましょう。
【採用決定時】採用稟議書に必要な項目と書き方
採用決定時に人事・採用担当者が採用稟議書に記載する項目とその書き方を紹介します。また、採用稟議書のフォーマットも用意しておりますので活用ください。
【採用決定時】採用稟議書に必要な項目
●採用予定者についての情報
●採用理由
●入社予定日
●就業場所・職種・仕事内容
●労働条件
採用予定者についての情報
ほとんどの企業では、一部の関係者のみで選考を行い、その情報を基に合否を判断する必要があります。「名前」や「年齢」といった基本情報に加えて、採用基準となる「業務経験」や「保有資格」を満たしているかなど、採用予定者についての情報を記載し合意を得ましょう。
採用理由
採用予定者に関する情報とともに、採用の決め手となったポイントやその候補者の強みなど、具体的な採用理由を記載しましょう。
採用理由の例文
| 採用理由が経験・実績 | ●●の業務経験が豊富なだけでなく、コミュニケーション能力が高く、チームメンバーと協力して▲▲プロジェクトを進めることが期待できるため、採用を希望します。 |
|---|---|
| 採用理由が保有資格・スキル | ●●の資格を保有しているだけでなく、実際に●●の資格を活かして前職では▲▲に取り組むなど、実行力があると判断したため、採用を希望します。 |
| 未経験者の採用 | ・今後、事業展開を予定している▲▲事業に関する知識を独学で身に付けるなど自己啓発に積極的で、向上心があると判断したため、採用を希望します。 ・前職では●●プロジェクトのマネージャーを担当するなど統率力があり、将来の幹部候補になることが期待できるため、採用を希望します。 |
入社予定日
新しい人材を雇う場合、入社日までに「入社後の研修の準備をする」「指導役を決める」「制服やPCなど業務で必要な備品を用意する」などの対応が必要になります。「●●年7月1日入社予定」といったように具体的な入社予定日を採用稟議書に明記し、事前準備を促しましょう。
就業場所・職種・仕事内容
新しい人材にどこでどういった業務を担当してもらうのかも、意思決定者が求めている事柄です。「本社」「大阪支社」「横浜支店」といった就業場所と、「企画職」「商品開発」「カウンター業務」といった職種を稟議書に記載しましょう。
また、「担当してもらうクライアント」や「携わってもらうプロジェクト」などの仕事内容を具体的に記載することで、意思決定者がより具体的な内容をイメージできます。
労働条件
雇用するに当たっての「就業時間」や「休日」「賃金」「加入保険」などの労働条件を採用稟議書に明記しましょう。
労働者に対して交付する「労働条件通知書」の項目を記載しておけば、併せて合意を得られます。労働条件の項目は就業規則で定めていることも多いため、内容を確認しながら記載するとよいでしょう。
(参考:『【記入例・雛型付】労働条件通知書とは?雇用契約書との違いや書き方をサクッと解説』)
採用稟議書の提出から承認までのスケジュール
採用稟議書を提出してから承認されるまでの期間は、数日~2週間程度が目安です。これはあくまでも目安であり、承認者の数などによっても左右されるため、可能な限り余裕を持って提出することを心がけましょう。
なお、採用稟議書の工程は「作成したものを提出して、承認を得る」とまとめるとシンプルに思えますが、必要なフローを細分化すると以下のような流れとなります。
1.採用稟議書を作成する(起案)
2.あらかじめ関係者の了承を得ておく
3.直属の上司に採用稟議書を提出する
4.承認経路に従って承認が進められる
5.決裁権限のある者により採用稟議書が決裁される
上記2の工程を見るとわかるように、採用稟議書を作成したら提出前に「根回し」を行うのがポイントです。承認者など、採用稟議書の内容に関係する社内の相手に情報を共有しておくことで、その後の承認や決裁後の施策実行がスムーズに進みます。
なお実際の承認は、社内の規定に基づいて複数人により進められることが一般的です。そのため、余裕を持って提出する必要があります。
また、承認の途中で採用稟議書の内容に不備が発覚した場合は差し戻されるので、その際は速やかに対応しましょう。
最後に、決裁者が「決裁」を行えば、採用稟議書に記載した内容で採用活動を進められます。
採用稟議書のフォーマットと例文
先述したように、採用稟議書が必要となる場面は「求人募集を開始する際」と「採用が決まった際」の2つあり、それぞれの場面で記載する内容も異なります。
ここではケース別にフォーマットと例文を紹介するので、採用稟議書の作成が初めてとなる人事・採用担当者は、ぜひ役立ててください。
【採用稟議書のフォーマット例】
●求人募集開始時の記入例
●採用決定時の記入例
求人募集開始時の記入例
まず、求人募集を始めたい場合の採用稟議書の記入例を項目ごとに紹介します。
| 件名 | 営業部門の中途採用について |
|---|---|
| 導入文 | 営業部門での新規採用について、ご承認をお願い申し上げます。 |
| 採用目標 | ●採用予定人数:3名 ●雇用形態:正社員 ●募集職種:営業職(▲▲事業) ●募集期間:令和●年●月~●月 ●入社予定日:令和●年●月●日 |
| 採用目的 | 当社は今後、▲▲事業の拡大を予定しています。しかし現在の営業メンバーは既存業務に追われており、▲▲事業に専念することが困難な状態となっています。 そこで▲▲事業に関連する知識を持ち、一定の営業経験のある人材を営業職として中途採用することで、▲▲事業の成長につなげたいと考えています。 |
| 募集要項 | ●学歴:不問 ●経験:▲▲事業に関する営業経験1年以上 ●資格:不問 ●その他:コミュニケーションスキルが高いこと、責任感・協調性があること、基本的なPCスキルがあること(Word、Excel、PowerPoint、ビジネスメールのやり取りなど) |
| 選考方法 | ●書類選考:顔写真付き履歴書、職務経歴書 ●一次面接:人事部長、営業部長 ●二次面接:社長 |
| 採用予算 | 100万円(求人広告費、面接交通費等) |
| 給与体系 | ●月給30万~40万円(固定残業代月30時間分を含む) ●賞与年2回 ●各種手当(通勤手当、住宅手当等) |
求人募集を開始する際の採用稟議書では、「なぜ採用するのか」「どのように進めるのか」「どれくらいの費用をかけるのか」を明確に示すことが大切です。
採用決定時の記入例
続いて、人材の採用が決まった場合の採用稟議書の記入例を紹介します。
| 件名 | 営業部門の中途採用者決定について |
|---|---|
| 導入文 | 営業部門の中途採用者が決定しましたので、報告いたします。 |
| 採用者情報 | ●名前:●● ●● ●経歴:■■大学卒業後、株式会社●●にて営業職として5年間勤務。▲▲事業に関する知識・営業実績が豊富。 |
| 採用理由 | ●書類選考では、営業実績が豊富であることに加え、マネジメント経験もあることから、営業部の発展に貢献できる人材だと判断しました。 ●面接では、これまでの営業活動で蓄積した▲▲事業に関する知識や経験を詳しく説明しており、仕事に対する熱意と視座の高さを感じました。 ●コミュニケーションスキルも高いため、社内外問わず適切に連携し、積極的に営業活動を行える人材だと考えます。 ●なお、求人募集時の稟議書に記載した条件を全て満たしています。 |
| 採用条件 | ●雇用形態:正社員 ●月給35万円(固定残業代月30時間分を含む) ●賞与年2回 ●各種手当(通勤手当、住宅手当等) |
| 入社日 | 令和●年●月●日 |
採用決定時の採用稟議書では、「どのような人材を」「なぜ採用するのか」を明記します。また、求人募集時の採用稟議書と整合性が取れている必要があるため、齟齬(そご)がないかよく確認しましょう。
採用稟議書で承認を得るためのコツ
採用稟議書の主目的は、決裁権のある担当部署や上長から採用活動に関する承諾を得ることです。
そのためには、ただフォーマットに沿って作成するのではなく、いくつかのコツを押さえる必要があります。
【採用稟議書のフォーマット例】
●重要な点をわかりやすく記載する
●想定されるリスクと対処方法を明記する
●データや見積書を用意する
●関係者に事前共有する
重要な点をわかりやすく記載する
採用稟議書を作成する上で、誰が読んでも内容がわかるように記載することは、大前提です。内容が伝わらなければ承認に時間がかかったり、差し戻されたりする可能性があります。
「何を承認してほしいのか」「何を伝えたいのか」を整理しつつ、情報を過不足なく盛り込みましょう。
また、専門用語を多用しないことも大切です。専門用語は可能な限り一般的な言葉に置き換えて、置き換えが難しいものは注釈を記載することをお勧めします。
想定されるリスクと対処方法を明記する
採用稟議書の内容を実行するにあたり、想定されるリスクやデメリットについてあらかじめ言及しましょう。
なぜなら、理想論だけでなくリスクなどの地に足のついた内容が書かれていることで、誠実さが伝わるためです。
例えば、予算に関しては「なぜこの金額なのか」「万が一、予算を超える場合はどのように対処する想定なのか」といったように、根拠とリスクの対処法を記載しておくことが大切です。
データや見積書を用意する
過去のデータや見積書など、具体的な根拠が添付されていると、承認者や決裁者にとって判断の一助となります。過去にも採用活動を実施した場合は、そのときのデータを添付することで「過去の実績に基づいて、今回はこのように判断している」という根拠を伝えられるでしょう。
関係者に事前共有する
採用稟議書を提出する前に、関係者に対し個別で情報を共有しておくことも、承認してもらうためのコツとして挙げられます。
採用稟議書を突然提出するのではなく、「なぜ、今採用活動を行いたいのか」を伝えておくことで、採用稟議書の内容を理解するための補助線となり、承認をスムーズに得られる可能性が高まります。
上司との直接の会話や会議中など、適切なタイミング・手段で伝えましょう。
採用稟議書を書くときの注意点
採用稟議書の作成する際に、3つの注意点も押さえる必要があります。
【採用稟議書を書くときの注意点】
1.決裁者視点で採用の必要性が判断できる内容を記載する
2.余裕のあるスケジュール設定をする
3.必要情報を過不足なく記載する
決裁者視点で採用の必要性が判断できる内容を記載する
決裁者の目線で考え、新規採用を行うにふさわしい内容を採用稟議書に明記することを忘れてはなりません。たとえ内容がわかりやすくとも、根拠が不足していれば、残念ながら承認してもらえない可能性があります。
先ほど紹介した記入例を参考に、「現状に対して、なぜ採用活動を行う必要があるのか」「なぜ、この候補者を採用したいのか」を客観的な理由とともに記載しましょう。
余裕のあるスケジュール設定をする
採用活動を始めたい時期や、候補者の入社日から逆算して、余裕のある日程で採用稟議書を提出することも大切です。
採用稟議書を提出してから決裁されるまでの目安は数日~2週間程度です。担当者が出張していたり、繁忙期で承認まで手が回らなかったりすると、想定よりも日数がかかる可能性もあります。
また必要に応じて、承認者や決裁者にリマインドを行うことも検討しましょう。
必要情報を過不足なく記載する
採用稟議書の内容に記入漏れや情報の不足がないように記載する、という点にも注意が必要です。不備があると差し戻される可能性もあり、そうなると決裁までに時間がかかってしまうことも考えられます。
特に注意したい項目としては、募集要項や採用コストなどが挙げられます。「採用稟議書の内容と実態が違っていた」といったことのないよう、よく確認した上で必要な内容を記載しましょう。また、採用決定後の採用稟議書では、候補者の履歴書や職務経歴書なども資料として添付する必要があります。
採用稟議書の作成は、採用活動を行う上で必須
採用活動は企業の経営や業績にも関係するため、関係者と事前に情報を共有し、採用稟議書を通じて合意を得る必要があります。採用稟議書を作成する際は、ぜひ本記事でお伝えした内容をご参考ください。
求人募集や採用を適切なタイミングで行えるように、社内での稟議のフローを事前に確認し、余裕を持って取りかかることも大切です。
(制作協力/株式会社eclore、編集/d’s JOURNAL編集部)
採用目的別でわかる面接質問例サンプルシート【Excel版】
資料をダウンロード