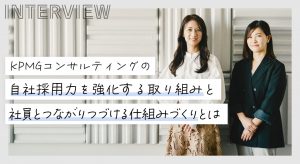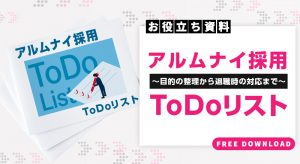アルムナイ採用の成功共通点は「つながり」。再入社者に聞いた前職に戻った理由とは

-
再入社の決め手は「かつての上司・同僚とのつながり」。退職時には転職や独立などの選択肢を理解し、出口で気持ちよく送り出すべき
-
他社を経験することで、自社の強みと弱みが見えるようになる。アルムナイは「自社の足りないところへアプローチしてくれる」存在
-
再入社の手段をつくる前に、現役メンバーの従業員体験を向上させる。アルムナイへの取り組みは新たに入社する人にとっても安心材料
卒業生や同窓生を意味する「アルムナイ」。人材採用の厳しさが増す中、一度自社を退職した人の再入社を歓迎するアルムナイ採用の動きが広がっています。過去の退職者とのネットワークをつくったり、再入社をスムーズにする制度を整えたりと、新たな取り組みを進めている企業も多いのではないでしょうか。
一方で気になるのは、再入社を決めた人の動機や心理です。以前勤めた企業への出戻りを決意した理由は何だったのか。再入社によってどのようにキャリアが広がったのか。この記事では「パーソルキャリアを一度退職し、再入社した」3人と、アルムナイプロジェクトに取り組む人事・採用担当者に話を聞き、アルムナイ採用のポイントを探ります。
 アルムナイ採用でパーソルキャリアに再入社した3名。左から、濱田氏、藤本氏、鈴木氏
アルムナイ採用でパーソルキャリアに再入社した3名。左から、濱田氏、藤本氏、鈴木氏
再入社の決め手は、かつての上司・同僚の言葉だった
——みなさんがパーソルキャリアに再入社した経緯を教えてください。
鈴木氏:私はパーソルキャリア戻るつもりはなかったんです。当社を退職した後はSaaS系ベンチャー企業に挑戦し、マネジメントを務めながら試行錯誤していました。
そんなときに、パーソルキャリア時代の上司と会い、仕事やキャリアについて相談する機会がありました。転職先はとてもいい会社だと感じていたものの、自分が本当にやりたいことをできていない気もする…。そんな考えを打ち明けたところ、「その悩み、うちなら払拭できそうだから戻ってこない?」と言ってもらえたんです。パーソルキャリアが嫌で辞めたわけではなかったので、「戻る道があるのならぜひ!」と思いました。
濱田氏:私は、以前に担当していた求人広告とは違う領域の法人営業を経験するためにITベンチャー企業へ転職しました。SaaSプロダクトのインサイドセールスやカスタマーサクセスを一通り経験。最初はうまくいき、業績も上がっていたのですが、違和感を徐々に覚えるようになりました。SaaSではプロダクトを売って終わりではなく、顧客に使い続けてもらうことが大切。しかし実際は1年程度での解約が多く、決して顧客満足度が高いとは言えない状況でした。自分が信じ切れないプロダクトを売り続けるのがしんどくなっていたんですよね。
そこで転職活動を始め、ストレングスファインダーを使って自分の強みと向き合った結果、「個別化」や「親密性」など、キャリアアドバイザー(以下、CA)向けの特性があることに気付きました。新たにCAに挑戦するなら、幅広い領域を支援でき、昔の仲間にも支援してもらえそうなパーソルキャリア以外に考えられませんでしたね。かつての同期がCAを務めていたので、現場の実情なども聞かせてもらった上で再入社を決めました。

藤本氏:私は、パーソルキャリアを辞めたときの自分は「視野が狭かった」と感じています。人材紹介サービスのリクルーティングアドバイザー(以下、RA)を務める中で、一担当者として世の中へ及ぼす影響が小さいと感じてしまっていたんです。そこで、人事側に回ってみたいと思い転職しました。
でも外に出てみると、パーソルグループの影響力を改めて感じることにもなりました。人事・採用担当者としてセミナー受講などを検討していると、登壇者にはパーソルキャリアの人がたくさん。人事・採用担当者をやっているとパーソルグループの名前を見ない日はありません。それに、人事・採用担当者の立場では転職希望者個人のインサイトがなかなか見えないという現実にも直面しました。そうした情報をキャッチするソリューションとして、人材紹介事業の価値を改めて感じたんですよね。「本当はもっとやれることがあるのでは?」と思い、以前の上司に感情を吐露して、再入社を勧めてもらいました。
——さまざまな理由がありますが、以前の上司や同僚とのつながりが決め手になったことは共通していますね。再入社の際に不安はありませんでしたか?
鈴木氏:ありませんでしたね。以前のつながりが続いていましたし、再入社のアクションを支援してくれる人もたくさんいましたから。
濱田氏:私は不安でしたよ。それまでは法人営業のキャリアだけで8年。CAのように個人に向き合う仕事の経験がなく、その先のキャリアもイメージできていませんでした。だからこそ、リアルな実情を教えてくれた同期の存在が大きかったです。
藤本氏:私の場合は以前の退職から日が浅く、もとの所属組織に戻る前提だったので、不安はありませんでした。短期間の出戻りなので周囲の目は気になりましたが、組織内にはすでに出戻りの先例をつくってくれた先輩が2人いたので、そこまでプレッシャーを感じることはありませんでしたね。
他社を経験して気付いた、自社の「強み」「課題」
——再入社後、仕事への向き合い方に変化はありましたか?
藤本氏:RAという職種の捉え方が大きく変わりました。以前は役割に限界があると思っていましたが、転職時に感じた「もっとできることがあるはず」という思いによってその壁がなくなり、再入社後は人材紹介サービス以外のソリューションも含めて積極的に提案するようになりました。自分自身が人事・採用担当者を経験したことで、人事側の忙しさや苦労を理解できるようになったことも大きかったですね。
濱田氏:私は、パーソルキャリアに戻ってきてからはとても充実していて、心から幸せを感じています。私がマッチングできたからこそ実現する転職があり、感謝の声もたくさんもらえるんです。以前は月曜日が嫌で仕方なかったのですが、今はまったく苦になりません。現在の組織では法人営業の経験者が少なく、企業側の理屈をなかなか想像できない面もあるので、法人営業キャリアの強みも活かせていると感じます。

鈴木氏:私は再入社後、以前よりも役割が広がりました。SaaS系ベンチャーでの強固な営業スキーム構築の経験を活かし、リード獲得のマーケティングとインサイドセールスの強化を担当しています。マーケティングツールを使い、データ活用につなげる仕事なども担うようになりました。一度転職したことを大いに活かせていると感じます。
——別の企業を知ったからこそ、自社の組織風土の強みが見えるようになった面もあるのでしょうか。
濱田氏:それはありますね。パーソルキャリアには人に関心を持ち、相手の話を親身になって聞こうとする人が多い。もともと新卒で選んだ会社なので、カルチャーへのマッチングを改めて感じています。
藤本氏:戻ってきてからは、仕事を楽しむための仕組みづくりを一生懸命やる会社なのだと再発見しました。パーソルキャリアの「はたらいて、笑おう。」という価値観について、以前は当然のことのように思っていたのですが、他社へ転職してみるとそれが当たり前ではないことに気付いたんです。パーソルキャリアでは、社員のモチベーションを高めるための施策やイベントが本当に多いんですよ。
鈴木氏:ただ、人によってはやりがいを感じにくい部分もあるかもしれません。SaaS系ベンチャー企業では、規模の小さい企業が多いこともあり、良くも悪くも数字を重視する文化がありました。一方、パーソルキャリアは企業規模が大きいが故に、一人ひとりの仕事がどこまで全社業績につながっているのか見えづらい面もあるのかもしれません。
まずは現役メンバーの従業員体験を向上させるべき
——アルムナイ採用担当の篠崎さんに聞きます。企業側から見て、アルムナイの再入社にはどんな意義を感じていますか?

篠崎氏:通常の中途採用と比較して、アルムナイの皆さんは人材育成の観点でも組織開発の観点でも、圧倒的になじむスピードが速いと感じます。
もともと在籍していた会社なので社内風土や作法を理解していますし、当社の経験と外部での経験を良い形でミックスしてくれることも心強いです。鈴木さんが指摘していたように、自社に足りないところへもアプローチしようとしてくれます。
また、採用ブランディングの観点でも企業としてはありがたいですね。中途入社する人や新卒入社する人にとっても、アルムナイの存在が安心感につながっているようです。アルムナイは「卒業したら関係が終わるわけではない」という企業の姿勢を体現してくれている存在なのだと思います。
——再入社制度を設計・運用する上で留意すべきことは。
篠崎氏:制度設計をする際には再入社に向けた集客や仕組み・枠づくりなどに目が行きがちです。しかし、そもそも就業時に満足していなければ再入社を検討してもらえません。再入社の手段をつくることと同時に、現役メンバーの従業員体験を向上させることが大切ではないでしょうか。
その上で「出口対策」も重要。人事・採用担当者の立場としては、従業員に退職されるのは悲しいことです。とは言え、その人の人生やキャリアを会社が全て背負えるわけではありません。転職や独立などの選択肢を理解し、出口で気持ちよく送り出せるよう、人事と現場管理職が意識を高めるべきだと思います。
この2つを同時に考えながら、再入社の定義付けや、受け入れ体制をどうするのかなどの設計をしていくのがお勧めです。
——アルムナイとの関わり方においては、どんなことを大切にしていますか?
篠崎氏:つながりの手段として、当社では2023年にアルムナイコミュニティを立ち上げました。アルムナイコミュニティのアプリを通じて、当社の今が見える仕組みを整えているほか、アルムナイ向けのイベントも定期的に開催しています。
再入社の選択肢だけではなく、現役従業員とのコラボレーションなども含めて、幅広い可能性を提案しています。

濱田氏:こうした機会が整備されていることで、従業員は「変な辞め方はできないな」と感じるようになるのかもしれませんね。退職時に揉めてしまうと再入社時のデメリットにつながり、自分のキャリアの可能性を狭めてしまうので。
藤本氏:良好な関係を保って辞めていくことは本当に重要ですよね。どんな経緯や理由があっても、最後は互いに理解し合って退職する。それが再入社を促進する第一歩ではないでしょうか。
鈴木氏:パーソルキャリアの場合は、誰かが退職する際にも「相手のキャリアを応援する」スタンスを貫く人が多いと感じますよ。だからこそ私たちは、退職後もパーソルキャリアとつながり続けていられたのだと思います。
取材後記
取材を終えて印象に残ったのは、アルムナイの3人が冷静にパーソルキャリアの今を見つめていることでした。他社を知ることで、自社の強みや弱みと率直に向き合える人が増える。それこそがアルムナイ採用に取り組む意義なのかもしれません。ただし、せっかくアルムナイが新しい視点を持ち込んでくれても、その提案を煙たがるような組織では活かしきれないでしょう。篠崎さんは「制度設計・運用を頑張るだけではなく、組織全体で異文化や新しいソリューションへの寛容性を持てるようにすることも大切」だと指摘していました。
企画・編集/髙橋享(d’s JOURNAL編集部)、野村英之(プレスラボ)、取材・文/多田慎介、撮影/塩川雄也
アルムナイ採用 ToDoリスト
資料をダウンロード