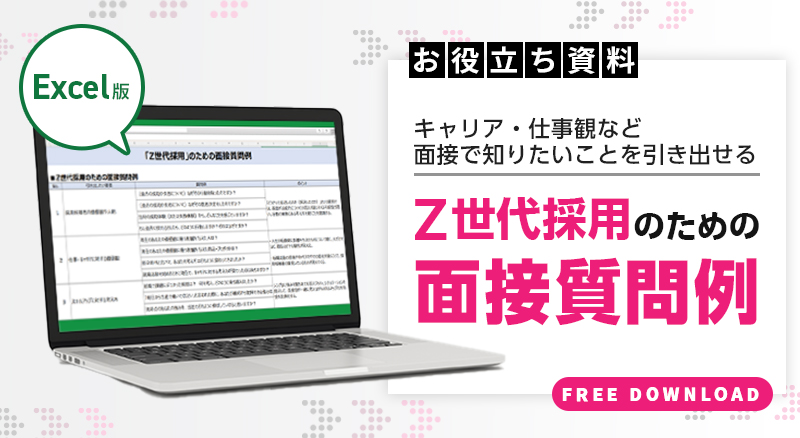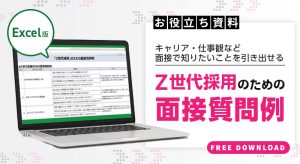Z世代の採用戦略とは?企業が押さえるべき施策とポイント
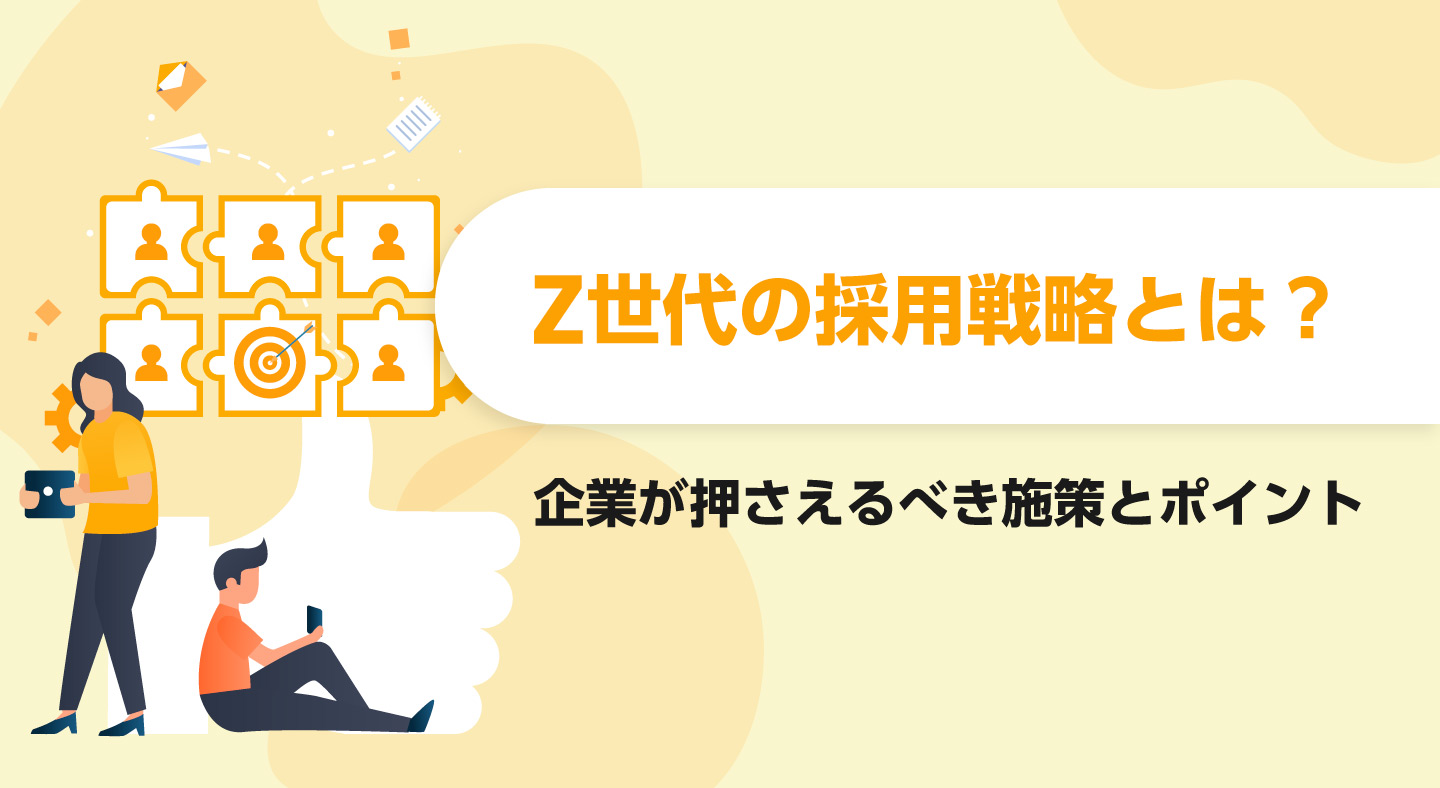

d’s JOURNAL編集部
近年の採用手法の多様化により、「求人を出して応募を待つ」という従来の受け身の戦略では、若年層の採用は難しくなってくるでしょう。持続的な企業運営のために、いわゆる「Z世代」の価値観や志向を理解した採用戦略を立てる必要があります。
本記事では、Z世代の定義や価値観を踏まえた上で、取るべきコミュニケーションと採用時のポイントを解説します。Z世代の採用を考えている企業は、ぜひ参考にしてください。
Z世代採用時に活用できる面接質問例を、下記より無料でダウンロードいただけます。採用活動の参考資料としてぜひご活用ください。
Z世代を採用する前に押さえておくべき基本知識
採用戦略を立てるに当たって、まずはZ世代の定義や特徴などを確認しましょう。
Z世代の基本知識
●Z世代の定義
●Z世代の特徴
●Z世代とほかの世代の違い
Z世代の定義は「1990年代後半~2010年代前半生まれの若者世代」
Z世代は、1990年代後半~2010年代前半に出生した世代を指します。インターネットやデジタル機器がすでに普及した時代に生まれ、扱いにも慣れていることから「デジタルネイティブ世代」とも呼ばれます。
それ以前の1960年代~1980年代半ば生まれは「X世代」、1980年代半ば~1990年代前半生まれは「Y世代」と呼ばれ、これに続く形で「Z世代」という言葉が登場しました。
なお、欧米の考え方が国内に広まったことで、この年代に生まれた世代を対象に使われている概念であり、明確な定義はありません。
Z世代の特徴は「PCよりスマホに慣れたデジタルネイティブ世代」
Z世代の大きな特徴は、デジタルネイティブという点です。PCよりもスマートフォンの方が使い慣れている傾向にあり、メールや電話ではなくInstagramやLINEといったSNSで主にコミュニケーションを取るとされています。
日常的にインターネットを利用することが当たり前の世代といえるため、情報収集の手法も多岐にわたります。X世代やY世代が主に活用しているGoogle検索ではなく、SNSを使って多面的な検索を行うことも特徴の一つです。
また、情報収集が多様化した環境下で育ったZ世代は、国内外のニュースにも関心を持ち、世界の社会情勢・環境問題に興味を抱く人が多い傾向にもあります。2011年に起こった東日本大震災をはじめとする大規模災害の経験から、人や環境の持続可能性を考える意向が強いとされています。
Z世代・X世代・Y世代の違いや特徴を一覧表で比較
時代や社会的な環境の変化に伴い、Z世代以外にもX世代やY世代など、さまざまな呼び名が使われてきました。以下の表で世代ごとの特徴を確認してみましょう。
Z世代とほかの世代の特徴
| 名称 | 生まれた年代 | 特徴 |
|---|---|---|
| X世代 | 1960年代~1980年代前半 | ●情報収集にさまざまなツールをバランス良く活用する ●個人主義的な考え、独立心が強い |
| Y世代(ミレニアル世代) | 1980年代半ば~1990年代後半 | ●デジタルパイオニアとも呼ばれる ●安定的な志向が強い |
| Z世代 | 1990年代後半~2010年代前半 | ●デジタルネイティブとも呼ばれる ●世界的な情勢、環境問題に興味を持つ |
| α世代 | 2010年代前半~2020年以降 | ●デジタルリテラシーがさらに高い ●プログラミング教育が必修となった |
このように、世代間でさまざまな特性がありますが、いずれも個人差があるものなのでその世代の全ての人に当てはまるわけではありません。あくまでも「世代的にはこういった傾向がある」という一つの目安として捉えてください。
Z世代が企業選びで重視するはたらき方や価値観
続いて、仕事や働き方に対するZ世代ならではの価値観を紹介します。
Z世代の仕事や働き方への価値観
●昇進よりも自己成長を重視する傾向
●多様性や社会課題に対する高い関心
●現実主義で効率の良い働き方を重視
●副業やパラレルキャリアに前向きな傾向
●福利厚生の充実度を重視
昇進よりも自己成長を重視する傾向
Z世代の多くは、従来のように「昇進=成功」といった価値観に強くこだわるわけではありません。役職や肩書よりも、自分らしく働ける環境や、スキルアップ・自己成長の機会を重視する傾向があります。
その背景には、「責任が重くなることへの不安」や「プライベートの時間を大切にしたい」という意識があり、ワーク・ライフ・バランスを損なうようなキャリアアップには慎重な姿勢を見せることもあります。また、Z世代は日本経済の停滞期に育ったことから、安定志向や現実的な価値観を持つ人が多いとも言われています。
ただし、これは「成長意欲がない」という意味ではありません。自分のペースでスキルを磨きたい、専門性を高めたい、社会に貢献したいといった前向きな意欲を持つ人も多く、企業側がその意欲を引き出せる環境を整えることが重要です。
例えば、昇進以外にも「専門職としてのキャリアパス」や「社内副業制度」「新規事業への挑戦機会」など、多様な成長の選択肢を提示することで、Z世代のモチベーションを高めることができます。
多様性や社会課題に対する高い関心
Z世代は新たな働き先を探す際に、性別や人種、文化の違いといった多様性を受け入れている、また社会問題に取り組んでいる企業かどうかを重視する傾向にあります。
中でも、SDGsに取り組んでいるか否かを重視する傾向にあり、より良い世界を目指すための企業姿勢を見られています。株式会社ネオマーケティングが調査した「日本と米国のZ世代意識調査:SDGs編」(※1)では、Z世代による社会問題への関心度が高まっていることがわかりました。
Z世代の採用を目指す場合には、会社として社会問題に向けて実践している施策をアピールする姿勢が重要です。
(参考:『ダイバーシティーとは何をすること?意味と推進方法-企業の取り組み事例を交えて解説-』)
出典(※1)『日本と米国のZ世代意識調査:SDGs編』
現実主義で効率の良い働き方を重視
Z世代の傾向として、ワーク・ライフ・バランスを優先し、効率の良い働き方を求める点も挙げられます。働き方改革により、ワーク・ライフ・バランスが世間的に重視されるようになった影響で、Z世代にとっても会社選びの際には大きな要素となるようです。
現実主義で自分自身の時間を大切にする人が多い傾向にあることから、仕事とプライベートのバランスが取れる制度が整っている企業かどうかを見極めているのです。残業時間がない、あるいは有給を取得しやすいといった条件も、働く上で重要視されるポイントといえます。
副業やパラレルキャリアに前向きな傾向
さまざまな社会情勢の影響を受けたことで、Z世代は複数の企業で活躍できるパラレルキャリアに関心を持つ傾向にあります。
パラレルキャリアは、本業とは別に、第二の活動としてキャリアアップやスキルアップを目指す働き方です。近年は「終身雇用」「年功序列」という考え方が薄くなってきており、転職や副業などでスキルアップを目指したいと考えるZ世代は少なくありません。
このような環境下でZ世代を採用するには、一つの職場、また従来の働き方に固執しない「副業解禁」など寛容な働き方の整備が求められます。
福利厚生の充実度を重視
Z世代は仕事での安定性を求める傾向が顕著です。そのため、福利厚生の充実度も欠かせない要素といえます。
しかし、単に福利厚生を充実させれば応募が増えるわけではありません。Z世代の特徴に合う、ワーク・ライフ・バランス系の「フルフレックス制度」や、自己啓発系の「資格取得補助」といった項目を充実させる必要があります。
Z世代に選ばれる会社となるよう、採用戦略の一環としてこのような福利厚生の整備を検討してみてはいかがでしょうか。
Z世代採用時に活用できる面接質問例を、下記より無料でダウンロードいただけます。採用活動の参考資料としてぜひご活用ください。
Z世代の応募者に効果的な採用手法
Z世代の採用を目指すに当たっては、その特性を押さえた上で適切な採用戦略を立てることが肝要です。インターネットやデジタル機器を駆使する世代という点を踏まえ、以下で紹介する2つの採用手法を取り入れてみてください。
SNSを活用した「ソーシャルリクルーティング」
まず挙げられる手法が、Z世代の主なコミュニケーションツールであるSNSを活用した「ソーシャルリクルーティング」です。
SNSはZ世代の多くが活用しているため、顕在化している転職希望者だけでなく、膨大な数の潜在層の人材にもアプローチできます。SNSをうまく活用して自社の魅力を多角的にアピールできれば、自社が求めるZ世代の人材の採用につながるでしょう。
ソーシャルリクルーティングに取り組む際は、目的に合わせてツールを使い分けることが重要です。例えば、会社説明会やイベントなどは最新情報をチェックしやすいX(旧:Twitter)、社内の雰囲気や社員の姿を伝えたいなら写真や動画で視覚的に訴えられるInstagramといった具合です。
どのツールを使うとしても、アカウントのフォロワー数を伸ばすまでに時間を要するため、効果が出ないからといってすぐに中止するのではなく、中長期的な視点で運用しましょう。SNS運用とSNS広告を併用することも検討すると良いでしょう。
(参考:『ソーシャルリクルーティングとは?メリットや進め方を解説』)
スカウトで心をつかむ「ダイレクト・リクルーティング」
SNS上での承認欲求が強い傾向にあるZ世代には、直接スカウトメールを送る「ダイレクト・リクルーティング」も有効な手法といえます。ダイレクト・リクルーティングでは、Z世代の転職希望者と1対1 のコミュニケーションを図れます。
転職希望者に対してメッセージを送る際は、前述したZ世代の特性をきちんと理解した上で、一つひとつに工夫を凝らしましょう。「この会社は自分を理解してくれている」「プロフィールを読み込んで興味を持ってくれている」と思ってもらえれば、自社への入社意欲を高められるはずです。
(参考:『ダイレクトリクルーティングとは?人材紹介サービスとの違いや導入のメリット』)
Z世代の採用で効果的なコミュニケーション方法
デジタルネイティブかつ、多様な価値観を抱くZ世代には、その特性を踏まえたコミュニケーションを取ることが欠かせません。ここでは、効果的な2つの方法を紹介します。
フラットな関係構築を促す「カジュアル面談」
Z世代の選考では、本選考の前にカジュアル面談を設けることをお勧めします。カジュアル面談は、企業とZ世代の転職希望者がフラットな立場で対話し、相互理解を深める場です。
カジュアル面談を実施すれば、自社の経営理念や企業文化に対して転職希望者がどの程度共感しているのかを確認できます。選考ではなく、あくまでもお互いを知る場となるため、転職希望者にも気軽に参加してもらいやすく、従来の採用手法では出会えない人材と出会える可能性もあります。
カジュアル面談によって、一人でも多くの転職希望者と交流し、良好な関係を続けることが、自社が求める人材を採用するための重要な一歩です。
(参考:『カジュアル面談とは?採用面接との違いや実施するメリット・当日の流れを解説』)
効率性を重視した「オンライン面談・面接」
インターネットやデジタル機器に慣れているZ世代に合わせて、オンラインでの選考も取り入れたいところです。カジュアル面談と同様に、多くの転職希望者と出会えるチャンスを増やす手立てとして、オンライン面談・面接は有効です。
Z世代は、働き方だけでなく求職活動でも効率性を求める傾向にあります。そのため、面接会場まで足を運ぶ手間の削減につながるオンライン面談・面接を設けることは、Z世代から好印象を抱いてもらうために必要な要素といえます。
(参考:『オンライン面接を徹底解明!メリット・デメリットや導入に当たっての注意点』)
Z世代の採用活動で意識すべき7つのポイント
最後に、Z世代の採用に踏み出すに当たって、意識したい7つのポイントを紹介します。
Z世代の採用で意識したいポイント
1.TikTokやYouTubeなど動画コンテンツを活用する
2.企業のビジョン・価値観は言語化して発信する
3.SNSや面談での透明性あるコミュニケーションを心がける
4.インターンシップや体験型プログラムを充実させる
5.若手が活躍できる多様なキャリアパスを提示する
6.社員インタビューで「リアルな働く姿」を伝える
7.ワーク・ライフ・バランスを整える
TikTokやYouTubeなど動画コンテンツを活用する
日常的にTikTokやYouTubeなどの動画サービスに触れているZ世代は、採用活動でも動画コンテンツを積極的に活用している傾向にあります。新型コロナウイルス感染症による影響を受け、オンラインでの採用活動を余儀なくされた背景も少なからず影響しているでしょう。
実際に働いている社員の声や職場の雰囲気、1日の仕事の流れなどを、動画にまとめて発信することで、テキストベースでの発信よりもZ世代からの興味・関心を寄せられるはずです。
企業のビジョン・価値観は言語化して発信する
Z世代の特性として、企業の存在意義や社会的貢献度などに共感するため、企業のビジョン・価値観は可能な限り明確に、かつわかりやすく伝えるような工夫は必須です。存在意義や社会貢献度などは具体的なデータやエピソードで可視化し、採用サイトやソーシャルリクルーティングなどであらゆる転職希望者に発信します。
SDGsや多様性への取り組みを示すことができれば、より共感や支持を得られる企業となり、応募数の増加も見込めるでしょう。
SNSや面談での透明性あるコミュニケーションを心がける
Z世代の採用戦略を成功に導くには、透明性の高いコミュニケーションを通して、企業の価値を相違なく伝えることが求められます。
何度も述べているように、Z世代はインターネットを巧みに使いこなすため、企業のリサーチ能力も高い傾向にあります。企業の口コミサイトや、SNSでの評判などを確認している人材が想定されるため、それを念頭に置いた戦略立てが欠かせません。
SNSアカウントやオンラインセミナーなどで転職希望者から質問があることを想定し、それに対する誠実な回答を用意しておくことをお勧めします。
インターンシップや体験型プログラムを充実させる
Z世代が働く上では、実際の業務内容や職場の雰囲気を重視する傾向にあるため、それを疑似体験できるような体験型のプログラムを充実させる工夫も必要です。
例えばプロジェクト型インターンシップを提供した場合、Z世代の転職希望者は与えられた課題解決に挑戦し、社員がフォローに入ることで、仕事のやりがいを肌で感じてもらえます。またジョブシャドウイングであれば、社員に半日から1日密着して仕事ぶりを観察してもらえるので、職場の雰囲気や企業文化をより深く理解してもらえる機会となるでしょう。
このような短期間でさまざまな社員と交流できる採用プログラムを提供することで、自社が求める人材の採用だけでなく、採用後の早期離職の防止も期待できます。
若手が活躍できる多様なキャリアパスを提示する
昇進よりも自己成長を重視する傾向があるZ世代の転職希望者は、自己実現を優先する傾向にあるため、企業の多様なキャリアパスを明示しましょう。
具体的には、研修制度や資格取得支援制度、ジョブローテーション、また社内副業制度や新規事業提案制度といった挑戦の場を提供した上で、自社の魅力を高める工夫が必要です。
また、若年層の社員向けのメンター制度や1on1、早期育成プログラムなどを通して、「年齢にかかわらず、活躍できる環境」という強みもアピールしましょう。
(参考:『1on1ミーティングとは|目的や得られる効果と導入・実施方法を解説』)
社員インタビューで「リアルな働く姿」を伝える
Z世代の転職希望者は、実際に働く社員や職場の様子を、具体的にイメージできる社員インタビューを求める傾向にあります。入社後に一緒に働くことになる先輩や同僚の人柄を事前に確認できることで、「この会社で働く自分」をより意識してもらえるようになります。
採用サイトに載せているテキストだけでは伝えられない自社の魅力を、社員インタビューによって発信し、Z世代の関心をつかみましょう。
ワーク・ライフ・バランスを整える
Z世代の多くは、効率の良い働き方を重視して企業を探すため、ワーク・ライフ・バランスを見直す必要があります。
例えば、有給消化率が低い、また残業が多い企業はZ世代からは敬遠される可能性が高いといえます。プライベートも充実させられるような環境を整えるために、「実労働時間の把握」「休日労働の場合の代休の有無を明示する」などといった対応を取りましょう。
そのほか、リモートワークと出社を組み合わせた「ハイブリッドワーク」を好む傾向にもあるとされています。フルリモートやフル出社という選択肢ではなく、それぞれを場合に応じて選べるような環境を整えておくことも、Z世代の採用につながる一歩かもしれません。
Z世代を採用するには「世代特性に合った環境づくり」が不可欠
本記事では、Z世代の採用戦略について詳しく解説しました。
Z世代は、インターネットやデジタル機器に慣れているため、採用活動での情報収集の手法は多岐にわたります。「転職希望者からの応募を待つ」という受け身の戦略では、Z世代の採用にはつながりません。
ソーシャルリクルーティングやダイレクト・リクルーティングを活用するなど、Z世代の特性に合わせた採用戦略を立てましょう。
Z世代採用時に活用できる面接質問例を、下記より無料でダウンロードいただけます。採用活動の参考資料としてぜひご活用ください。
(制作協力/株式会社eclore、編集/d’s JOURNAL編集部)
「Z世代採用」はどうすべき?すぐに活用できる面接質問例
資料をダウンロード