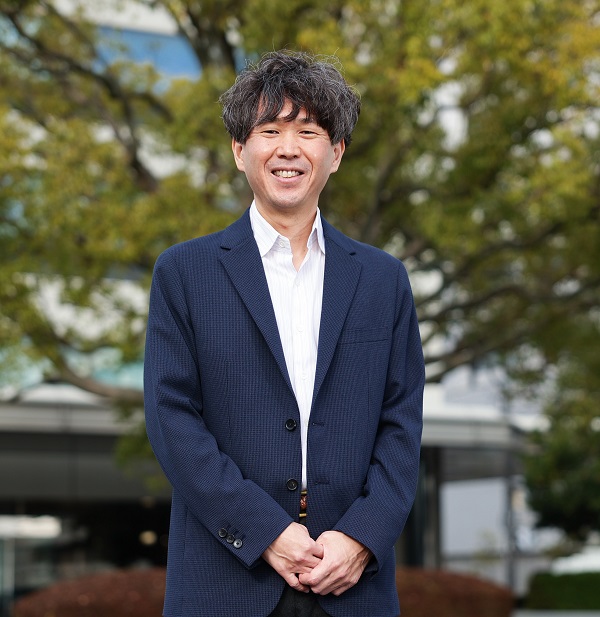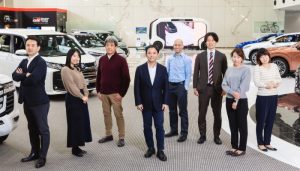マツダ「デジタル道場」でIT×製造業人材を変革。重要性増すシステムズエンジニアリングをどう強化する――?

自動車業界でSmall Playerのマツダは自動車づくりにおいて「人と共に創る独自性」をうたっている。その上でCASEと言われる業界大変革期を乗り越えるために人材育成にも余念がない。CASEの内「Connected(コネクティッド)」を担うマツダコネクト機能の開発現場ではどのようなビジョンを掲げてプロジェクトを推進、そして人材育成が行われようとしているのか。現場を担うリーダーたちの話しを伺った。
マツダの最先端技術のひとつ、マツダコネクトとは
新型車「CX-60 PHEV」の公開など、マツダ株式会社(本社:広島県安芸郡、代表取締役社長兼CEO:丸本明)に注目が集まっている。
同社は、CASE(※1)と呼ばれる変革の時代を迎えている自動車産業に対して、積極的に参画している。以下は、2030年に向けて同社が取り組むCASEに対応した新技術の商品化一覧(一部抜粋)だ。
■ 環境対応技術
・新世代ガソリンエンジン「SKYACTIV-X」
・マルチ電動化技術「SKYACTIV EV専用スケーラブルアーキテクチャー」
・マイルドハイブリッドシステム「Mハイブリッド」
■ コネクティッド技術・サービス
・日本・米国・欧州でサービス開始
・自動運転技術につながる先進安全技術
そしてこの「Connected(コネクティッド)」を担っているのが、同社の展開する「マツダコネクト」である。同社では搭載している車両のソフトウエアを常にアップデートして、最新のサービスを適時利用できるコネクティビティサービスのシステムだとしている。
マツダコネクトはカーナビ、エンターテインメント、コミュニケーション、セッティング、車両情報確認などができる機能が備わっており、最新版ではスマートフォンと連携して遠隔での車両状態確認やナビの目的地設定なども実装されている。
このマツダコネクトの機能・システムを開発しているのが、統合制御システム開発本部のマツダコネクト・コネクティビティ開発チームである。同チームは後述する安全運転支援技術「MAZDA CO‐PILOT CONCEPT(マツダ・コ・パイロット・コンセプト)」にも携わっている。
今回はこの開発チームの、先進的な取り組みや組織編成、次代のエンジニアを育てる育成環境などについて見ていこう。
次項からは、統合制御システム開発本部の主査 岡野英紀氏(以下、岡野氏)をはじめ、情報制御モデル開発部の池田和裕氏(以下、池田氏)、森田晃之氏(以下、森田氏)、仲野 雄二氏(以下、仲野氏)、さらに社内留学制度の活用で現在同部門に配属されているベガ・ラミレス・アントニオ氏(以下、トニー氏)のコメントを交えて紹介しよう。

自動車産業の最先端技術を担う「コネクティッド」、その開発チームとは
■ マツダコネクトとはどのようなプロダクトなのか
岡野氏:モバイルデータ通信の高速化や通信技術の進化によって、クルマがネットワークにつながり新たなサービスや機能を拡大できるコネクティッドカーへの需要が高まりました。もちろん世界中の自動車メーカーがこの技術の進歩に取り組んでおり、当社も例に漏れずしのぎを削っています。
当社のコネクティッドカーの中心システムとなるマツダコネクト・コネクティッドサービスは、ドライバー、クルマ、クラウド、環境とつながる情報(データ)のハブとして機能します。従来のナビゲーション機能のほかに、エンターテイメント、エマージェンシーコールなどつながるサービスなどともリンクしています。
新商品群では、Mazda3を筆頭にCX-30、MX-30、直近ではCX-5、CX-8などに車載通信機を搭載したマツダコネクトを選択(※2022年3月時点、Mazda3の一部のグレードを省く)できます。選択していただいたお客様には当社の充実したコネクティッドサービスの提供と利用ができるというものです。
マツダコネクトは日々進化しています。「何がお客様への価値につながるか」を大事に、私たちは開発を続けています。

■ 開発チームの業務について
池田氏:マツダは「人を中心とする」自動車開発を進めており、いわゆる「マツダらしさ」という価値を創造するために、マツダコネクト・コネクティッドサービスの技術開発に挑んでいるのが私たち開発チームです。
クルマを通じて、人とクルマをつなぎ、今までにない新たな価値を実現するのが主なミッションとなります。最近では「MAZDA SPIRIT UPGRADE」など、積み上げたデータからエンジン制御プログラムのさらなる進化・開発にも余念がありません。
主な担当は、クルマの内部構造を電子制御するECU(Electronic Control Unit)となります。マツダコネクトをよりユーザーが使いやすいものにするためにGUI(Graphical User Interface)といった分野もその管掌範囲です。社内に搭載されたディスプレイのグラフィックの見栄えなども担っています。
ですが、単純に機能を載せるだけでなく、HMIを構築・進化させ、その上で「古くならないシステム」を目指しています。アップデート可能なソフトウエアなど拡張性のあるシステム開発などには特に注力しています。
森田氏:コネクティッドの領域は、クルマそのものの機能だけではなく、スマホのアプリといった分野にまで関わってくるため、特にさまざまな部門や組織と密接に開発を進めていきます。私は車載通信機の分野の開発を主に担当しており、その管掌範囲を超えることもあります。
一般的な製造業の開発現場では、技術部門やカスタマー部門などアサインされているメンバーのバックボーンが違うため、要求することやその観点も違う。そのため要件定義などを行う際に、互いに共通言語や認識が合わず企画や開発の進行がうまくいかないケースがあります。
要求は技術畑でなければあいまいで抽象的になるので、そこをどう整合性をとってサービスとして成り立たせるのかが一番のポイントです。
当社には部門を超えて協働できる共創の文化があるため、上記のような課題に対し、全社で一枚岩となって自動車開発を進めていくことができる土壌があります。
とはいえ、コネクティッドは当社の中でも比較的新しい分野です。プロジェクト立ち上げ当初は、「どんな技術を追求するのか」「何をお客様に提供したいのか」が、部門間・メンバー間の中で目線が合っていなかったのです。
そこで、そうした要求や要望を吸い出して明らかにする活動を始めました。具体的には「まずお客様にどういう価値を提供していくか」を可視化する仕様書のようなテンプレートを作り、部門を超えて共通認識を持てるフローなどを確立しました。
今はコロナ禍で実現しないのですが、2年前まではみんなで大部屋に集まり喧々諤々とやっていました。時にはコンテキストやシーケンスの図を手書きしてディスカッションを行い、「何がやりたいんだ!」「クルマがどう動くのか説明しろ」など言い合いに発展することもあって…今では良い思い出です(笑)。他部門の要求が分からない時、後ろにある背景を読み解くことから始めるべきということがこの取り組みでわかりました。
池田氏:他部門の要求があいまいだったとき、矢面に立って「それでは実現できません」としっかり言えるのが森田でした。「こんなサービスを実現したい」と思ったらしっかり明言する、ビジュアル化するという作業を文化として根付かせた。この功績は大きいですよ。
最初は抵抗を感じていた他部門メンバーも次第にその仕様書に落としていく工程に徐々に慣れていき、最後は全員で共通の目線のもと開発を行えるようになりました。
この取り組みの最初の起点となったのは、2018年のMX-30開発の時です。サービス部門に「こことここの項目を記載してください」と仕様書フォーマットを送る。そして項目を埋めてもらい、同様に関連部門にも依頼する。
このようにしてひとつの仕様書を完成していきました。丁寧で分かりやすい仕様書のそれは、さながら難解なジグソーパズルが完成していくかのようでした。
部門の垣根が低く、かつ共創の文化があるマツダならではの環境が成し得た取り組みでしたね。

■ チームの特徴や魅力について
森田氏:もともとGUIなど開発していたチームがベースとなり、コネクティッドに取り組むにあたり、外とつながるため新たに「車載通信機」の領域をアドオン的に結成されました。それが現在の開発チームの概要です。
約70%がキャリア採用であり、うち60%が20代・30代で構成された若いチームです。その出身業界や職種もさまざまで、私のように家電業界出身や組み込み系のGUIを開発していた者、スマホのソフトウエアのアプリケーション開発を行っていた者などが在籍しています。ちなみにメンバー間の仲も良く、社内外の駅伝にもチームを結成して参加するほど結束力も高いのが特徴です。
仲野氏:コネクティッドの領域は、これまでサプライヤーさんに頼りきりで行ってきた背景もあって、自社で内製力を高めて競争力をつけたいという意向もあります。そのため外部(キャリア採用)からの新しい風がとりわけ必要なチームとなっています。
コネクティッド領域は業界でも比較的新しい分野ということもあり、ゼロから作っていく達成感があります。それに開発のスパンが短いことも特徴です。一般的に自動車製造は長い期間を掛けて、その上さまざまな部署と絡みながら大きなプロダクトを作るものですので、短い開発期間が好きな人には良い環境だと思います(笑)
現在のチームはキャリア採用が多く、自分のやりたい事をしっかりと聞いてくれて、その業務を優先してくれる環境です。先行・量産開発と別れていないので、そのどちらもやれることが特徴です。メンバーの自主性とやる気を尊重してくれるので、手を上げればどんどん新しいことにチャレンジできることも魅力の一つでしょうか。
森田氏:またマツダはSmall Playerである故だと思いますが、骨太留学と言われる社内の留学制度があります。他本部から1~2年目の社員を留学生として毎年受けいれています。その際、一人一人にペアコーチをつけて留学生が迷わないように、また教える事を通じてコーチ側にも大きな学びを得てもらうことを実践しています。
これにより本来部署に戻った後、構築した人間関係が助けとなり、自然と共創を生み独自性を創り出すきっかけになっています。これが当たり前のように実践されているのがマツダの強みであると思います。
トニー氏:私は社内留学制度を活用してMDI&IT本部から現在のチームに留学しています。これまで経験してこなかった領域、特に車載のソフトウエアに関するあらゆるいろんな技術を学べる点は自分のキャリアにとってもプラスとなりました。周囲のメンバーもさまざまなバックボーンを持っているので、とても刺激的です。

IT人材育成施策「マツダ デジタル道場」とは
■ マツダには「デジタル道場」という学びの場があるとか
森田氏:「デジタル道場」は正式な呼称がまだ決まっておらず、あくまで仮称であることをご留意ください。主な目的はIT人材育成の場とその機会をつくり、社内のデジタル技術に強い人材を増やすことにあります。
自動車製造業のこれからは、システムズエンジニアリングがかなり重要なポジションを占めるだろうとの観点から、育成の場が自社内でつくられており、コネクティッドサービスも同様に力を入れたかった。
先ほどの仲野の話にもありました通り、サプライヤーさん頼みという側面が強く、私自身がコネクティッドサービスの開発で大変苦労しました。そこでこの分野の技術の蓄積と共通認識を持てる機会が増えれば…、という願いで自社内につくることにしたのです。
まだ取り組みはじめではありますが、シミュレーション環境を作って、PoC(Proof of Concept/概念実証)を行い、新たなアイデアやコンセプトの実現可能性やそれによって得られる効果などについて検証できるシステムなども組みました。
これは、インターン生や新しく入社された方への研修とOJTにも効果を発揮しましたし、他部門がその技術の理解をより深めるためにも役立ちました。
コネクティビティサービスは、バックボーンが違うさまざまな部門や人材が関わるため、「どうしたらサービスは良くなるのか」といった課題をより簡易的に模擬しながら考えていく必要があります。
例えば、要件の妥当性などはクルマやサービスのことが多角的に分からなくてはもちろん話になりません。そこで実践的にソフト開発をやってもらうことで、この分野の共通認識や基礎知識を作ることができる。ソフトなど実際に動くものが可視化されたら、よりサービスについても深く考えられるでしょう。本来の部門に帰っても要件が出しやすくなる。それが狙いであります。

仲野氏:マツダのシステムズエンジニアリング全体の強化も目的です。今後当社でもさまざまなシステムが統合制御されて、より複雑に、高度化していくでしょう。
これまでは「私の担当はECU」「私の担当はスマホアプリ」といったドメインスペシャリストばかりでしたが、統合されるシステム全体を多様な視点から俯瞰的に見ることができる総合エンジニアの存在が必要になってきます。それを全体で強化していきたいという想いを持っています。
例えば、モデルベース開発(MBD:Model Based Development)(※2)でHMIを作っても実装した際には予想と違う結果になってしまっては無駄骨です。そこはハードとソフトを一気通貫で開発する必要があります。そんなとき「デジタル道場」で培った開発の知識が功を奏することもあるわけです。
森田氏:まだ立ち上がり半ばで人を集める段階の施策ではありますが、将来的には、新しくマツダの仲間に加わっていただいた方をデジタル道場がサポートして、「こんな成長ができた」「こんなキャリアを歩みたい」と思ってくれると嬉しいですね。
特にカスタマーサービス本部やMDI&IT本部、海外拠点とも連携して施策を大きくしていけたらいいです。デジタル道場の卒業生が、次々に活躍して、「あの時の道場のお蔭だった」と言ってもらえたら最高です。

マツダが目指すコネクティビティの世界
現在のマツダコネクト・コネクティビティシステムの源流のひとつが、1990年4月に登場するユーノスコスモに搭載されていた、日本初のGPS式カーナビであるCCS(カーコミュニケーションシステム)だ。
その頃よりマツダはロータリーエンジンだけでなく、CCSのような魅力的でいて、独自性の強い商品を展開している。車載インフォテインメント(IVI/in-vehicle infotainment)においても独自性が発揮されていたことが分かる。
マツダコネクト・コネクティッドサービスはドライバー、クルマ、クラウド、環境のすべてが情報とつながる中枢のようなものである。
「マツコネコネクト・コネクティビティシステムの開発は、お客様の反応をとても身近に感じることができます。GUIなどはデザイン的な側面もはらんでいますから、『あの画面かっこいいね』という声も聞こえます。より多くのお客様に『マツダコネクトいいね』と言ってもらいたいですし、認知されることにやりがいを感じられる仕事だと思っています」(森田氏)。
また一方で、安全運転支援技術「MAZDA CO‐PILOT CONCEPT(マツダ・コ・パイロット・コンセプト)」も同社が大きく打ち出す独自の技術だ。2022年から順次市販車への採用を進めていく。
これは「ドライバー状態検知技術」、「CO-PILOTによる仮想運転技術」、「異常時退避技術」という3つのコア技術で構成されており、常にドライバーの状態を見守り、急病や居眠りなどの異常があればシステムが運転を引き継ぎ、安全にクルマを止めることを目的としている。ほかの大手自動車メーカーが打ち出す自動運転技術とは一線を画しており、あくまで人が主役、安全運転支援技術であるのだ。
マツダには「クルマは走って楽しむもの」という考えがあり、「人馬一体」というキーワードを開発コンセプトにしている。人間中心の設計というマツダのフィロソフィーは、こうしたコネクティビティシステムの開発にも生かされているというわけだ。
さらに2025年からは技術進化した「CO-PILOT 2.0」の導入を計画。安全に路肩へ退避する際に自動で車線変更することやドライバーの異常の予兆を事前に検知する技術の確立を進めている。
最後に岡野氏はこう締めくくる。
「CO-PILOTを含めたマツダコネクト・コネクティッドサービスは、間違いなくこれからの社会になくてはならないものとなるでしょう。それに機能面ではまだまだオリジナリティを追求していけると思っています。『マツダならでは』を体現して、お客様に価値あるものを提供していく――。モノづくりの神髄を味わえる環境ですので、さまざまなバックグラウンドを持つ新しい仲間ももっと招き入れて、共創を行っていきたいですね」。
自動車開発はハード一辺倒だった世界からソフトウエアにも注力していく世界であることが、マツダの事例からお分かりいただけるであろう。今後の開発はクラウド、スマホなど他機器との連携開発(システム開発)などの重要性が高まっていくと見られている。
コネクティッドカーは、今後の安心安全なクルマ社会にはなくてはならない存在だ。今回はこのような技術潮流の中心にいる、マツダの最新技術に携わる人物たちを紹介した。

【取材後記】
デジタル道場から想起するのは、ドミニカ共和国にある広島カープ球団が運営する野球学校である。同じ広島に拠点を置く企業・団体らしく通ずるものがあるのかもしれない。共創を大事にするマツダの環境で生まれたデジタル道場は、今後の製造業界でIT人材を育成するエポックメイキングな存在になる可能性を秘めている。その道場を卒業したシステムエンジニアが、広島から素晴らしい商品を世界に届ける――。そんな未来に大いに期待したい。
取材・文/鈴政武尊、編集/鈴政武尊・d’s journal編集部
【特集記事(自動車メーカー)】
□ 【マツダ】独自戦略で疾走するマツダ。製造業のITイメージを壊す新組織「先進ITチーム」とは
□ 【マツダデザイン】赤のインパクト。マツダデザインが抱える「色開発の匠集団」
□ 【トヨタ自動車】なぜトヨタは新卒採用一辺倒からキャリア・第二新卒採用に注力したのか
□ 【本田技術研究所】ときにミラクルを起こす「はずれ値人材」が自動運転を実現
【関連記事】
【関連資料】
□ これ1つで解決! 知れる、分かる、採用できる RPO完全導入マニュアル
□ 【採用ツール比較表付】母集団形成の基本
□ 辞退を未然に防止するための 内定者フォローのポイント