女性管理職比率の向上をはじめとした、ダイバーシティを推進する楽天の採用・育成の取り組みとは
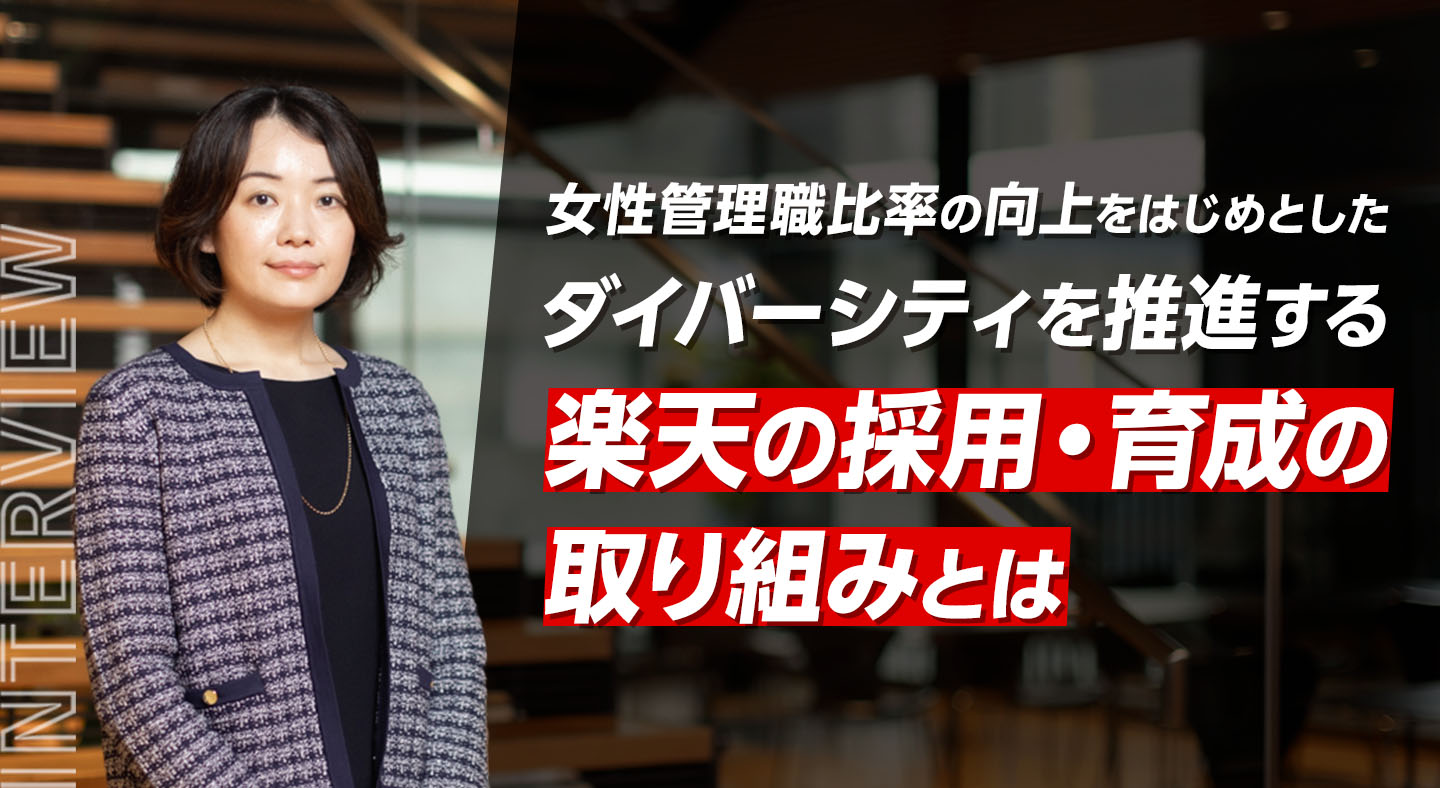
-
採用サイト内の「Women’s Career」で女性活躍ストーリーを発信。応募書類への年齢・性別の記載を不要とし、履歴書の写真貼付も廃止
-
「面接官」「従業員」「マネージャー」各対象向けの研修を実施し、アンコンシャス・バイアスの新たな気付きを組織全体でシェア
-
役員・管理職も定時で仕事を終えて子どもを迎えに行ける。社内託児所の活用で示した女性活躍のロールモデル
女性従業員比率は約40%、女性管理職比率は約32%(2023年12月時点)——。女性活躍がなかなか進まない日本企業の平均値から見れば、楽天の現状は飛び抜けた成功例であるように感じます。しかし、楽天は2030年に向けてさらに高い目標を掲げ、足元では女性管理職の中途採用を強化。「事業成長のために女性活躍をさらに進めていく」と話します。
女性がいきいきと働き、責任ある立場で活躍できる理由はどこにあるのでしょうか。その背景には、創業からずっと多様性に富む組織づくりにこだわり、多様性によってイノベーションを生み出してきた同社の強い想いがありました。
「性別に関係なく活躍するのは当たり前」。楽天の日常風景を伝えていくために
——楽天が女性管理職採用を推進する背景を教えてください。
大前氏:当社は「イノベーションを通じて、人々と社会をエンパワーメントする」ことをミッションとしています。このミッションを進めていくためには、多様な人材とアイデアがオープンに行き交う企業文化が欠かせません。そこでグループ人事統括部の各部署のリーダーが参画してダイバーシティ・エクイティ・インクルージョンを推し進める部署を設置し、採用、育成、環境整備、文化醸成などさまざまな角度から施策を実行しています。

女性管理職採用もその一環です。現状、当社の女性従業員比率は約40%ですが、女性管理職比率は約32%と、全社の比率からは少ない状態にあります。女性管理職比率を高めるために内部育成に取り組むとともに、管理職クラスの採用も進め、内部育成と採用の両方を推し進めたいと考えています。
採用活動では、応募時に年齢・性別の情報や本人画像の提供を問わないことを対外的に公表しました。また、当社における女性の働き方をイメージしてもらいやすいように、採用サイト上で「Women’s Career」を開設しています。
——他社と比較して、御社は女性従業員比率・女性管理職比率ともに高い状態にあると思います。どんな要因があるのでしょうか。
大前氏:当社ではアサインメントや昇進に性別などの属性が影響することは一切ありません。属性にかかわらず、純粋にパフォーマンスによって評価する文化が根付いています。また、本社の隣のビルに社内託児所(楽天ゴールデンキッズ)を設けるなど、子育て中の社員が働きやすい環境を前々から整えてきました。
その意味では、私たちにとって社内に活躍する女性が多いのは当たり前のことで、性別や国籍を問わず、多様性を重んじているため、女性に限ってPRするということは少なかったです。ただ、採用市場では体育会系のイメージで見られることも多く、実態とはかけ離れた形で、女性が働きづらい会社だと思われてしまうこともありました。そこで「Women’s Career」のように、あえて女性の活躍を発信するコンテンツをつくっています。
——女性管理職採用にはどんな課題を感じていますか。
大前氏:世の中全体で女性管理職経験者が少ないため、採用活動では管理職未経験者にも対象を広げていかなければ母集団形成ができません。そのため、入社後のオンボーディングが以前にも増して重要になってきていると感じます。
入社後は、女性をエンパワーメントするためのセミナーや研修の機会を多数用意。社内エグゼクティブを含む女性ロールモデルによるパネルディスカッションを開催し、そうした場を通じて社内での人脈づくりができるようにサポートしています。
多様性が高まる中で気付いた「アンコンシャス・バイアス」
——女性管理職を採用するために、社内の体制づくりで工夫していることはありますか?
大前氏:これは女性に限ったことではありませんが、採用において性別や年齢、国籍などでバイアスをかけてしまうことがないように、面接官向けの研修を徹底しています。新たに面接官となる人には、必ず事前に本研修を受けてもらうようにしています。
面接官向けの研修では、一般的な面接の流れやルールを解説した上で、女性や外国人などの対象ごとに留意すべきことや、どんなやり取りをするべきかなどを学んでもらっています。
また、従業員を対象にアンコンシャス・バイアスに関する理解を高める研修を行ったり、マネージャーを対象に多様なメンバーを活かすリーダーシップの研修を実施したりと、全社規模での取り組みを進めているところです。
※研修は正社員・契約社員が対象

——御社で意識すべきアンコンシャス・バイアスには、どのようなものがあるのでしょうか。
大前氏:組織の多様性が高まれば高まるほど、新たな気付きがもたらされます。当社にはさまざまな国からメンバーが集まっており、国籍によっても、人と人との適切な距離感や望ましいアイコンタクトの在り方が異なります。こうした気付きをシェアして組織全体でアップデートしていかなければ、アンコンシャス・バイアスが拡大してしまいかねません。
女性に関して言えば、上司が勝手に「子育てがあるから大変だろう」と思い込んで出張を要する業務にアサインしなかったり、海外派遣の対象者に加えなかったりすることもあるでしょう。でも、良かれと思って、配慮したつもりでやったことが、結果的に本人のキャリア意向とは真逆になってしまっているかもしれませんよね。
こうしたすれ違いが起きないようにするためには、前提として、上司が一人ひとりの部下のキャリア意向を理解していなければいけません。そこで2017年以降は、職場で上司・部下による1on1を実施し、キャリアへの考え方を柔軟に共有できるようにしています。
社内託児所を活用して「定時で子どもの迎えに行く」働き方も
——女性役員である大前さんのキャリアについてもお聞きします。大前さんご自身も、社内託児所を活用していたそうですね。
大前氏:はい。子どもが0歳のころ、過熱する待機児童問題もあって保育園が見つからず、社内託児所を活用しました。同じように役員や管理職で社内託児所を活用している人は少なくありません。実際に役員や管理職も工夫しながら定時に業務を終わらせて、子どもを迎えに行くことができています。こうした姿は、多くの従業員のロールモデルになっていると思います。
——育児休業の前後で、キャリアが中断する不安はありませんでしたか?
大前氏:周囲には育休から復帰して活躍している女性が多かったので、私自身はそこまで不安に思っていませんでした。ただ、以前と比べて時間に制限があるのは事実なので、効率性はより意識するようになりましたね。
——そうした中で役員へ昇格することについて、大前さんはどのように捉えていたのでしょうか。
大前氏:より高いレベルの課題解決に挑めることをポジティブに捉えていました。
当社グループは成長し続け、新しい分野に次々と挑戦しています。そのため人事面でも新たな課題が次々に出てきています。そうした課題を乗り越え、良い方向へ変えていく機会がたくさんあることにワクワクしていましたね。

事業成長のために、女性管理職比率36%(2030年)を目指す
——今後、御社はどのようにして多様性ある組織を進化させていくのでしょうか。
大前氏:当社は、Diversity(多様性)だけではなく、Equity(公平性)、Inclusion(包括性)、そしてBelonging(帰属)を重視し、多様な人材が一致団結した文化や強い帰属意識をもって働ける職場を目指しています。多様性や異文化理解を促進する研修を行ったり、さまざまな社内ネットワークをつくったりして、働きやすい環境づくりをサポートしているのです。
同時に、会社が目指す方向などを直接社員に伝える機会として「週1回の全社朝会」などの取り組みを継続し、多様性と統一性の両方を軸に取り組んでいます。
当社はグローバルで3万人が働く規模となり、展開するサービスは70を超えています。そんな組織にあっても取り組みをオープンに共有する文化が維持され、日々イノベーションが生まれている。この当社ならではの強みを今後も発展させていきたいですね。
女性管理職比率については、2025年に33%、2030年に36%を達成する目標を掲げています。そのためには社内昇進だけでなく、外部採用もさらに強化していく必要があるでしょう。これは単なる課題として認識しているのではなく、私たちの事業成長のために欠かせない目標なのです。
取材後記
「多様な人材が集まり、オープンにつながることでイノベーションが生まれる。これが当社の一番の価値だと思う」。取材の中で、大前さんはそう話していました。多様性が高まれば高まるほど意見の違いを乗り越えなければならない場面が増え、ときには議論が白熱することもあるといいます。それでも「違う考え方の人同士のほうが突破口が見つかりやすい」「多様性があるからこそチームワークが面白い」と大前さん。楽天にとっての多様性とは、世の中やステークホルダーからの見え方を気にするようなレベルのものではなく、事業戦略の根幹にあるものなのだと感じました。
企画・編集/森田大樹(d’s JOURNAL編集部)、野村英之(プレスラボ)、取材・文/多田慎介、撮影/安井信介
【関連記事】
■ 「人柄」を大切にするカクヤスグループの採用戦略
■ 若手のリクルーターや人材紹介サービスと進める、ラクスのエグゼクティブ人材採用・招聘戦略
■ エグゼクティブ人材採用・招聘におけるkubell(旧Chatwork)の工夫とは
■ エグゼクティブサーチを活用した日鉄エンジニアリングの取り組みとは?
■ エグゼクティブ人材を迎え入れたタムラ製作所。その具体的な取り組みと秘訣とは?
■ 経営・人事がしなやかに連携する、コクヨの「エグゼクティブ人材招聘」ノウハウ
■ 経営層・CxO・事業部長などのエグゼクティブ人材を登用・採用する際に大切にすべきこと
■ エグゼクティブ人材招聘の「要件定義」「母集団形成」はどう考えればよいのか?
■ エグゼクティブ人材の「選考・オファー」において成否を分けるポイントとは
【エグゼクティブ人材】Executive Agent
資料をダウンロード













