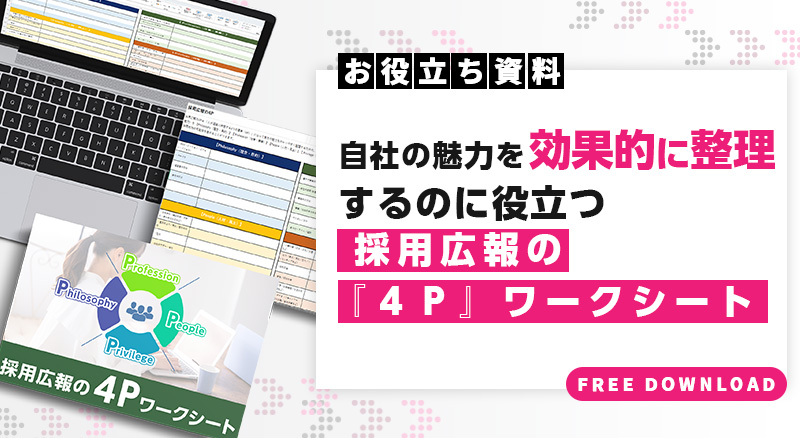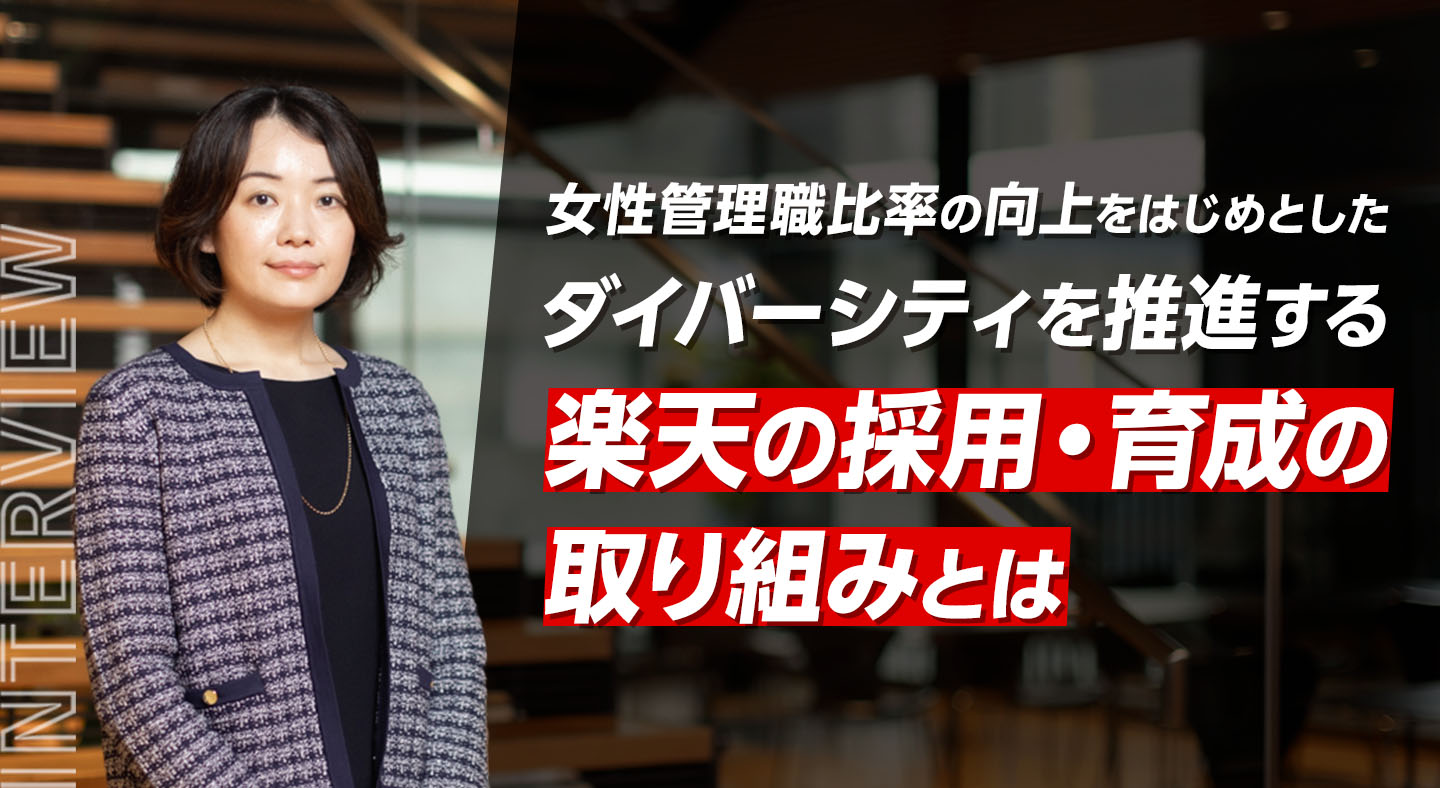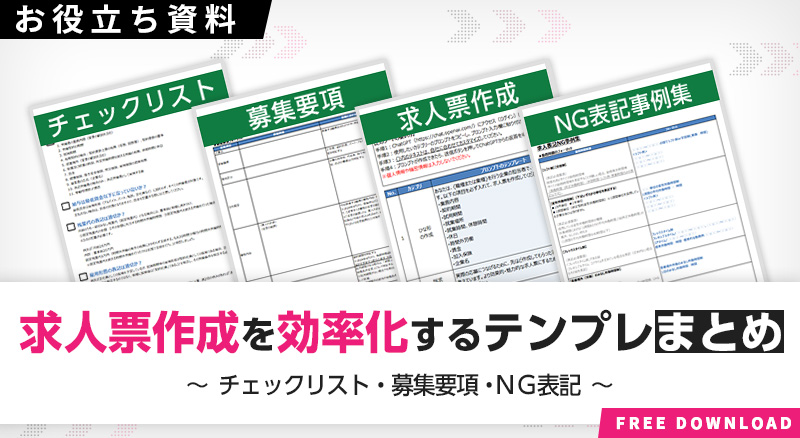魅力がないなら“つくる”!ネガティブな自社イメージから強みに変えるコツ

-
ネガティブワードの裏側にあるポジティブな要素を「見つける」、ない場合は魅力を「つくる」取り組みを
-
社内の改善なしで外面ばかり良いことを発信しても信頼を損ねてしまう。事実をもとにポジティブな要素を伝えることが第一歩
-
広報が話題をつくり、人事が仕組みを整える。両者がうまく連携することでリアルな魅力が生まれる
採用がうまくいかないと悩む人事・採用担当者からは、「うちは魅力がない」「どう伝えたらいいかわからない」といった悩みの声が聞かれます。自社のネガティブな面を意識しすぎてしまい、なかなか前向きな発信ができないと感じている人も多いのではないでしょうか。
そこで参考にしたいのが、広報のプロフェッショナルの視点です。令和PR代表の小澤美佳氏は「ネガティブワードの裏側にあるポジティブな要素を探すべき」「本当にポジティブな要素がないなら、“つくる”という方法もある」とアドバイスします。
転職希望者に誤解を与えることなく、自社の本当の魅力を伝えるにはどうすべきなのでしょうか。人事・採用担当者の多くが陥りがちな、ネガティブな自社認識からの逆転法を聞きました。
実態が伴わないのに「自社の魅力」をそれっぽく発信するのは逆効果!
──魅力的な求人票を発信したいと考えていても、自社のネガティブな面に目が行ってしまう人事・採用担当者もいるようです。
小澤氏:私自身もそうした場面に出会うことはよくあります。
ある企業のPR支援に入った際には、人事・採用担当者から「うちは給料が安くてなかなか応募が集まらない」といったネガティブな言葉ばかりが出てきました。でも、ネガティブに考えているままでは採用を前に進めることができません。
大切なのは、まず自社のありのままを伝えようとすること。そして、ありのままでは魅力を伝えられないなら魅力をつくり出し、外に出せないようなことがあるなら改善していくことが大切だと思います。
これは私自身がずっとこだわってきたことでもあります。私はリクルート勤務時代、企業の採用活動を支援する中で、外に発信する前に顧客の社内を改革することに力を入れていました。社内がぐちゃぐちゃな状況で実態が伴っていないのに、外部へ「自社の魅力」をそれっぽく発信していると、社内の従業員に悪影響をもたらすおそれがあるからです。
たとえばある企業の営業部門では、売れる営業パーソンに仕事が集中して疲弊していました。何かしらの仕組みを変えないと、人を採用しても離職が続きかねません。そこでまず、営業アシスタントのポジションを新たに設けることで営業パーソンがコア業務に集中し、サポートを受けられる仕組みが必要といった提案を行い、対策を進めました。

──なぜ自社についてネガティブな印象が先に出てくることがあるのでしょうか。
小澤氏:日本人ならではの謙遜する姿勢が影響しているのかもしれません。海外企業の場合は「うちは最高だぜ!」とポジティブに表現し、自社に自信を持っていることが多いのですが、日本企業ではたらく人は「いやぁ、うちなんて……」と謙遜しがちですよね。
でも、そうした謙遜を取り払って深く話を聞いていくと、ネガティブなだけではなく、「実はこんないいところもあるんです」といった情報が出てくることも多いんです。自社のことになると、客観的に見つめ直すのが難しいのかもしれません。
「話題をつくる広報」と「基盤をつくる人事・採用担当者」が連携して自社の魅力を確立
──ネガティブな事実を前向きに伝える際の考え方を教えてください。ポジティブに言い換えて伝えることはできるのでしょうか。
小澤氏:ネガティブな言葉を裏返して、ポジティブに変換すること自体はできるでしょう。
たとえば、忙しい職場であることを「成長機会が多い」「裁量が大きい」と表現したり、変化が少ない現状を「安定した環境がある」「腰を据えてはたらける」と言い換えたり、古い会社と表現してしまうことを「歴史と実績がある」「信頼される基盤がある」と表記してみたり。
それらの裏返しが事実なら、誇りを持って伝えるべきでしょう。ただし、嘘や誇張にならないよう十分に留意する必要があります。
目の前の言葉を懐疑的な視点で見ていくと、ネガティブな言葉とは逆のケースもあることに気づきます。「うちの職場はみんな静かで活気がない」と聞いたときに、本当に静かなのか疑問に思って現場へ行ってみると、「従業員がメリハリをつけてはたらき、高い生産性を実現している」事実を発見したこともありました。
ただ表現を言い換えればいいわけではなく、ネガティブな言葉からそこにある真実を見つけることが大切です。ネガティブワードの裏側に本当にポジティブな要素があるなら、それを探す。ポジティブな要素がなければ、つくるという方法もあります。

──「ポジティブな要素をつくる」とは?
小澤氏:たとえばPR支援を行った物流企業では、これまで男性中心社会で運営してきたものの、少しずつ増えつつある女性ドライバーのはたらきやすさにも配慮した環境を整えていこうとしていました。ただし、人事的な基盤はまだ整っていませんでした。
そこで私は物流企業と美容師不足が問題になっている美容院をつなげ、女性ドライバーにより美しく輝いてもらうために髪型やメイクを整えて変身してもらいました。またその姿でトラックの前で写真を撮るとともに、女性ドライバーの座談会を行って発信しました。まず話題性をつくり、女性ドライバーが日々の仕事で感じている課題感をあぶり出していったんです。
そうして出てきた課題感をもとに、新たな手当、女性専用の更衣室など、女性ドライバーがはたらきやすい環境をつくろうと人事・採用担当者が中心となって意見交換を重ねている最中です。それをまた広報的に発信することで、リアルを伴う魅力となって伝わっていると感じています。
話題をつくって転職希望者の興味をひく広報と、リアルな基盤をつくる人事。この両者が連携することで、自社の魅力を確たるものにしていけるはずです。逆に広報と人事が分離した状態だと、何をやっても一時的な効果に終わってしまうかもしれません。
現場で従業員の声に耳を傾ける努力も必要
──自社の本当の魅力を伝えるためのポイントをお聞かせください。
小澤氏:転職希望者に訴求するうえで、「実態との認識のずれがない」ということは重要だと思います。
よくあるのは、「うちはとてもいい会社」だと人事・採用担当者や広報が言っているのに、蓋を開けてみるとどんどん人が辞めているという現実です。
会社としてはメリットだと考えていることでも、個々の従業員が実際にどう受け止めているかはわかりません。その意味では、現場で従業員の声に耳を傾ける努力も必要でしょう。従業員の多くが納得していなかったり、メリットを感じていなかったりするのに、「うちにははたらきやすい環境が整っている」と外部へ伝えるのは誇張ですよね。
自社に本当にある魅力を「見つけに行く」、そして「魅力がないのであればつくる」。これを強く意識していただきたいと思います。
【取材後記】
かつては人材業界の最前線で企業と向き合い、現在は広報のプロフェッショナルとして多くの企業に寄り添う。そんな小澤さんが指摘する「広報と人事の連携」の重要性に深くうなずく取材となりました。昨今の採用成功企業では、広報と人事が同じ部門に属し、日常的に連携していることも珍しくありません。人的リソースの限られる中小企業でも、広報的機能と人事的機能の役割分担を検討し、最適な体制を築いていくべきではないでしょうか。
企画・編集/森田大樹(d’s JOURNAL編集部)、岩田悠里(プレスラボ)、取材・文/多田慎介
求人票作成を効率化するテンプレまとめ ~チェックリスト・募集要項・NG表記~
資料をダウンロード