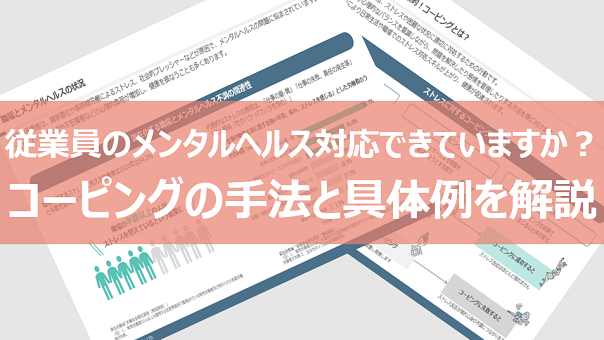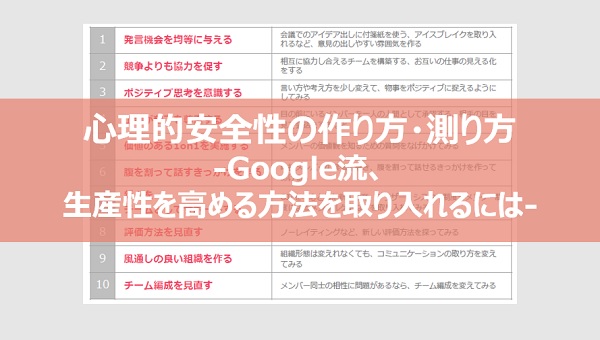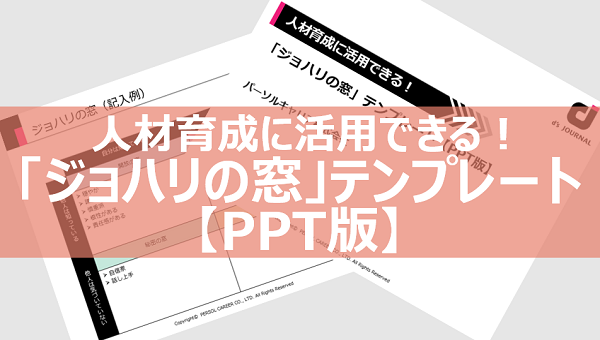チャレンジしたいときにできれば制度はいらない。“人起点”の組織をつくる、バリューブックス【連載 第13回 隣の気になる人事さん】

全国各地の人事・採用担当者や経営者がバトンをつなぎ、気になる取り組みの裏側を探る連載企画「隣の気になる人事さん」。
第12回の記事に登場した株式会社ロフトワークの皆さまは、本の買取・販売事業を起点にして異業種とも協業し、さまざまなプロジェクトを展開する株式会社バリューブックスを「気になる企業」として紹介してくれました。
▶ロフトワークの皆さまが登場した第12回の記事はコチラ
人材紹介サービスや求人広告を一切使わず250人超の母集団を形成!ロフトワークの「デザイン経営×採用ブランディング」とは
同社は、カフェを併設した実店舗「NABO」、地域を回って本の販売や寄付を行う「ブックバス」、本の買取査定金額をNPO法人や大学などへ寄付する「チャリボン」といった多岐にわたる取り組みを進めています。こうしたプロジェクトは本業のビジネスへ還元されるとともに、従業員が社会とつながり、やりがいを見出すことにもつながっているといいます。中小企業においても人的資本経営の実践が求められる今、学ぶべきところの多い企業だと言えるのではないでしょうか。
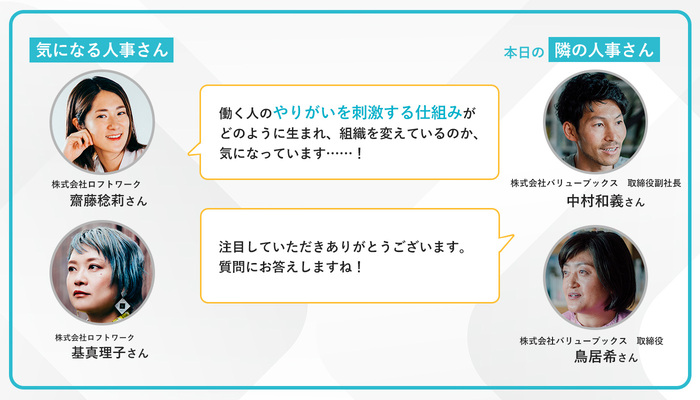
きっかけは「やりがいを感じられない」という1人の声
——貴社では本業を起点にして、社外とも柔軟に連携する形でさまざまなプロジェクトが進められていますね。
鳥居氏:私の知る限りでは、「ブックギフト」が最初ですね。これはバリューブックスで働くスタッフが、家族などの身近な人に感謝されるきっかけになってほしいという思いで生まれた取り組みです。スタッフの子どもが通う保育園や学校に本を寄贈するなど、さまざまな形で当社に集まる本を届けてきました。
当社の倉庫には、全国のお客さまから買取依頼のあった本が1日に約3万冊届きます。そのうち、値段を付けて買取できるのはおよそ半分くらい。残り半分は、かつては古紙回収に回すしかありませんでした。買取できないものでも本のまま活用するにはどうすればいいのか。その答えとしてブックギフトに取り組み始めました。

バリューブックス社の倉庫。1日に3万冊の本が届く
——なぜ「スタッフが感謝されること」を重視したのですか?
鳥居氏:創業した当初、会社を辞めていくスタッフの理由は、子どもの卒業や引っ越しなど、ライフステージの変化がほとんどだったそうです。でもその中に1人、「ネットだけで買取・販売する仕事ではお客さまとやり取りする機会が少なく、やりがいを感じられない」と言って辞めた人がいたようで。
中村氏:そんなケースは初めてだったので、創業者の中村大樹が、それを問題だと考えました。仕事を通じて身近な人に感謝される機会があれば、この仕事にやりがいを見出してもらえるのではないか。そう考えてブックギフトを始めたと聞いています。

とはいえ、働く人のためだけにこうした取り組みを進めているわけではありません。小さい会社なので、CSR(※)のような活動を続けていくのは難しい。小さい利益で何か形だけ取り組むのではなく、本業のビジネスにいい影響を与えていくことと、スタッフのやりがいも高めていくことの両立をしないと、たとえいい取り組みだったとしても続けていくことが難しくなってしまうときがあります。ブックギフトにしても、もちろんスタッフのやりがいや幸せを考えていますが、本を廃棄しなければならないのはもったいないという思いもありますし、この取り組みが知られることによって、より多くの本の循環が生まれることも狙っています。
(※)企業活動において、社会的公正や環境などへの配慮を組み込み、従業員、投資家、地域社会などの利害関係者に対して責任ある行動をとるとともに、説明責任を果たしていくことを求める考え方(厚生労働省HPより)
仕事への向き合い方は人それぞれ。全ての想いが利益につながる仕組み
——本業から派生する形で展開されるプロジェクトは、スタッフの皆さんのやりがい向上にどのようにつながっているのでしょうか。
鳥居氏:本の買取金額を、売ってくださった方の希望に応じて別のところへお支払いする「チャリボン」という取り組みがあります。こうした事業が日々の仕事に組み込まれていることを前向きに捉え、「うれしく思っている」と話すスタッフは多いですね。
中村氏:バリューブックスの取り組みに共感して求人に応募してくれる人もたくさんいます。ただ、僕たちは一つの強烈なカルチャーで結束している集団というわけではなく、スタッフの考え方も人それぞれ。さまざまな取り組みへの関心度には濃淡があると思いますよ。

鳥居氏:実際に、社会貢献だけでなく「フレキシブルに働きたいから」「人と関わる仕事が苦手だから」などさまざまな応募理由がありますね。そういうものだと考えていますし、もちろん社会貢献がしたいという思いで仲間に加わってくれる人も歓迎しています。
——「社会貢献」のイメージが強くなりすぎると、本業で成果を出すことに興味を持たない人ばかり集まるなどの弊害もあるのでは?
中村氏:当社の場合は、全ての取り組みをビジネスにつなげることが前提です。応募者にはそこを確実に理解していただき、一緒に考えてもらえるよう努めています。
理想論としては、全てのプロジェクトはビジネスに紐付く形で設計されているので、「とにかくチャリボンに関わりたい!」という人が加わっても結果的には本業に貢献してくれることになる。本が好き、社会の役に立ちたいなど、それぞれの想いを活かしてくれれば利益につながる。そんな状態を目指しています。
マネジメントの在り方さえも現場で決める「セルフマネジメント型組織」
——2018年からは「セルフマネジメント型組織」への移行を進めています。これはどのような組織形態を目指した挑戦なのでしょうか。
鳥居氏:セルフマネジメント型組織を構想したきっかけは、2018年に出版された書籍『ティール組織』(英治出版)です。私たちも会社が決めたリーダーに従うのではなく、それぞれの人がそれぞれの場所でリーダーシップを発揮できる自律分散型組織になった方がうまくいくのではないかと考えました。
組織の在り方を模索する中で、それまでの1年間は、ピラミッド型組織を志向し、各部署に部長を置いて経営チームと連動させる形を目指していました。でも「これを追求してもみんながハッピーになれない」と考え、各部署のマネージャーポジションを廃止しました。
中村氏:当社にはマネージャー人材が少なかったし、もっと言えば「マネジメントがしたい」「マネジメントを究めたい」と考えている人自体も少なかったんだと、あとで気付きました。それなのに、マネージャーを指名して役職を持ってもらっても、慣れない中で試行錯誤をするものの、本人はつらくなってしまうときがあるし、メンバーとしても、慣れないマネジメントを受けている状態で、お互いにハッピーになれない状態でした。
——とはいえ、倉庫内のルーティン作業などは管理職を置き、マネジメントを効かせたほうがスムーズに回るのでは?

中村氏:もちろんそうした業務もあります。実際に倉庫はピラミッド型組織に戻っていますね。でもそれは、その在り方を現場のメンバーが求めていたからです。
セルフマネジメント型組織へ移行したときも、会社から指名されたリーダーがいなくなったというだけで、現場の中に自然とリーダーが生まれ、自然とマネジメント体系が生まれるのであれば、それを否定していたわけではありません。倉庫のようにたくさんの人が同じ作業をする場では、ルールや指示系統が明確なほうが働きやすいのも事実ですから。
一方、マーケティングやデザイン、システムなど個々の力を発揮することでクリエイティブな仕事が求められる部署では、一人ひとりがリーダーシップを発揮し、大きな裁量を持てる体制が根づきつつあります。
——それぞれの部署や現場の特性に応じて、マネジメントの在り方を自分たちで考えてもらうと。
鳥居氏:はい。セルフマネジメント型組織への移行の根本にあるメッセージは「みんな大人だから普通にやろう」ということなんです。自分が変えたいと思うことがあれば人のせいにせず自ら動けばいいし、やりたいと思うことがあれば仲間を集めて挑戦すればいい。会社の利益、事業の発展につながることでなら自由にやっていこうと。
中村氏:その判断を上に求めるのではなく、現場にいる人たちが決めるということですね。
他社にあるから必要とは限らない?バリューブックスが現状「人事部も置いていない」理由
——貴社の取り組みは、まさに「人を最重要資源とする経営=人的資本経営」だと感じます。昨今では中小企業でも人的資本経営の実践を目指し、従業員エンゲージメント向上に取り組むところが増えていますが、バリューブックスではどのような指標を置いていますか?
中村氏:従業員エンゲージメント向上が「従業員によるエンゲージメントを高める」という意味だとすると、率直に言って、僕はあまりエンゲージメントのことは考えていないんですよね。その文脈で経営者と従業員という二者に分かれているのは、少し違和感があって。

鳥居氏:私も同じです。私は「従業員エンゲージメント」が「社員によるエンゲージメント(社員がエンゲージすること)」のように聞こえて、その主語の置き方に疑問を感じています。本来、「エンゲージ」は双方向の動きで成り立つものではないでしょうか。ここは二者に分けた表現になってしまいますが、会社がコミットしなければ社員もコミットするはずがなく、逆も然りです。だから社内ではエンゲージメントという言葉自体、使うことがありません。
——人材育成や成長の後押しについてはどのように進めているのでしょうか。
中村氏:当社は特段の育成プログラムや研修制度を設けていません。定期的な部署異動の制度もありません。人事部も置いていないんです。
ただ、会社のメンバーに成長のチャンスをつくっていくこと自体は必要だと思っています。エンジニアの仕事に興味がある人には実際に部署異動してチャレンジしてもらうなど、個人を見て、それぞれの興味・関心を後押していくことを大切にしています。型にはまった管理職がいなくても、もっと身近な存在として、各部署にそうやって人を後押しできる人がいることが重要だと思っています。僕自身も「これやってみなよ」と次々にチャンスをもらい、新しい仕事にチャレンジしてきた結果として今があります。
鳥居氏:入社の動機が人それぞれであることと同じで、どんなふうに成長していきたいか、どんなことにやりがいを見出していきたいかも、個人が起点だと思っています。だから、コンプライアンス関係などは別として、全ての人を対象にして一律の制度を設ける必要はないようにも感じます。
組織として「チャレンジすることは尊い」という共通認識を持ち、チャレンジしたい人が必要なときに、必要な学びを得られることは単発でやってきましたが、もう少し仕組み可した方がいいのかな、とは考えています。
中村氏:そうですね。僕も「みんなを変えたい」という思いはありません。だから“今は”そういう意図で人事部がなくてもいいと思っています。セルフマネジメント型組織の中でそれぞれの現場が最適な方法を追求しているように、一人ひとりの個人もまた、自分にとって最適な働き方、最適なキャリアの在り方を追求してほしいと思っています。それが僕たちにとっての、人を大切にし、人を起点にして動く組織の在り方です。
写真提供:株式会社バリューブックス
お役立ち資料
取材後記
バリューブックスは事業や組織の在り方についてたくさんの情報を発信していますが、その中に「人的資本経営」や「エンゲージメント向上」といった“人材業界における注目ワード”は登場しません。取材を進め、働く個人と徹底的に向き合い続けてきた会社の歴史を聞いていると、こうしたワードを必要としない理由を理解できる気がしました。個人の価値観と事業発展がシームレスにつながり、多様な人材を受け入れられる組織をつくる。これこそが人的資本経営の自然な実践の形なのかもしれません。
企画・編集/海野奈央(d’s JOURNAL編集部)、野村英之(プレスラボ)、取材・文/多田慎介、撮影/篠原幸宏(バリューブックス)