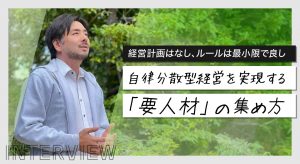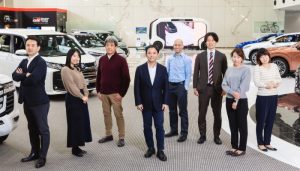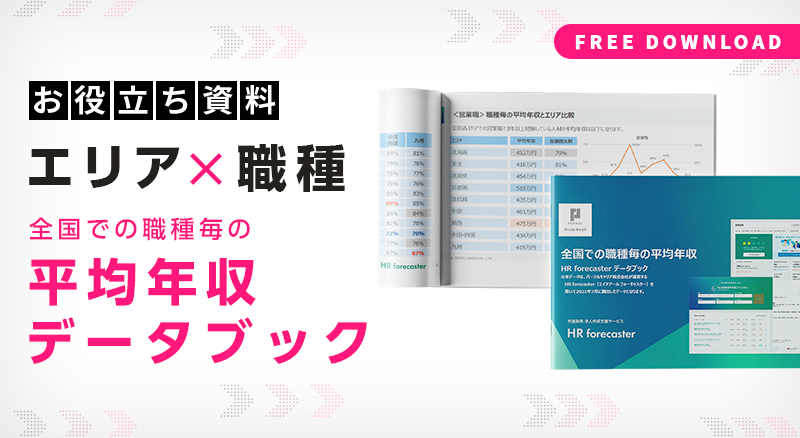<前編>人事は「管理屋さん」になるな。安全地帯を飛び出し、現場のインサイトを理解せよ——私のルール【木下達夫】

-
リーマンショック後に得た教訓「人事は企業内で最も冷静でいなければならない部門の一つ」
-
サバティカル休暇の申請を通じて得た「ルールだけでは判断できないときのために人事責任者がいる」という学び
-
人事だけに打ち込んでいると「管理屋さん」になってしまうかもしれない。自ら「海外勤務の異職種」に挑戦し、人事以外の視点を持つ
人事の腕の見せどころは、個人と組織の「WIN-WINの最大化」を実現すること——。パナソニック ホールディングスのグループCHROを務める木下達夫さんは、人事パーソンとしての信念をそう語ります。
外資系企業で社会人としてのスタートを切り、財務・営業企画など人事以外のポジションも数多く経験。テックカンパニーの急成長に寄与した後は、日本を代表する大企業の人事トップへ。過去の得意領域だけにとらわれず、新たなフィールドへ次々と挑戦し続ける木下さんは、どのような軸を持って自らのキャリアを築いてきたのでしょうか。インタビューは、木下さんが人事としての道を歩み出したP&G時代のエピソードから始まります。
「採用以外の知見がない」ことに焦りを覚えた20代後半
——木下さんが新卒でP&Gを選んだ理由を教えてください。
木下氏:学生時代にマーケティングを学んでいたため、私はもともとマーケター志望でした。当時から「マーケティングといえばP&G」のブランドがあり、私は迷わず、職種別採用を行っていた同社にエントリー。
その選考の中で、「P&Gは人事にもマーケティングの考え方を取り入れているんだよ」という興味深い話を聞いたんです。マーケターが消費者のインサイトを分析するように、人事も転職希望者や学生のインサイトを理解し、コミュニケーションの在り方をデザインしているのだと。
近年、「エンプロイー・エクスペリエンス」(Employee Experience:従業員が働くうえで得られる体験)として多くの企業で取り入れられるようになった考え方を、P&Gは当時から実践していたわけです。そうした新しい人事の考え方に引かれ、私はマーケティングから人事へと志望を変更して入社しました。
入社後は主に新卒採用に従事し、社内のIT部門を担当するHRBPも経験。P&Gには約5年間お世話になりました。

——その後、木下さんはGEジャパンへ転職しています。同じく外資系企業への転身ですね。
木下氏:転職のきっかけは、GEが設けていた「HRリーダーシッププログラム」という人事パーソンの養成プログラムを知ったことです。これは人
当時の私は20代後半。30代以降のキャリアを考え、採用以外の知見がほとんどないことに焦りを覚えていた私は、このプログラムに挑むことにしました。
——木下さんが経験した「人事以外のポジション」とは。
木下氏:最初のポジションは財務でした。当時はアメリカとカナダに金融事業があり、私は初めての海外勤務で、初めて内部監査の仕事を担当することになったんです。
その後も海外工場のサプライチェーン管理や営業企画などを経験し、HRリーダーシッププログラムを終えた後は、日本国内の工場人事に従事して鍛えられました。
ルールだけでは判断できないときのために人事責任者がいる
——GE時代に木下さんのキャリアの転機となったエピソードを教えてください。
木下氏:30代半ばで金融部門のGEキャピタルへ異動し、人事の部長職を務め、経営陣の一員として初めてPL責任者になりました。ありがたい経験をさせてもらったのですが、同時に私は人事として、大いに反省することにもなりました。
私が赴任したのはリーマンショック直前のタイミングで、金融業界はイケイケの状態だったんです。海外GEの金融関連部門からは「こんなにマーケットが成長しているのに、日本のGEキャピタルは保守的すぎる」「もっと著しい成長を目指すべきだ」と言われていました。
そこで私は営業職の大量採用に動き、100人を超える人材を採用しました。ところがそれから1年あまりでリーマンショックの激震が走り、GEキャピタルはすべての融資を停止。事業そのものが半分くらいの規模になってしまい、拡大していた組織ではリストラを断行せざるを得ませんでした。
あのイケイケな時期に、私自身もヒートアップし過ぎていたのでしょう。「人事が事業成長のボトルネックになっている」などと言われ、責められていたことにも焦りを感じていました。自分の経験を活かして採用にテコ入れし、たくさんの人材に集まってもらったのに、多くの人に去っていただくしかなかったんです。
この経験は私に重い教訓をもたらしてくれました。人事は企業内で最も冷静でいなければならない部門の一つ。上からも下からも横からもプレッシャーを受ける立場ですが、それでも常に冷静でいなければいけません。
その後のキャリアでは、サバティカル休暇を取得したことも転機になりましたね。

——サバティカル休暇?
木下氏:GE入社10年の節目に、アジア・アフリカ・南米など普段は行かない国々を旅して視野を広げたいと考え、8カ月の休暇を取ることを計画したんです。当時のGEではサバティカル休暇を認める制度はありませんでしたが、人事トップが特例的に認めれば許可が出る可能性もありました。
そこで、日本法人の人事ヘッドを務めていた八木洋介さん(現:株式会社people first代表取締役)のもとへ行き相談しました。休暇取得が認められなかった場合や、休暇を取って戻ってきた後にポジションがなかった場合は、退職するつもりでしたね。
そんな想いを直接ぶつけてみたところ、八木さんは「面白い!良い経験になるね」と言ってくれたんです。「木下くんを求める事業部門はたくさんあるから、戻ってきてからのことも心配いらないよ」とも。そうして特例のサバティカル休暇取得が認められました。
後から聞いた話では、ある人事メンバーから「人事なのに特例扱いしていいのか」という疑問の声も上がっていたそうです。それに対して八木さんは「人事責任者としての自分の仕事は、特例をつくること。ルールだけでは判断できないときのために俺がいるんだ」と。
もう、最高にかっこいい言葉ですよね。
ルールはあくまでも組織を円滑に運営するための手段。ルールだけでは判断できないときのために人事責任者がいる——。八木さんの教えは、後に別の企業でCHROを務めることになった私の指針となりました。
私を信頼し、責任を被ってくれた上司の想いに応えるため、私はその後も7年間GEで人事を務めました。サバティカル休暇を経て会社へのロイヤリティが高まり、それまであまり興味を持っていなかったコーポレート部門の仕組みづくりにも積極的に携わったんです。事業会社と協力してHRインフラやシステムを整備し、オペレーションの基盤をつくりました。
結果的に、この経験はメルカリやパナソニックグループでのCHROの仕事にとても役立っています。食わず嫌いをせず、何でもやってみるべきなのだと実感しましたね。
口説き文句は「“Go Bold”を人事領域にも求めたい」
——GE退職後、木下さんが次のステージとして選んだのはメルカリでした。
木下氏:GEを辞める直前に、私は東南アジアのHRヘッドを務めていました。ここではローカル人材の引き上げや組織開発とともに、カルチャー変革も担っていたんです。
それまでのGEは、必要な工程を計画して順番に進めていく、いわゆるウォーターフォールの発想による計画性を強みにしていました。それが時代の変化によって、シリコンバレーのテック企業のようにアジャイルでオープンなカルチャーが求められるようになったわけです。そんなカルチャー変革の仕事を経験し、「次はテック企業に身を置いてみたい」と思うようになりました。
——外資系企業での経験が豊富な木下さんであれば、海外テック企業からの引き合いも多かったのでは。
木下氏:私自身、当初は外資系のテック企業に移ることを考えていましたし、実際にお話もいただいていました。そんなときに知り合いを通じて「日本のユニコーン企業であるメルカリが、グローバル人事の知見を持つ人を探している」と聞いたんです。
創業者の山田進太郎さんをはじめとした経営陣に会ってみたところ、彼らが「日本発のグローバルテックカンパニーになりたい」と本気で考えていることが分かりました。海外から100人単位でエンジニアを採用する一方、社内はまだ英語対応していなくて大混乱。メルカリのバリューとして知られる“Go Bold”(大胆にやろう)を地で行く行動力に驚きました。
そんな進太郎さんは、私への口説き文句として「“Go Bold”を人事領域にも求めたい」と言ったんですよ。人事を大胆にやろうぜ、なんて言う経営者には初めて会いました。入社後も1on1などの機会を通じて、進太郎さんは「もっと大胆に攻めていいですよ」と常に背中を押してくれました。
メルカリのCHROを務めた5年半、私が担った最大のアジェンダは、ローカルからグローバルテックカンパニーへと飛躍する足場づくりに他なりません。現在ではエンジニア組織の人員の半分が海外出身で、執行役員やディレクタークラスにも外国籍の人材が名を連ねています。海外からやって来る人が、遜色なく力を発揮できる環境となりました。

——メルカリには、それまでの外資系巨大企業とは異なるカルチャーがあると思います。ご自身を新たな環境へフィットさせることには苦労もあったのでは。
木下氏:入社当初はメンバーからたくさんのダメ出しを受けましたね。「達夫さん、チャットの返信が遅いです!」とか(笑)。
人事部門内でも、「その施策はオーソドックスすぎて、全然“Go Bold”じゃないと思います」「達夫さんがやろうとしていることを実現したら大企業病になってしまいませんか?」など、みんなが私に対して真っ向から意見を出してきました。これまでに身を置いてきた外資系企業よりもオープンで、率直に議論するカルチャーがありましたね。
こうやって言ってもらえるのはとてもありがたいことだと感じていました。完璧なリーダーなんてどこにもいないし、どんな立場になっても自分の伸びしろを見つけ、成長していかなければいけませんから。
自分の中に蓄積された過去の常識で判断せず、いかにアンラーニングして変化できるか。そんな気付きを与えてもらいましたね。
人事を「事業から遠い存在」にはしたくない
——これまでのキャリアについて聞き、職種や企業を飛び越えて大きな変化を求めてきた姿が強く印象に残りました。木下さんはなぜ恐れずに異分野へ飛び込んでいけるのでしょうか。
木下氏:変化しようとするときに、怖さや不安がまったくないわけではありません。それでも変化は必要だと思うんですよね。
部下や転職希望者などと接する際、私は「成長したいなら自らのコンフォートゾーン(安全地帯)を出るべきだ」とよくアドバイスしています。変化が大きければ大きいほど苦労しますが、その分だけ鍛えられるわけですから。
そうして異分野へ飛び込むときには、私は好奇心を持って事業や組織を理解することを重視してきました。どんな事象にも背景や経緯があります。その文脈を深く理解することが正しい打ち手につながり、自らを成長させる原動力になるんです。

——木下さんはこれまでのキャリアで、人事としての限界を感じたり、人事の仕事にネガティブな感情を抱いたりしたことはありましたか。
木下氏:振り返ってみると、私が人事の仕事にネガティブな気持ちになる瞬間というのは、人事と事業の距離間を感じたときだったと思います。
もともとマーケターを目指してしていたこともあり、私は「人事パーソンとして事業にインパクトを与えたい」と常に考えてきました。しかし現実には、人事の立場にいることで情報が入って来なかったり、事業の意思決定に関われなかったりする状況に直面したこともあります。人事が事業から遠い存在になってしまうことが、私はとにかく嫌なんですよね。
若手のころは採用に携わっていたので、各部門の管理職やリクルーターと連携する機会を通じて、事業側のやりがいや苦労を理解することができました。それでも、人事だけに打ち込んでいると自分でも気付かないうちに「管理屋さん」の思考になってしまうことがあります。だから私は、30代を前にして人事以外の視点を持ちたいと考えたんです。
自分から事業部門へアプローチして現場のインサイトを理解し、肌感を共有する。その挑戦は今も変わらず続けていますよ。
***
人事として大切にしている信念「個人と組織の『WIN-WINの最大化』を実現する」。後編記事では、その信念の意味と、「パナソニックグループが変われば、日本が変わる」と、2024年7月にパナソニック ホールディングスのグループCHROに木下さんが就任したころの想いと取り組みをお伝えします。
後編記事:<後編>パナソニックの変革を支える「6つの原則」。人事パーソンが本当に果たすべき役割とは——私のルール【木下達夫】
取材後記
1本の記事では紹介しきれないほどの多彩なエピソードを披露してくれた木下さん。インタビューを終えて、来し方を振り返る木下さんが本当に楽しそうに、熱を込めて話してくれた姿が強く印象に残りました。巨大企業のCHROという立場でありながらも率直に自らの経験を語り、自然と聞き手の学びへつなげていく。そんな木下さんの在り方に、「人を元気にする人事パーソン」の真髄を見た気がします。後編記事では、木下さんがパナソニックという新たな舞台で挑む変革テーマに迫ります。
企画・編集/田村裕美(d’s JOURNAL編集部)、野村英之(プレスラボ)、取材・文/多田慎介、撮影/塩川雄也
全国(エリア)での職種毎の平均年収データブック
資料をダウンロード