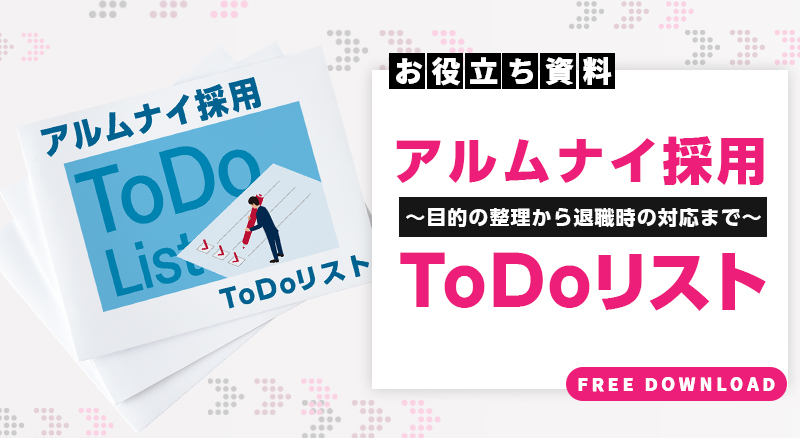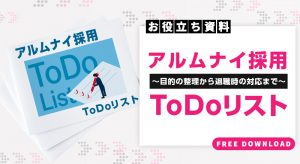アルムナイ採用とは?メリットや成功させるポイントも解説


d’s JOURNAL編集部
多くの企業が抱える課題として、人手不足が挙げられるでしょう。「求人広告を出しても、なかなか応募が来ない…」と悩む企業も少なくありません。
こうした課題を解決できる採用手法として、「アルムナイ採用」があります。
本記事では、アルムナイ採用の概要を説明するとともに、導入するメリットや成果を上げるために意識すべきポイントを解説します。効果的な採用活動を実施するための、参考にしてください。
アルムナイ・アルムナイ採用とは
アルムナイ(alumni)とは、日本語に訳すと「卒業生」「同窓生」といった意味の言葉です。そこから転じて人事領域では、「定年退職者以外の退職者」を指す言葉として使用されています。
近年、人材を資本と捉えて企業価値につなげる「人的資本経営」の考え方が広まっており、アルムナイも自社の資産として捉える企業が増えています。そして、アルムナイの活用方法の一つが、退職した人材を再び雇用する「アルムナイ採用」です。
詳しくは後述しますが、アルムナイ採用のメリットは、自社の文化や理念を理解した人材が新たな知識やスキルを身に付けた状態で再就職してくれることにあります。ミスマッチの心配が限りなく低い、かつ即戦力としての活躍が期待できる人材を採用できるため、非常に効果的な採用手法であるといえるでしょう。
(参考:『アルムナイとは?注目される理由とメリット・デメリットを解説』)
ジョブリターン制度との違い
アルムナイ採用と同じく、退職者を対象に再雇用を図る制度が「ジョブリターン制度」です。一見、似た制度にも思えるこの2つですが、両者がアプローチする退職者は、次の点で異なるものと考えられることが多いです。
アルムナイ採用とジョブリターン制度の対象となる人材
| 対象 | |
|---|---|
| アルムナイ採用 | 家庭の事情やキャリア形成などの理由で転職・起業した人材 |
| ジョブリターン制度 | 結婚・出産・育児・介護などの理由で離職した人材 |
このようにアルムナイ採用では、退職後もほかの企業で継続して働いている人材を対象とするケースが一般的です。対して、ジョブリターン制度では、職歴にブランクがある人材を採用することを指すことが多いです。
なお、企業によってはこの2つの制度を同様のものとして捉えるケースもあるほか、それぞれを「カムバック制度」と呼ぶこともあります。
(参考:『【事例あり】ジョブリターン制度とは?注目される理由や導入のメリット』)
リファラル採用との違い
アルムナイ採用と混同しがちな手法としてはほかに、「リファラル採用」もあります。
リファラル(referral)は「紹介」「参照」といった意味であり、リファラル採用は、社員から知人や友人を紹介してもらい、選考へとつなげる採用手法のことをいいます。
アルムナイ採用でも退職者から連絡を受ける導線として、自社の社員を介すケースはありますが、採用の対象はあくまで「退職した人材」です。リファラル採用では、これまで企業と接点のなかった人材が対象となるため、この2つの採用手法は明確に異なります。
(参考:『リファラル採用とは?導入のメリット・デメリット、運用のポイントを紹介』)
アルムナイの採用が増えている背景
アルムナイの採用が増えている背景として、少子高齢化による慢性的な人手不足が考えられます。
日本では、15歳以上65歳未満の生産活動の中心となる「生産年齢人口」が年々減少しています。総務省のデータによると、生産年齢人口は、1995年の8,716万人をピークに減り続け、2024年には7,373万人程度にまで減少したことが判明しました。
これに伴い、中途採用のニーズも高まり、売り手市場化が続く転職市場では、高いスキルを持つ人材を採用することが困難になっています。こうした中で過去に自社で働いた経験があり、即戦力としての活躍が期待できるアルムナイは、重要な人材資源として注目を集めているのです。
(参照:総務省『生産年齢人口の減少』、総務省統計局『人口推計(2024年(令和6年)10月確定値、2025年(令和7年)3月概算値)』)
(参考:『出戻り社員が求められる背景と採用のためのアプローチ方法』)
アルムナイ採用を実施するメリット
アルムナイ採用の導入は、企業にさまざまな利益をもたらします。ここでは、アルムナイを再び迎え入れる4つのメリットを解説します。
メリット①自社を理解している人材を採用できる
アルムナイを採用するメリットとして最初に挙げられることは、自社への理解度が高い点です。
アルムナイは自社での勤務経験から、業務内容や社風を既に把握しています。そのため、再度研修を実施するにしても、ブランクを埋める程度で済み、入社後はすぐに戦力として活躍してくれるはずです。また、アルムナイ以外の中途採用の場合に懸念されるミスマッチによる早期離職も起こりにくいと考えられます。
このように、即戦力としての活躍が期待できるアルムナイは、企業にとって安心して雇える貴重な人材といえます。
メリット②自社にない視点からの意見を得られる
自社にはない視点からの意見を得られる点も、アルムナイ採用を実施するメリットの一つです。
自社以外の環境で経験を積んだアルムナイがもたらす新たな視点や知識、スキルは在籍中の社員の刺激となるでしょう。業務プロセスや組織構造の見直しだけでなく、新たなアイデアを取り入れる機会にもなるかもしれません。
特に、さまざまな職務経験を培ってきたアルムナイであれば、組織のイノベーションの推進に貢献してくれる存在として期待できます。
メリット③雇用や教育にかかる費用を抑えられる
アルムナイ採用は、雇用や教育にかかる費用を抑えられる点も魅力です。
一般的に、アルムナイ採用は自社の社員からアルムナイに連絡を取ることで採用活動が始まります。これにより、求人広告や人材紹介サービスを利用する必要がなくなる、あるいは利用する場面を絞れるようになるため、その分費用を削減できる可能性があります。
また、アルムナイは業務内容や方針をよく理解しているため、教育にかかる費用も、アルムナイ以外の中途採用の場合と比べて少なく済むでしょう。
つまりアルムナイ採用には、即戦力としての活躍が見込める人材の採用だけでなく、採用の前後にかかる費用の抑制も期待できるわけです。
メリット④在籍中の社員のエンゲージメントを向上できる
アルムナイ採用では、社員のエンゲージメント(貢献意欲)の向上をもたらす可能性もあります。
過去に社員として働いていたアルムナイが再び戻ってくるという事実は、その企業がはたらきやすく、魅力的な職場であることの証明になります。「一度退職してもまた戻りたいと思える職場」という好印象が在職中の社員にも広まり、エンゲージメントの向上につながるのです。
また、アルムナイ採用が活発化すれば企業イメージの向上も期待できます。アルムナイ以外の転職希望者からも、「風通しの良い職場なんだ」とポジティブなイメージを抱いてもらえるようになるでしょう。
アルムナイを採用する際の懸念点
アルムナイの採用には上記のメリットがある一方で、企業にとっていくつかデメリットとなり得る要素もあります。ここからは、アルムナイを採用する際の3つの懸念点を解説します。
懸念点①退職率が上昇する恐れがある
アルムナイ採用を導入すると、退職率の上昇につながる懸念もあります。これは在職中の社員に「退職しても再度雇用してもらえる」という心理が働きやすくなり、退職するハードルが下がってしまう可能性があるためです。
アルムナイ採用の制度化による社員の軽率な退職を防ぐためには、再雇用に関する一定の条件の設定・周知が重要です。「退職者全員が無条件に対象となるわけではない」と社員に理解してもらえれば、制度導入による人材流出のリスクを軽減できるでしょう。
懸念点②給料や待遇を慎重に決める必要がある
アルムナイ採用の実施に伴って、アルムナイへの給料や待遇に関する取り決めを慎重に定めることが求められます。この点を十分に検討せずに決めてしまうと、人材が集まらない、または社員から不満が生じる恐れがあります。
例えば、アルムナイに在籍し続けている同期社員と同程度の給料しか保証されないのであれば、再就職にあまり魅力を感じてもらえないでしょう。反対に、アルムナイを優遇しすぎて、在籍社員との間の待遇差が大きくなってしまうと、今度は在籍中の社員の不満につながるケースも考えられます。
アルムナイ採用を導入する上では、アルムナイと在籍中の社員の双方が納得する形になるよう、給料や待遇を決めなければなりません。
懸念点③アルムナイが職場になじめない可能性がある
「在籍中の社員に悪い印象を持たれていないだろうか」という気持ちから、アルムナイが不安や後ろめたさを感じる場合もあります。企業側がこの点を理解していないと、採用になかなか結びつかない、また採用できたとしても早期に退職してしまうかもしれません。
こうした懸念点を払拭するためには、アルムナイ採用に関して社内全体を通して理解が進むよう、企業としても万全のバックアップ体制で望むことが重要です。
アルムナイ採用を導入する流れ
ここからは、アルムナイ採用を実際に導入する際の手順を紹介していきます。
アルムナイ採用を導入する流れ
①採用に関する取り決めを定める
②アルムナイ採用の実施を周知する
③アルムナイと定期的に交流する
詳細を順に確認していきましょう。
(参考:『【ToDoリスト付】効率的に即戦力の人材を採用!アルムナイ採用を仕組み化する方法』)
ステップ①採用に関する取り決めを定める
アルムナイ採用を導入する際は、最初に採用条件や選考の内容など、採用に関する取り決めを設定します。
特に採用条件は緩く設定しすぎると、在籍中の社員の退職を誘引する可能性があります。そのため、アルムナイ採用は決して退職を推奨するものではないことを明言するとともに、条件を厳格に決めておきましょう。例えば「勤続○○年以上の人」「○○以上の役職経験がある人」のように、一定の水準を条件に盛り込めると、安易な退職は免れるはずです。
また、給料や待遇面のルールも決める必要があります。これについても、アルムナイ・在籍中の社員の双方から不満が出ないよう、慎重に設定したいところです。
ステップ②アルムナイ採用の実施を周知する
採用に関する取り決めの設定が済んだら、アルムナイ採用の導入を社内外に周知します。
在籍中の社員に伝える際は、導入の目的やメリット、また前述のステップで決めた採用条件を丁寧に説明する工夫が大切です。これにより、アルムナイ採用の実施に対する社員からの理解を得やすくなり、アルムナイが円滑に働ける環境づくりの足掛かりとなります。
アルムナイに周知するには、自社Webサイトに情報を掲載する、あるいはアルムナイに直接メールを送るといった方法があります。その際に、制度の概要を説明するとともに、戻ってきてほしいと思っている気持ちを率直に伝えることで、アルムナイの再就職への心理的ハードルを下げられるでしょう。
ステップ③アルムナイと定期的に交流する
アルムナイ採用は、社内外への周知を終えたら、すぐに応募が集まるというものではありません。募集開始後には、アルムナイの再就職の意欲を高めるために、在籍中の社員との交流の場を用意するなどの方法もあります。
例えば、懇親会や同窓会形式のイベントを開催するなどの方法が挙げられます。こうしたイベントを通して、企業文化や社内の現状、そして再び自社で活躍してくれることを期待している気持ちを、アルムナイに直接伝えられるわけです。
また、直接的なアプローチ方法ではないものの、SNSやメルマガ配信を活用して情報共有することも一つの手です。対面のイベントには出席できない人材にも、自社の近況や採用情報を届けられます。
アルムナイ採用を成功させるポイント
ここからは、アルムナイ採用を成功させるために、実践すべき施策を紹介します。
ポイント①働き方のバリエーションを増やす
アルムナイ採用を成功させるためのポイントとして、働き方のバリエーションを増やすことが挙げられます。
近年、働き方の多様化が進んでおり、正社員以外の働き方を望む声も増えています。そうした人材を取りこぼさないように、「時短勤務」「業務委託」「リモート勤務」「アルバイト」など、さまざまな選択肢を用意しておくことが重要なのです。
とは言え、アルムナイが望む働き方が自社の業務内容とマッチしていなければ、わざわざ導入する意味がありません。新しい働き方を導入する際には、企業にとってデメリットとなり得るものは避け、自社とアルムナイの双方が高い満足度を得られるものを選びましょう。
ポイント②イグジットマネジメントに注力する
アルムナイ採用を円滑に実施するための環境づくりの一環として、「イグジットマネジメント(出口戦略)」への注力も大切です。
イグジットマネジメントとは、社員が退職する際、トラブルなく送り出すために企業があらかじめ戦略を立てておくことを指します。この考えに基づいた退職プロセスを踏むことで、円満な関係のまま社員を送り出せ、退職後も良好な関係を維持し、将来的な再雇用の可能性を高められるわけです。
イグジットマネジメントに基づいた具体的な行動としては、面談を通じて社員の退職理由やキャリアプランを聞き出すことがおすすめです。退職者が企業に対して感じている不満や課題への理解を示し、この場で感謝の気持ちをきちんと伝えられると、好意的な感情を持ち続けてもらえるでしょう。
ポイント③社内の受け入れ体制を整備する
アルムナイ採用を実施する際は、社内の受け入れ体制の整備も欠かせません。アルムナイ向けの研修プログラムや、復職後のキャリアプランを準備しておきましょう。
このように受け入れ体制を整えておくことで、アルムナイに安心感を与えられるとともに、復職を歓迎しているというアピールにもつながります。その結果、職場復帰に対するアルムナイの心理的抵抗を押し下げる効果が期待できます。
(参考:『【ToDoリスト付】効率的に即戦力の人材を採用!アルムナイ採用を仕組み化する方法』)
アルムナイ採用ToDoリストの無料ダウンロードはこちら
ここまで、アルムナイ採用の流れやポイントを解説してきましたが、初めて制度を導入する場合にはスムーズに対応できない場合もあるでしょう。
そこで、アルムナイ採用の導入に際して、工程ごとに対応すべきタスクをまとめた「アルムナイ採用ToDoリスト」を作成しました。アルムナイ採用を適切に導入して、効果的な採用活動を実施したいとお考えであれば、ぜひ以下からダウンロードしてください。
アルムナイ採用の導入事例
最後に、アルムナイ採用を導入し成果を上げている企業の事例を紹介します。
デロイト トーマツ合同会社
デロイト トーマツ合同会社では、アルムナイとの交流を大切にしているそうです。アルムナイのキャリア形成の支援、また社員との親睦の場の提供を目的として、イベントの開催やメルマガの配信、e-ラーニングの提供など、さまざまな活動を展開しています。
こうした活動を通じ、同社では現在4,500人ものアルムナイと接点を持っているとのことです。この中で採用活動が活発に行われていることはもちろん、アルムナイが社員とインフォーマルに関わり合い、好影響を生み出しているといいます。
(参考:『企業目線でアルムナイは動かない―。共創を重視したデロイト トーマツ流 成功の舞台裏』)
パーソルキャリア株式会社
パーソルキャリア株式会社は、アルムナイとの交流を促進するため、2023年4月に「アルムナイコミュニティ」の運営を開始しました。退職時に人事から入会案内を行い、専任担当者2名が定期的な情報発信やイベントなどの交流機会の創出、業務委託案件や再入社の対応までを行っています。
これらの施策により、登録者は2024年1月時点で1000名に近づき、再雇用や業務委託案件も創出しています。加えて、再入社者へのインタビュー記事を採用ページに掲載し、再入社したからこそわかる自社の魅力を語ってもらうことで、採用ブランディングにもつなげています。
(参考:『採用コストを掛けられない、即戦力の人材を獲得したいという採用担当者の方へ。中小企業こそやるべき!?「アルムナイ採用」の設計ノウハウ』)
株式会社インテグレート
株式会社インテグレートでは、さまざまなフィールドで培った経験や知見を社内で生かしてもらうべく、アルムナイ採用の実施を始めました。
再就職を果たした社員からは「さまざまなことに挑戦できる場だと改めて感じた」「新しいことにも挑戦していく社風はとても刺激的」といった声が上がっているそうです。
こうした前向きな言葉が見られるところから、同社ではイグジットマネジメントに成功していることがうかがえます。退職後も円満な関係が続けられており、それが結果として再雇用につながっているのでしょう。
(参考:『採用コストを掛けられない、即戦力の人材を獲得したいという採用担当者の方へ。中小企業こそやるべき!?「アルムナイ採用」の設計ノウハウ』)
アルムナイ採用を導入して即戦力となる人材を採用しましょう
本記事では、アルムナイ採用の概要や導入するメリットを解説しました。
アルムナイ採用とは、自社を退職した人材を再び雇用する採用手法です。アルムナイには、自社での勤務経験を生かした即戦力としての活躍が期待できる上に、雇用や教育にかかる費用の最適化を図れます。
アルムナイ採用を導入する際は、採用条件を慎重に決めるとともに、再雇用後のフォローアップ制度も充実させることを心掛け、効率的な採用活動を実施しましょう。
「適切に導入できるか不安」という場合には、「アルムナイ採用ToDoリスト」をご利用ください。導入手順ごとに実施すべき施策がまとめられており、円滑な導入に役立つはずです。
(制作協力/株式会社eclore、編集/d’s JOURNAL編集部)
アルムナイ採用 ToDoリスト
資料をダウンロード