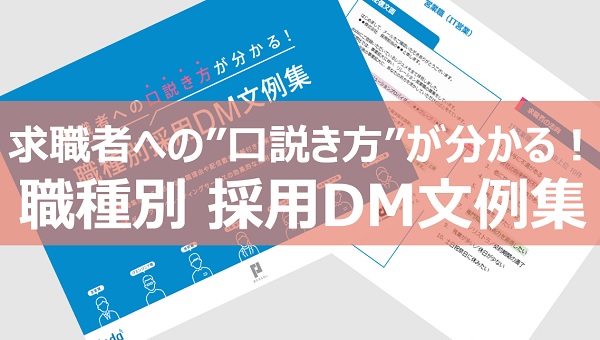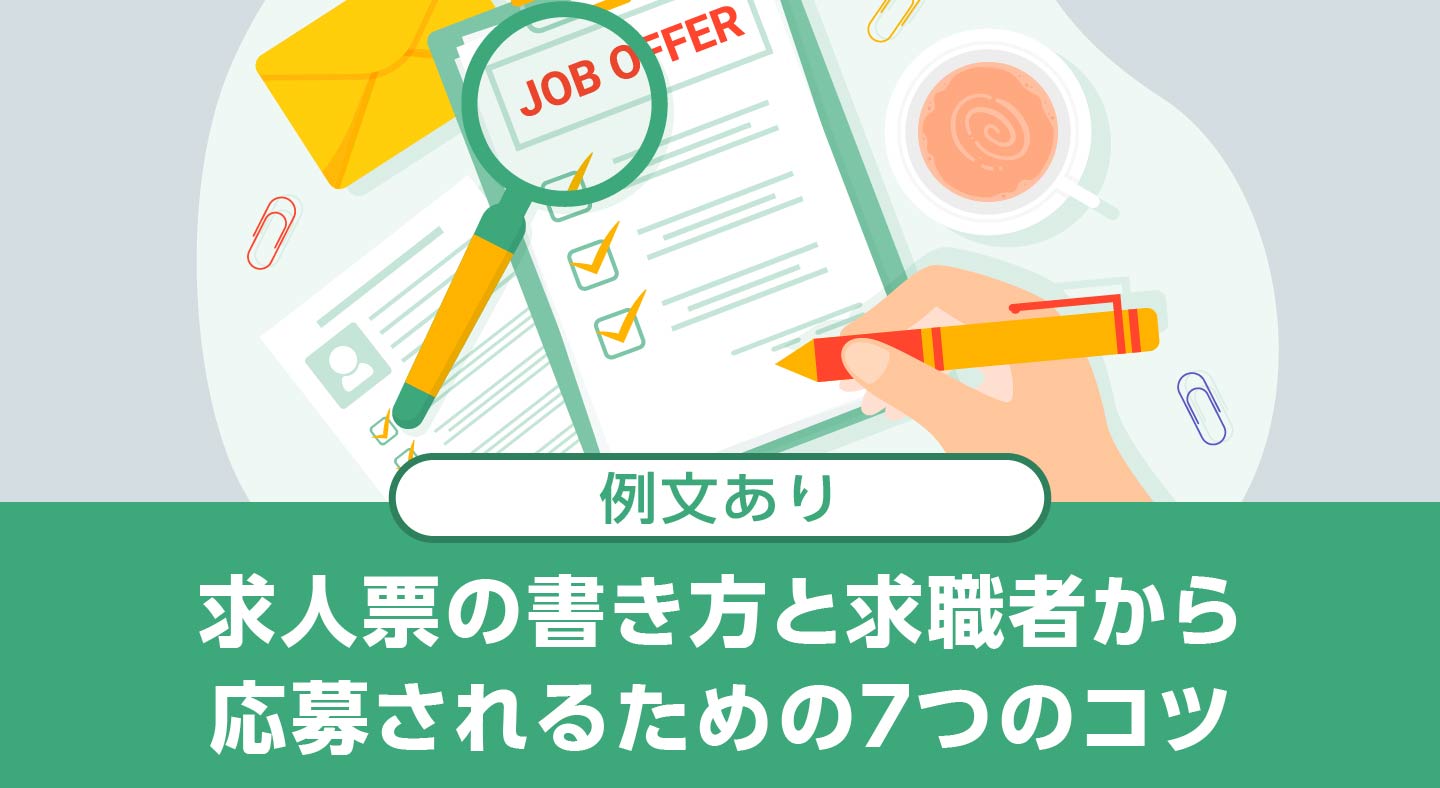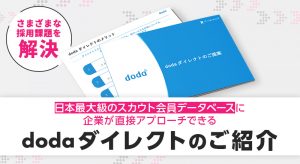ダイレクト・ソーシングの導入や運用時によくある悩みと採用に成功するためのコツとは
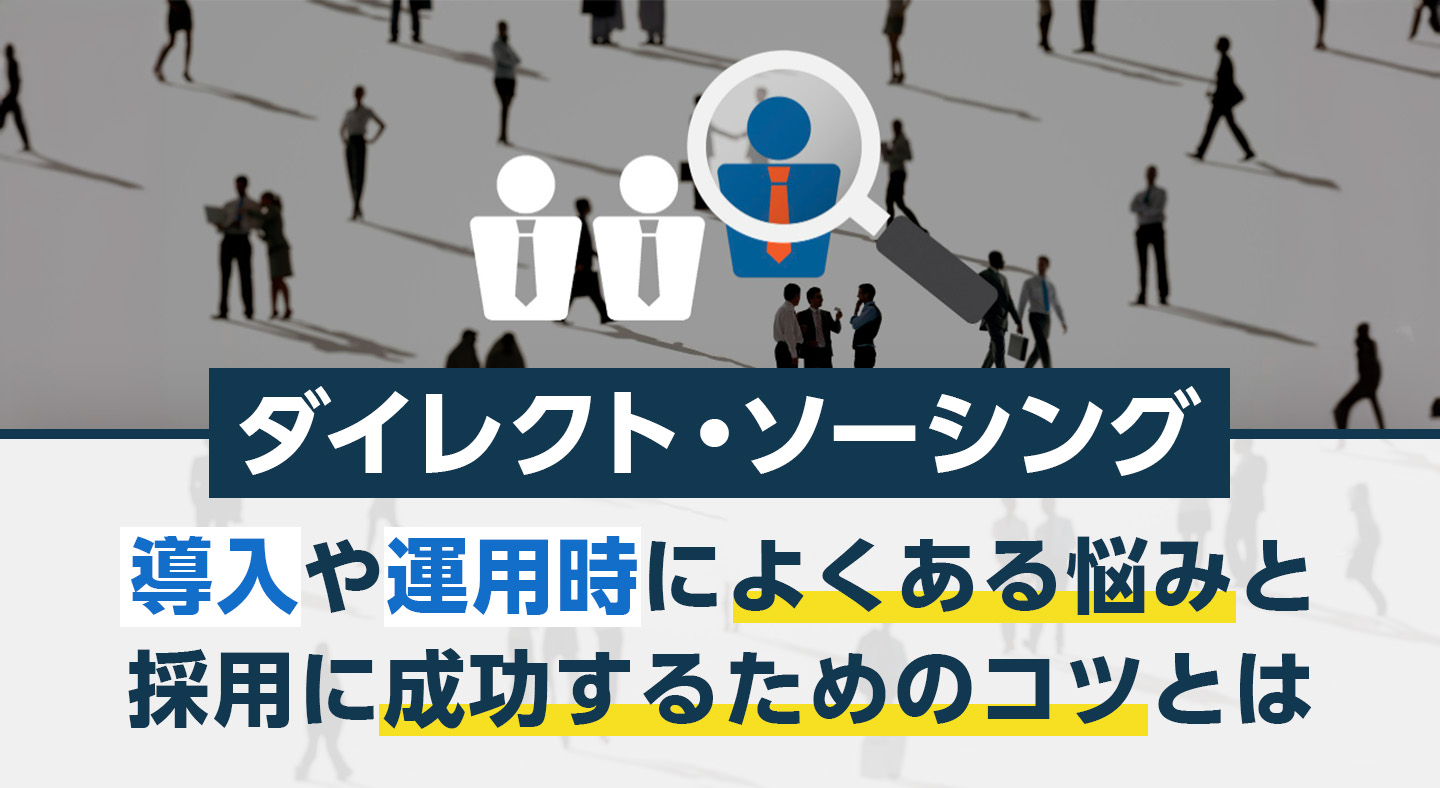
-
転職市場の現状や採用方針を共有し、現場とともにスカウトメールを送信。協業体制の構築には第三者が現場へ入ることも効果的
-
現場ヒアリングで求める人物像を具体化し、自社ならではの訴求ポイントを見いだす。過去の入社者へのインタビューも貴重な情報源に
-
カスタマーサクセスが介在することで「自社採用力向上」につなげ、「採用に本気で取り組む全社体制」を構築している
転職市場での競争が激しさを増す中、人材紹介サービスや求人広告といった従来の手法に加えて、新たにダイレクト・ソーシングを導入する企業が増えています。一方で採用に関わる人員が限られている企業では、「運用に工数を割けない」「現場とうまく連携できない」「自社の魅力がうまく伝えられない」といった理由から、なかなかサービス導入に踏み出せないケースも多いようです。
ダイレクト・ソーシングを始める際にはどんな課題があり、どのように乗り越えていくべきなのでしょうか。この記事では、パーソルキャリアが提供するダイレクト・ソーシングサービス「doda ダイレクト」のカスタマーサクセスとして、サービス導入後の採用成功に向けたサポートを担う2人にインタビュー。ダイレクト・ソーシング導入から採用成功のコツを聞きました。
多くの企業で「自社のリソースで運用しきれるだろうか」という不安が。工数削減や現場連携の秘訣
——ダイレクト・ソーシングを導入したいと考えてはいても、「自社のリソースで運用しきれるだろうか」と不安に感じる人事・採用担当者も多いように思います。
伊島氏:その不安はとてもよく理解できます。ダイレクト・ソーシングは自社で求人票をつくり、転職希望者を探し、スカウトメールを送らなければなりません。ここになかなか時間を割けないという声は実際に多いです。私たちがサポートしている企業の多くは、人事部門がなかったり、総務チームの中で採用を兼任していたりするケースも多いので、運用工数や負担をできるだけ削減するためのサポートにも力を入れています。
林氏:実際の現場では、計画を立てるところからサポートしています。スカウトメールを毎月どれくらい送るかの配信計画を立てて、週や日に落とし込んで目標設定をするんです。他の業務と並行して進めている中で、どうしてもスカウトメール対応の優先順位が下がってしまうことも多いので、事前にスケジュールに組み込むことで配信する時間を確保してもらうようにしています。
スカウトメールを初めて送信する担当者は、レジュメを読み込み配信対象か否かを判断することや文面作成に時間がかかってしまうケースもありますが、1~2カ月程度で慣れていくことが多いです。うまく運用している担当者は、毎日15~30分の時間を確保して10通程度配信したり、週に1~2回の頻度で新規登録の方をメインに配信したりするなどして効果的に運用しています。
伊島氏:募集内容や対象者によっては、一斉送信機能を使ってまとめてスカウトメールを送信するほうが効果的なこともありますね。ダイレクト・ソーシングは公開型の求人ではないので、スカウトメールを送らなければ何も始まりません。まずは数を送ることが大切なんです。ダイレクト・ソーシングに一定の手応えを感じられるようになった企業では、アシスタントを増員したり、代行業者を頼ったりして、担当者の工数を削減しながらダイレクト・ソーシング活用を拡大するケースも増えています。
——人事だけでなく、入社者を受け入れる現場側とも協業体制を築くべきなのでしょうか。
伊島氏:はい。人事と現場の協業はとても大切です。人事が現場の採用ニーズを把握し切れないまま、経験年数や年収などの条件だけでアプローチする転職希望者を大まかに決めてもなかなかうまくいきません。応募が来たとしても、現場での面接の通過率は低いでしょう。
林氏:中途採用では、企業の中長期計画を実現するためにどんな人材を採用すべきか、バックキャスト的な思考で経営・人事・現場が話し合える体制があることが理想です。とは言え、ただでさえ本業で忙しい現場の協力を得るのは簡単ではないとも思います。そこで私たちカスタマーサクセスでは、第三者として現場に介在し、ヒアリングや提案を行っています。第三者が介在することで、現在の転職市場の厳しさを現場に理解してもらう意味でも効果的です。
データベースの検索結果から社内で議論を重ねることで、最適な人材と出会える確率が高まる

——ダイレクト・ソーシングを始める際、企業はどのような壁にぶつかるのでしょうか。
伊島氏:ダイレクト・ソーシングを始める際に、要件定義の設定ができないことの課題は多いです。そのため、まず募集職種ごとに求める人物像を現実的なレベルで設定することが重要です。しかし採用する現場のニーズを明確に理解できていないと、表面的な要件でしか対象を捉えることができません。実際にデータベースを検索してみると「自社の求める転職希望者がほとんどいない」といったことも起こります。
林氏:経験者採用だけでなく、未経験者採用の場合も求める人物像の設定に苦戦することがあります。対象が幅広いだけに、あいまいな条件になりがちなのです。これではスカウトメールを送る際のメッセージをユニークにすることができません。
——求める人物像を設定する際の秘訣は。
伊島氏:ヒアリングを通じて現場サイドが求める人物像をつかみ、転職市場を踏まえて設定していくことが大切です。その上でデータベースから実際に転職希望者を検索し、この結果をもとに企業内で議論していくことで、より自社に最適な人材と出会えるようになっていきます。
転職希望者の検索の仕方にもさまざまなノウハウがあります。たとえば営業経験者の募集で、現場から「数字に貪欲な人がほしい」と言われている場合。転職希望者の内面をイメージし、フリーワード検索を活用してレジュメ内に「目標」「達成率」などと書かれている人を見つけられれば、求める転職希望者に出会える可能性が高まります。
林氏:未経験者採用の場合は、過去に入社した従業員の傾向からひも解いていくことが多いですね。どんな理由で転職・入社したのかを聞けば、その従業員が以前に属していた業界の人が抱える志向や不満を想定できるからです。どんな業界にいる人が、どんな転職理由で動くのか。そこまで転職希望者心理を掘り下げて考え、スカウトメールを送ることが大切だと思います。
——スカウトメールを送る際は、どのように訴求すれば応募効果を高められるのでしょうか。
林氏:ご承知の通り昨今は超売り手市場で、即戦力の経験者採用では大手をはじめとしたたくさんの企業が採用に取り組んでいます。転職希望者は待遇アップや柔軟な働き方を求めていますが、賃上げやリモートワークなどはすでに多くの企業が行っており、なかなか差別化を図れません。だからこそ、転職希望者がどんな不満を持って転職活動をしているのかを仮説立てし、その仮説を踏まえて自社ならではの訴求ポイントを伝えるべきなのです。
伊島氏:全員に届くような求人票やスカウトメールは、結果的に誰にも届かないこともあります。求人広告とは違い、ダイレクト・ソーシングは自社内で柔軟に打ち出し内容を見直せるので、ABテストのような形で訴求ポイントを変えながら検証していくことも大切だと考えています。
訴求力アップ、現場連携向上、入社受諾促進の工夫で採用へつながった事例
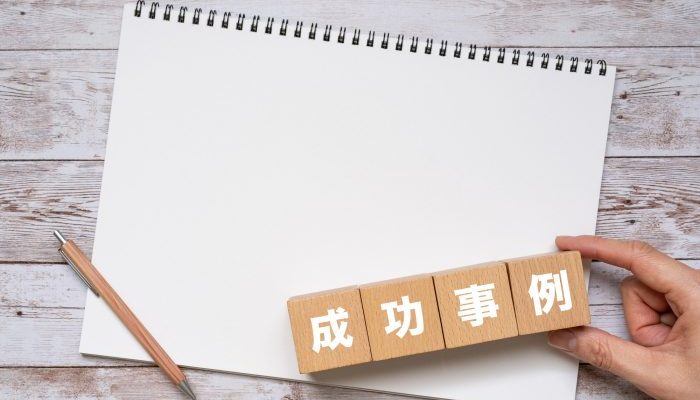
——工夫や改善を行ったことで採用成功につながった事例を教えてください。
林氏:食品・飲料領域で独自素材の研究と開発に特化している中小企業では、自社の強みを棚卸しして訴求ポイントにつなげることで採用につなげています。
この企業は従業員数が少ないものの、専門知識を有するイノベーター集団。中途採用で求めていたのは食品素材領域での課題解決型の開発・応用研究経験者でした。ただ、スカウトメール配信対象者が20名程度と少なく、どのように求める人物像を定め、その転職希望者に向けた魅力を打ち出していくかが課題となっていました。
そこで、この企業だからこそ打ち出せる魅力を追求。現場へのヒアリングを通じて課題解決型の研究職の魅力を探っていったのです。結果、「研究の自由度が高く経営層に直接提案できる」「大学との共同研究を進めているため最新の研究成果に触れられる」「安定した利益を確保しており、その利益を基盤に新たな研究開発に挑める」ことなどを訴求ポイントとして打ち出すことで応募率が向上し、採用成功につながっています。
——現場との連携を深めることで採用成功に至ったケースもお教えください。
伊島氏:ある企業では、スカウトメールの送信ができれば一定の応募者が集まるものの、人事・採用担当者側からではなく、現場主導でスカウトメールを送らなくてはならない体制でした。ただ、現場では採用の温度感が高まっておらず、スカウトメール送信も後回しになりがちだったのです。
そうなってしまう原因は、現場担当者が転職市場の厳しさを知らず、会社がどのように採用に乗り出しているか、人事・採用担当者側が何をどう頑張って採用しようとしているかなどの方針も理解されていないことにありました。
そこで現場における採用への温度感を改めてヒアリングし、転職市場や企業としての採用方針を、営業・施工管理・設計などの部署ごとに説明していったのです。さらに現場担当者へは、採用活動の進捗状況を周知。事業部ごとの配信数・応募数・採用決定数などを定期的に共有し、意識を高めていった結果、各部署でスカウトメール送信数が増えて採用に至っています。
——入社受諾促進の工夫で採用成功に至ったケースはありますか。
林氏:ある企業では、営業職ポジションで入社承諾前の辞退が多いことに悩んでいました。目標達成意欲が高い人にアプローチしていたのですが、既存の「年俸450万円(インセンティブ込み)」という条件では他社と比べて見劣りしてしまい、選考に進むもののなかなか入社受諾に至らなかったのです。しかし現場にはアプローチする対象を変えたくないという強い意向がありました。
この状況で入社受諾につなげるために行ったのが、現場のトップ営業に協力してもらうことでした。現年収550万円の方から応募があり、選考を通して絶対に採用したいと感じる人材だったため、条件面談にトップ営業の社員の方に参加してもらったんです。面談では自身のインセンティブの取り方や年収アップの可能性を説明。その結果、応募者の入社意向を高めることに成功しました。
カスタマーサクセスの役割は「自社採用力を高め、採用に本気になってもらう」こと

——こうした事例にも現れているように、ダイレクト・ソーシングを有効活用するためにはサポート体制の存在も欠かせないと感じました。dodaのカスタマーサクセスでは、具体的にどのようなサポートを行っているのでしょうか。
伊島氏:カスタマーサクセスが介在する最大の意義は、企業の採用力を伸ばすためのインプットにあると思っています。私たちはdoda ダイレクトを通じて、自社採用力を高めるお手伝いをしているのです。その意味では将来的に「カスタマーサクセスの力を借りなくてもダイレクト・ソーシングを運用できる」という状態になっていただくことが理想なのかもしれません。
最近では人事・採用担当者の方々だけでなく、経営層の方々とも転職市場や採用戦略について話す機会が増えました。私たちが介在することで、1社でも多くの中小企業を元気にできればと思っています。
林氏:私たちに寄せられている期待は、単に運用方法を説明することだけではなく、現場を巻き込みながら「企業全体で採用活動に本気になっていただく」ためのアプローチをすることだと認識しています。企業の行動変容につながる提案ができることこそがカスタマーサクセスの価値なのです。
お客さまの中には、社長や人事・採用担当者が1人でダイレクト・ソーシングの運用を担っているケースも少なくありません。中小企業の経営者や人事・採用担当者はなかなか助言を得られない立場で、孤独になりがち。私たちはその近くで常に寄り添い、本音で会話しながら、人と組織についてともに考えるパートナーでありたいと思っています。
取材後記
「運用工数や負担をできるだけ削減するためのサポートにも力を入れている」という言葉があったように、doda ダイレクトは現在、本職と採用を兼任している企業での導入例も増えているそうです。施工管理やエンジニアなど採用難度の高い職種の場合も、自社が求める転職希望者へ直接アプローチできる「攻めの手法」としてダイレクト・ソーシングが定着しつつあるといいます。人材紹介サービスや求人広告といった外部サービスの効果をさらに高める意味でも、今後は自社採用力アップにつながるダイレクト・ソーシングの取り組みが必須となっていくのかもしれません。
企画・編集/森田大樹(d’s JOURNAL編集部)、野村英之(プレスラボ)、取材・文/多田慎介
【関連記事】
■ 中小企業の人事・採用担当者必見!“ぼっち人事”でも効率的に進められるダイレクト・ソーシング
■ スカウトメール活用ガイド|例文付きで反応率を高める書き方を解説
■ 採用できないのは“自分たちのスタンス”が原因かも…。プロ直伝!ダイレクト・ソーシングの成功法
■ 知らないうちに転職希望者から嫌われる!?ダイレクト・ソーシング“NG例とその対策”
「doda ダイレクト」のご紹介
資料をダウンロード