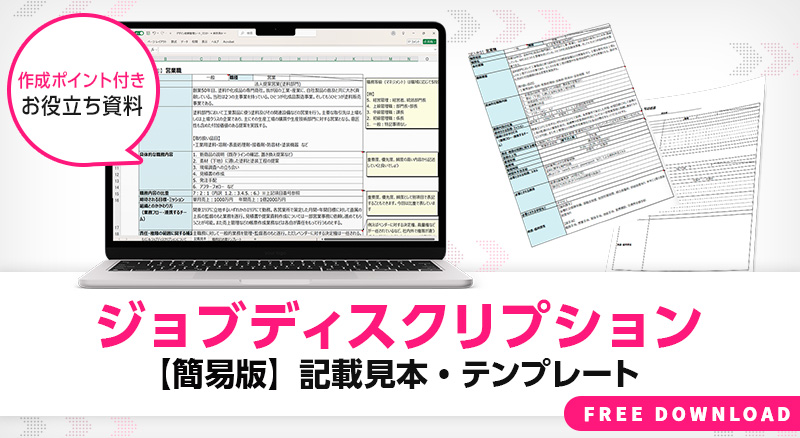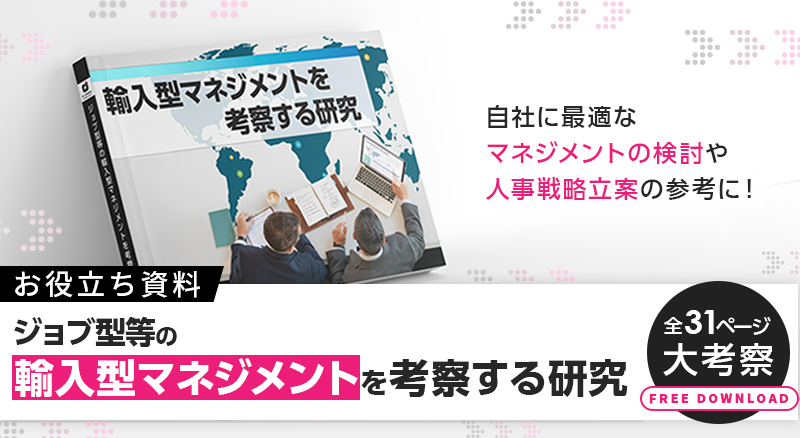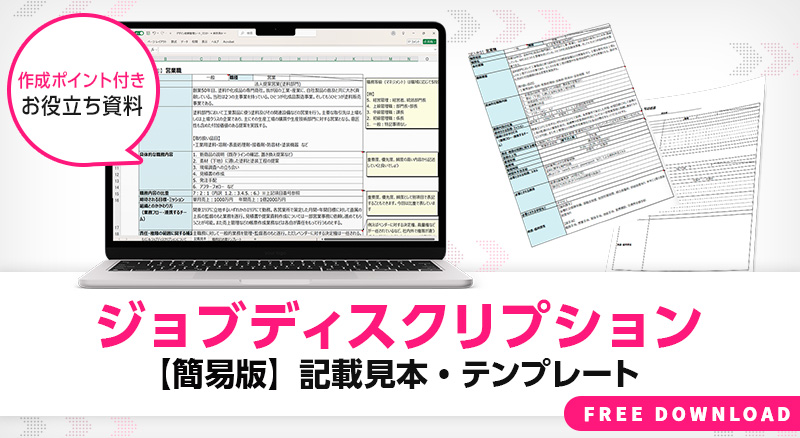ジョブ型雇用とは|制度のメリット・デメリットや導入事例を解説
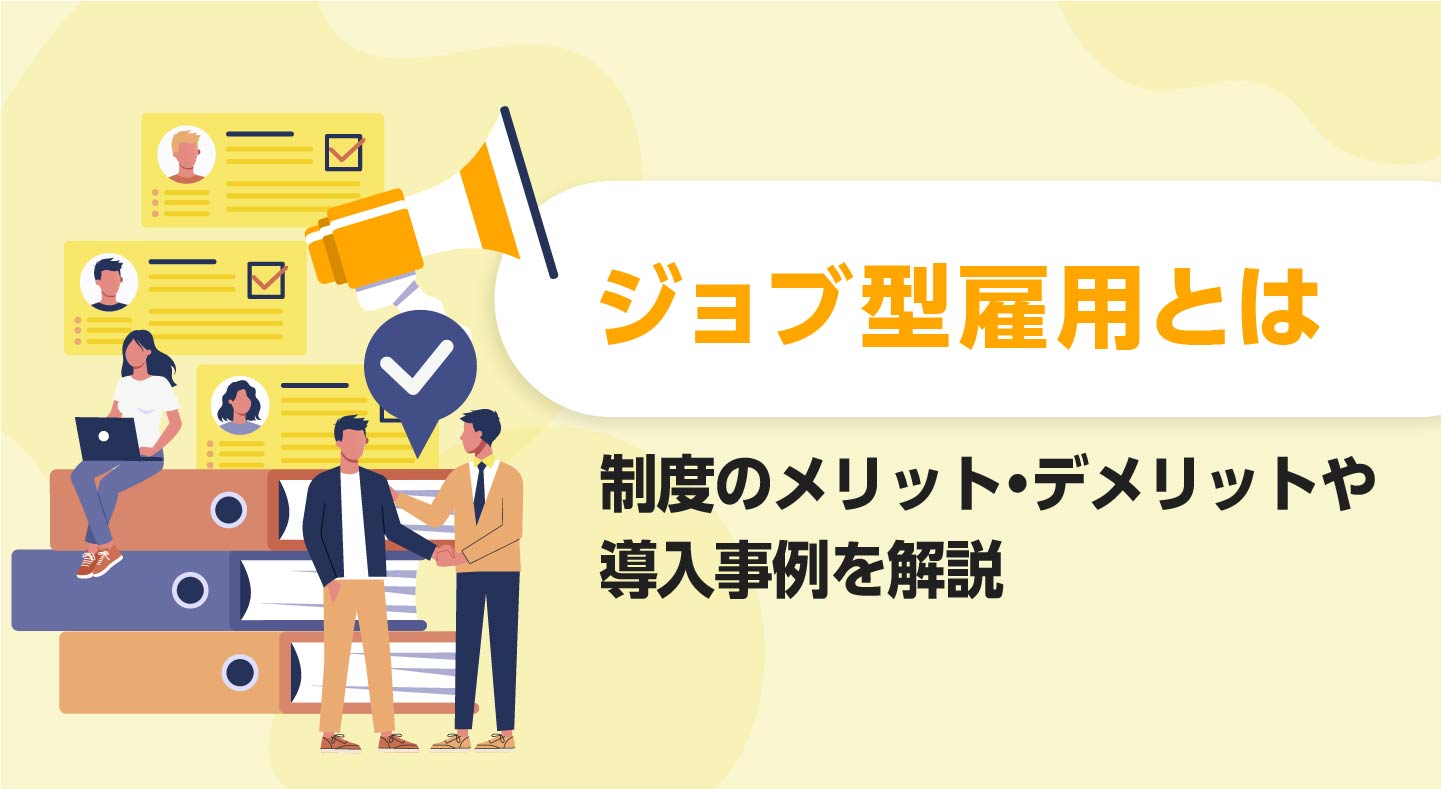

d’s JOURNAL編集部
募集している特定の職務を遂行する上必要な能力を持つ人材を採用する、ジョブ型雇用。
「ジョブ型雇用を導入することによるメリットを把握したい」「ジョブ型雇用の導入事例を知って参考にしたい」と考える人事・採用担当者もいるのではないでしょうか。
この記事では、ジョブ型雇用のメリット・デメリットや、企業での導入事例などを、わかりやすく紹介します。
ジョブ型雇用とは?
ジョブ型雇用とは、職務内容を明確に定義し、その職務を遂行するにふさわしいスキルや経験を持つ人材を雇用する方法のことです。採用時には、必要なスキルや能力、職務内容などを細かく記載した「職務記述書(ジョブディスクリプション)」を基に、契約を結びます。
ジョブ型雇用について、経団連は「採用と大学教育の未来に関する産学協議会・報告書『Society 5.0に向けた大学教育と採用に関する考え方』」で、以下のように定義しています。
特定のポストに空きが生じた際にその職務(ジョブ)・役割を遂行できる能力や資格のある人材を社外から獲得、あるいは社内で公募する雇用形態のこと。
引用:経団連 採用と大学教育の未来に関する産学協議会・報告書『Society 5.0に向けた大学教育と採用に関する考え方』
ジョブ型雇用で重視されるのは、特定の職務に関する「スキル」や「能力」です。年齢や学歴にとらわれず、その職務に対するスキルを持つ人材を採用する手法です。
国内外での導入状況
ジョブ型雇用が主流となっているのは、アメリカやカナダ、ドイツといった欧米諸国です。
日本では、ジョブ型雇用はそれほど普及しておらず、採用後の職務や勤務地を限定しない「メンバーシップ型雇用」が一般的です。しかし近年では、リモートワークの普及や、専門性の高い職種が増えたことによって、大企業を中心にジョブ型雇用での採用が広まりつつあります。
ジョブ型雇用で重要な職務記述書(ジョブディスクリプション)に記載するべき項目
ジョブ型雇用での採用で締結する職務記述書には、職務内容や必要なスキルのほかにも、職務名や職務概要などを記載する必要があります。以下に、企業が職務記述書に特に記載するべき項目をまとめました。
職務記述書に記載するべき項目
会社概要/職務階級/職種/職務名
職務概要/具体的な職務内容/職務内容の比重
期待される目標/ミッション
組織との関わり方
責任・権限の範囲に関する補足/直属の上司/部下の人数
雇用形態/勤務地/勤務時間/時間外手当支給の有無
必要とされる知識やスキル/必要とされる学歴/資格/待遇や福利厚生
ジョブ型雇用を導入した企業は、人事評価にも職務記述書を用います。職務記述書に記載した項目に伴う成果で人事評価を行うと、公平性が担保され、入社した社員が納得のいく評価を与えられます。
ジョブ型雇用と成果主義は何が違う?
ジョブ型雇用は「成果主義」と言われることもありますが、それは誤解です。ジョブ型雇用では、「成果」ではなく、あくまで「定められた職務を滞りなく遂行すること」が求められます。
報酬も職務内容によってあらかじめ職務記述書に定められており、成果の高低が給与額に反映されるわけではありません。そのため、ジョブ型雇用と成果主義は分けて考える必要があるでしょう。
ジョブ型雇用が注目されている背景
ジョブ型雇用が日本で広まった理由として、最初に考えられるのは「経団連によるジョブ型雇用の推奨」です。そのほかには、「少子高齢化が原因の人材不足」「ダイバーシティーの推進」「テレワークの普及」といった出来事なども挙げられます。
以下では、ジョブ型雇用が注目されるようになった背景を、詳しく解説します。
経団連によるジョブ型雇用の推奨
ジョブ型雇用は、経団連が「2020年版経営労働政策特別委員会報告」を発表したことで、注目されるようになりました。
報告では、メンバーシップ型雇用の利点を活かしながら、ジョブ型雇用の特徴を取り入れる「自社型雇用システム」の推進が必要であると提起されました。これを受けて、多くの企業が雇用システムを一から見直す機会につながり、ジョブ型雇用が注目を集めるきっかけになったといえます。
(参照:週刊 経団連タイムス『2020年版経労委報告を公表(2020年1月23日 No.3439』)
少子高齢化による人材不足
次に挙げられるのは、少子高齢化や育児・介護によるキャリア中断などを理由とした、企業の人材不足です。近年は転職希望者数に対して求人数が多い売り手市場が続いており、新卒の一括採用だけで対応するのが難しくなっています。
特に専門性の高い職種では慢性的に人材が不足していることもあり、求めるスキルや仕事の内容、勤務地を限定した求人のほうが人材を集めやすいという考え方が広まりつつあるのです。
ダイバーシティーの推進
顧客の価値観の多様化やグローバル化の推進により、ダイバーシティーの必要性が高まっていることも、ジョブ型雇用が注目される一因です。スキル重視のジョブ型雇用では、年齢や国籍にとらわれず、職務記述書の内容と転職希望者のスキルを基に採否を決定します。
そのため、多様な人材や働き方を受け入れやすいといえるでしょう。ジョブ型雇用は「海外人材の採用」「育児や介護と両立しながらの時短勤務者の採用」「退職者の再雇用」を通して、ダイバーシティーを推進できる採用方法と考えられているのです。
テレワークの普及
働き方改革の推進や2019年に発生した新型コロナウイルス感染症の影響により、テレワークが急速に普及したことも要因の一つです。個々の役割が明確になっているジョブ型雇用は、テレワークとの相性が良いとされています。
具体的には、「通勤負荷の軽減」「マネジメント工数の削減」などの効果が期待できるでしょう。
採用力の強化
ジョブ型雇用であれば採用力の強化につながる点も、日本で注目され始めた理由の一つです。
ジョブ型雇用は、転職希望者が企業の求めているスキルや経験を持っていることが採用の前提条件であるため、自社が求める人材を採用できる可能性も高まります。また、職務記述書に記載した職務内容や必要なスキルを、企業と転職希望者の双方で確認した上で契約を結ぶため、人材のミスマッチも起きにくくなります。
ジョブ型雇用を活用して採用力が強化されると、スキルを持った人材を数多く採用できる可能性が高まり、企業はさらに安定した成長を見込めるでしょう。
ジョブ型雇用の教育
ジョブ型雇用は、応募職種に必要なスキルや能力が備わった人材のみを採用するため、入社後の人材育成は、ほとんど必要ありません。しかし社員がスキルを伸ばせるように、研修や学習コンテンツといったプログラムを揃えておくことが、ジョブ型雇用での人材育成で大切なポイントです。
具体的には、「職種別のキャリアパスの提示」「提示した先の支援」を行う必要があります。社員はこれらをうまく活用し自主的に学ぶことで、職務に必要な知識の習得につながるわけです。
企業が感じるジョブ型雇用のメリット
ジョブ型雇用の導入によって企業側が享受できるメリットには、「生産性の向上」「費用の削減」などがあります。ここからは、それらのメリットを6つに分けて、詳しく紹介します。
メリット①業務効率化により生産性が向上する
ジョブ型雇用によって採用された社員は、保有するスキルや経験を基に、あらかじめ定められた職務に従事します。職務範囲や責任が明確になることで職務に集中できる環境が整うため、「業務の効率化」「生産性の向上」「専門分野に強い人材の育成」につながることがメリットとして挙げられます。
また、ジョブ型雇用では、年齢や勤続年数ではなく、仕事の遂行能力に応じて人事評価を行います。「スキルの高さ」が評価に直結するということもあり、自ら目標を定め、職務に意欲的に取り組む社員が増えるといった効果も期待できます。
メリット②費用を削減できる
ジョブ型雇用では、必要なスキルや能力をあらかじめ企業が定めた上で人材を募集するので、ミスマッチが起こりにくく、採用にかかる費用を削減できます。これは採用後、職務に対する教育を、企業が一から行う必要がないためです。
また、ジョブ型雇用での給与は年功序列制度ではなく、スキルや職務の内容に応じて額が決まる職務等級制度が適用されます。そのため、年功序列によって年々高騰する人件費の抑制にもつながります。
ジョブ型雇用は、採用時にかかる教育費や研修費はもちろん、人件費も削減できる制度といえるのではないでしょうか。
メリット③即戦力の人材を採用しやすくなる
ジョブ型雇用は、自社が求めるスキルや経験を備えていることが採用の条件であることから、即戦力として活躍できる人材を採用できる可能性があります。
また、勤続年数や年齢ではなく、就業後の職務内容とそれを遂行するための実務能力に応じて給与を定めるため、一般的な新卒・中途採用に比べ、待遇が良くなる傾向があります。給与額で競合他社との差別化を図れれば転職希望者が集まる可能性も高まり、自社が求める人材を採用しやすくなるでしょう。
メリット④若手社員に活躍の場を提供できる
ジョブ型雇用では、必要な職務に適した人材を配置するため、職務を任された若手社員は自身のスキルを遺憾なく発揮してくれます。社員一人ひとりの生産性の向上だけではなく、将来的には企業の大きな成長にもつながるでしょう。
メリット⑤入社後のミスマッチを防止できる
ジョブ型雇用では、事前に職務内容を明確にして募集を行い、転職希望者はそれらを理解した上で応募をします。職務記述書によって勤務条件が定義されるので、転勤や異動もありません。
そのため、「スキルや適性のミスマッチ」「本人が希望するキャリアとのミスマッチ」「働き方のミスマッチ」などが起こりにくく、モチベーションの低下や早期退職を防ぐことができるといえるでしょう。
(参照:『ミスマッチとは?新卒・中途採用の早期離職防止に有効な原因別の対処方法を紹介【資料付】』)
メリット⑥社員を正当に評価できる
ジョブ型雇用は、職務記述書によって詳細な評価基準が定められているため、社員を客観的な視点で正当に評価できます。
人事評価に評価者の主観が反映された場合、社員によってばらつきが出て、評価そのものの正当性が失われてしまいます。結果、人事評価制度への不満につながり、自社の信頼が失われ、退職者が相次いでしまうかもしれません。採用時に用いた職務記述書を使用すれば、社員のスキルや能力に基づいた公平な人事評価が行えます。
企業が感じるジョブ型雇用のデメリット
ジョブ型雇用にはさまざまなメリットがある一方、デメリットがあるのも事実です。そこでここからは、ジョブ型雇用の導入によって、企業側が感じる5つのデメリットを紹介します。
デメリット①採用の難易度が上がる
ジョブ型雇用では高度な専門スキルを持った人材の採用を目的とするため、競合他社との競争率は必然的に高くなります。急な欠員が出た場合には、同様のスキルや資格を持った経験者を募集しなければならず、代替要員を採用するまでに時間がかかってしまうこともあるでしょう。
また、多くの候補の中から自社を選択してもらうためには採用広報や母集団形成の工夫が必要となるため、採用の難易度が上がることがデメリットだといえます。
デメリット②帰属意識が生まれにくい
ジョブ型雇用では新卒採用のような一斉研修がなく、保有する専門スキルを基にそれぞれの職務に従事することが一般的です。また、勤続年数による報酬のメリットもないことから、より良い条件を求めて転職をする可能性もあります。
そのような理由から、「チームワークを醸成しにくい」「帰属意識が生まれにくい」「人材が定着しにくい」といったデメリットが発生します。チームで行う作業や長期的なプロジェクトが多い企業では、そもそもジョブ型雇用がマッチしない可能性があるため、導入前に十分検討しましょう。
デメリット③退職率が上昇する可能性がある
ジョブ型雇用を導入すると、社員の退職率が上がる恐れがあります。
ジョブ型雇用は、あらかじめ決定した担当する職務や勤務地などが、入社後に変更されることはほとんどありません。したがって、競合他社がより良い条件で人材を募集していた場合、社員がその会社に転職する可能性があるのです。
また、ジョブ型雇用は成果を基に評価するため、社員は常に高い成果を出し続けなければなりません。職務を遂行する上で責任感やプロ意識を求められることが負担となり、退職へとつながる恐れもあります。
どれほどスキルを持った人材でも、仕事の精度には波があるでしょう。ジョブ型雇用の場合、成果を出せない期間が続けば待遇は上がらないため、待遇面での不満を抱える社員の退職が相次ぐと、退職率の上昇は避けられません。
デメリット④制度を見直す必要がある
新たにメンバーシップ型雇用を導入した場合、制度の抜本的な見直しが必要となります。
メンバーシップ型雇用は、職務や勤務地を設定せずに雇用契約を結ぶ方法です。職能資格制度を採用しているため、年功序列や勤続年数に基づいて給与が決まり、人事評価の項目には人間性やコミュニケーション能力が含まれます。
一方、ジョブ型雇用は職務や勤務地を定めた後に人材を採用するため、メンバーシップ型雇用とはまったく異なります。スキルや職務の成果を基に人事評価を行い、その成果に応じて給与体系を決定するのが基本です。
このようにメンバーシップ型雇用とジョブ型雇用では、給与体系や評価項目が異なるので、制度そのものを変更する際は、企業にとって大きな負担となるでしょう。
デメリット⑤転勤・異動ができない
ジョブ型雇用の社員は、原則、職務記述書に記載されている職務や勤務地で業務を遂行します。そのため、メンバーシップ型雇用では一般的な転勤やジョブローテーションなどを行えません。
「人材が必要になったタイミングで転職希望者がいるとは限らない」「特定の職務が不要となった際には解雇せざるを得ない状況も想定される」ことに留意して採用を進めましょう。
転職希望者が感じるジョブ型雇用のメリット
ジョブ型雇用は企業側だけではなく、転職希望者にとってもメリットがあります。それでは一つずつ、詳しく見ていきましょう。
メリット①スキルアップが期待できる
ジョブ型雇用では、転職希望者が得意とする分野の職務のみが任されるため、その分野のスキルを存分に伸ばせます。また、異動の心配もないので、担当する職務のスキルや経験を積み続けられるでしょう。
したがってジョブ型雇用は、もともと得意としている職務に集中して取り組めるため、そのスキルを極めたい、あるいは伸ばしたい転職希望者に最適な制度だといえます。
メリット②成果を出せる可能性が高い
ジョブ型雇用の採用であれば、あらかじめ職務内容が決まっているほかに、職務に付随するスキルや経験を持った人材しか採用されないため、成果を出せる可能性が高まります。
自身が得意とする職務で成果を出し続けると、それに応じて給与が上がります。もともとのスキルを活かして知識をより深められたら、入社後間もないタイミングでも高収入を狙えるかもしれません。職務で結果を出すと給与がアップするため、社員のモチベーションを長く維持できます。
転職希望者が感じるジョブ型雇用のデメリット
ジョブ型雇用は、転職希望者にもデメリットが生じます。そこでここからは、転職希望者目線でのジョブ型雇用のデメリットを詳しく解説します。
デメリット①キャリアアップが難しい
ジョブ型雇用で入社すると、キャリアアップが途端に難しくなる可能性が高まります。
ジョブ型雇用によるキャリア形成を図るには、特定の職務にただ従事すればよいわけではなく、結果を出す必要があります。職務で良い結果を出せなければ人事評価は下がり、キャリアアップもかなわないでしょう。
ジョブ型雇用の場合、企業は基本的に、研修やプログラムを社員に向けて提供しません。そのため、職務で結果を出すだけではなく、自身の目指すキャリアに合わせてスキルを磨き続ける必要があります。
一部の企業では、ジョブ型雇用のこうしたデメリットを補うために、教育研修や社外講座などを提供し、社員が自主的に学べる環境を整備しています。ただし、ジョブ型雇用でのキャリアアップは、主に自己研鑽によるものだと留意しておきましょう。
デメリット②仕事がなくなる可能性がある
ジョブ型雇用では、担当している職務や職種が不要となった際、社員は職を失う可能性があります。
しかし、日本の企業の場合は、担当する職務がなくなると同時に解雇されるケースはほとんどありません。日本では労働力不足が課題となっているため、リスキリングを活用して、異なる職種に就いてもらうという方法を取る企業が数多く存在します。
したがって「任されている職務が不要になったら、突然解雇されてしまうかもしれない…」と過度な不安を抱える必要はないでしょう。
必ずしもジョブ型雇用が推奨されるわけではない
これまでご紹介したように、ジョブ型雇用の導入にはメリット・デメリットがそれぞれ存在します。企業の規模や取り扱う商材・サービス、企業理念によってはメンバーシップ型雇用のほうが適しているケースもあるため、必ずしもジョブ型雇用が推奨されるわけではないことを念頭においておきましょう。
一方で、「職務の複雑化」「労働人口の減少」「法改正」などのさまざまな影響により、ジョブ型雇用がマッチするような時代の変化があることも事実です。今後は、世情や自社の状況を踏まえながら、必要に応じて自社の雇用システムを見直していくことが重要になるでしょう。
ジョブ型雇用を導入する上での課題
現在の日本企業が、完全にジョブ型雇用へ切り替えることは難しいといえるでしょう。その理由について「人事部の運用コスト」「既存社員への説明・合意獲得」「新卒(若手社員)の教育」の3つの観点から解説します。
人事部の運用コスト
職務記述書は一度作成した後も定期的に見直す必要があるため、職種別に職務内容を把握し、評価基準を調整していくのは非常に工数がかかります。
また、メンバーシップ型雇用とジョブ型雇用とでは特徴が異なるため、制度上の矛盾がないよう十分な準備期間を経て移行し、効果についても検証し続ける必要があるでしょう。このように運用体制を整える必要があるため、運用を担う人事部のコストがかかることが課題です。
既存社員への説明・合意獲得
日本でもジョブ型雇用の導入が進んではいるものの、多くの企業では依然として、終身雇用や年功序列を含めたメンバーシップ型雇用が慣例化していることも事実です。
ジョブ型雇用への切り替えはさまざまな制度変更を伴うため、既存社員から不満が出ることも予想されます。不満を解消できないまま移行してしまうと、チームビルディングに支障が出たり、早期退職につながったりする可能性もあるでしょう。既存社員が納得できるよう客観性・透明性のある説明を行い、合意を得ることが重要です。
新卒(若手社員)の教育
メンバーシップ型雇用の新卒一括採用では、スキルや能力が発達段階である人材を総合職として採用することも多く、職種や仕事内容をローテーションさせながら適性を見極めていきます。それを前提とした現在の日本の教育制度では、卒業後即戦力として活躍できるレベルの専門スキルを獲得することが難しいため、若手社員に対しては企業側が教育する必要性があることも課題として挙げられるでしょう。
これら3つのデメリットのほか、専門性を突き詰めるジョブ型雇用では、多角的・横断的な視点が求められるゼネラリストの育成が困難になる可能性もあります。そのため、統括管理を行う幹部候補者には、期間限定でジョブローテーションを実施するなどのフォロー施策が必要となるでしょう。
日本企業ではハイブリッド型がよく見られる
前述の課題点もあり、ジョブ型雇用への完全移行は、特に安定した人材配置を行いたい中小企業にとっては難しい判断だといえるでしょう。職務の生産性が不安定な状態や、既存の社員からの不安を解消できないまま導入しては、ジョブ型雇用の本来の効果が発揮できない可能性もあります。
そうした懸念から、日本では採用戦略や人事評価などの一部分にジョブ型雇用の特徴を取り入れる「ハイブリッド型」を運用する企業が多く見られます。例として、「一定の年齢になったら異動をなくし、職務の範囲を限定する」「勤続年数を給与に反映させない」などの方法があります。
メンバーシップ型雇用かジョブ型雇用かの二択ではなく、自社の企業風土や労働慣行に合った方法を模索するとよいでしょう。
ジョブ型雇用を導入する流れ
ここまでの内容を踏まえて、ジョブ型雇用への理解がより深まったのではないでしょうか。それでは次に、ジョブ型雇用をスムーズに導入するための流れを解説します。
ステップ①職務内容を設定する
まずは、ジョブ型雇用を取り入れる職務内容を具体的に決定します。
職務内容を定義する際に必要な項目は、以下の通りです。
定義すべき主な職務内容
職務名称
職務目的
職務内容
職務および責任の範囲
新たにジョブ型雇用に切り替える場合は、その職務の担当者と適宜話し合い、双方の認識に齟齬がないかどうかを確認してください。
ステップ②職務記述書を作成する
職務内容の決定後は、職務記述書を作成します。一般的に、職務記述書は職務と職務要件で構成されています。職務要件とは、職務を遂行する上で必要なスキルや能力、経験、知識などのことです。
職務記述書は、人材を募集する際に提示するものであるため、募集要項と似ていますが、以下のように記載項目が異なります。
職務記述書と募集要項の記載項目の違い
| 職務記述書 | 募集要項 | |
|---|---|---|
| 記載項目 | 職務名 職務概要 職務内容 期待される目標とミッション 責任と権限の範囲 組織に関する事項(直属の上司や部下の人数など) 雇用形態 勤務時間 必要な知識やスキル 必要な学歴 資格など |
職務内容 勤務時間 就業場所 始業と終業時刻 休憩時間 休日 給与 加入保険 試用期間 企業名など |
上記の表で見てとれるように、職務記述書は転職希望者に期待する目標やミッション、職務の遂行に必要な知識などを詳細に記載します。こちらは雇用契約の締結時だけではなく、採用後の人事評価にも用いられるので、内容に誤りが生じないよう、複数人の確認を踏まえて作成することが大切です。
ステップ③制度を整える
メンバーシップ型雇用からジョブ型雇用に切り替える場合、あらゆる制度を改めて整備する必要があります。
まず、メンバーシップ雇用時に採用していた給与から、成果に見合った給与体系に変更します。加えて、インセンティブを設定するときは、複数の競合他社の相場を確認することが大切です。もし競合他社よりも低かった場合、転職希望者からの応募が集まらない恐れがあるためです。
また、ジョブ型雇用に切り替えても社員が着実にキャリアアップできるよう、明確な評価基準の設定も欠かせません。評価基準を決定する際は、メンバーシップ型雇用の社員と評価や待遇面で不公平が生じないように、複数人で協議した上で内容を定めてください。
ステップ④ジョブ型雇用の導入を社内に周知する
新たにジョブ型雇用を導入する際は、その旨を社内全体に必ず周知しなければなりません。ジョブ型雇用の導入は、社員一人ひとりに不公平が生じる可能性だけではなく、退職率が上がる原因にもなるためです。
すでに解説した通り、メンバーシップ型雇用は、職能資格制度によって給与体系や昇格を定めるのが一般的です。一方、ジョブ型雇用は職務等級制度を採用しており、職務によって給与が変動します。つまりジョブ型雇用の場合は、給与体系に年功序列制度が反映されなくなるので、不利益を被る社員が出てくる可能性もゼロではありません。
したがって、ジョブ型雇用を導入する意図や、雇用条件について全社員にていねいに説明し、制度を周知することが大切です。
ステップ⑤管理職から導入する
ジョブ型雇用は、組織の運営や社員の日々の職務に大きな影響を与えるため、先んじて役割や責任範囲が明確な管理職から導入する方法も一つの手です。
実際に、ジョブ型雇用を取り入れたいくつかの企業は、管理職から一般職へという順序で導入を進めています。管理職がジョブ型雇用の詳細を一足先に把握すれば、全社員に適用された場合の人事評価や部下のマネジメントなども滞りなく対応できるでしょう。
(参照:日本経済新聞『ジョブ型雇用は仕事に人を充てる ぬるま湯人事を排除』)
ステップ⑥職務記述書を定期的に見直す
職務内容は、自社の事業内容や部門の目標などによって変わることがあります。したがって、最初に取り決めた職務記述書の内容は1年に1度、もしくは半期に1度の頻度で定期的に見直しましょう。
職務記述書の変更は、その現場の変化に合わせて行うため、人事・総務ではなく、主に現場の社員が担当します。
同じ内容の職務記述書を何年も使い回すと、職務内容や求められるスキルが更新されないため、企業と社員の間で認識のズレが生じ、社員が不満を抱える原因となります。そのため、定期的に見直しを行い、変更があればその都度改善することが大切です。
ジョブ型雇用の企業事例
各企業は、ジョブ型雇用をどのように取り入れて運用しているのでしょうか。企業の取り組み事例や成果をご紹介します。
三菱ケミカル株式会社
三菱ケミカル株式会社では「主体的なキャリア形成」「透明性のある処遇・報酬」「多様性の促進と支援」を人事制度改革の3本柱に掲げ、ジョブ型雇用を導入しました。「社内公募制のルール化やキャリアチャレンジ制度の創設」「職務や貢献による処遇・報酬体系へのシフト」「定年の引き上げや福利厚生のカフェテリアプラン化」などを行い、相互に連動させながら運用しているそうです。
制度の変更については、解説動画を配信したりイントラネットに掲載したりしたほか、説明会をていねいに実施。社員が新たな仕事を希望したり、より高度な仕事にチャレンジしたりと、前向きな変化が生まれているようです。
(参照:『年功序列と決別し、ジョブ型雇用を導入した三菱ケミカル。その大改革がもたらした変化とは?』)
双日株式会社
「多様性を競争力に」をテーマにダイバーシティー経営に取り組んでいる双日株式会社では、2021年3月に設立した新子会社「双日プロフェッショナルシェア(SPS)」でジョブ型雇用を採用。対象は総合職の双日社員35~55歳で、本人の希望・同意が移籍の条件です。
週2日は双日以外での勤務が可能で、グループ会社での兼業のほか、副業、起業、介護、家業など、個々が自由に選択できます。「フルフレックス制が基本」「フルリモート勤務も可能」「定年は70歳」とし、それぞれのスキルを活かして長く働ける環境を整備しているそうです。
外部企業とのマッチングの仕組みをつくるなど、企業と人材のネットワークを広げることで、双日の競争率や企業価値を高めていくことを目指しています。
(参照:『週3日勤務で副業OK。ジョブ型雇用で「社員のやりたいこと」を支援する双日の、新たな成長戦略とは』)
富士通株式会社
富士通株式会社は2019年に「IT企業からデジタル変革(DX)企業への転換」を宣言し、全社を挙げて変革を行っています。
人事に関連するところでは、各事業部がそれぞれのビジョン実現に向けてフレキシブルに動けるよう、「事業部門起点のジョブ型人材マネジメント」に権限を移譲。社内外から人材を集め、適材適所が実現するよう工夫を重ねています。
社内の人材の流動化については「希望部署に期間限定で異動できる」「所属を変えずに他部署の仕事ができる」などの制度を設け、気軽かつ個々のニーズにリーチしやすい施策を実施。ポスティング制度を導入し、年間2,500人以上が自ら制度を活用し異動をしているそうです。
(参照:『「このままでは生き残れない」――。風雲児 時田社長リーダーシップのもと、富士通が選択したVUCA時代における「パーパス」と「社員の意志」』)
まとめ
日本でも導入する企業が増えているジョブ型雇用は、これまで主流であったメンバーシップ型雇用とは異なる特徴を持つ採用方法です。
「生産性の向上」や「ミスマッチの防止」などのメリットがある一方で、「採用の難易度が上がる」「帰属意識が生まれにくい」といったデメリットも懸念されます。
部分的な導入も視野に入れつつ、自社にマッチするかどうかを十分に検討した上で、導入するかどうかを判断しましょう。
(制作協力/株式会社eclore、編集/d’s JOURNAL編集部)
ジョブディスクリプション 記載見本・テンプレート【簡易版】
資料をダウンロード