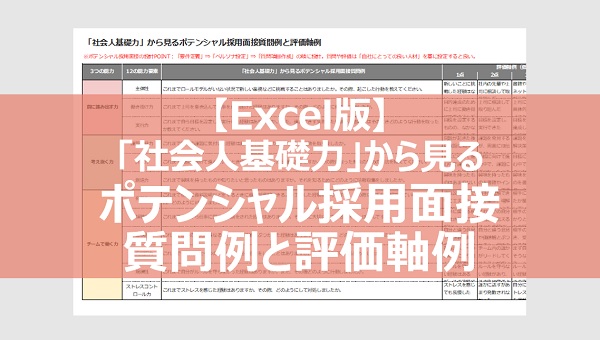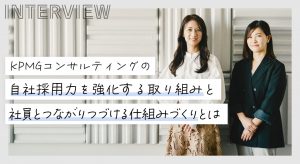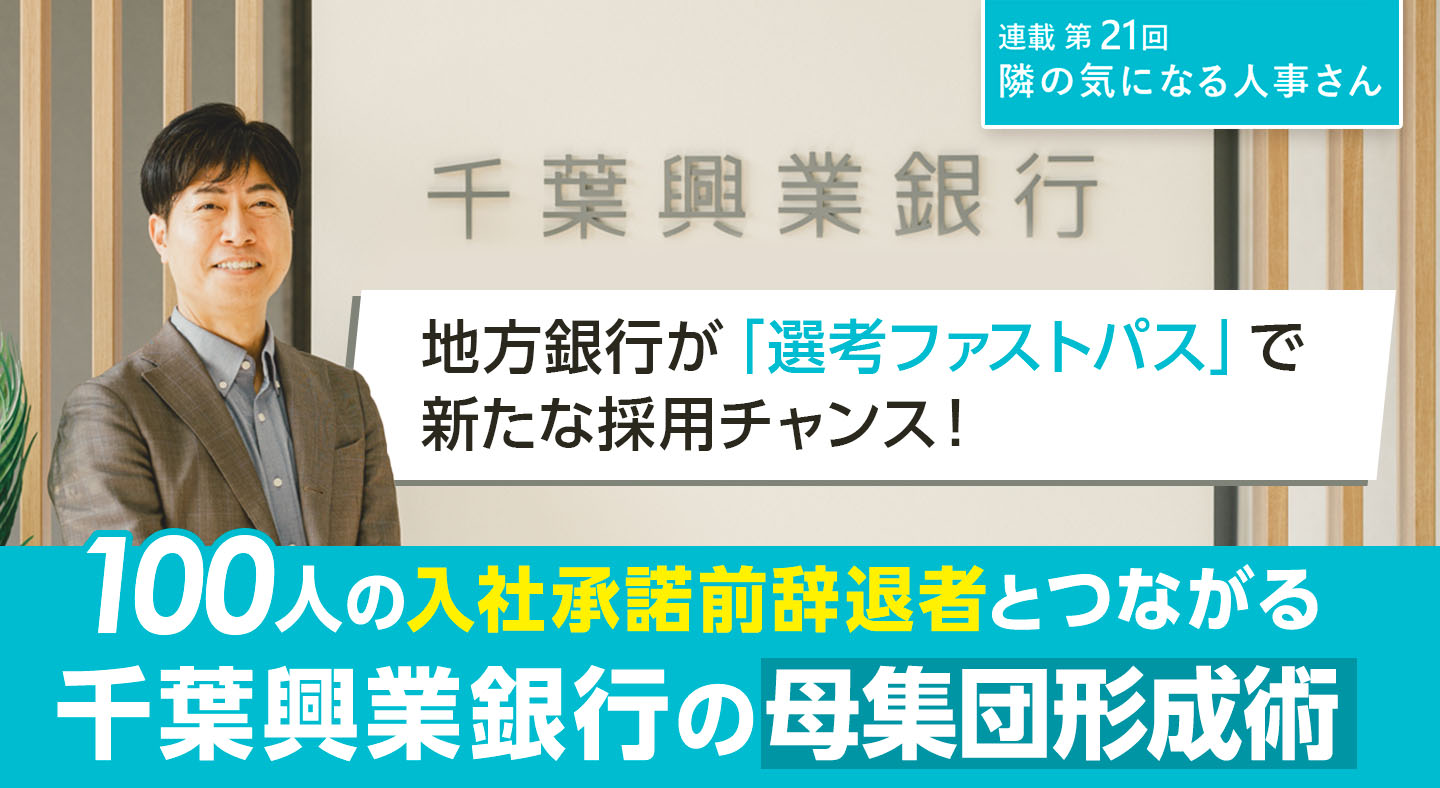「越境採用」で元高校球児やリケジョが入社。年間5,000人以上の母集団形成、約200人の採用を創出するオープンハウス・アーキテクト

オープンハウスグループの株式会社オープンハウス・アーキテクト(本社所在地:東京都中野区、代表取締役:長井 光夫)は、施工・建築などに特化した総合建設会社だ。首都圏を中心に、手ごろな価格の建築設計を提供。直近5年間で売上高を2倍以上に伸ばしている。
また採用に関しても採用難度が高いと言われている建築・建設業界で、母集団形成を年間で約5000人、採用は約200人という成功実績を持つ。
さらに建築士、建築施工管理技士などの資格を有する社員が、専門スキルを活かして活躍する一方で、業界未経験の人材も多数活躍しているという。それを可能にしているのが「越境採用」と呼ばれるポテンシャル採用だ。
人材不足が深刻化する建築・建設業界における、同社の母集団形成と採用戦略に迫った。

オープンハウス・アーキテクトのこれまでと現況
――まず、オープンハウス・アーキテクトのビジネスやこれまでの歩みについてお聞かせください。
岡村美雪氏(以下、岡村氏):オープンハウス・アーキテクトは、オープンハウスグループのなかで建築・設計を担う企業です。
中間業者を通さずに、資材を直接仕入れたり、スケールメリットを活かした交渉をすることで、高品質で手ごろな価格の家を提供することが 当社のビジネスモデルです。
――最近は、首都圏の土地価格の上昇について報じられていますが、ビジネスモデルに変化はありましたか。
岡村氏:確かに近年は都内、特に都心の土地価格が上昇しています。コロナ禍では、郊外の戸建てのニーズが高まっている時期もありましたが、最近は再び都心回帰の兆候が見られますので、郊外、都心、いずれのニーズにも応えられるようにしています。

建設専門職の採用に奏功した「越境採用」とは?
――採用活動の取り組みについてうかがいます。近年、転職市場では「異業種から異職種」への転職が増加傾向にあり、御社でも業界や経験の壁を越えた「越境採用」の取り組みをされています。
藪口 京介氏(以下、藪口氏):若年層の建築業界離れや高齢化が進み、建築業界は求人数に対して応募者が少ない状況です。応募者の数は、今後も減少傾向と推測しています。
建築業界の求人は、「業界経験者や建築を専攻した人が対象」「男性が多い業界」というイメージを抱いている人が多いと思います。しかし当社では、応募対象者の枠を広げるために、経験、出身業界、学生時代の専攻などあらゆるカテゴリを問わず応募することができる「越境採用」を実施しています。それを可能にするために、社内の仕組みや制度も整えてきました。
――「越境採用」における異業種からの応募者の傾向はありますか。
藪口氏:設計は経験者のみの採用ですが、施工管理職や営業職などは経験不問です。いわゆる専門職と言われる施工管理を未経験者が経験できる職場は多くないので、その点で採用の優位性があると思います。
当社で採用した方の経歴も多岐にわたります。例えば、元甲子園球児や大手銀行員、起業経験者など、さまざまな業界から新しいキャリアを求めて人が集まってくれています。また、いわゆる理系女子と言われる「リケジョ」からの応募も少なくはなく、採用に至るケースも増えています。
選考の基準としては、真面目で誠実であることや、これまでのキャリアにおいてどんな思いで取り組んできたかなどを、採用の判断としています。

未経験からの就職・転職の「越境採用」を可能にした戦略
――異業種の経験者や未経験者が活躍するための社内の仕組みは、どのように構築されたのでしょうか。
藪口氏:文系出身者や女性でも長期的なキャリアが築けるよう、施工業務プロセスの分業化を促進し、独自開発したDXシステムによって業務フローに合ったシステム構築をしてきました。
そうした取り組みのかいあって、現在は文系・理系出身、性別、年齢問わず、入社直後から早期に活躍できるという段階に来ています。ちなみに新卒採用の女性比率は45%と、男性比率の高い建築業界の中では極めて高い割合を達成しています。
――施工の仕事の分業化をされているとのことですが、どのように分業を進めていったのでしょうか。
藪口氏:施工管理の仕事は、大きく分類して「安全管理」「品質管理」「工程管理」「予算管理」の4つに分かれます。現場が全ての管理を担う会社もありますが、当社では分業化を進めてきました。
各工程の中で切り出せるところは切り出し、本社が統括して行う、というイメージで、例えば「予算管理」は本社の積算部門が、業者との契約は本社の渉外企画が担う、といった具合です。
業務を切り出した後は、職人や技術者の工程管理、現場の事故を防止する安全管理、耐震性基準を満たしているかといった品質管理など、現場でしか担えない業務に集中してもらうことになります。
一方で、DX化などにより紙の処理といったアナログ的な業務も極力減らし、施工管理にまつわる業務はさまざまな面で合理化を進めています。
――施工業務で分業以外に留意している点はありますか?
岡村氏:未経験者や他業種の経験者を採用する場合は、受け入れる側の教育に対する前向きな姿勢や社内研修の仕組みがあるかどうかも重要だと思います。
当社の場合は「背中を見て覚えろ」という雰囲気ではなく、「きちんと教える」ことを大切にしてきました。結果、未経験社員の活躍が可能となり、成功体験の積み重ねが現場の安心感につながっていると思います。

――「きちんと教える」ことを根付かせるために、教える側のレベルアップか、ルールや制度を整えるのか、どちらを重要視していますか。
藪口氏:新卒入社の社員に関しては「メンター制度」を整えて定期的なフォロー研修も行っていますが、越境採用の社員の教育に関してはルールで縛り過ぎず、各現場の臨機応変な対応で実施しています。
これは一朝一夕でできた制度や環境ではなく、長い時間をかけて経営層から現場へ、「社内で受け入れて教える雰囲気」を積極的に醸成してくれたたまものだと思います。
もちろん現在は、全てを現場に任せるということはなく、レポートラインを確保して、適宜ディカッションやメンバーとの面談などを実施。細かな点でも人事主導として行っている面があります。
母集団形成のための「情報発信」の手法とは?
――未経験者が仕事の具体的なイメージを持って応募に至るためには、何らかのフックが必要だと思います。オープンハウス・アーキテクトとして取り組んでいることはありますか。
藪口氏:当社の仕事、業界、業務に関する情報を正しく伝えていくための取り組みを行っています。
具体的な内容としては、直近の2年で採用サイトを充実させました。現在では、新卒採用の総合サイト、文系向けサイト、理系専門職サイト、キャリア採用、越境採用という5つのチャネルを用意しました。
さらに、オウンドメディア「Architect Now」を開設し、さまざまな切り口で情報発信をしています。求職者の方が会社の雰囲気や業務の具体的なイメージを持ってもらうことにつながっていると思います。
――オウンドメディアでは、どのようなコンセプトで情報を発信していますか。
藪口氏:社員のインタビューや対談など、内容はさまざまです。基本的なルールとして「正しい情報を伝える」「等身大の日常を伝える」というコンセプトを大事にして運営を行っていますね。
新卒採用、キャリア採用、いずれの対象者にとっても、現場のリアルな空気感が伝わりやすいサイトになっているのではないかと思います。

――メディアの反響はいかがでしょうか。
藪口氏:サイトを見て、これまで抱いていた建築業界に対する堅いイメージが変わったという声があったほか、記事の内容から当社の熱量や誠実さを感じ、求人への応募につながったというケースもあります。
中途採用の場合には、当社が積極的にいろんなことに取り組み、時代に合わせて変化している点に魅力を感じてもらえているようです。また、オフィスの景観や雰囲気、業務の見せ方などを工夫しているので、言い方は難しいのですが、「建設会社っぽくない」と感想をいただくことも多いですね。
――情報発信を積極的に行ってきた2年間の気づきや課題はありますか。
岡村氏:気づきとしては、求められるものは時々刻々と変わっているということです。網羅すべき情報やサイトの魅せ方は、数カ月単位で変えています。その時々で良い記事を作ることができても、半年後には「こうすればよかった」というところが出てきますね。
例えば、Webサイト制作の業界にもUI/UXデザインのはやり廃りがありますよね。それらをキャッチアップしてWebサイトを改善していくように、私たちも時代に応じて変化する世間のトレンドをキャッチアップし、情報発信の工夫をしています。また、内容だけでなく「見て」「触れて」「体験できる」ようなコンテンツ設計も心がけています。
――中途採用、新卒採用ともにオンラインを通じた採用が多いのでしょうか。
藪口氏:現在は、新卒採用はオンラインを通じた採用が多く、中途採用は転職エージェント経由が多くなっています。
――転職エージェントを通じたアプローチでは、応募者に対してどのような魅力を伝えていますか。
藪口氏:相手によって伝え方は異なりますが、グループの規模感、成長性、給与面、変化が多い点、評価制度の納得感などがメーンになってくるのではないかと思います。ほかにも「まず、会ってみる」という感じのカジュアルな面談の機会も設けています。
越境採用においては特に、事前のカジュアルなコミュニケーションも功を奏しているように思います。

採用市場における建設業界のイメージを変えていきたい
――積極的な情報発信を始めてから、応募者に何か変化はありましたか。
藪口氏:当社では現在、若くして出世・昇格するイメージを持って入社してきた社員が活躍していますが、応募動機は多様化していると感じます。新卒採用の学生については、建築のDXに携わりたい、こんな設計をしたいなど、具体的なビジョンや自己実現のイメージが付加されてきました。
――建築業界のイメージとしては「休みが取りづらい」「きつい」といったものがあると思いますが、オープンハウス・アーキテクトはいかがでしょうか。
岡村氏:年末年始休暇のほか、5月と8月のお盆期間には2週間弱ずつ長期休暇を取得することができます。分業制やDXを進めることで、1人当たりの生産性を試算しながら、休みを増やしてきた背景になります。
――最後に今後の採用・人材戦略の展望についてお聞かせください。
藪口氏:採用市場への多角的なアプローチをする必要があると考えています。
変化に対応し続け、キャリア採用、新卒採用、リファラル採用に加え、潜在層にアプローチするための取り組みをしていく所存です。また、女性の活躍推進をしている当社では、女性社員が長期的に活躍しやすい土壌を、さらに整えていく予定です。
岡村氏:お客さまに喜んでもらい、なおかつ会社の売上が伸び、社員も会社も「幸せ」になってもらいたいと考えています。そのためには昨今、「人的資本経営」と呼ばれている通り、社員(人材)の力が重要です。
「人は財産」という考えの下、今後も個々の社員を尊重し、より良い制度を整えていきたいと思います。

【取材後記】
昨今、建築業の人手不足が叫ばれているが、高齢化が進み、近い将来には人材不足がさらに深刻化するとの試算がある。建設業(採掘含む)の有効求人倍率は約6倍に届こうとしている中、母集団を業界経験者に絞ることのないオープンハウス・アーキテクトの「越境採用」と呼ばれる取り組みは、専門職を採用するための1つの事例として参考になるだろう。
企画・編集/鈴政武尊・d’s JOURNAL編集部、制作協力/シナト・ビジュアルクリエーション
【関連記事】
□ 「ウェルネス×DX」を成長戦略に、年間1万人応募、500人採用に成功するnobitel
□ 「失われた30年を5年で取り戻す」――。AKKODiSコンサルティングが描く人財戦略
□ NTTデータ、経験者採用を5年間で20人から500人超へ拡大
【関連資料】
□ 採用取り組み事例:株式会社NTTデータ 「情報発信はオウンドメディアで」
□ 採用取り組み事例:ヤフー株式会社 「仲間を集める」から「仲間をつくる」へ
□ 採用取り組み事例:株式会社いーふらん 年間200人採用成功