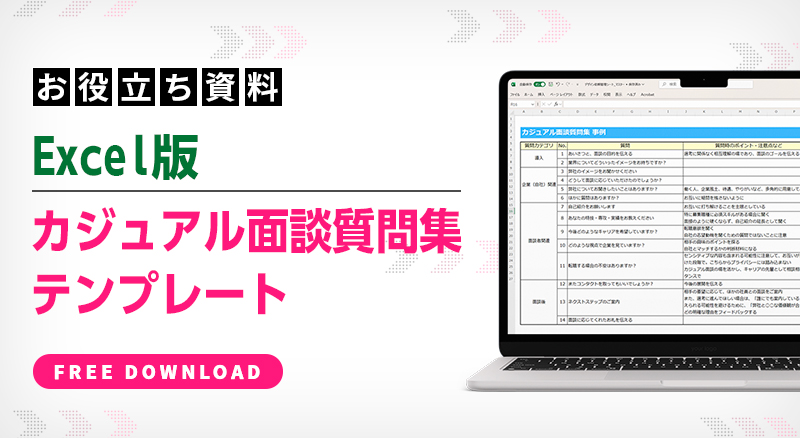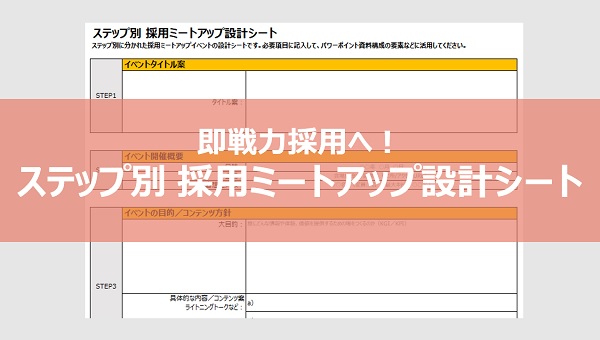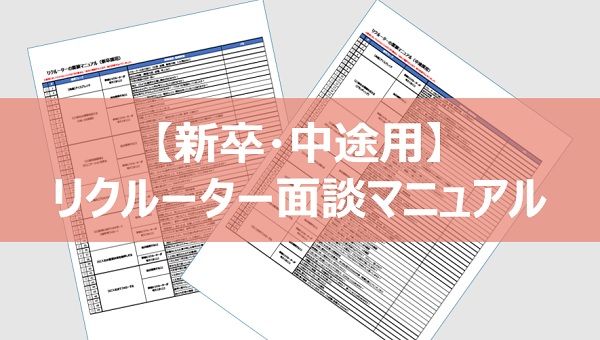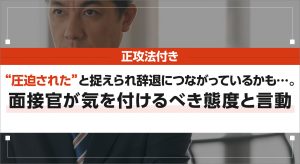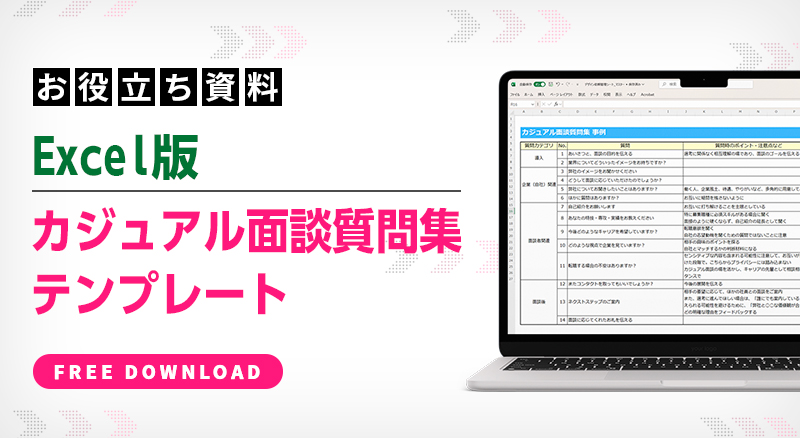“ゆる転職”層を惹きつけるには?中堅・中小企業が今こそ取り組むべき採用戦略
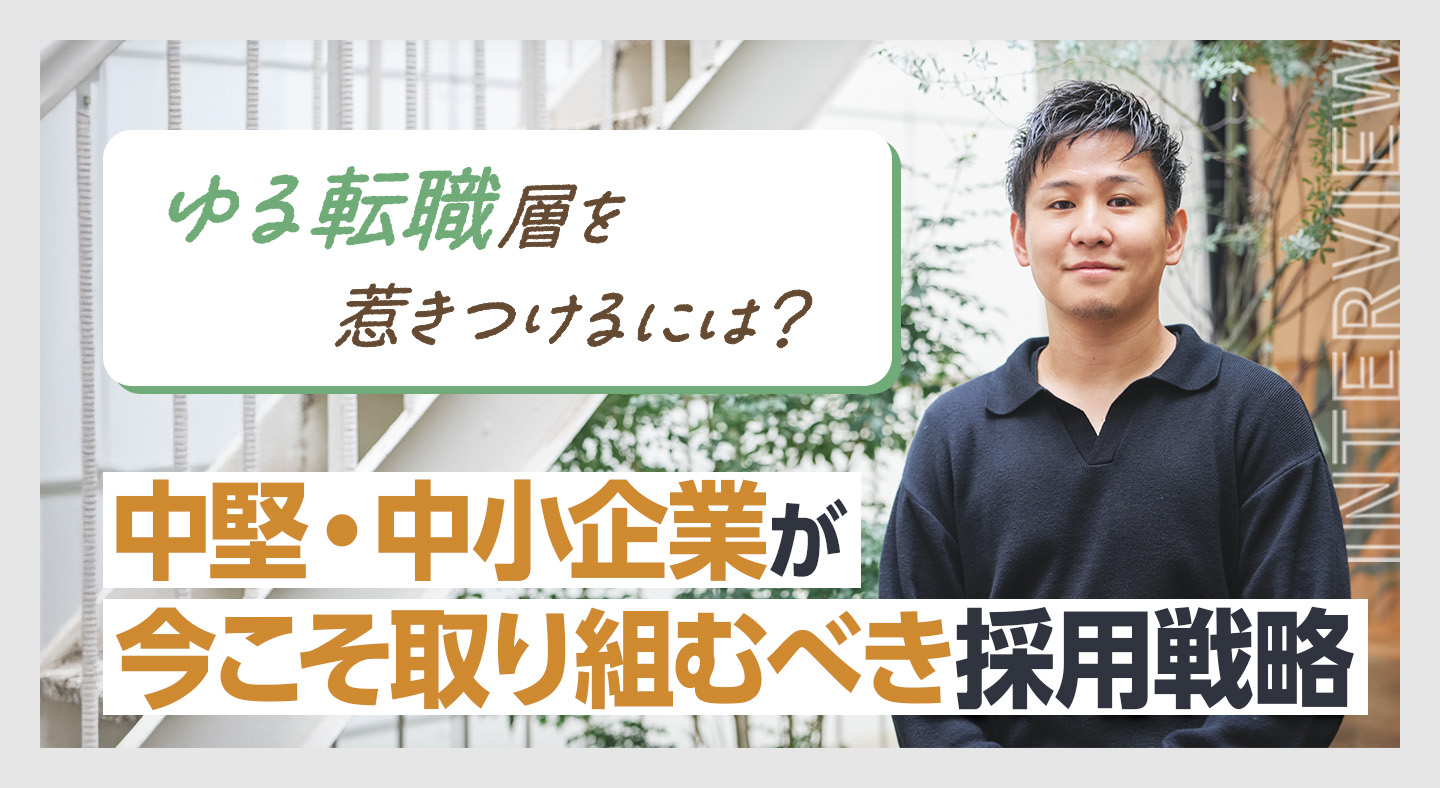
-
新社会人の間で「ファーストキャリア=通過点」という意識が定着。慎重に情報収集しながら転職を視野に入れる「ゆる転職」が一般化している
-
自社のことを知らない「ゆる転職層」とのコミュニケーションでは、広く一般的に興味を持ってもらえるテーマの「浅いコミュニケーション」が有効
-
中堅・中小企業こそ、現場とともに「浅いコミュニケーションのカジュアル面談やミートアップ」に取り組むことが有効な母集団形成策となる
入社して間もない新社会人が、4月のうちに転職サイトへ登録するケースが急増しています。「doda」の「新社会人の転職サイト登録動向」によると、2025年4月に登録した新社会人の数は2011年比で30倍を超え、過去最高水準になる見込みです。
こうした登録者の目的は、今すぐに転職を考えているというよりも、「自分の市場価値を知っておきたい」「将来の成長機会を逃したくない」といった情報収集が中心だと考えられます。待遇や職場環境を冷静に比較しながら、長期的な目線でキャリアを考える「ゆる転職層」が確実に増えているのです。
カジュアル面談プラットフォーム「Pitta(ピッタ)」を運営する中村拓哉氏は、ゆる転職層を「中堅・中小企業にとって貴重な採用対象」「適切にコンセプト設計を行い、カジュアル面談やミートアップを行うことが有効」だと指摘します。ゆる転職層に効くアプローチとは? 具体的な戦略を聞きました。
ゆる転職をしている人は、キャリア形成への本気度が高い
──入社間もない時期に転職サイトへ登録する新社会人が増えています。中村さんはこの状況をどう見ていますか。
中村氏:そもそも、新卒入社時点でのマインドセットが大きく変わってきたのではないかと思います。
現在では「ファーストキャリア」という言葉が一般的になりました。若手のほとんどはセカンドキャリアやサードキャリアがある前提で考えており、最初の会社に骨を埋めるつもりはないでしょう。
これは無理もないことだと思います。ひとつの会社でずっと食べていける保証はなく、個人は自分でキャリアをつくっていかなければならない時代になりましたから。
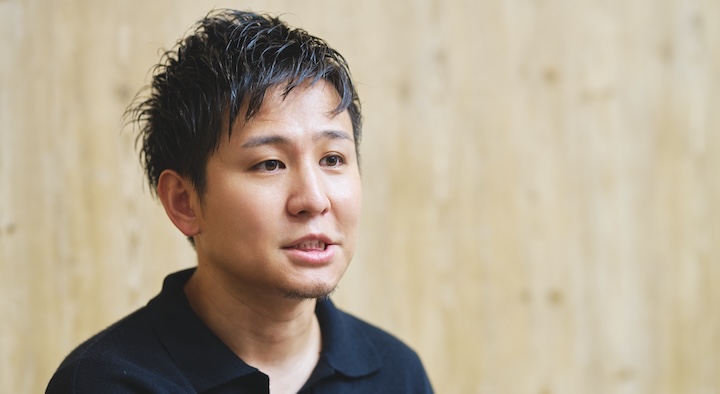
──待遇や職場環境を冷静に比較し、長期目線でゆるく転職活動を続ける、いわゆる「ゆる転職」の動きも増えてきました。
中村氏:Pittaのユーザーでも、カジュアル面談をしながらゆる転職をしている人は多いと感じます。
「ゆるい転職」という言葉だとあまり深く考えていないように聞こえるかもしれませんが、ユーザーと触れ合うと、むしろ逆の印象を受けるんですよね。みんな「転職でミスりたくない」と考え、慎重に活動している。すぐに転職するかどうかは別として、キャリア形成への本気度は高いと思いますよ。
──そうしたゆる転職中の人が、本格的な転職モードへと切り替わるタイミングは?
中村氏:考えられるのは「とんでもなく魅力的な企業に出会えたとき」でしょう。本気で転職するつもりはなかったのに、Pittaでカジュアル面談を受けた結果、その企業に一気に惹かれるというケースもまれにあります。しかし、実際にはそうしたケースは多くありません。
多くの場合は外発的要因がきっかけです。転職モードに切り替わった人の話を聞くと、現職の環境が大きく変わったり、人間関係に影響が生じたりしていることが多いのです。
その意味では、企業は転職希望者のモードが切り替わるタイミングを待つしかないのかもしれません。「どうすればうまくモードを移行させられるか」という発想は捨てるべきでしょう。
企業がやるべきなのは「想起度」を高めることだと思います。転職モードに入ったときに、自社を転職先の候補として思い出してもらえる確率を高めるのです。想起してもらったときにすぐ接点を持てるよう、アクセスできる情報をたくさん用意しておくことも重要です。
うまい企業は、プレスリリース配信タイミングなどで「うちでイベントをやるんですけど来ませんか?」といった案内を随時出し、定期的なコミュニケーションの機会を設けていますね。
「自社を知らない人」との接点では、広く一般的に興味を持ってもらえるテーマを設計
──ゆる転職層へのアプローチとして、具体的にはどんな手法が有効でしょうか。
中村氏:定期的なコミュニケーションの機会を通じて自社を理解してもらうには、カジュアル面談やミートアップが有効だと思います。
1対1のカジュアル面談に気後れしてしまう人でも、ミートアップの機会があればより気楽に参加できるかもしれません。企業としては、多くの転職希望者と同時に接点を持てる魅力があります。
ただし、適切なコンテンツを用意できなければカジュアル面談やミートアップを機能させることはできません。

──適切なコンテンツとは?
中村氏:「深いコミュニケーション」と「浅いコミュニケーション」に分けて考えることが大切です。
「深いコミュニケーション」は、すでに自社を知っていたり、業界について情報収集していたりする人向けに、仕事内容やはたらく環境、チームの状況などを説明するもの。これは一般的にカジュアル面談で話す内容としてイメージしている人事・採用担当者が多いかもしれません。
しかし、母集団の裾野を広げていかなければならない段階では、ゆる転職層は基本的に自社のことを知りません。そこでまずは、広く一般的に興味を持ってもらえるテーマを設定する必要があります。こうした「浅いコミュニケーション」ができている企業は少ないのではないでしょうか。
【関連記事】
・カジュアル面談で聞くべき質問例8種類!目的や進め方も解説
・【成功体験談付】エンジニア採用にも有効!「カジュアル面談」活用術
・ミートアップとは?採用における役割や実施ステップを解説
・【2社事例・設計シート付】新採用メソッド「ミートアップ」活用術
現場メンバーへは、採用活動への協力を「個人のメリット」として伝える
──転職希望者の興味・関心をとらえ、浅いコミュニケーションのテーマを設計するコツを知りたいです。
中村氏:中堅・中小企業やベンチャーの多くは、コーポレートサイトや求人票で自社の情報の一部しか発信していません。でも求人内容や業界、事業、組織の魅力を深掘りしていけば、自社だからこそシェアできるノウハウやTipsが見えてきます。たとえばAI展望などのノウハウを交換したり、同職種の仲間同士で雑談できる場を設けたりといった具合です。
ここで重要なのは、人事だけでなく現場にも意見を出してもらうことです。私たちがカジュアル面談やミートアップのテーマ設計で関わる際は、人事・採用担当者だけでなく現場関係者にも集まってもらい、スプレッドシートを用意して一斉に意見を書き込んでもらっています。現場が持っている知見や経験を活かせば、「自社がリアルに語れるテーマ」が見えてくるんです。
実際のカジュアル面談やミートアップにも、テーマを一番語れる現場の人に参加してもらったほうがいいですね。特にミートアップの場合は、上司と部下の関係性など、自社の「素の部分」も見てもらえますから。

──ただ、「現場の協力を得るのは難しい」と感じている人事・採用担当者も多そうです。
中村氏:現場の人にとっては、採用に関わり、一緒にはたらく人を自分たちで選べるほうがメリットがあるはずです。「人事が勝手に選んだ人ではなく、自分たちで選んだ人とはたらきませんか?」と伝えることから始めてみてはどうでしょうか。
うまくやっている企業では、「採用活動で社外へ露出している人=自社のハイパフォーマー」という図式にしているケースもあります。「◯◯さん、採用イベントに登壇して顔を売っておきませんか?」と、採用活動への協力を個人のメリットとして伝えることも有効です。
【関連記事】
・リクルーター面談とは?目的やメリット・実施の流れを解説【質問例付き】
・【マンガから学ぶ】ぼっち人事、兼任人事も!「リクルーター制度」導入で優秀な人材を採用しよう
「他社の話をあまり聞いていない」ゆる転職層にチャンスあり
──カジュアル面談やミートアップに参加してもらったものの、その後の選考プロセスに進まないケースも多いと思います。次のステップへ進んでもらうため、企業が留意すべきポイントを教えてください。
中村氏:一度のカジュアル面談やミートアップで全てを決めてもらおうとしないことが大切です。私が見ていて「もったいないな」と思うのは、最初のカジュアル面談を「半分は転職希望者の見極め、半分は自社の訴求」にしている企業。むしろ最初の接点を自社の訴求に全振りしている企業のほうが採用に成功しているのではないでしょうか。
今は転職希望者がウインドウショッピングのように企業を見比べている時代です。企業側に少しでも見極めようとする姿勢があると、転職希望者は一気に冷めてしまいます。
また、カジュアル面談やミートアップの場で「次の選考を受けてみませんか?」とアプローチすることも大切です。意外とこれを怠っている企業が多いように感じるのです。
ゆる転職の場合、転職希望者から次回へのアクションを起こしてくれる可能性は低いです。転職希望者の求めている情報を伝えた上で「当社に興味を持ってもらえましたか?」と聞き、興味を持ってもらえたなら、次の設定を行うべきでしょう。

──カジュアル面談やミートアップ以外に有効な施策はありますか?
中村氏:動画や音声のコンテンツも有効だと思います。動画や音声のコンテンツは何かをしながら情報も得ることができるカジュアルなコンテンツなので、ゆる転職層とも親和性が高いです。自社の情報だけを発信し続けるコンテンツは興味を持ってもらいにくいので、たとえば外部の方を呼んで役立つ情報を話してもらうなど、先ほどもお話しした「浅いコミュニケーション」を意識したコンテンツ設計が重要です。
──中村さんは、ゆる転職層へアプローチするメリットをどのように考えていますか?
中村氏:企業によっては、ゆる転職層へのアプローチのほうが採用効率が高い場合もあるでしょう。
採用市場の過熱によって、積極的に転職活動をしている顕在層には、短期間に1人あたり数百通のスカウトが届くことも珍しくありません。一方、潜在層であるゆる転職の人には、直接的なスカウトは少ないと考えられます。
つまり、ゆる転職層は大手を含めて「他社の話をまだあまり聞いていない」と言えるのです。大手と比べて不利になりがちな中堅・中小企業こそ、ゆる転職層へのアプローチに力を入れるべきではないでしょうか。
【関連記事・資料】
・採用広報とは?7つの手法と成功させるためのポイントを解説
・定着率90%以上の優良企業なのに応募が来ない!?認知拡大に悩むBtoB企業の動画広告活用術
【取材後記】
人生のかかった転職活動で、人はそう簡単に“ナーチャリング”されません──。取材中の、そんな中村さんの言葉が印象に残りました。昨今では「いかに転職希望者の入社意向を高めるか」に腐心している企業も多いと思いますが、ゆる転職層のように長期的な視点で情報収集している人に対して、そのアプローチはむしろ逆効果なのかもしれません。カジュアル面談やミートアップを通じて、ゆるやかでも確かな接点を保ち、「思い出してもらえる企業」であり続けることが、次の採用成功につながると感じました。
企画・編集/海野奈央(d’s JOURNAL編集部)、岩田悠里(プレスラボ)、取材・文/多田慎介、撮影/塩川雄也
カジュアル面談質問集テンプレート【Excel版】
資料をダウンロード