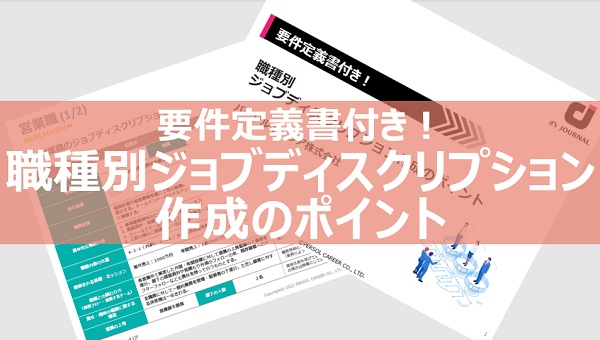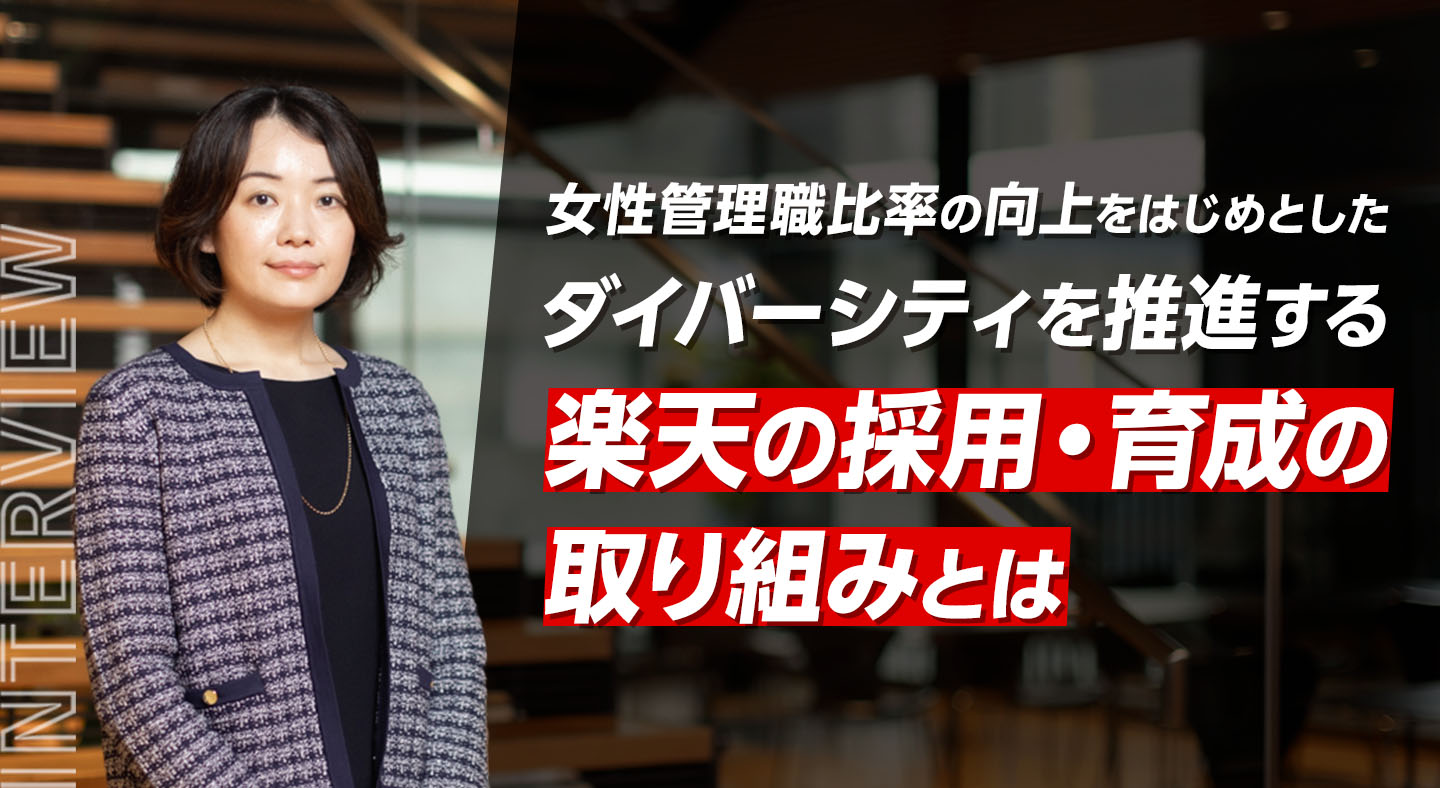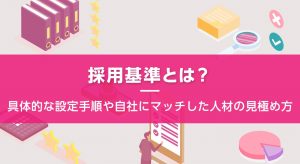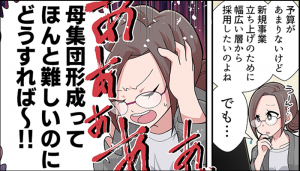ヒントは「戦隊ヒーロー」にある!?ニーズが高まるCxO採用を成功させるためのポイントを解説【エグゼクティブ人材採用ノウハウ :後編】

-
M&Aや事業承継、女性役員確保…。大手企業でも中小企業でもCxO採用ニーズが高まり、特定の個人に注目が集中している
-
どこもほしがる「大谷翔平のような人材」を探すのではなく、複数の人材でチームを組む「戦隊ヒーロー採用」を目指す企業も
-
良い候補者が見つかったのに「社内で迷走して選考が止まる」企業も。重要なのはCxO招聘に向けた方針を整理し、社内の合意形成を図るプロセス
新規事業推進や組織再編に取り組む企業が増える中、CxO(経営幹部)の採用・招聘ニーズが高まり続けています。ただ、その採用難度は非常に高いのが現実。パーソルキャリア エグゼクティブエージェントの第一線で数多くのCxO採用を支援する澤本氏は、「最適なプロ経営人材は引く手あまた」「本当に自社が必要とする人材を定義するべき」と指摘します。
CxO採用を成功させるためにはどのような準備が必要なのでしょうか。現状のCxO採用を巡る市場観や、企業に求められる体制づくりについて聞きました。
CxO採用では特定の個人に注目が集中している
——CxO(経営幹部)の採用ニーズについて、現在の市場の動きを教えてください。
澤本氏:ニーズは高まり続けていると感じます。
背景の一つには、PE(プライベート・エクイティ)ファンドなどからの案件が増加していることが挙げられます。海外企業がM&Aなどの財政政策を練る中で、円安の日本はターゲットになりやすく、投資先の経営幹部人材を求めるファンドのニーズが拡大しているのです。国内の動きだけを見ても、事業承継を課題とする中小企業のニーズが高まっていますし、スタートアップには常に採用ニーズがあります。
また、女性役員の招聘に動く企業が増えていることも最近の特徴でしょう。国は上場企業に向けて、「2030年までに女性役員比率30%」を達成するように求めています。そのため、大手企業を中心に女性役員候補を外部から招聘しようとする動きが盛んになっているのです。

——企業としては、内部昇格でCxO人材を育成することがベターであるようにも思います。
澤本氏:もちろん、どの企業も内部昇格に力を入れていると思います。ただ最近では「社内のメンバーを引き上げようとして白羽の矢を立てても、なかなか本人が同意してくれない」という悩みもよく聞きますね。特に女性役員の育成については、当の女性側に、30%という目標達成だけを目指して数合わせのような昇格を行おうとする動きを嫌う人も多いです。
——そうした背景もあってCxOの採用市場が高まっているのですね。競合が多い分、候補者探しは非常に難度が高いのでは?
澤本氏:はい。ここ1〜2年は特に、対象となる候補者を見つけることが困難になってきています。どんな企業も求めるようなプロ経営人材は国内中を見渡しても本当に少なく、特定の個人に注目が集中しているのが現状です。
メンバー層の採用でも最適な転職希望者と会えない難しさはあると思いますが、CxO人材はさらに輪を掛けて難しいと言えるでしょう。
1人ではなくチームで課題解決する「戦隊ヒーロー採用」のすすめ
——こうした状況の中でCxO人材を招聘するためには、どんな準備をするべきでしょうか。
澤本氏:前述の通り、トップレベルの最適なプロ経営人材はどこもほしがっています。野球の世界に例えるなら、「大谷翔平選手の獲得に向けて多数のチームが群がっている」ような状態なのです。
ここで立ち止まって考えたいのは、自社の課題や困りごとを解決するために「大谷翔平クラスの人材が本当に必要なのか」ということ。どこからも求められるようなトップレベル人材ではなくても、これまでの経験やスキルを活かし、自社に貢献してくれる人材がいるかもしれませんよね。
——たしかに、これまで経営の第一線で活躍してきた実績がない人でも、自社の課題や困りごとを解決してくれる可能性はありますよね。
澤本氏:はい。たとえば長年経理畑を歩み、管理職を務めてきた人には、そのキャリアの中で経営危機を救う立役者となった経験があるかもしれません。職務経歴書上は派手な経歴に見えなくても、企業の経営を支える能力を持つ人材はたくさんいるのです。
また、「1人のスーパーヒーロー」ではなく、「たくさんのヒーロー」を求めることも有効ではないでしょうか。

私は支援先企業との会話でよく「戦隊ヒーロー採用」を提唱しています。戦隊ヒーローの定番といえば、それぞれに異なる能力や強みを持った5人の仲間が敵に立ち向かうストーリーですよね。企業のCxO採用でも、同じようにチームを組む発想が必要だと考えています。
私たちが企業と対話し、本当に必要な要件を洗い出していくと、「これらの課題に1人で対応するのは難しいのでは」と感じることも少なくありません。あくまでも課題解決ありきで、本当に必要な経験やスキルは何なのか。それを洗い出していくことが大切です。
解決策としては、経験豊富な人材を複数名迎え入れ、経営課題を解決するチームをつくる方法があるかもしれません。
たとえば商社出身の方などは、新たなビジネスの商流をつくることに長けています。経験豊富なシニアの方が定年後の活躍の場を求め、後継者問題を抱える企業の中継ぎ的な形で登板することもあります。
こうした方向性は、自社だけで考えていてもなかなか見えてこないかもしれません。自社には本当にスーパー経営人材が必要なのか?そんな悩みをさらけ出して壁打ちの会話ができる「かかりつけエージェント」と関係を築いておくことをおすすめしたいですね。
「迷走して選考が止まる」もったいない状況を回避するために
——CxO採用に向けて、社内の環境整備や体制づくりで留意すべきことには何がありますか?
澤本氏:「外部からCxO候補を迎え入れる」と意思決定するまでの間に、内部昇格なども含めて社内ではさまざまな可能性を議論してきているはずです。そうした複雑な過程があればあるほど、「結局のところ、誰を招聘すればいいのかわからない」といった状況に陥ってしまうことがあります。
特に、過去にCxO採用に失敗した経験がある企業だと、慎重になりすぎて選考中に迷走し始めることもあります。せっかく良い候補者が見つかり、アプローチするところまで進んだのに、社内で迷走して選考が止まってしまうわけです。

——なぜそのような状況になってしまうのでしょうか。
澤本氏:招聘するための議論を進める中で、社長の一存だけでは決まらず、いろいろな人の意見が入ってくることが要因です。「本当にこの人でいいのか」「他の候補者と比較しないとわからないのではないか」という迷いが生じてしまい、選考が先に進まなくなってしまうのです。
CxO採用の経験が乏しい企業では、候補者が自社のカルチャーにフィットするか不安になったり、本当に課題を解決してくれるのかを疑問視したりして、あえてNG理由を探してしまうこともあります。
うまくいっている企業の場合は、招聘に向けた方針が社内で合意形成されています。そのため選考で迷うことがなく、スピーディーに候補者を口説くことができるわけです。
自社は何のためにCxO人材を外部から迎え入れるのか。本当に必要な人材はどんな人なのか。どのようなスタンスで選考に臨み、誰がどんな役割を果たして候補者を口説いていくのか。私たちエージェントはこうした一連の戦略を整理し、社内の合意形成を図るプロセスを重視しています。自社内だけで環境を整備するのが難しい場合は、これらのプロセスも含めて人材紹介サービスを頼っていただけたらと思います。
取材後記
トップレベルのプロ経営人材を招聘するのは、大谷翔平選手の獲得を目指すようなもの——。取材の中で澤本さんが話していた例えを聞いて、CxO採用の難しさを認識し、現実的な方策に目を向けるようになる経営者も多いそうです。「本当に必要な経験・スキルは何なのか」を整理し、要件定義や社内合意形成を進めていくプロセスには、メンバー層の採用で蓄積した知見も活きるはず。非常に難度の高いCxO採用だからこそ、現代的な人事の知見が求められるのだと感じました。
企画・編集/森田大樹(d’s JOURNAL編集部)、野村英之(プレスラボ)、取材・文/多田慎介、撮影/塩川雄也
【関連記事】
■ 女性管理職比率の向上をはじめとした、ダイバーシティを推進する楽天の採用・育成の取り組みとは
■ 「人柄」を大切にするカクヤスグループの採用戦略
■ 若手のリクルーターや人材紹介サービスと進める、ラクスのエグゼクティブ人材採用・招聘戦略
■ エグゼクティブ人材採用・招聘におけるkubell(旧Chatwork)の工夫とは
■ エグゼクティブサーチを活用した日鉄エンジニアリングの取り組みとは?
■ エグゼクティブ人材を迎え入れたタムラ製作所。その具体的な取り組みと秘訣とは?
■ 経営・人事がしなやかに連携する、コクヨの「エグゼクティブ人材招聘」ノウハウ
■ 経営層・CxO・事業部長などのエグゼクティブ人材を登用・採用する際に大切にすべきこと
■ エグゼクティブ人材招聘の「要件定義」「母集団形成」はどう考えればよいのか?
■ エグゼクティブ人材の「選考・オファー」において成否を分けるポイントとは
【エグゼクティブ人材】Executive Agent
資料をダウンロード