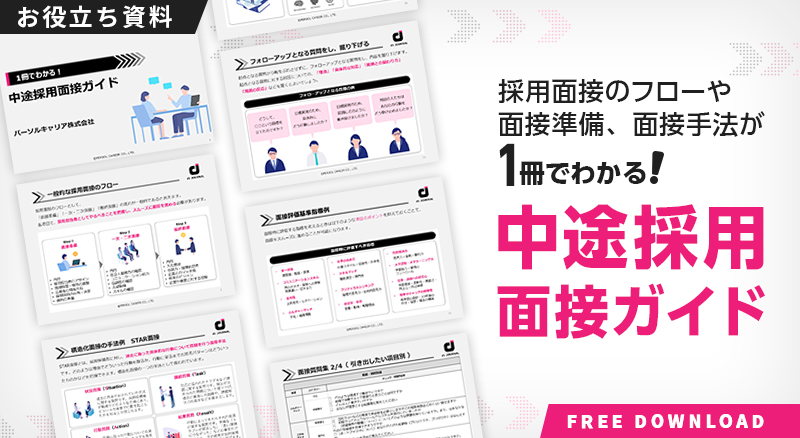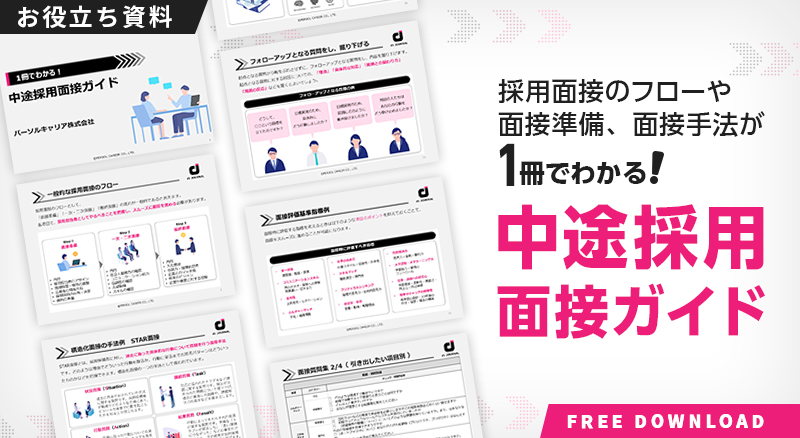【2025年版】採用手法16選を徹底比較|メリット・デメリット・最新の注目トレンド


d’s JOURNAL編集部
採用手法が多様化する現在、各手法の特徴や最新のトレンドを把握した上で、自社の採用課題に合った手法を選ぶことが大切です。
採用コストや母集団の質に課題を感じている場合、従来の採用手法を見直すことから始めましょう。
この記事では、代表的な16種類の採用手法について、それぞれの特徴や選び方のコツ、最新のトレンドなどをご紹介します。
中途採用における面接の手法やポイントをまとめた「面接ガイド」を、下記から無料でダウンロードいただけます。採用手法とあわせて、ぜひご活用ください。
採用手法の比較一覧
自社に合った採用手法を見つけられるかどうかが、採用活動の成否を左右することも少なくありません。よって採用手法を選択する際は、事前の入念な比較・検討が重要となります。その際に、特に重視したいポイントが以下の5つの項目です。
採用手法を比較する際の5つの項目
●難易度:必要な知識やノウハウ、工数などに基づいた実施に際しての難易度
●コスト:実行時に生じる費用
●工数:人事・採用担当者が費やすことになる対応工数
●緊急度:人材をどれだけ早く採用できるかの指標
●対象:採用の対象(中途か新卒か)
そして、これら5つのポイントに基づいて、代表的な採用手法16種類を比較したものが以下の一覧表となります。
| 採用手法 | 難易度 | コスト | 工数 | 緊急度 | 対象 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人材紹介サービス | 中 | 高 | 低~中 | 高 | 中途・新卒 | ●採用要件に合った人材を人材紹介会社に紹介してもらう ●採用業務の多くを代行してもらえるため、自社の工数はそれほどかからない ●成功報酬型のため成果が出るまで費用がかからない ●ほかの採用手法と比べて費用が高くなる傾向がある |
| 転職サイト | 低~中 | 低~中 | 中~高 | 中~高 | 中途 | ●求人広告を掲載し転職希望者からの応募を待つ ●転職希望者への対応は自社で行うため、工数はある程度かかる ●自社の求人を幅広い層に周知できる ●採用に至らなくとも費用が発生する可能性がある |
| ダイレクト・ソーシング | 高 | 低 | 高 | 中~高 | 中途・新卒 | ●人材データベースなどを活用して、企業が転職希望者へ直接アプローチする ●スカウトメールの文面作成などで工数が生じる ●費用は、前課金型や、成功報酬型などプランを選べる場合がある ●採用活動のノウハウがなくては成果を出せない |
| ソーシャルリクルーティング | 中~高 | 低 | 高 | 低 | 中途・新卒 | ●SNSを通じて自社の情報発信や転職希望者との交流を図る ●定期的な更新が必要となるため、一定の工数が生じる ●費用を抑えながらさまざまな人材層にアプローチできる ●投稿する内容次第で情報漏えいや炎上などの事態に発展する恐れがある |
| 合同説明会(転職フェア・イベント) | 高 | 中~高 | 高 | 低 | 中途 | ●転職希望者が多く集まるイベントに出展し、自社の理念や事業内容を対面で発信する ●配布資料やブースの準備などで、人事・採用担当者の負担が増える可能性がある ●競合他社に先んじて人材にアプローチできる ●イベントに出展しても必ず来場者の興味を引けるわけではない |
| オンライン転職フェア・イベント | 低~中 | 低 | 低~中 | 低 | 中途 | ●企業に応募する前の人材とオンラインで交流する ●ブースや配布資料などの事前準備が必要なくなるため、業務負担は少ない ●費用や工数を抑えつつ、求人に応募する前の転職希望者と交流できる ●実地イベントほど自社の温度感が伝わらない可能性がある |
| アルムナイ採用 | 中 | 低 | 中~高 | 中 | 中途 | ●自社ではたらいていた人材を再採用する ●関係維持のための定期的なコミュニケーションや待遇調整などで一定の工数がかかる ●自社に精通している人材を採用できる ●退職時の関係によっては再採用に応じてもらえない |
| リファラル採用 | 中~高 | 低 | 中~高 | 低 | 中途 | ●社員の友人・知人を人材として紹介してもらう ●制度の整備や、不採用だった場合には推薦者に対するフォローなども必要となるため、一定の工数がかかる ●自社に合った人材を効率良く採用できる ●推薦者の人材に対する評価が主観的で、活躍が見込めるかどうか定かではない場合もある |
| タレントプール | 中~高 | 低 | 中~高 | 低 | 中途 | ●活躍が見込める人材の情報を自社内のデータベースに蓄積する ●データベースの作成や管理で一定の工数が必要となる ●採用費用を抑えつつ、自社に合った人材へ効率良くアプローチできるようになる ●中長期的な運用が必要となるため、すぐには成果が出ない |
| ミートアップ | 高 | 低 | 中~高 | 低 | 中途 | ●交流会や勉強会を開催してそこで自社のアピールを行う ●事前準備や当日の対応のための工数が必要となる ●自社の魅力をより具体的に伝えられる ●人事・採用担当者の業務負担は増加する |
| 自社ホームページ | 中~高 | 低 | 高 | 低 | 中途・新卒 | ●自社のホームページを活用して転職希望者に情報を発信する ●ホームページの運用保守やSEO対策などが欠かせないため、一定の工数を要する ●自社の魅力を自由に発信できる ●人事・採用担当者の業務負担が増加する可能性がある |
| インターンシップ | 中~高 | 低 | 高 | 低 | 新卒 | ●就職前の学生を受け入れて実際の業務を体験してもらう ●企画や運営、学生のサポートなどで一定の工数が必要となる ●将来の活躍が見込める学生に早期からアプローチできる ●成果が出るまでにそれ相応の期間を要する |
| カジュアル面談 | 中~高 | 低 | 高 | 低 | 中途・新卒 | ●企業と転職希望者の相互理解を目的に行われる面談で、合否に影響しない ●通常の選考とは別に実施するため、人事・採用担当者の業務負担は増加する ●採用のミスマッチ防止や、転職希望者への動機付けがかなう ●通常の面接とは違った進め方を意識しなくてはならない |
| 人材派遣 | 低~中 | 高 | 低~中 | 高 | 中途・新卒 | ●要件に合った人材を人材派遣会社に派遣してもらう ●採用選考や教育などが必要ないため、人事・採用担当者にかかる負担は少ない ●人事・採用担当者の工数を抑えつつも、スピーディーに人材を採用できる ●派遣される人材を選べない |
| RPO(採用代行) | 低~中 | 高 | 低~中 | 低 | 中途・新卒 | ●外部の業者に採用業務の代行を依頼する ●人事・採用担当者の業務負担を大きく減らせる見込みがある ●採用活動の品質を高められる ●費用が高額になる傾向にある |
| ヘッドハンティング | 高 | 高 | 中~高 | 低 | 中途 | ●外部で活躍している人材に直接アプローチする ●人材像の明確化や認識合わせで一定の工数が必要となる ●ハイクラス人材へ効果的にアプローチできる ●費用が高額かつ、採用活動が長期化する可能性がある |
採用手法の比較を行う際は、この表を参照しながら自社の状況に合っているかどうかを判断しましょう。
採用手法16選の特徴やメリット・デメリット
ここからは、16の各採用手法の特徴をさらに深掘りしていきます。
●人材紹介サービス
●転職サイト
●ダイレクト・ソーシング
●ソーシャルリクルーティング
●合同説明会(転職フェア・イベント)
●オンライン転職フェア・イベント
●アルムナイ採用
●リファラル採用
●タレントプール
●ミートアップ
●自社ホームページ
●インターンシップ
●カジュアル面談
●人材派遣
●RPO(採用代行)
●ヘッドハンティング
人材紹介サービス
| 特徴 | ●採用要件に合った人材を人材紹介会社に紹介してもらう ●求人票の作成や転職希望者との日程調整などの採用業務の一部を代行してもらえる |
|---|---|
| 難易度 | 選考基準を自社内で整備する必要があるものの、それ以外の採用業務は人材紹介会社に任せられるため、難易度はそれほど高くない |
| コスト | ほかの採用手法と比較して高い傾向がある |
| 工数 | 採用業務の多くを任せられるため、人事・採用担当者の工数はあまりかからない |
| 期間 | 要件の提示から人材の紹介、そして採用に至るまでで数週間~数カ月を要する |
| 対象 | 中途・新卒 |
| メリット | ●成功報酬型のため成果が出るまで費用がかからない ●人事・採用担当者の工数を抑えられる |
| デメリット | ●ほかの採用手法と比べて費用が高くなる傾向がある |
| 活用例 | ●専門領域などのハイクラス人材の即戦力となる人材を採用したい場合 ●急な欠員に対応したい場合 |
人材紹介サービスでは、人材紹介会社が企業からの依頼を受けて、要件に合致する人材を紹介します。自社の人事・採用担当者の工数は抑えつつ、活躍が見込める人材を効率良く探せる点が強みです。
(参考:『人材紹介サービスとは?人材派遣との違いや手数料をわかりやすく解説』)
転職サイト
| 特徴 | ●求人広告を掲載し、転職希望者からの応募を待つ ●さまざまな業種・職種を取り扱う「総合型」と、特定の業種・職種や地域にフォーカスした「特化型」の2種類が存在する |
|---|---|
| 難易度 | 特殊な対応は必要ないため難易度はそれほど高くない |
| コスト | 一度の広告掲載で複数人を採用するなどして費用を抑えられる |
| 工数 | 転職希望者への対応が発生するため一定必要となる |
| 期間 | 求人の掲載から採用に至るまでで数カ月程度必要となる |
| 対象 | 中途 |
| メリット | ●自社の求人を幅広い層に周知できる ●複数人採用しても費用が変わらないため、費用対効果を高められる |
| デメリット | ●採用に至らなくとも費用が発生する前課金型が多い傾向にある ●転職希望者への対応で一定の工数が生じる |
| 活用例 | ●費用を抑えつつ大規模な母集団を形成したい場合 ●求人情報を多くの転職希望者に周知したい場合 |
転職サイトは、一般的に広く使われている採用手法の一つです。
人材を募集している企業が求人広告を掲載し、転職希望者からの応募を待つ形で採用活動を行います。掲載された求人広告はインターネットを通じて誰でも閲覧可能であるため、非常に幅広い層へ自社の求人を周知できます。
ダイレクト・ソーシング
| 特徴 | 人材データベースなどを活用して、企業が転職希望者へ直接アプローチする |
|---|---|
| 難易度 | 採用業務のほとんどを自社で行う上にノウハウも必要となるため、難易度は高い |
| コスト | 利用料がかかるものの、効率良く活用すれば1人当たりの採用費用を抑えられる |
| 工数 | 転職希望者とのやり取りや書類選考、スカウトメールの文面作成など、人事・採用担当者の対応工数は多い |
| 期間 | アプローチから選考までがスムーズに進めば迅速に人材を採用できるが、数カ月かかる場合もある |
| 対象 | 中途・新卒 |
| メリット | ●活躍が見込める人材を自社で探し、採用できる ●転職希望者だけではなく転職潜在層にもアプローチできる |
| デメリット | ●採用活動のノウハウがなくては成果を出すことが難しい ●人事・採用担当者の業務負担が増加する |
| 活用例 | ●従来の採用手法で母集団形成がうまくいかない場合 ●専門的なスキルを持つエンジニアなど、絶対数が少ない人材を採用したい場合 |
ダイレクト・ソーシングは、企業の人事・採用担当者が能動的に転職希望者へアプローチする採用手法です。
人材データベースなどを活用して、自社に合っていると思われる人材を探し、直接スカウトを行います。採用の売り手市場が続く今日では、この「攻め」の採用が非常に高い効果を発揮します。
(参考:『攻めの採用「ダイレクト・ソーシング(ダイレクトリクルーティング)」とは?』)
ソーシャルリクルーティング
| 特徴 | SNSを通じて自社の情報を発信し、幅広い人材と交流を深める |
|---|---|
| 難易度 | SNSを運用する上でのノウハウが必要となるため、難易度は高い |
| コスト | SNSの利用自体にはほとんど費用がかからないため、ほかの採用手法と比較して支出を抑えられる |
| 工数 | 定期的な情報の更新が必要になるほか、投稿する内容の精査なども行わなければならないため、一定の工数を要する |
| 期間 | 中長期的に運用しなくては成果が見込めないため、数カ月~1年以上は必要となる |
| 対象 | 中途・新卒 |
| メリット | ●ほかの採用手法と比べて費用がかからない上に、自社に合った人材を見つけられる可能性も高い ●転職潜在層を含めた、幅広い層に自社の魅力を発信できる |
| デメリット | ●SNSの定期的な更新で工数が生じる ●投稿する内容次第では、情報漏えいや炎上などの問題が発生する恐れがある |
| 活用例 | ●転職サイトや人材紹介サービスではアプローチできない層を採用したい場合 ●自社の魅力や職場環境の様子を広く発信したい場合 |
SNSに特化した採用手法が、ソーシャルリクルーティングです。SNSを通じて自社の魅力を発信したり、転職希望者との交流を図ったりすることで、認知拡大やブランディングの強化を行います。
(参考:『ソーシャルリクルーティングとは?メリットや進め方を解説』)
合同説明会(転職フェア・イベント)
| 特徴 | 転職希望者が多く集まるイベントに出展し、来場者との交流を図る |
|---|---|
| 難易度 | 事前準備や当日の対応、また来場者の関心を引くための工夫も必要となるため、難易度は高い傾向にある |
| コスト | イベント出展料のほかブースの準備にもコストが発生する場合もある |
| 工数 | パンフレットや資料、当日利用する動画などの準備が欠かせないため、人事・採用担当者の負担は増える |
| 期間 | イベントの開催期間は数日程度だが、成果が出るまでにはさらに長い期間を要する |
| 対象 | 中途 |
| メリット | ●企業に応募する前の人材と接点が持てる ●多種多様な人材層にアプローチできる機会を得られる |
| デメリット | ●イベントの準備で人事・採用担当者の負担が増す可能性がある ●イベントに出展しても来場者の興味を引けるとは限らない |
| 活用例 | ●大規模な母集団形成を図りたい場合 ●自社の魅力や強みを、よりリアルな目線で転職希望者に伝えたい場合 |
転職活動を本格的に始める前の人材と接点を持ちたいのであれば、転職フェアやイベントなどの合同説明会に出展しましょう。イベント中に自社に興味を持ってくれた人材と交流を深めれば、競合他社に先んじて動機付けを行えます。
オンライン転職フェア・イベント
| 特徴 | インターネットを通じて転職希望者と交流を図る |
|---|---|
| 難易度 | 実地でのイベントと比較して必要な準備は減るため、実施に際してのハードルは下がる |
| コスト | イベント出展料はかかるものの、それ以外の費用は抑えられる |
| 工数 | ブースや配布資料などの準備がなくなるため、実地のイベントよりも工数がかからない |
| 期間 | イベントの開催期間は数日程度だが、成果が出るまでにはさらに長い期間を要する |
| 対象 | 中途 |
| メリット | ●実地イベントと比較して、準備にかかる費用や工数を大きく削減できる ●遠方に住んでいる転職希望者にもアプローチできる |
| デメリット | ●インターネット回線やオンライン通話の環境を整備する必要がある ●オンラインでのコミュニケーションとなるため、自社の雰囲気が伝わりづらい |
| 活用例 | コストや業務負担を抑えつつ、企業へ応募する前の人材と気軽に交流を図りたい場合 |
「実地で開催されるイベントへの出展は難しい…」という場合には、オンラインイベントへの参加を検討したいところです。オンラインであれば事前準備にかかる工数が少なくなる上に、遠方に住んでいる転職希望者とも接点を持てる見込みがあります。
アルムナイ採用
| 特徴 | 過去に自社ではたらいていた人材を再度採用する |
|---|---|
| 難易度 | すでにある程度の関わりがある人材にアプローチするため、実施に際してのハードルはそれほど高くないが、継続的な接点が必要となる |
| コスト | 人材紹介サービスや転職サイトなどを使わずに採用できるため、費用は抑えられる |
| 工数 | 関係維持のための定期的なコミュニケーションや、再採用時の待遇調整などで一定の工数がかかる |
| 期間 | 一部の採用フローをスキップできるため、早ければ1~2週間で採用に至る場合もある |
| 対象 | 中途 |
| メリット | ●自社に精通している人材を採用できる ●人材が外部で培ってきた視点を自社に取り入れられる |
| デメリット | ●退職時の関係によっては再採用に応じてもらえない可能性がある ●既存社員の退職率が上がる恐れがある |
| 活用例 | ●自社の企業文化に精通しており、かつ即戦力となる人材を採用したい場合 ●既存社員のエンゲージメントを高めたい場合 |
アルムナイ採用は、定年以外の理由で退職した人材を再度採用する手法です。
自社の企業文化や業務内容などをすでに把握している人材であるため、多少のサポートは必要となるものの、即戦力としてのはたらきが期待できます。
(参考:『アルムナイ採用とは?メリットや成功させるポイントも解説』)
リファラル採用
| 特徴 | 社員の友人・知人を人材として紹介してもらう |
|---|---|
| 難易度 | 制度を事前に社内に浸透させる必要があるほか、通常の採用とは違った点に気を付ける必要があり、難易度は高い傾向にある |
| コスト | 外部サービスを使わないため採用費用を大きく抑えられる |
| 工数 | 制度を整備する必要があるほか、不採用となった場合の推薦者のフォローなども求められるため、ある程度の工数はかかる |
| 期間 | 効果の即効性は薄く、通常の採用フローと同様に数週間~数カ月程度を要する |
| 対象 | 中途 |
| メリット | ●自社の企業文化や雰囲気にマッチした人材を採用しやすい ●ほかの採用手法と比較して、かかる費用を大きく抑えられる |
| デメリット | ●事前に制度を社内に浸透させる、また社員のエンゲージメントを高める必要がある ●人材に対する推薦者の評価が客観的ではない可能性がある |
| 活用例 | ●自社に理解のある人材を重点的に採用したい場合 ●採用活動にかかる費用を抑えたい場合 |
リファラル採用では、社員の友人・知人を紹介してもらう形で人材を採用します。社員を通じて自社の情報や雰囲気をすでに知っている可能性が高く、企業文化や雰囲気とのミスマッチが発生する可能性を大きく減らせます。
(参考:『リファラル採用とは?導入のメリット・デメリット、運用のポイントを紹介』)
タレントプール
| 特徴 | 過去に応募があった人材や自社のイベントに来た転職希望者など、活躍が見込める人材の情報を自社内のデータベースに蓄積する |
|---|---|
| 難易度 | ただ情報を蓄積するだけではなく、それをどのように活用していくかの知見も必要になるため、実施に際して一定のハードルがある |
| コスト | タレントプールを活用すれば外部サービスを利用しなくても済むため、長期的な観点ではコストパフォーマンスに優れる |
| 工数 | タレントプール作成までの要件定義やデータベースの構築などで、一定の工数が必要となる |
| 期間 | 中長期的に運用する必要があるため、成果が出るまでに短くとも数カ月は要する |
| 対象 | 中途 |
| メリット | ●自社での活躍が見込める人材に効率良くアプローチできるようになる ●採用活動にかかるコストを削減できる |
| デメリット | ●成果が出るまでに中長期的な運用が必要となる ●タレントプールの管理工数が生じる |
| 活用例 | 自社での活躍が見込める人材を少しでも多く把握したい場合 |
将来的に自社での活躍が見込めそうな人材の情報を、自社内のデータベースに蓄積していけば、後々の採用活動をより効率良く進められます。この採用手法を、一般的に「タレントプール」と呼びます。
採用活動が難化する現代では、このようにして人材に関わる情報を少しでも多く保有することが非常に重要となるのです。
ミートアップ
| 特徴 | 交流会や勉強会を開催し、そこで自社のアピールを行う |
|---|---|
| 難易度 | 転職希望者に興味を持ってもらうための工夫が必要になるため、実施難易度は高い |
| コスト | 小規模な交流会であるため、費用はそれほどかからない |
| 工数 | 事前準備や当日の対応が必要になるため、人事・採用担当者の業務負担は増える |
| 期間 | あくまでも交流が目的であるため即効性はなく、採用活動としての効果を得られるまでには数カ月を要する |
| 対象 | 中途 |
| メリット | ●転職希望者の自社に対する理解度を深められる ●採用ブランディングとしても効果を発揮する |
| デメリット | ●人事・採用担当者の業務負担は増加する ●興味を持ってもらうための工夫ができなくては、成果が望めない |
| 活用例 | ●特定の領域に関心を持つ転職希望者とのネットワークをつくりたい場合 ●自社の強みや商品の魅力を直接伝えたい場合 |
ミートアップは、もともと特定の領域に関心を持つ人々が集まり、情報交換を行うイベントとして広まったものです。しかし近年では、自社の情報を効果的に発信するための場として、企業の採用活動でも取り入られています。
(参考:『ミートアップとは?採用における役割や実施ステップを解説』)
自社ホームページ
| 特徴 | 自社のホームページを活用して転職希望者に情報を発信する |
|---|---|
| 難易度 | サイト運用やSEOの知識など、採用以外の領域でのノウハウも求められるため、難易度は高い傾向にある |
| コスト | ホームページの作成時にはイニシャルコストがかかるものの、長期的に見れば採用費用を抑えられる |
| 工数 | コンテンツ作成や検索順位対策などが必要となるため、ある程度の工数を要する |
| 期間 | 即効性は薄く、数カ月~1年以上の中長期的な取り組みが必要 |
| 対象 | 中途・新卒 |
| メリット | ●自社の魅力を自由に発信できるため、独自性をアピールしやすい ●長期的な観点では採用費用を抑えられる |
| デメリット | ●ホームページの運用保守やSEO対策などで、業務負担が増加する可能性がある ●成果が出るまでに中長期的な期間を要する |
| 活用例 | ●採用活動を通じて自社の企業ブランディングも強化したい場合 ●より深いところまで自社の魅力を転職希望者に知ってもらいたい場合 |
外部のサービスやサイトを使わずに、自社のホームページを活用して採用活動を行うという方法もあります。自由な情報発信が可能で、すでにホームページがある場合は追加の費用もほとんどかからない点が特徴です。
(参考:『転職希望者の約8割が見ている!転職先候補から外されない採用サイトの作り方』)
インターンシップ
| 特徴 | ●就職前の学生を受け入れて、実際の業務やはたらき方を体験してもらう ●1日で終わるカジュアルなものから、1カ月以上の長期的なタイプまで存在する |
|---|---|
| 難易度 | 受け入れ態勢の整備が必要になるほか、学生にレクチャーするノウハウも求められるため、実施に際して一定のハードルがある |
| コスト | インターンシップの実施に費用はかかるものの、そのまま採用できればトータルでの採用費用は大きく抑えられる |
| 工数 | インターンシップの企画や期間中の運営、学生のサポートなどに工数を使う必要がある |
| 期間 | インターンシップ自体に最長で数カ月、その後の成果につながるまでにさらに期間を要する |
| 対象 | 新卒 |
| メリット | ●将来の活躍が見込める学生に早期からアプローチできる ●採用のミスマッチ防止につながる |
| デメリット | ●インターンシップの企画・運営に相応の工数が必要となる ●成果が出るまでに期間を要する |
| 活用例 | 新卒採用で母集団形成を図りたい場合 |
インターンシップは、特に新卒採用で効果的な手法です。
就職活動が本格化する前に、自社でのはたらき方や実際の業務を知ってもらうことで、「ここではたらきたい」という想いを効果的に引き出せます。また、採用のミスマッチを防止するための手段としても有用です。
カジュアル面談
| 特徴 | ●選考の前に、企業と転職希望者の相互理解を深める目的で行われる ●面談の内容が合否に関係することはない |
|---|---|
| 難易度 | 通常の面接とは異なるアプローチが求められるほか、全社的な協力が必要となるケースもあるため、実施に際して一定のハードルがある |
| コスト | カジュアル面談自体に費用はそれほどかからず、採用効率が向上すれば長期的な費用対効果は高まる |
| 工数 | 通常の選考に加えて行うことになるため、人事・採用担当者の業務負担は増加する傾向にある |
| 期間 | カジュアル面談のあとに選考を行うため、即効性は期待できない |
| 対象 | 中途・新卒 |
| メリット | ●採用のミスマッチを防げるだけではなく、自社への志望度を高められる可能性もある ●転職潜在層にもアプローチできる |
| デメリット | ●採用業務にかかる工数は増える ●通常の面接とは違った進め方を意識しなくてはならない |
| 活用例 | ●選考の辞退や早期離職といった、採用のミスマッチが多発している状況を変えたい場合 ●より幅広い層へアプローチしたい場合 |
カジュアル面談は、企業と転職希望者の相互理解を目的とする面談です。
採用面接と異なり、カジュアル面談は選考の合否に影響を与えません。リラックスした雰囲気で会話を行い、お互いにマッチしているかどうかを確かめ合うことに比重が置かれます。
(参考:『カジュアル面談とは?採用面接との違いや実施するメリット・当日の流れを解説』)
人材派遣
| 特徴 | ●要件に合った人材を人材派遣会社に派遣してもらう ●人材との雇用契約を結んでいる主体は派遣会社であり、任せられる業務内容にも制限がある |
|---|---|
| 難易度 | 人材派遣会社に要件を伝えるだけで良いため、難易度は高くない |
| コスト | 派遣された人材1人当たりの費用は高い傾向にある |
| 工数 | 書類選考や面接といった対応のほか教育も必要ないため、人事・採用担当者の負担は少ない |
| 期間 | 早ければ数日のうちには、遅くとも数週間で人材を迎え入れられる |
| 対象 | 中途・新卒 |
| メリット | ●人事・採用担当者の工数を抑えつつも、スピーディーに人材を採用できる ●給与や各種保険などに関する手続きが必要ない |
| デメリット | ●派遣される人材を選べない ●人材の意向次第で契約が更新されない可能性がある |
| 活用例 | ●繁忙期の一時的な労働力不足を解消したい場合 ●急な欠員に対応したい場合 |
スピーディーに即戦力となる人材を採用したい場合には、人材派遣が効果的な採用手法となり得るでしょう。特に、必要なスキルを持っている人材を一時的に自社に迎え入れたい場合に最適です。
なお、人材紹介サービスと似ているように思えますが、派遣される人材と雇用契約を結ぶ主体はあくまでも派遣元の会社であり、雇用形態はまったく異なることに注意しましょう。
RPO(採用代行)
| 特徴 | 外部の業者に採用業務を代行してもらう |
|---|---|
| 難易度 | 採用業務の一部、あるいは全てを業者に任せることになるので、実施難易度は低い |
| コスト | ほかの採用手法と比較すると高額になる傾向がある |
| 工数 | 人事・採用担当者の業務負担を大きく減らせる |
| 期間 | RPOの利用前に要件の擦り合わせなどが必要になるため即効性は薄く、成果が出るまでに数週間~数カ月ほどかかる |
| 対象 | 中途・新卒 |
| メリット | ●採用活動の品質を高められる ●採用活動にかかる工数を削減できる |
| デメリット | ●ほかの採用手法と比較して費用が高い傾向にある ●社内に採用ノウハウが蓄積されにくい |
| 活用例 | ●採用活動で成果を出せていない期間が続いている場合 ●採用業務の工数を減らして、社員がコア業務に割ける時間を増やしたい場合 |
募集要件の設定や転職希望者の対応などの採用業務を、外部の業者に代行してもらう手法がRPOです。採用のプロに業務を任せることで自社の採用力を高められるほか、採用活動にかかっていた工数の削減もかないます。
(参考:『RPO(採用代行)とは?費用や委託できる業務範囲、メリット・デメリットについて解説』)
ヘッドハンティング
| 特徴 | 外部で活躍している人材に直接アプローチする |
|---|---|
| 難易度 | 採用要件の整理がより高度なものとなるほか、ヘッドハンティングの際の交渉が難航する可能性もあるため、難易度は高い |
| コスト | ハイクラス人材の採用に成功した場合は高額なコストが発生する |
| 工数 | 人材像の明確化や業者との認識合わせ、また採用が決まったあとの待遇の擦り合わせなどで一定の工数が必要となる |
| 期間 | ハイクラス人材の絶対数が少なく、採用するまでに数カ月以上かかることが一般的 |
| 対象 | 中途 |
| メリット | ●自社の求めるハイクラス人材へ効果的にアプローチできる ●転職活動をしていない層にもアプローチできる |
| デメリット | ●ほかの採用手法と比較して高額な費用がかかる ●採用活動が長期化する傾向にある |
| 活用例 | 高度なスキルや経験を持つ人材を何としても採用したい場合 |
ヘッドハンティングでは、人材紹介サービスなどを通じて、外部で活躍している人材に直接アプローチをかけます。ダイレクト・ソーシングと似ていますが、ヘッドハンティングは経営層や幹部候補といったハイクラス人材の採用に特化している傾向にあります。
(参考:『ヘッドハンティングとは?言葉の意味や導入するメリットなどを紹介』)
中途採用における面接の手法やポイントをまとめた「面接ガイド」を、下記から無料でダウンロードいただけます。採用手法とあわせて、ぜひご活用ください。
近年の採用市場の動向
コロナ禍による採用活動のオンライン化や、労働人口の減少による採用難易度の向上により、今後は企業側から転職希望者にはたらきかけていく「攻め」の採用手法が一般化していくと予想されます。
実際、従来のようにただ応募を待つのではなく、企業側から転職希望者に直接アプローチするダイレクト・ソーシングや、社員から人材を紹介してもらうリファラル採用が活発化してきています。
ダイレクト・ソーシングやリファラル採用の入り口として注目されているのが「カジュアル面談」です。カジュアル面談とは、企業と転職希望者がお互いを良く知るために対等な立場で話し合う面談のこと。あくまでお互いの情報交換が目的のため、企業は面接のように合否を決定しません。人材の採用が難しい現在の採用市場では、より多数の人材にアプローチできる手法として、カジュアル面談を導入する企業が増えています。
(参考:『自社に最適な人材採用を。ダイレクト・ソーシングの活用方法』、『カジュアル面談とは|導入メリットや面談の流れを解説【質問集付き】』)
最新の採用手法のトレンド
ここで、採用手法の最新のトレンドもチェックしておきましょう。中途採用と新卒採用で効果的な手法が異なるため、個別に解説します。
中途採用の流行
中途採用では、即戦力としての活躍が期待できる人材を優先的に採用したいケースがほとんどです。そのため、特に「アルムナイ採用」や「リファラル採用」がメジャーな手法として主流となりつつあります。
アルムナイ採用は、企業文化への理解がある上に、スキル面もクリアしている人材を採用できるので、中途採用では有力な手法の一つです。リファラル採用も、社員の知り合いを紹介してもらうという仕組み上、企業文化に理解がある人材を採用できる可能性が高いため、活用されています。
中途採用で成果を出したいのであれば、自社の状況を一度整理した上で、上記の採用手法導入の検討をしてみましょう。
新卒採用の流行
これまで新卒採用では、広く人材を募集する「マス型採用」が一般的でしたが、近年は個別の候補者にフォーカスする「個別採用」も取り入れられつつあります。
中でも注目されている手法が、「ダイレクト・ソーシング」です。アプローチの過程でコミュニケーションを重ねるため、候補者が自社に合っているかどうかを入念に判断できます。また、応募を考えていなかった候補者に自社の魅力を訴求できる点も、大きな強みです。
このほか、自社の魅力を詳細にアピール可能な「自社ホームページ」も、効果的な入社動機づけの手段としてという理由から多くの企業で活用されています。
(参考:『「働きたい!」エンジニア転職“潜在層”から逆オファーが来るほど!採用~定着に効いている最強!?オウンドメディアとは【隣の気になる人事さん】』、『母集団形成と選考を改善し、ミスマッチ解消にも効く!「採用ピッチ資料の作り方」最前線』)
採用手法を選ぶ際の3つのポイント
採用手法のトレンドをご紹介しましたが、あくまで世の中の流れとして増えているだけであり、トレンドの採用手法が必ずしも自社にとって効果的な方法とは限りません。
自社に合った採用手法を選ぶために押さえておきたいポイントを3つご紹介します。
1.自社の採用課題を把握する
2.採用したい人材の人材像を明確にする
3.複数の採用手法を活用する
自社の採用課題を把握する
自社で抱えている採用課題によって、最適な採用手法も変わります。よって、まずは自社の採用課題を把握することから始めましょう。
例えば、「採用費用の増加」が課題としてある場合は、以下の採用手法が効果的な手段として挙げられます。
対して、「業務負担の増加」や「母集団形成の難航」などが課題の場合は、また別の採用手法が有用な選択肢となり得ます。
【人事・採用担当者の業務負担を減らしたい場合の採用手法】
●人材紹介サービス
●人材派遣
●オンライン転職フェア・イベント
●RPO(採用代行)
●ヘッドハンティング
【自社に興味を持っている人材で母集団を形成したい場合の採用手法】
●転職サイト
●ダイレクト・ソーシング
●ソーシャルリクルーティング
●カジュアル面談
●アルムナイ採用
適切な採用手法を選ぶためにも、まずは自社の状況を一度整理して、課題を洗い出しましょう。
採用したい人材の人材像を明確にする
転職希望者の人材像を明確にすることで、その人材に適した採用手法を選択できます。そのためにも、まずは求める人材の年齢や学歴、資格などのハード面と、性格や価値観などのソフト面に分けて、「必須条件」と「希望条件」を洗い出しましょう。次に、洗い出した条件を基にペルソナを設定します。
実在する人物であるかのように設定することで、採用したい人物により適した採用手法を打ち出しやすくなり、自社に合う人材を採用できる可能性が高くなります。ペルソナの設定に迷う場合は、自社で活躍する社員を参考にすると良いでしょう。
(参考:『採用ペルソナとは?設定ノウハウや手順・具体例をまとめて紹介【テンプレート付】』)
複数の採用手法を活用する
どの採用手法にもメリット・デメリットがあります。採用する人材によっても適した採用手法があり、難易度の高い採用手法だけに固執すると採用が進まないケースも想定されます。
また、自社が抱える採用課題によっても、以下のように適した採用手法を選定できます。
●コストを抑えたい:自社ホームページ、リファラル採用、ミートアップなど
●早めに採用したい:人材紹介サービス、人材派遣、転職サイトなど
●ミスマッチのない採用をしたい:人材紹介サービス、ダイレクト・ソーシング、ヘッドハンティングなど
特に、ダイレクト・ソーシングに代表される個別採用でのアプローチは、人事・採用担当者のスキルによって結果が左右される側面もあるでしょう。一つの採用手法に頼るのではなく、柔軟に複数の手法を組み合わせて母集団を形成していくことをお勧めします。
まとめ
多様化する採用手法から自社に合ったものを選ぶためには、自社の採用課題を明確にした上で、求める人材に適した手法であるかを検討しましょう。
各採用手法には一長一短があるため、一つの手法にこだわるのではなく、複数の手法を組み合わせることも重要なポイントです。
今回の記事で紹介した採用手法の特徴や最新のトレンドなどを参考に、自社の採用手法を見直してみてはいかがでしょうか。
(制作協力/株式会社eclore、編集/d’s JOURNAL編集部)
採用面接のフローや面接準備、面接手法が1冊でわかる!「中途採用面接ガイド」
資料をダウンロード