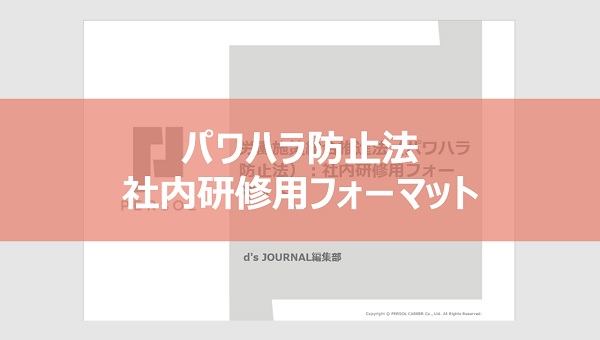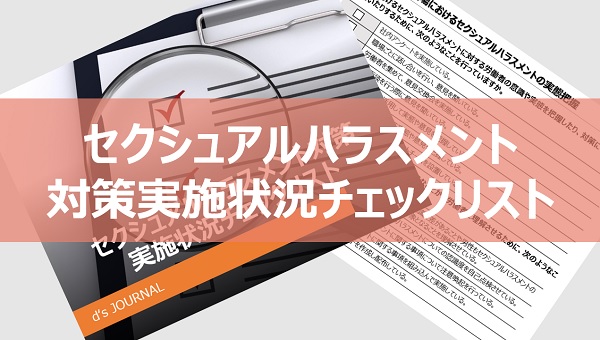【弁護士監修】自分の“普通”は誰かの“不適切”?ハラスメント一覧とマネジメント層の心得
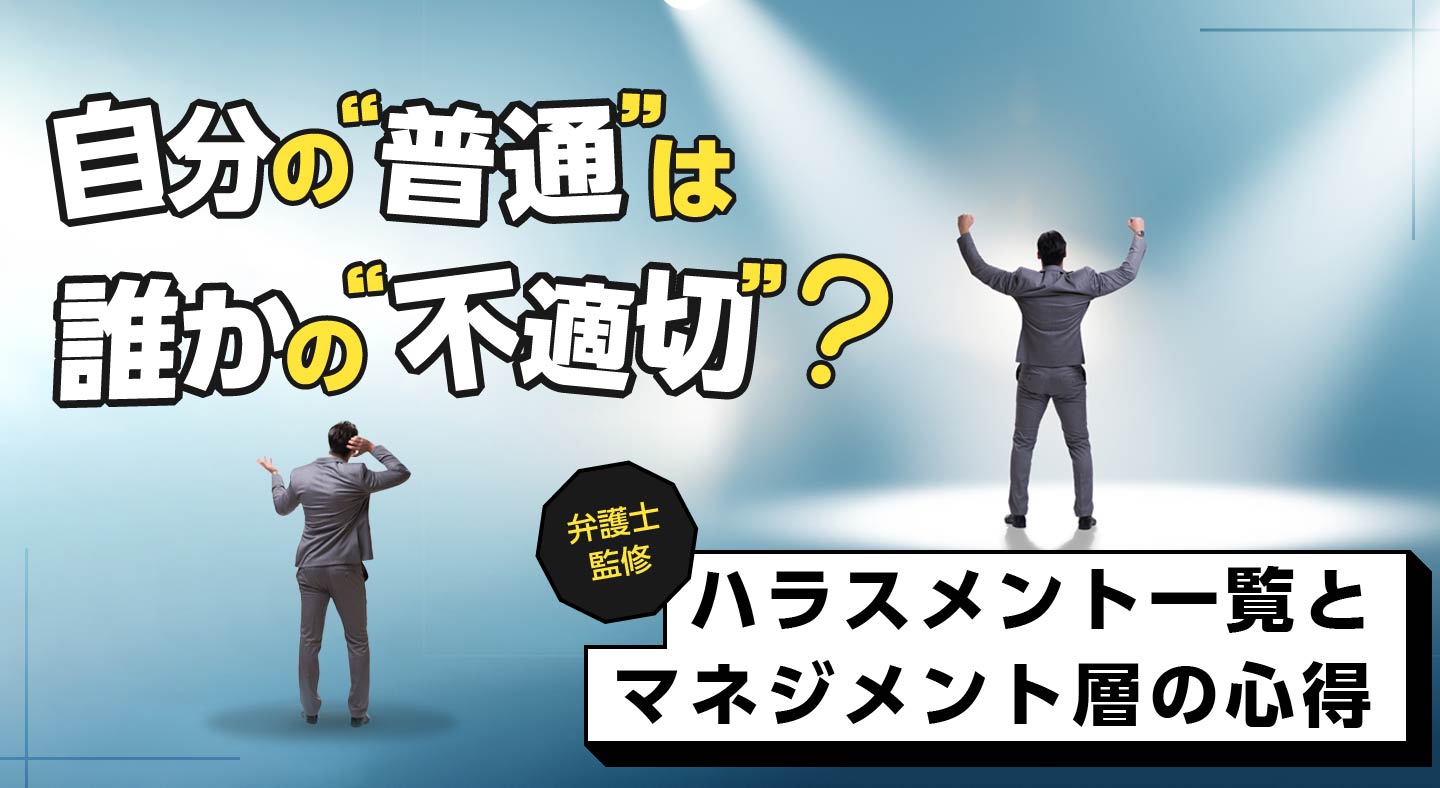
-
「ハラスメント」が転職理由ランキングの上位になっており、人材の流出を防ぐためにも、ハラスメント対策は急務
-
パワハラ、セクハラ、マタハラなどの一般的なハラスメントだけでなく、ジェンハラ、エイハラなどの新しい形のハラスメントも認識する必要がある
-
情報や自身の言動を常にアップデートし、日ごろのコミュニケーションにおいても、信頼関係の構築に努めることが大切
ハラスメントとは、人を不快にさせる言動や嫌がらせのこと。各種法律により、企業には職場における「パワハラ」「セクハラ」「妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント(マタハラ、パタハラ)」への対策を講じることが義務付けられています。
一方で、「●●ハラ」と呼ばれるハラスメントの種類は増えており、「どのような言動がハラスメントに当たるのか」「部下や同僚、上司に対してどう接することが適切なのか」と不安になる方もいるのではないでしょうか。
この記事では弁護士監修のもと、ハラスメント対策の重要性を解説するとともに、職場で気を付けたいハラスメントの種類や具体的な言動などを紹介します。自身の言動を振り返れる「ハラスメント セルフチェックシート」もぜひご活用ください。
ハラスメント対策の重要性

「転職サービスdoda」が2024年3月に発表した「転職理由ランキング」では、「ハラスメントがあった(セクハラ・パワハラ・マタハラなど)」が10位に入り、前回の17位から大幅に順位を上げました。また、併せて調査を行った「転職の一番の理由」(単一回答)の3位は「ハラスメントがあった」で、前年度9位から6つ順位を上げており、ハラスメント対策は人材の流出を防ぐためにも急務であることがわかります。
仮にハラスメントをしてしまった人にとっては「過去には当たり前だったこと」「親しさを表すつもりの言動」であってハラスメントに無自覚であったとしても、受け取り方には個人差があり、相手が不快と感じれば、それはハラスメントになり得ます。実際ハラスメントに当たるか否かについてはケースバイケースで判断されるものの、もし自身がハラスメントをしてしまった場合、組織のメンバーからの信頼を失うだけでなく、場合によっては、社内的地位を失ったり被害者から損害賠償を請求されたりすることもあるかもしれません。
なお、ハラスメントは主に業務中の「オフィス」で起こるとイメージする方もいるかもしれませんが、「出張先」や「業務で使用する車中」「取引先との打ち合わせ場所」なども「職場」に該当します。加えて、「歓迎会」や「取引先との懇親会」なども、実質的には職務の延長と考えられるため、ハラスメントが起き得る場面として十分な注意が必要です。
多くの場面で発生し得るハラスメントだからこそ、これを防ぐためには、個々が自身の認識をアップデートし、多様性のある社会に対応することが重要です。
■参照:厚生労働省『職場における パワーハラスメント対策 セクシュアルハラスメント対策 妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント対策は事業主の義務です!』
職場で気を付けたいハラスメント一覧

実際に、ハラスメントにはどのような種類があり、どういった言動が該当し得るのでしょうか。ここでは、職場で気を付けたいハラスメントを紹介します。
パワハラ(パワーハラスメント)
パワハラとは、職場での地位や優位性を利用して嫌がらせを行うこと。2020年6月1日(中小企業は2022年4月1日から)に施行された改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)により、企業にはパワハラを防止するための措置を講ずることが義務付けられています。
同法では、パワハラを「優越的な関係を背景とした言動」「業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」「労働者の就業環境が害されるもの」の3つの要素を全て満たすものと定義しています。パワハラの種類と代表的な言動例を、6つのパターンに分けると以下のとおりです。上司と部下の関係では指導の域を超えて起こりやすい言動も多いため、日ごろから意識を持ってコミュニケーションを取りましょう。
| パターン | 代表的な言動例 |
|---|---|
| 身体的な攻撃 | ・殴打、足蹴りを行う ・相手に物を投げつける など |
| 精神的な攻撃 | ・人格を否定するような言動を行う ・長時間にわたる厳しい叱責を繰り返し行う ・能力の否定や罵倒的な内容のメールを送信する など |
| 人間関係からの切り離し | ・長時間にわたり別室に隔離したり自宅研修をさせたりする ・一人の従業員に対し集団で無視をする など |
| 過大な要求 | ・新卒者に対しベテラン従業員レベルの業務目標を課す ・業務とは関係のない私的な雑用の処理をさせる など |
| 過小な要求 | ・退職させるために誰でも遂行可能な業務を行わせる ・嫌がらせのために仕事を与えない など |
| 個の侵害 | ・職場外でも監視したり私物の写真撮影をしたりする ・性的指向や性自認を本人の了解なく他者に暴露する など |
■参照:
・【弁護士登壇】パワハラ防止法の改正に伴う企業の対応や対策のポイントを解説/2022年4月から中小企業も対応必須
・【弁護士監修】パワハラ防止法成立。パワハラ問題へ企業はどう対応する?対策法を紹介
・パワハラとコンプライアンスの関係性とは?企業が対応すべきポイント
セクハラ(セクシュアルハラスメント)
セクハラは、相手の意に反する性的な言動のことです。2020年施行の改正男女雇用機会均等法第11条でも、企業にはセクハラの防止措置が義務付けられています。具体的に、「性的な言動」とは、以下のような言動を指します。
セクハラとなり得る言動例
性的な内容の発言
●性的な事実関係を尋ねる
●性的な内容の情報・うわさを流布する
●性的な冗談やからかい
●食事やデートへの執拗な誘い
●個人的な性的体験談を話す など
性的な行動
●性的な関係を強要する
●必要なく身体へ接触する
●わいせつ図画を配布・提示する など
セクハラの被害者・加害者には男女ともに該当し、異性に対するものだけではなく、同性に対するものも含まれます。被害を受ける人の性的指向や性自認にかかわらず、相手が不快に感じる「性的な言動」であればセクハラに該当し得ることに注意が必要です。
■参照:【弁護士監修】どこからセクハラ?事例や裁判例と共に職場で取り組むべき対策をご紹介【対策チェックシート付き】
マタハラ(マタニティハラスメント)/パタハラ(パタニティハラスメント)
マタハラやパタハラは、「マタニティ(母性)」もしくは「パタニティ(父性)」とハラスメントを組み合わせた言葉です。妊娠・出産・育児休業等にまつわる嫌がらせなどを指します。
職場でのマタハラやパタハラには、「産前休業」や「育児休業」、「子の看護休暇」「時間外労働や深夜業の制限」「所定労働時間の短縮措置」といった男女雇用機会均等法や育児・介護休業法に定める制度を利用させないなどの「制度等の利用への嫌がらせ型」と、妊娠・出産という状態に対して不利益な取り扱いを行うなどの「状態への嫌がらせ型」があります。
マタハラ/パタハラとなり得る言動例
制度等の利用への嫌がらせ型
●時間外労働の制限を請求された際、「制度を利用するのであれば昇進させられない」と言う
●育児休業の取得を相談された際、制度を利用しないように指示する
●子の看護休暇を利用したことに対し、悪口を言う など
状態への嫌がらせ型
●産前休業・育児休業の取得を請求された際「母親なら仕事は辞めて子育てに専念すべき」と価値観を押し付ける
●「時短制度を利用する人には大きな仕事を任せられない」と雑務のみに従事させる
●妊娠報告に対し「仕事のしわ寄せが来て大変だ」と発言する など
両法では、パワハラやセクハラと同様に、企業に職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの防止措置を講じることを義務付けています。2019年の法改正により、相談したことなどを理由とする不利益取り扱いの禁止が加わったため、職場でも「制度の利用を阻害しない」「自分の価値観を押し付けない」など、より意識を高めて従業員とのコミュニケーションを行う必要があるでしょう。
■参照:
・マタハラとは?定義や具体例の解説と企業がすべき対応とは?
・パタハラとは?事例から見る実態と、企業における予防対応方法
SOGIハラ(SOGIハラスメント)
SOGIハラの「SOGI(ソジ・ソギ)」は、「Sexual orientation and gender identity」の略で、「性的指向(好きになる人の性)」と「性自認(自らが認識している自分の性)」という意味で、SOGIハラはこれらに対するハラスメントを指します。
SOGIハラとなり得る言動例
●性的指向や性自認に対し差別的な言動(呼称や嘲笑など)をする
●性的指向や性自認などを理由に不利益な待遇を強いる
●性的指向や性自認を本人の許可なく公表する(=アウティング)
●望まない性別での生活を強要する など
性的指向や性自認に関することを本人が望まない形で暴露する「アウティング」は、パワハラにも該当する言動です。同様に、性的指向や性自認にかかわらず、相手が不快と感じる性的な言動はセクハラに該当する可能性があります。
■参照:SOGIハラとは?言動の具体例や組織での防止策を紹介
モラハラ(モラルハラスメント)
モラハラとは、言葉や態度で、相手の人格や尊厳を傷つけること。精神的な嫌がらせを指し、物理的な暴力行為は含まれないことが一般的です。その性質上、パワハラの「精神的な攻撃」に該当するとされています。指導の一環のつもりが、指導の域を超えてしまうことがないか、日ごろの言動を見直してみましょう。
モラハラとなり得る言動例
●無視をする、業務に必要な連絡をしない
●人格を否定する
●他の従業員がいる前で過剰に叱責する
●本人に聞こえるように悪口を言う、舌打ちをする など
ロジハラ(ロジカルハラスメント)
ロジハラは、正論を振りかざして相手を追い詰め、相手を不快にすること。「論理的な」「理にかなった」を意味する「ロジカル(logical)」とハラスメントを組み合わせた言葉です。ロジハラはパワハラの一種で、職場における優越的な関係を背景に、業務上必要かつ相当な範囲を超えて正論を振りかざし就業環境を害することと考えられています。正論が悪いというものではありませんが、パワハラ・モラハラ同様に、日ごろのコミュニケーションにおいて注意が必要です。
ロジハラとなり得る言動例
●相手の話を一切聞かず、一方的にミスを指摘する
●正論をもって相手を執拗に追い詰める
●自らの正論のみを強く主張し、その場のメンバーを萎縮させる など
■参照:ロジカルハラスメント(ロジハラ)とは?起きる原因と企業ができる対処法を解説
ジタハラ(時短ハラスメント)
ジタハラは、労働時間を削減するための具体的な提案や改善策などを示さないにもかかわらず労働時間の短縮を現場に強いることです。働き方改革の推進により長時間労働の是正を試みたことなどが背景と考えられていますが、具体策がない上での時短の強要はサービス残業や業務の自宅への持ち帰りなどを発生させる可能性があり、この点でも問題視されています。
ジタハラとなり得る言動例
●「長時間労働をなんとかしろ」という指示のみで提案や運用サポートがない
●業務量が変わらないのに「残業は月●時間までに収めろ」と指示する
●定時にタイムカードを押した後にサービス残業をさせる など
エイハラ(エイジハラスメント)
年齢(エイジ age)を理由としたハラスメントをエイハラと言います。ベテラン社員から若手社員に向けられることもあれば、若手社員が中高年社員に対して行う場合もあります。
エイハラとなり得る言動例
●「最近の若者は」「これだからゆとり世代は」と揶揄する
●「若いからこれくらいできるだろう」と力仕事や残業を強要する
●「この年でこんな簡単な仕事もできないのか」と嫌味を言う など
ジェンハラ(ジェンダーハラスメント)
ジェンハラとは、「男らしさ」「女らしさ」といった自身の持つ男性や女性のイメージで差別をしたり人を非難したりすること。ジェンハラには、セクシュアルマイノリティーに対する差別的な言動も含まれると考えられています。
ジェンハラとなり得る言動例
●「男のくせに~」「女なのに~」と侮辱する
●「力仕事は男性」「お茶出しは女性」など、男女問わず可能な業務であっても特定の業務を男女どちらかのみに対応させる
●同性愛者に対する否定的な発言をする
●身体的な性が女性、性自認が男性である従業員にスカートの着用を強要する など
【番外編】ハラハラ(ハラスメントハラスメント)
ハラハラは、ハラスメントハラスメントの略語で、業務上適切な指導であるにもかかわらず、ハラスメントであると過剰に主張する行為のことです。
ハラハラとなり得る言動例
●遅刻が多いことに対し、上司から生活リズムを整えるよう指導された→「モラハラを受けた」と相談窓口に相談する
●スキルアップのために、上司から通常業務より一段階レベルの高い業務を任せられた→「過大な要求でパワハラだ」と主張する
●子の看護休暇を取得した際に、翌日同僚から子どもの体調を尋ねられた→「プライベートの侵害です」と発言する など
業務上必要かつ適切な範囲で行われる指示や指導は、ハラスメントに該当しません。従業員の被害者意識が強い場合や、指示・指導とハラスメントの区別がついていない場合もあるため、企業としてハラスメントの基準やアドバイスの範囲を明確にしておくなどの工夫をするとよいでしょう。
マネジメント層の心構えと対応方法

ハラスメントの種類や該当し得る言動は多岐にわたり、同僚や上司、部下などから起こるものもあります。特にマネジメント層としては、ハラスメントを意識するあまり、チームのメンバーとコミュニケーションが取りにくいと感じることもあるかもしれません。
もちろん、マネジメント層にはチームのメンバーを指導・育成する責任があり、時には厳しい指摘や指導が必要な場面もあります。重要なのは、自身が権威を持っていることを自覚し、「ハラスメントが自身や企業、部下にもたらす影響を理解する」「ハラスメントと捉えられないコミュニケーションや指導方法を身に付け、部下との間に信頼関係を築く」ことです。
そのためには、ハラスメントについて常に情報をアップデートし、自分の中の「普通」を見直すことや、アサーション(相手の気持ちや考えを尊重しながら自身の意見をその場に適した表現で伝えるスキル)、アンガーマネジメント(自身の怒りの感情を理解し、コントロールするスキル)などを学び、実行することが大切です。
【無料】関連お役立ち資料
まとめ
ハラスメントは価値観の違いや無意識の偏見、「この程度のことなら許される」「この人であれば大丈夫」という思い込みなどから発生します。良好な人間関係を築くためには、ハラスメントとなり得る言動を理解し、そのような言動を取らないこととともに、適切なコミュニケーションや指導方法を学ぶことが大切です。“不適切”と判断されないためにも、今回紹介した内容やセルフチェックシートなども活用してみてはいかがでしょうか。
(企画・編集/田村裕美(d’sJOURNAL編集部)、制作協力/株式会社mojiwows)
関連記事
・部下育成のポイントと指導法|失敗しやすい事例を紹介
・成功する組織の秘策は“感情”にあった。成果を出すリーダーが実践する「感情マネジメント」と「EQの鍛え方」
いますぐ自分でチェック!ハラスメント セルフチェックシート
資料をダウンロード