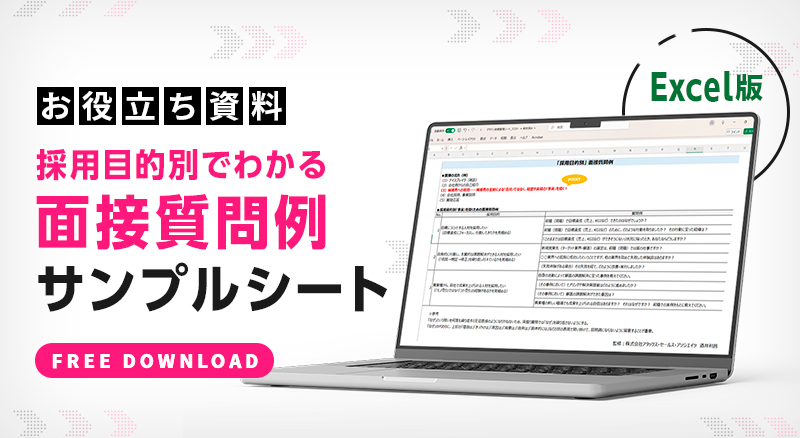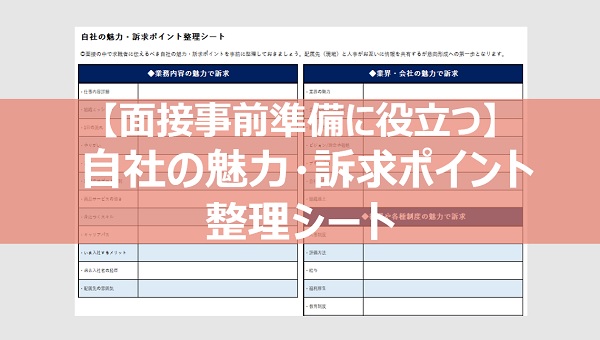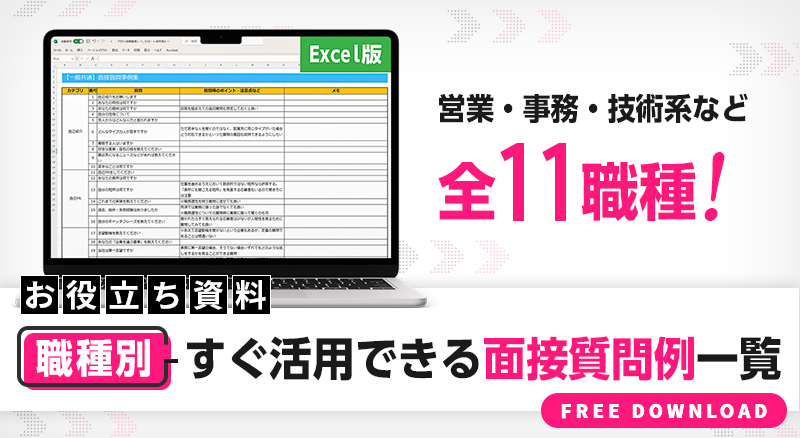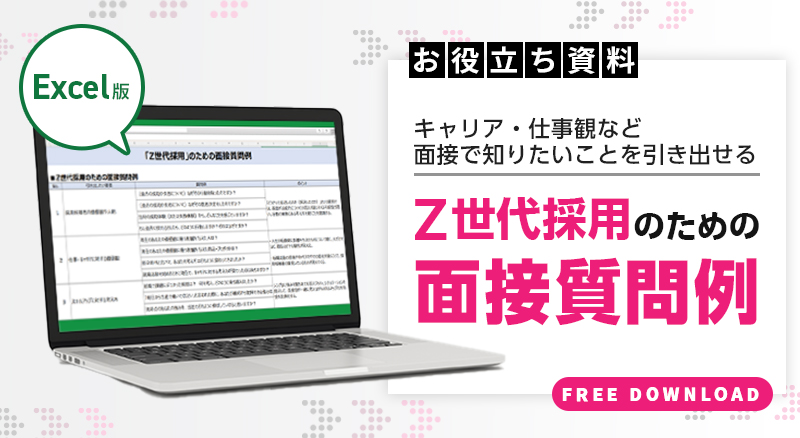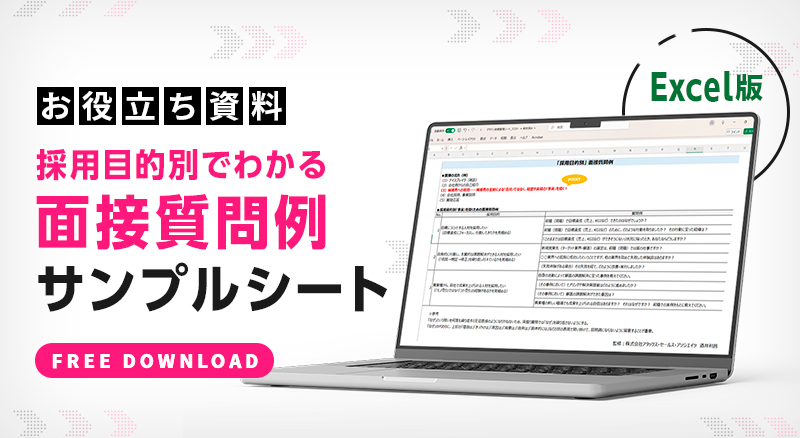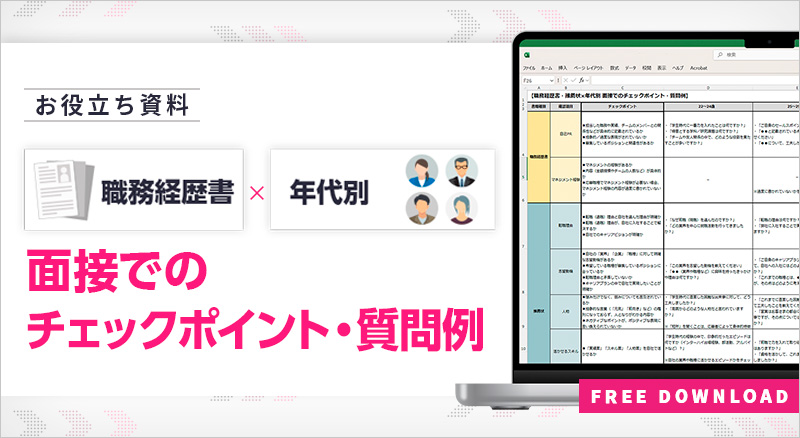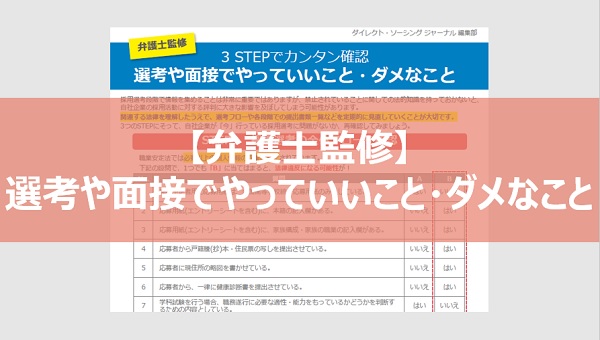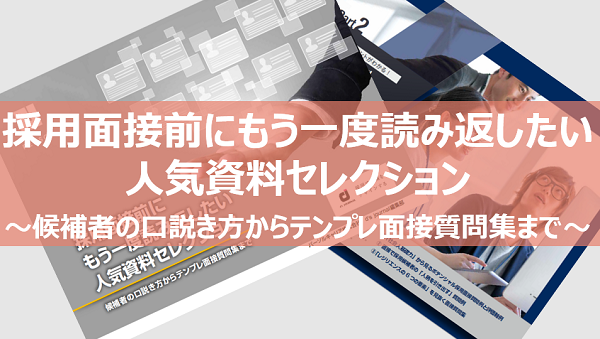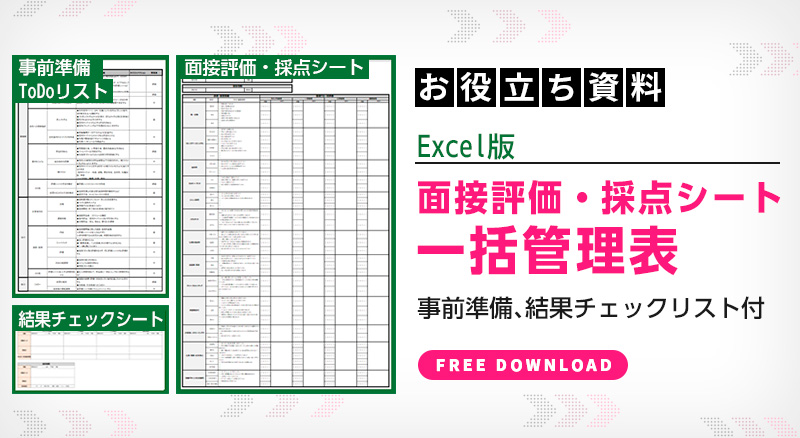今日から使える面接官マニュアル【質問事項はこれでOK】
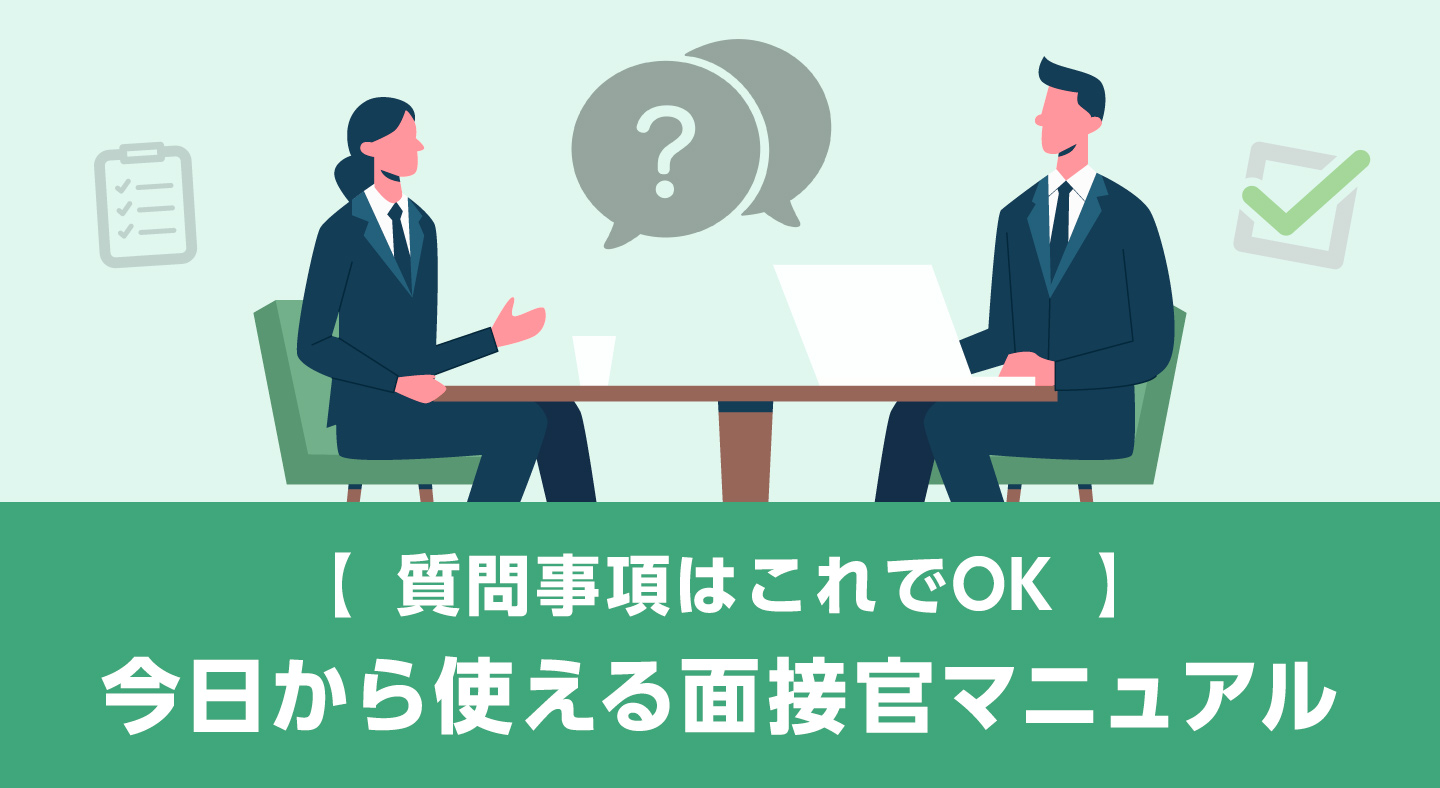

d’s JOURNAL編集部
自社での活躍が見込める人材を採用するためには、まず採用面接を成功させなくてはなりません。よって必然的に面接官は重要な役割となるわけですが、中には任命されたばかりで何もノウハウがない、という方もいらっしゃるでしょう。
そこで本記事では、面接の際に意識すべきポイントや採用面接の具体的な流れなどを解説します。今日からすぐに使える質問例も紹介しているので、面接予定のある面接官はぜひご覧ください。
採用目的別に使える資料を下記から無料でダウンロードいただけますので、ぜひご活用ください。
面接官の役割とは?
まずは、面接官の役割を把握しておきましょう。
面接官には、「見極め役」と「会社の顔」という2つの役割が存在します。それぞれの詳細は以下の通りです。
(参考:『面接官のやり方と心得|事前準備や質問例など基礎ノウハウを解説【マニュアル付】』)
自社に合った転職希望者を選ぶための「見極め役」
面接官は、見極め役、つまり「その転職希望者が自社に合っているかどうかを判断する」という役割を担っています。
履歴書や職務経歴書からもある程度の人材像は把握できますが、記載内容の正否や人となりなどは、実際に話してみないとわからないものです。そういった、対面しないと判断できない要素を面接の場で深掘りすることが、面接官の大切な役割だといえます。採用のミスマッチを避けるためにも、「この人は自社で活躍できるだろうか」「既存社員との関係を構築できるだろうか」といったポイントをしっかりと見極めましょう。
なお、近年では見極めだけではなく、転職希望者に対する動機づけや、入社の意思決定のためのフォローなども面接官の役割として定着しつつあります。
また、転職希望者側は面接を通じて「この会社で良いのだろうか」と判断しています。従って、面接の段階から動機づけしておくことが非常に重要なのです。また、転職希望者が何か疑問点や不安な点を抱いているようであれば、親身になって解消してあげることも、面接官の対応としては欠かせません。
(参考:『【人材紹介サービスのプロに聞く】採用候補者の入社意向の高め方。面接前後に“見落としがち”なポイント解説』)
自社をアピールするための「会社の顔」
面接官には、自社の「顔」として転職希望者に接して、魅力づけを行うという役割もあります。
転職希望者が最初に関わる自社の関係者は、ほとんどの場合で面接官となるはずです。そして面接官の印象が、そのまま転職希望者にとっての「会社の印象」となります。「この会社の対応は良かったな」と転職希望者に思ってもらうためにも、会社の代表としての意識を持ち、丁寧な言動・振る舞いで面接に臨むことを心がけましょう。そこで良い印象を与えられれば、たとえ入社につながらなかったとしても、採用ブランディングとしては成功したといえます。
また、自社で働くメリットや他社にはない魅力をアピールして、転職希望者の入社意欲を高めることも大切です。例えば、キャリアプランや入社後の具体的な働き方を伝えられれば、「この会社でならこんなふうに働けそうだ」という前向きなイメージを引き出せます。こうした魅力づけは、一方的にではなく対話からの自然な流れで行うほうが効果的なので、面接の際に意識すると良いでしょう。
(参考:『面接は「見極め」だけじゃダメ!選ばれるための「魅力付け面接」メソッド ~初級編~』)
面接官が意識するべきこと
面接官としての役割を全うする上では、以下の4つの点を意識する必要があります。
会社の採用基準を明確に理解する
転職希望者と対面する前に、必ず自社の採用基準を理解しておきましょう。面接官の採用基準が会社とずれていると、採用のミスマッチが発生し、選考辞退や早期退職などを引き起こしてしまうためです。
会社の基準と同じ目線で人材を評価するためにも、評価項目や基準、また項目ごとの優先順位などを確認しておく必要があります。また、もし自社内で画一的な採用基準が定まっていないのであれば、まずはそこから設定しなくてはなりません。人材に求める要件や予算、スケジュール、また、転職市場の動向などを踏まえて、最適な採用基準を設けられると理想的です。
(参考:『採用基準とは?具体的な設定手順や自社にマッチした人材の見極め方|テンプレ付』)
転職希望者の目線になって本音を引き出す
転職希望者の本音を引き出せないと、自社に合っているかどうかをきちんと判断できません。そのため、面接官が転職希望者と同じ目線になり、良好な関係を築いてから面接を進める必要があります。
同じ目線になって会話を進めれば、転職希望者の緊張が解けて、その人本来の考え方や振る舞い方が少しずつ見えてくるはずです。そういった部分を深掘りできれば「困難な状況でどのように対応するか」「ほかの社員とどのように関わりそうか」などのポイントを見極められます。
(参考:『自社が求める人材の見抜き方・引き付け方はどうしたらいい?人材採用のための面接力向上術』)
選ばれる側であることも自覚する
採用面接は、企業が転職希望者を評価する場でもある一方で、転職希望者が「ここは自分に合っているだろうか」と企業を見定めるタイミングでもあります。この意識を持って面接に臨むことも、面接官としての大切な心構えです。
転職希望者に自社を高く評価してもらうためにも、言動や身だしなみに注意を払い、会社の顔としてふさわしい立ち居振る舞いでいることを徹底しましょう。また、先ほども伝えた通り、自社の魅力をアピールすることも重要です。
こうしたアピールポイントについては、面接官ごとにぶれが出ないように、社内で認識を統一しておかなくてはなりません。以下のフォーマットを利用すれば自社の魅力や訴求部分を画一的に整理できるので、関係者間で認識をすり合わせる際はぜひご活用ください。
バイアスにとらわれないように注意する
面接では、「この相手はこういうタイプだろう」とバイアスにとらわれてしまうことも少なくありません。そうしたバイアスが自身の中にもあることを認識した上で、客観的に評価しようとする姿勢も面接官には求められます。
バイアスには以下の通りいくつかの種類があり、それぞれ内容が異なります。
バイアスの種類と内容
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 確証バイアス | 第一印象に引きずられて、それを裏づける情報ばかり重視してしまうこと |
| ステレオタイプ | 学歴や性別、年齢などの属性による先入観で相手を評価してしまうこと |
| 類似性バイアス | 自身と共通点がある人物を無意識のうちに高く評価してしまうこと |
それぞれの特徴を理解し、どのような状況で発生し得るのかを把握することが、客観的な視点を持つためのポイントです。
(参考:『その判断軸、間違ってます!面接官がやりがちアンコンシャス・バイアス<お役立ち資料付き>』)
面接の理想的な進め方
ここからは、採用面接の理想的な進め方を、以下の8つのステップに分けて解説していきます。
【採用面接の8つのステップ】
①自己紹介・アイスブレイク
②自社の概要や業務内容の説明
③履歴書・職務経歴書の確認
④転職希望者の自己PRの確認
⑤転職希望者に対する質問
⑥転職希望者からの質問の確認
⑦事務的な要件の確認
⑧クロージング
各ステップで重要となる点を把握できれば、企業と転職希望者の双方にとって有意義な、質の高い面接を行えるでしょう。
①自己紹介・アイスブレイク
自社の説明や本格的な質疑応答へと入る前に、まずは来社していただいたことに感謝の意を示した上で、自己紹介を行います。この際は、自身の社内でのポジション(人事・採用担当者なのか、配属先の社員なのか)を中心に自己紹介することをおすすめします。相手の立ち位置を把握できれば、話すべき内容・聞くべき内容の軸が転職希望者の中で定まり、その後のコミュニケーションがスムーズになるためです。
自己紹介の後は、転職希望者の緊張をほぐすためにもアイスブレイクを実施しましょう。アイスブレイクに適した話題としては、面接とは関係ない、その日の天気や直近のニュースといった内容が挙げられます。
ただし、このタイミングから転職希望者の意向醸成を図るのであれば、仕事の内容を少し絡めて話しても良いでしょう。とは言え、あまりにも本筋に踏み込んだ内容だと、転職希望者を余計に緊張させてしまうかもしれません。主目的はあくまでも「話しやすい雰囲気づくり」であることを念頭に置き、適切なラインで話題を振れると理想的です。
(参考:『【面接官必見!】知らないと失敗しちゃうかも?有意義な面接のためのアイスブレイクとは~質問例付き~』、『良かれと思ったアイスブレイクが逆効果!?応募者の本音を引き出す面接テクニック』)
②自社の概要や業務内容の説明
アイスブレイクが済んだ後は、自社の企業概要や事業内容、また転職希望者に任せることとなる業務内容などを説明します。募集要項で詳細に記載しているかもしれませんが、このタイミングで改めて説明することで、採用のミスマッチが生じる可能性を減らせるかもしれません。
説明を終えた段階で「認識と違う点はございますか?」と確認し、特に問題がなさそうであれば次のステップに進みます。
③履歴書・職務経歴書の確認
ここから、採用面接の本題へと入っていきます。履歴書や職務経歴書の内容を基に質問・事実確認を行います。ごくまれではありますが、記載内容に誇張や虚偽があるケースも存在するため、口頭で詳細を確認することが大切です。
また、履歴書・職務経歴書の確認には、経験やスキルの有無を確かめるという意味合いもあります。特に、転職希望者が具体的に語れる内容は、ノウハウがしっかりと身に付いている部分だと思われます。そういった箇所をいくつかピックアップしておけば、この後のステップで一歩踏み込んだ質問を投げかけられるので、気になったポイントはメモしておきましょう。
④転職希望者の自己PRの確認
転職希望者の自己PRでは、まず本人の意欲や志望度の高さを確認します。その上で、自身のキャリアや強みを理路整然と話せているかどうか、という点も確認したいところです。筋道立てて自身の強みを話せる人材は、実際の業務でトラブルに直面した際も、冷静に対応できる見込みがあります。
なお、自己PRという明確なステップを設けずに、ここまでの話の中であわせて確認するという形式を取っても問題ありません。自己紹介の際にそのまま自己PRを行ってもらうパターンもあるので、自社の採用活動の方針に合った形式を選びましょう。
⑤転職希望者に対する質問
こちらからの質問ステップでは、人材の適性を深掘りできるかどうかが最も重要なポイントとなります。そのため、考え方や行動の軸、また仕事で大切にしていることなどについては、優先的に尋ねたいところです。
また、入社した後の具体的な目標や働き方に関して質問すれば、自社業務の理解度や実際の志望度も測れます。ここで明確なビジョンを語れるのであれば、自社での活躍が期待できる人材だと考えて良いでしょう。
「そういった観点を確認したいけれども、具体的な質問事項が思い浮かばない…」とお悩みであれば、ぜひ以下の面接質問例一覧をご活用ください。面接でそのまま使える質問例が職種ごとにまとめられているので、質問を準備する時間を大幅に削減できます。
⑥転職希望者からの質問の確認
こちらからの質問をひと通り聞き終えたら、今度は転職希望者からの逆質問を確認します。このステップで転職希望者の不安や懸念点を払拭できれば、「この会社で働きたい」という意欲を高められます。
また、転職希望者が臆せず質問できるように、話しやすい雰囲気をつくることも心がけましょう。転職希望者からの質問を確認し、認識の相違が生じている箇所を把握できれば、採用のミスマッチによる選考辞退や早期退職を防げます。
⑦事務的な要件の確認
面接を終える前に、実際に働くことになった場合の事務的な要件を確認しておきましょう。ここで確認すべき内容としては、以下が挙げられます。
【面接で確認すべき事務的な要件】
●入社予定日
●勤務体制・シフト
●給与面
入社が決まってから上記の内容ですれ違いが発生すると、その後の関係にも悪影響を与えてしまいます。予期せぬトラブルを防ぐためにも、このタイミングで再度認識をすり合わせておくべきでしょう。
また、他社への応募状況や選考状況の確認も非常に重要です。特に自社にマッチしている人材に関しては、他社の選考が進んでいるなら、こちらの選考スケジュールも早めたいところです。
⑧クロージング
全ての対応が完了したら、面接のクロージングを行います。今後の選考予定、または合否連絡の手段やスケジュール感を伝えた上で、転職希望者からの質問がなければ本日参加のお礼を伝えた上で、退室のお見送りをします。良い印象を持ったまま転職希望者に退室してもらうためにも、会社の顔としてふさわしい言動・振る舞いを最後まで徹底しましょう。
お見送り後は、転職希望者に対する所感や、自社に合う・合わないなどの判断を評価として整理します。なお、面接の結果が良かったのであれば、迅速に転職希望者へ伝えることを徹底してください。連絡が遅れると、その間に転職希望者が他社への入社を決めてしまうかもしれません。中途採用では、選考期間を可能な限り短縮することが非常に大切です。
(参考:『面接官必見!一見好印象でも“要注意”な回答例と見極め・深掘りポイント』)
今日から使える質問マニュアル
質問事項を事前にしっかりと準備できていれば、採用面接が成功する可能性は一層高まります。以下に、面接の各タイミングでそのまま使える質問例をご用意したので、ぜひ参考にしてください。
(参考:『面接官の質問55選!本音を引き出すポイントと注意点【面接質問シート付】』)
アイスブレイク
先ほどもお伝えした通り、アイスブレイクでは転職希望者の緊張をほぐすことが最優先事項となります。そのため、基本的には以下のような、誰でも答えやすい質問を準備しておくべきでしょう。
【アイスブレイクでの質問例】
●今日はどのような手段で会場までいらっしゃったのですか?
●急に寒くなってきましたが、ご体調はいかがでしょう?
●旅行が趣味と書いてあったのですが、実は私も旅行が好きなんです。
●気になることは何でも聞いてもらって大丈夫なので、ぜひいつでも質問してください。
質問を一方的に投げかけるだけではなく、自然と会話のキャッチボールが成立するように話を進められると理想的です。なお、面接の目的や転職希望者のタイプによっては、この段階で自社の事業や業務内容に関連する質問をしても問題ありません。
(参考:『【面接官必見!】知らないと失敗しちゃうかも?有意義な面接のためのアイスブレイクとは~質問例付き~』)
経歴やスキル
履歴書や職務経歴書を確認する際は、以下の質問でそれまでの経験や培ってきたスキルについて掘り下げます。
【経歴やスキルに関する質問例】
●○○の業務には何年ほど携わっていましたか?
●前職ではどのようなポジションで働かれていましたか?
●前職を退職された(退職しようと思った)きっかけは何でしょうか?
●トラブルに直面されたとき、どのように対処されましたか?
●○○のスキルを用いて取り組んだ事業やプロジェクトについて、可能な範囲でよいので教えてください。
なお経歴を尋ねる際は、前職を退職した(退職しようとしている)理由も確認することをおすすめします。退職理由には、転職希望者の本音が反映されやすいためです。ただし、「なぜ辞めたのか?」ばかりを深掘りすると、圧迫面接と捉えられてしまう可能性もあります。転職希望者の雰囲気や様子に応じて、質問内容を柔軟に変えることを意識しましょう。
志望動機や入社後のキャリアビジョン
転職希望者と自社の相性を確認する上で、志望動機を深掘りする質問は必要不可欠です。「自社についてどこまで把握しているのか」「本当に入社したいのか」といったポイントを、以下の質問でチェックしていきましょう。その際は、入社後の具体的なキャリアビジョンについても尋ねておきたいところです。
【志望動機やキャリアビジョンに関する質問例】
●弊社の求人に応募しようと思ったきっかけは何でしょうか?
●ほかの会社ではなく弊社を志望されている理由をお聞かせください。
●弊社のどこに魅力や強みを感じたのかお聞かせください。
●実際に入社したら、どのように活躍されたいですか?
●入社後3年で達成したい目標や、目指したいポジションなどがあればお聞かせください。
これらの質問に対して具体的に返答できる転職希望者は、入社意欲が高く、活躍も見込めると考えられます。
価値観や転職時に重視するポイント
経験・スキルの有無や志望度の高さだけをヒアリングしていると、雰囲気や労働条件の面でのミスマッチを見落としてしまいがちです。選考辞退や早期退職の可能性を減らすためにも、仕事に対する価値観や、転職活動で重視していることなども聞いておきましょう。
【価値観や転職時に重視するポイントに関する質問例】
●仕事をする上で一番大切だと考えていることは何でしょうか?
●ご自身が活躍できると思う職場とは、どのようなところでしょうか?
●今まさに転職活動中だと思いますが、会社を選ぶ際は何を重視されていますか?
●複数の会社で採用が決まった場合、何を基準に入社先を判断されますか?
●可能であれば、前職(現職)の給与額をお聞かせください。
これらの質問に対して本心で答えてもらうためには、やはり良好な関係の構築と話しやすい雰囲気づくりが欠かせません。アイスブレイクのタイミングのみならず、面接全体を通して物腰柔らかな雰囲気で臨むことが非常に大切なのです。
人間性や関係性に対する考え
価値観のほかには、人間性の部分や周囲との関わり方に対する考えなども、自社への適性を測る判断材料となり得ます。これらのポイントを確認する際に有用な質問は、以下の通りです。
【人間性や関係性に関する質問例】
●周囲の方からはどのような人だと言われることが多いですか?
●ご自身の長所・短所をそれぞれ挙げてください。
●職場でコミュニケーションを取る際は、何を大切にされていますか?
●チームで一つの仕事に取り組む際に、心がけていることや気をつけていることはありますか?
●チームを組む際はどのような役割になることが多いですか?
コミュニケーション力や協調性を確認する際は、上記の質問とともに前職での具体的なエピソードなども聞けるとより理想的です。
ストレス耐性
どのような経歴の人材であっても、環境が変われば多少なりともストレスがかかるものです。特に、それまでに経験のない業務や重要なポジションを任されるケースでは、より大きなストレスが生じるかもしれません。そのため、転職希望者のストレスに対する向き合い方も、しっかりと確認しておく必要があります。
【ストレスに関する質問例】
●どのような瞬間にストレスを感じますか?
●ストレスを感じたときの対象方法があればお聞かせください。
●これまでの経験の中で大きな挫折をしたことはありますか?また、それをどのように乗り越えましたか?
ただし、ストレスに関する話題ばかり深掘りすると「この会社でやっていけるだろうか」と不安を抱かせてしまうため、質問内容のバランスには気をつけましょう。
(参考:『ストレス耐性を面接で見極めるポイントとは?質問例や注意点を解説』)
こちらへの質問の確認
こちらから自然な流れで疑問点や不明点の有無を尋ねられれば、転職希望者としても質問しやすいはずです。以下の質問例を活用して、転職希望者に逆質問を促しましょう。
【こちらへの質問を確認する際の質問例】
●本日の説明で何か不明な点などはございましたか?
●実際の業務内容や職場の雰囲気に関してまだイメージできていなかったら、ぜひご質問ください。
●最後に伝えておきたいことや、アピールしておきたいことなどはありますか?
質問の内容次第ではネガティブな回答を避けられないかもしれませんが、そこでごまかすのではなく、正直に答える方が良い印象を与えられます。「○○はできませんが△△なら可能です」というように、別のポイントでカバーできるとなお良いでしょう。
さらに多くの質問例を準備しておきたいのであれば、以下の「面接でのチェックポイント・質問例」の利用をおすすめします。職務経歴書と年代の組み合わせでパターン化されているので、転職希望者の属性に合わせて質問を準備できます。
このほかにもさまざまなタイプの質問サンプル資料がダウンロードできますので、採用の目的に合わせてそれぞれご活用ください。
転職希望者に聞いてはならないNG質問
面接官として面接に臨む際は、職業差別につながる「聞いてはならない質問」の存在を事前に把握しておかなくてはなりません。以下で該当する質問例を解説しているので、面接予定の有無にかかわらず人事・採用担当者は一度ご確認ください。
なお、ここで解説するNG質問以外にも、選考や採用面接でやってはならない対応がいくつか存在します。以下の資料を用いれば、自社の選考プロセスにある問題点を3ステップで洗い出せるので、採用活動を始める前にチェックしましょう。
本人に責任のない事項
本人に責任のない以下の事項に関しては、面接で質問してはなりません。知らずに尋ねてしまうと問題に発展する恐れがあるので、面接の前に質問事項を洗い出して、該当する内容がないか確認することをおすすめします。
【本人に責任のない事項の内容】
●本籍や出生地に関すること
●家族に関すること(職業や続柄、健康、病歴、地位、学歴、収入、資産など)
●住宅状況に関すること(間取りや部屋数、住宅の種類、近隣の施設など)
●生活環境や家庭環境などに関すること
例えば、「お父様・お母様はどのようなお仕事をされていますか?」「今のお住まいは一軒家ですか?」といった質問は、上記の事項に該当します。自己紹介やアイスブレイクの流れで自然と聞いてしまう可能性もあるので、注意しましょう。
(参照:厚生労働省『公正な採用選考の基本』)
思想や信条など自由であるべき事項
思想や信条に関わることや、政治・宗教などに関連する事項も、聞いてはならない質問に該当します。これらは、誰であっても制限されてはならない事項であるためです。
【本来自由であるべき事項の内容】
●宗教に関すること
●支持政党に関すること
●人生観や生活信条などに関すること
●尊敬する人物に関すること
●思想に関すること
●労働組合(加入状況や活動歴など)、学生運動などの社会運動に関すること
●購読新聞・雑誌・愛読書などに関すること
「何か宗教を信仰されていますか?」「政治活動についてどう思われますか?」といった内容は当然上記に該当するため、面接で質問してはなりません。「どこの新聞を取っていますか?」などは、最近のニュースの話などからつながってしまうかもしれないため、話題の選び方や話の進め方にも気をつけたいところです。
ほかにも、結婚・育児や配偶者、本人の容姿、年齢などが、差別につながりかねない話題として挙げられます。「この質問なら大丈夫だろう」と個人で判断するのではなく、会社全体で取り上げて良い話題・悪い話題を整理することが、最適な対応だといえます。
(参照:厚生労働省『公正な採用選考の基本』)
(参考:『面接で聞いてはいけない質問・会話のNG行為とは?リスク回避のための具体的な対策』)
面接の際に取るべきではない行動
面接官が気をつけなければならないのは、質問の内容だけではありません。面接を受ける転職希望者が不快感を抱かないよう、以下の行動は慎んでください。
面接の際に取るべきではない行動
| NG行動 | ポイント |
|---|---|
| 威圧感のある態度 | 面接官と転職希望者の間に上下関係はない |
| フレンドリーすぎる態度 | 砕けすぎた態度も失礼に当たる |
| 資料の確認不足 | 履歴書や職務経歴書は、事前に読み込んでおく |
| 企業側の一方的な質問 | 一問一答ではなく、会話のキャッチボールを意識する |
| あいまいな回答 | 転職希望者からの質問に即答できない場合は保留とし、後日回答する |
面接官の言動は、こちらが思っている以上に転職希望者の印象に残ります。不適切な行動を取ってしまうと、転職希望者に選考を辞退されるほか、企業の悪い口コミが広がる恐れもあります。
面接の場では、質問内容とあわせて些細な振る舞いにも注意したいところです。
面接官が事前に準備すべきこと
面接を成功させるためには、転職希望者が時間をかけて面接対策をするように、企業側も入念に準備する必要があります。ここからは、自社に適した人材を採用するために欠かせない3つの事前準備を紹介します。
質問事項を洗い出す
まずは、面接で転職希望者に投げかける質問事項を準備しましょう。質問を準備していない状態で無計画に臨めば、転職希望者の考え方や行動特性などを深掘りできず、適性を判断することが難しくなります。
また、質問に詰まって会話が途切れると、転職希望者を不安にさせてしまいます。事前に送付された履歴書や職務経歴書がある場合は、面接までに目を通しておき、ある程度質問リストを作成しておけると理想的です。
面接のトレーニングを行う
本番を想定した面接のトレーニングも有意義です。具体的には、複数人でロールプレイングを実施するのがおすすめです。面接官役と転職希望者役を交互に演じ、用意した質問リストに過不足がないかを確認してください。
ロールプレイングの後は、転職希望者役から面接官役にフィードバックを行うことで、面接での振る舞いがブラッシュアップされるはずです。このようなトレーニングを重ねることは、本番での緊張の緩和や、企業としての面接スキルの向上につながります。
(参考:『採用を成功に導く面接官の5つのトレーニング方法と実施するメリット』)
評価シートを作成する
面接官が複数人いる場合、評価シートの作成が効果的です。面接官の主観によって採用基準がぶれないよう、評価項目をピックアップしておきましょう。
評価シートの作成に当たっては、採用したい人材の明確化が欠かせません。自社が求める人材像を具体的に設定し、それを判断するためのポイントを抽出してください。
また、評価シートの作成後も、面接を受ける転職希望者の傾向や価値観は変化するため、定期的に見直すことが大切です。このように、評価シートは公平な面接を実施したいときに役立ちます。
(参考:『【無料テンプレ有】面接評価シートとは?導入のメリットや書き方のポイント』)
自社に合った転職希望者を選ぶためのポイント
続いて、自社に適している転職希望者を選ぶために、面接の本番で心がけたいポイントを解説します。
自社の採用基準に即した質問を準備する
先ほどの事前準備の説明でもお伝えした通り、採用基準に則した質問を用意しておくことは大切です。採用基準を設定する際に優先順位を決めておけば、自ずと面接で聞くべき質問が浮かび上がってきます。
面接では、限られた時間の中で採用の判断材料となる回答を、可能な限り引き出さなければなりません。「基礎的な質問に時間を割いた結果、核心に迫る質問にたどり着かなかった」という事態に陥らないよう、時間配分にも注意しましょう。
質問の形式を使い分ける
質問の形式を使い分けながら、面接を進めることも効果的です。
イエスかノーで答えられる「クローズドクエスチョン」では、転職希望者の即断力や基本的な考え方を把握できます。例えば、業務経験の有無や、特定のスキルを保有しているかどうかといった質問に対し、明確な回答が得られます。一方「オープンクエスチョン」は転職希望者に自由度の高い回答を促し、その人ならではの視点や経験、価値観を引き出す有効な手段です。転職希望者自身が語るエピソードや背景には、書類からは読み取れない個性や問題解決力、柔軟な思考が隠れていることが多いため、幅広い情報を収集できます。
両者の質問形式を戦略的に使い分けることで、表面的な情報に加え、転職希望者の内面に迫れるようになるのです。
質問を深掘りする
面接がある程度進んだら、転職希望者が話したいくつかのエピソードに焦点を当て、その詳細を徹底的に掘り下げていきましょう。「どうしてそのように行動したのか?」「同じ状況になったらどう改善するか?」といった深掘り質問によって、転職希望者の具体的なスキルや仕事への向き合い方が理解しやすくなります。
また、突発的な問いかけに対する転職希望者の反応を観察することで、冷静さや適応力といった資質もあわせて評価できます。
(参考:『初めての面接官でも応募者を掘り下げられる!STAR面接ノウハウ ~やりがちな面接失敗行動付き~』)
書類の情報だけで判断しない
エントリーシートや履歴書といった書類は、転職希望者の基本的な情報や経歴を把握する上で有用ですが、そこに記された内容だけでは判断しきれない部分も多々存在します。書類では表現しきれないコミュニケーション能力や対人スキル、さらには柔軟な問題解決力は、実際の対話の中で初めて見えてくることがほとんどです。
そのため、面接では書類の内容を出発点としながらも、やりとりの中で「企業にとって本当に必要な資質を持った人材であるか」を見極めることが重要です。
オンライン面接を実施する際の注意点
最後に、近年導入する企業が増えている「オンライン面接」でのポイントを紹介します。
オンライン面接は、遠方に住んでいる方や現職が忙しい方でも日程を調整しやすいため、導入によって応募数の増加が期待できます。より多くの人材と面接を実施したいのであれば、以下のポイントを押さえた上で導入すると良いでしょう。
通信環境を整備する
オンライン面接を実施する上で必須となるのが、安定したインターネット接続です。面接前には接続テストを行い、Wi-Fiや有線LANの設定を確認しましょう。接続トラブルに備えて、スマートフォンのテザリングなど、予備の通信手段を用意しておくと安心です。
また、面接中は不要なアプリケーションを閉じ、ネットワークの負荷を軽減することも重要です。これにより、接続トラブルを未然に防ぎ、スムーズなコミュニケーションが取りやすくなります。
カメラの位置を調整する
転職希望者からの見え方を考慮して、カメラの位置も調整しておきたいところです。面接の際は、こちらの目線と同じ高さにカメラを設置することが望まれます。カメラが目線よりも下に位置していると、相手に高圧的な印象を与えてしまいます。
事前に自分の映り方を確認し、適切な角度や距離を調整することで、安心して面接に臨めるはずです。
音声トラブルの有無を確認する
オンライン面接では相手の様子がわかりづらいため、映像や音声に問題が生じていることに気づかず、話し続けてしまう場合があります。
事前にマイクやイヤホン、ヘッドセットの動作確認を行うのはもちろんですが、面接中もこまめに様子をうかがいながら進行するのが良いでしょう。こちらが一方的に話すのではなく、面接希望者と会話をキャッチボールすることで、トラブルが起こった際にすぐに気づくことができるのです。
身ぶり手ぶりを使って反応する
繰り返しになりますが、オンライン面接では対面の場合と比べて、相手の表情や雰囲気が読み取りにくいところがあります。このため、声のトーンだけでは伝わりきらない微妙なニュアンスを表現したいときは、身ぶり手ぶりを活用することがおすすめです。
転職希望者の話を聞く際も、相づちや手を使ったリアクションを取れば、しっかりと受け止めていることを示すと同時に、親しみやすい雰囲気づくりもかないます。
(参考:『オンライン面接を徹底解明!メリット・デメリットや導入にあたっての注意点』)
面接官としての役目を理解し、適切な準備をすることが採用面接の成功につながる
今回は、面接官が意識すべきことや面接の進め方、またすぐに使える質問マニュアルなどを紹介しました。
転職希望者の考え方や振る舞い方をしっかりと深掘りすることが、採用面接の主要な目的です。その実現のためにも、転職希望者の属性や特徴に合った質問事項を事前に準備しておきましょう。また、質問してはならないこと・取るべきではない行動もあるので、そちらも必ず把握しておく必要があります。
「中途採用の面接がうまくいかない…」とお悩みであれば、中途採用の総合的な支援を行っている『doda』にご相談ください。採用面接についてのお悩みだけではなく、そのほかの課題に関しても適切な改善策をご提案いたします。
(制作協力/株式会社eclore、編集/d’s JOURNAL編集部)
採用目的別でわかる面接質問例サンプルシート【Excel版】
資料をダウンロード