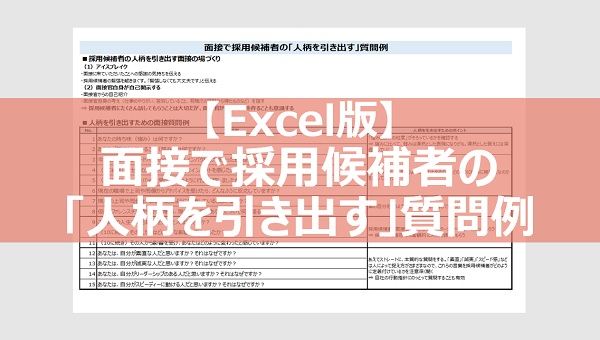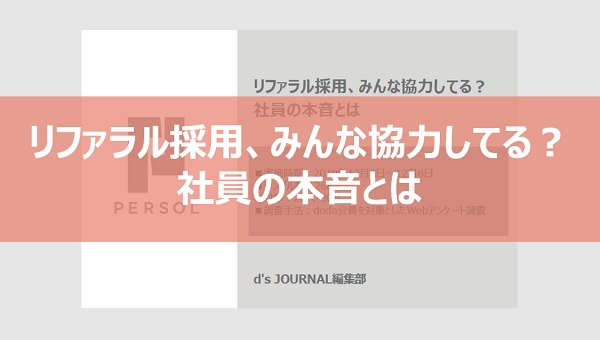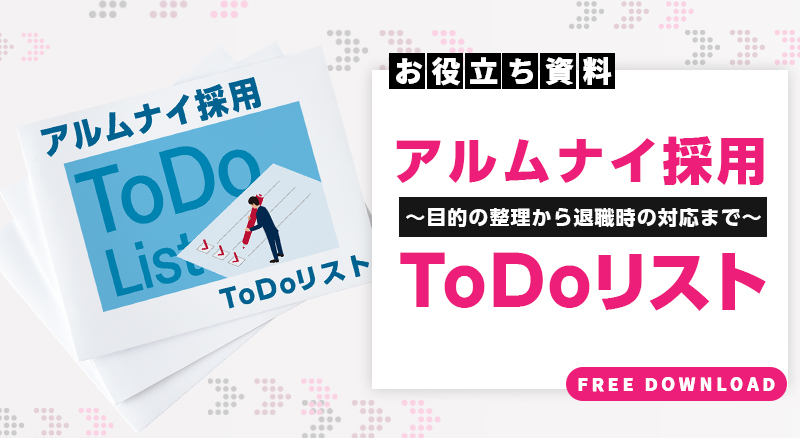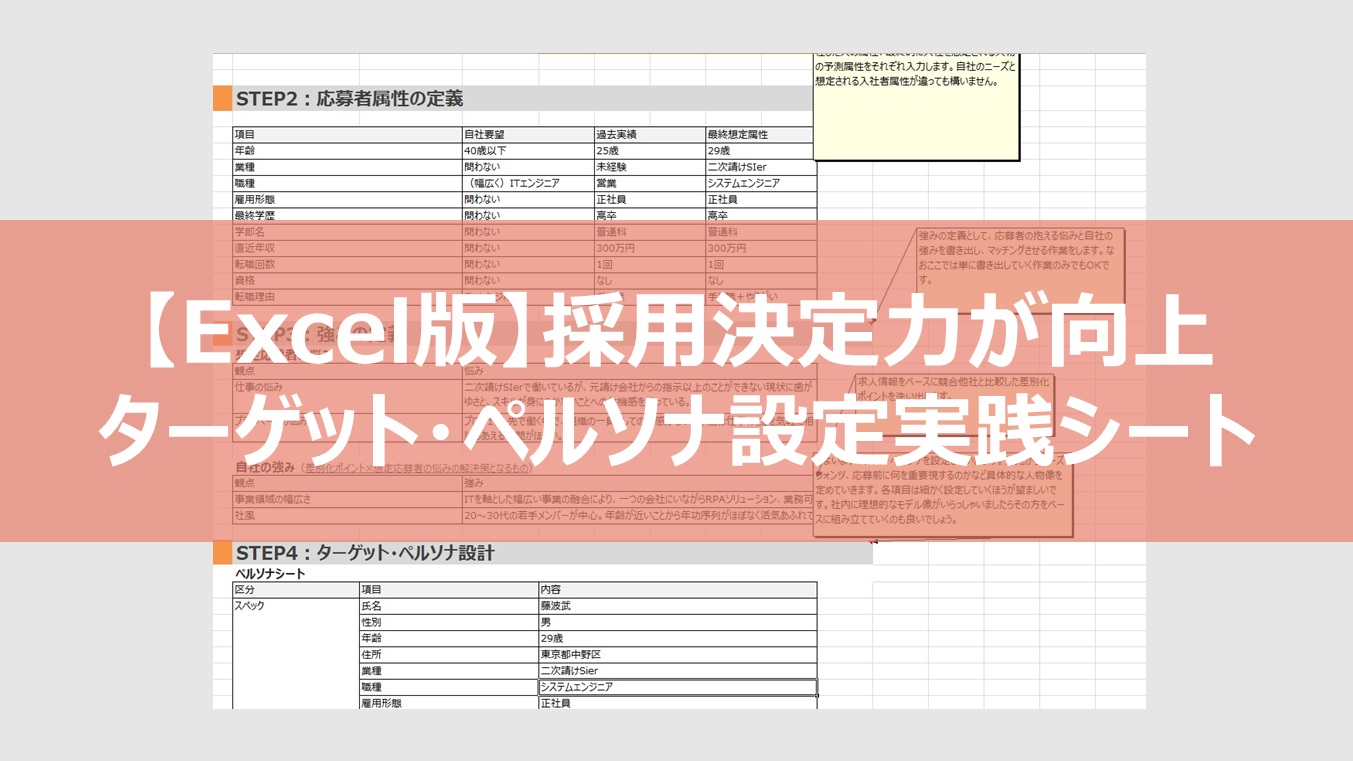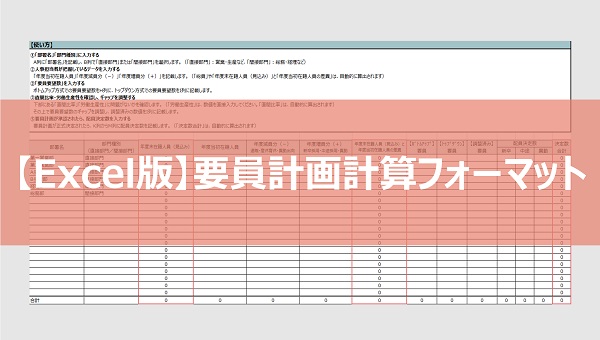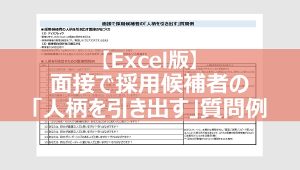人柄重視(人物重視)の採用手法とは? 面接の質問例や人柄を見極める方法を解説
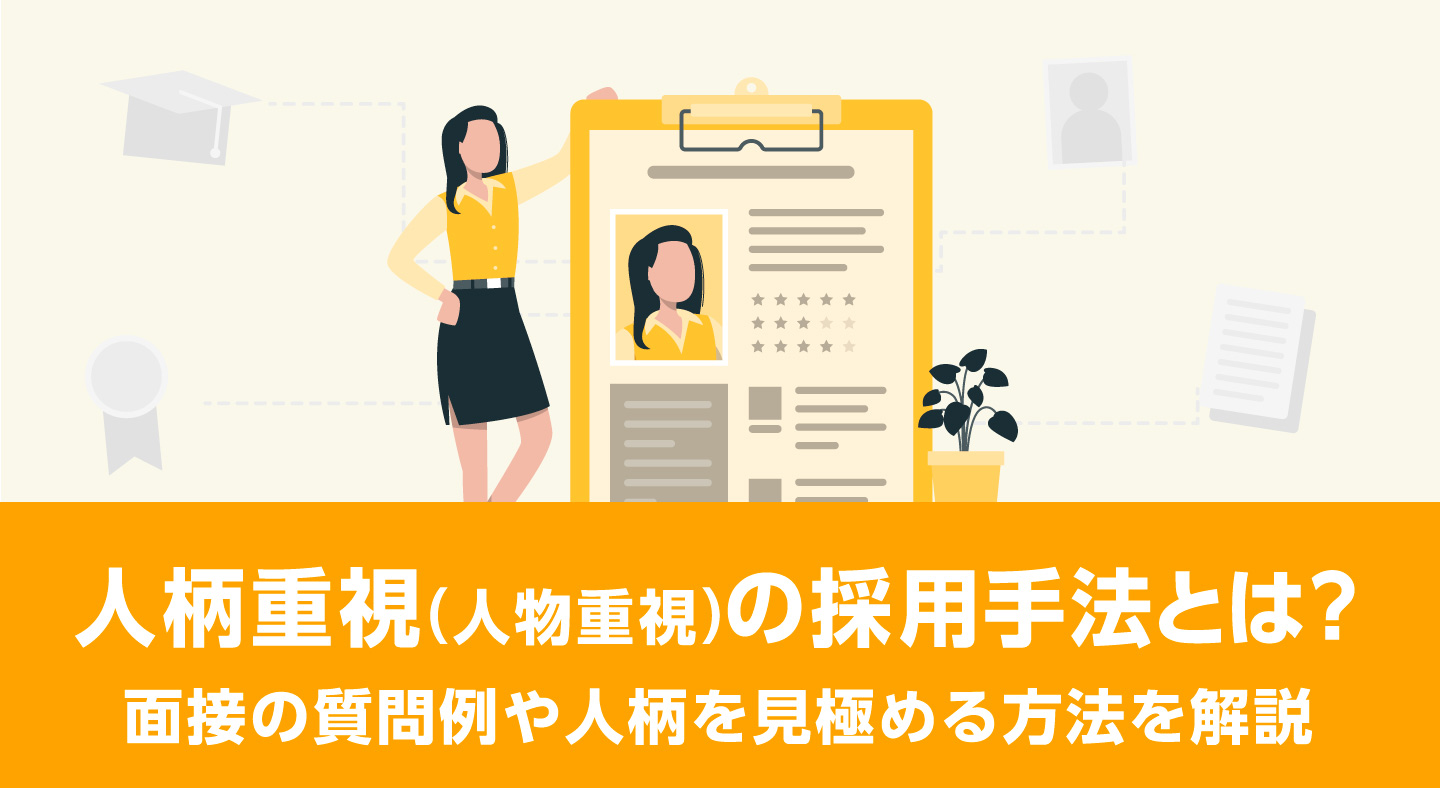

d’s JOURNAL編集部
新たに採用した人材が、入社後のギャップから早期退職につながるケースは、企業としては避けたいところです。長期的に活躍してくれる人材を採用するには、転職希望者の人柄の適切な見極めが欠かせません。
そこで本記事では、多くの企業が重視している人柄重視(人物重視)の採用手法について詳しく解説します。取り入れるメリットや面接時の質問内容などもご紹介しますので、人柄重視の採用を検討されている企業は参考にしてください。
面接で人柄を引き出す方法や具体的な質問を知りたい方は、下記資料を無料ダウンロードしてご活用ください。
人柄重視(人物重視)採用とは
人柄重視(人物重視)採用は、転職希望者の性格や価値観、考え方といった「人柄」に焦点を当て、選考を行う採用手法のことです。転職希望者のスキルや経験ではなく人柄を重視することで、企業の文化や雰囲気になじめる人材かどうかを見極めることに重きを置いている点が特徴です。
たとえ高いスキルや豊富な経験を持つ人材であっても、性格や考え方が自社に適していなければ早期退職につながる可能性があります。人柄重視の面接を取り入れることで、企業が求める人材の採用につながり、入社後のミスマッチを防げるのです。
ポテンシャル採用との違い
人柄重視採用と混同されやすい手法に「ポテンシャル採用」があります。ポテンシャル採用は、転職希望者の性格や考え方ではなく、潜在能力を評価基準とする採用手法であり、将来的に発揮される可能性のある、本人の能力に期待して採用を行います。
将来的な活躍が期待できる人材の採用が目的なので、若手の採用でよく用いられる方法です。
(参考:『ポテンシャル採用とは?導入のポイントとメリット・デメリットを紹介』)
多くの企業が人柄重視の採用を活用している理由
転職希望者の人柄を重視した採用手法を取り入れる理由は、企業によって異なります。以下で、よく見られる3つの理由をご紹介します。
長く勤めてくれる人材を採用したいから
数多くの転職希望者の中から時間をかけて採用した人材には、できるだけ長く働いてほしい、と考えるのはどの企業でも同じでしょう。しかし、上述の通りスキルや経験だけを重視した採用では、企業との価値観や考え方の違いによるミスマッチから、早期退職につながるリスクがあります。
採用面接で人柄を重視すると、自社の理念に共感できるか、また価値観が組織に合っているかどうかを見極められます。こうした見極めが早期退職のリスクを抑えることにつながるため、入社後の定着率向上に向けた有効な手立てとなるのです。
仕事に対して熱量が高い人材を採用したいから
たとえスキルや経験が十分でなくとも、仕事に対する熱量や意欲が高い人材であれば、会社にとってはプラスの要素となります。熱量の高い人材は、必要なスキルや能力を伸ばそうと仕事に前向きに取り組んでくれるためです。
また、社内に停滞感がある場合でも、意欲の高い人材の加入が新たな刺激となり、組織全体への良い影響が期待できます。
なお、こうした人材がスムーズに成長できるよう、企業側も教育体制をあらかじめ整えておかなければなりません。
社内の雰囲気に合う人材を採用したいから
同じ会社でも、職種やポジションによって求める人物像は異なるため、それぞれの雰囲気に合う人材を採用する必要があります。このような自社の文化や風土に合う人材を採用するには、「カルチャーフィット」を意識することが大切です。
カルチャーフィットとは、人材が企業独自の文化や風土になじんでいる状態のことを指します。選考に取り入れることで、企業の文化に転職希望者の価値観や考え方が合っているかどうかを判断する際の基準となるのです。
人柄重視でカルチャーフィットが十分な人材を採用できれば、入社後の雰囲気のミスマッチを防ぎ、早期退職のリスクの軽減につながるでしょう。
(参考:『カルチャーフィットとは?重要性と採用時の見極め方を解説』、『中途採用10人全員が退職したことも…。「他己紹介推薦文」必須!大都の徹底したカルチャーフィット採用戦略【連載 第15回 隣の気になる人事さん】』)
人柄重視の採用を行うメリット
続いて、人柄重視の採用で企業側がどのようなメリットを得られるのかを見ていきましょう。
メリット①母集団を形成しやすい
人柄重視の採用では、スキルや経験にこだわらずに選考を行うため、幅広い人材の応募が見込めます。このように、自社の求人に興味を持っている転職希望者全体の集まりを「母集団」と呼びます。
自社が求める人材を採用するためには、母集団の形成をどのように行うかが重要です。スキルや経験を重視しない求人は、実務経験がない人に「自分にもチャンスがある」と感じてもらいやすく、応募のハードルが低くなります。その結果、多様な人材からの応募につながり、結果として自社が求める人柄の人材を採用できる可能性が高まります。
(参考:『母集団形成とは?重要性と実践の手順、効果を上げるためのポイントを解説』)
メリット②活躍する人材の採用につながる
人柄を重視した面接で採用された人材には、長期的な活躍が期待できます。
スキルや経験を持った人材は、採用後に即戦力になり得るという点はメリットですが、人柄が社風にマッチしていなければ、早期退職のリスクは避けられません。一方、スキルや経験がなくとも、仕事に対する熱量や意欲が高い人材を採用できれば、自主的に学習してくれるので、早期の活躍が見込めます。
職種や業務内容を限定せずに、自社で活躍できる人材を採用したい場合には、「オープンポジション」での採用が有効です。オープンポジションは、募集する職種や業務内容を絞り込んでから求人を行う一般的な方法とは異なり、選考を進めていく中でポジションを決めていく方法です。
人柄重視の採用では、オープンポジションで転職潜在層にアプローチして、応募数の増加を目指してみるのもよいかもしれません。
(参考:『オープンポジションとは?メリット・デメリットや導入時のポイントを解説』)
メリット③ミスマッチが起こりにくく定着率が上がる
人柄を重視するという採用手法では、入社後のミスマッチを防いで定着率の向上が期待できます。企業の文化や風土に共感した上で働く環境であれば、居心地の良さから社員が長く働き続けやすくなるためです。
転職希望者の性格や考え方が既存の社員と合わない場合、早期退職につながるかもしれません。人柄重視の面接時にこれらのリスクを見極められると、定着率向上だけでなく、退職に伴う人手不足や新たな採用活動の負担の軽減にもつながります。
(参考:『ミスマッチとは?新卒・ミスマッチが起こる原因は?企業に与える影響と対応方法を紹介』)
メリット④組織力・エンゲージメントの向上が期待できる
企業が求める人柄の人材を採用できると、組織力やエンゲージメントの向上にもつながります。
意欲の高い人材は、自身に必要なスキルや知識を主体的に学び、早い段階で吸収します。その姿勢が既存の社員への良い刺激となり、組織力の向上につながる可能性があるのです。
また、企業の理念や文化に共感して入社した人材は、おのずとエンゲージメントが高まりやすく、既存の社員のパフォーマンスにも良い影響を与えます。その結果として、組織全体の生産性の躍進にも期待が持てるでしょう。
人柄重視の採用を行うデメリット
さまざまなメリットがある人柄重視の採用ですが、一方で注意すべきデメリットも存在します。導入した際に、「思ったような成果が得られなかった」という事態を避けるためにも、以下でご紹介するデメリットを押さえておきましょう。
デメリット①人柄を見極めることが難しい
「人柄を重視する」といっても、それを見極めることは簡単ではありません。面接官は、履歴書や職務経歴書などの情報を前提に、短時間の面接で転職希望者の人柄を理解する必要があります。
面接では、転職希望者はもちろん面接官も緊張するものです。そのため、転職希望者は本来の自分を出しきれないまま終わってしまう、また面接官側も転職希望者の人柄を見極めるための適切な質問ができない可能性があります。
スキルや経験は目に見えるものとして判断できますが、人柄の判断には正解がないため、転職希望者ごとの適切な判断が必要になります。
(参考:『面接官必見!一見好印象でも“要注意”な回答例と見極め・深掘りポイント』)
デメリット②認知バイアスの影響を受けやすい
転職希望者の人柄を適切に判断する上で注意すべき点が、「認知バイアス」です。
認知バイアスとは、物事を決定する際に固定概念や先入観などによって、無意識のうちに偏った判断をしてしまう心理的傾向のことです。例えば、転職希望者の外見だけで性格を決めつける、あるいは面接官本人と共通点があるということだけで優遇する、といった点が挙げられます。
認知バイアスは誰しも持ち得るものなので、面接官を含む人事・採用担当者は特に留意しておく必要があります。
デメリット③中長期的な育成が必要
人柄を重視する採用では、スキルや経験への優先度が下がるため、中長期的な育成に伴う費用の発生は避けられません。また、自社に合う人柄の人材を採用できたとしても、入社後の教育体制が整備されていなければ成長までに時間がかかり、生産性も落ちてしまいます。
人柄を優先的に考慮する採用では、育成にかかる費用や時間の目安を立てた上で、採用人数を決めておきましょう。
人柄を見極める採用手法とは
人柄を的確に見極めるためには、実際にどのような採用手法を取り入れるとよいのでしょうか。以下で、その具体的な手法について解説します。
リファラル採用
まず挙げられる手法は、自社に在籍している社員からの紹介によって人材を採用する「リファラル採用」です。社員の友人や知人であれば、転職希望者の人柄や性格を事前に把握した上で選考を進められるため、入社後のミスマッチを防ぎやすくなります。
しかしリファラル採用は、社員からの紹介がなければ成り立たないため、社員が「紹介したい」と思えるよう、自社の環境を整えておくことが欠かせません。
(参考:『リファラル採用とは?導入のメリット・デメリット、運用のポイントを紹介』、『失敗例から学ぶ!「リファラル採用」の意外な“落とし穴” ~解決ポイントも添えて~』)
アルムナイ採用
「アルムナイ採用」は、定年退職以外の理由で退職した社員を、再雇用する採用手法です。
お互いに人柄や企業の雰囲気を理解しているため、入社後のミスマッチが起こりにくいだけでなく、即戦力として活躍できる可能性も高い点が特徴です。また、実績の十分な人材であれば、教育にかかるリソースを抑えられる点も企業側のメリットといえるでしょう。
ただし、アルムナイ採用では、一度は退職している社員に「またこの会社で働きたい」と前向きに考えてもらえるような良好な関係性が前提となります。円満退職ではなく不満を募らせた状態で退職した社員に対するアプローチとしては、現実的ではありません。
(参考:『アルムナイとは?注目される理由とメリット・デメリットを解説』)
ソーシャルリクルーティング
SNSを活用して転職希望者とのコミュニケーションを図る「ソーシャルリクルーティング」でも、人柄を重視した採用が望めます。InstagramやX、TikTok、そしてFacebookといったSNSを通じて採用につなげる手法です。
SNSの投稿には投稿者の人柄が反映されているので、その内容が自社にマッチするかどうかを判断する材料となります。気になる人材がいれば、直接DMを送って連絡を取ることが可能です。
面接だけでは見極めが難しい転職希望者の人となりを把握でき、応募前の段階から人柄に触れられるため、入社後のミスマッチの防止にもつながります。
ミートアップ
ミートアップは、転職希望者との交流の場を設け、企業の魅力や雰囲気を直接伝えることで、人材の採用を目指す手法です。以下の3つの形式に分けられ、目的に応じて取り入れます。
ミートアップ採用の形式
●交流会型:カジュアルに意見交換する場
●勉強会型:企業主催の特定のテーマに関する勉強会
●説明会型:転職希望者に向けて、企業がビジョンや事業内容を説明する場
ミートアップは、あくまでも企業と転職希望者との交流が目的なので、通常の採用活動では出会えない転職潜在層の人材と接点を持てます。ミートアップを取り入れて転職希望者との交流の場を設けることで相互理解が高まり、自社が求める人材の採用につながりやすくなるでしょう。
(参考:『ミートアップとは?採用における役割や実施ステップを解説』)
適性検査(性格診断)の導入
人柄重視で人材を採用するなら、適性検査(性格診断)の導入も検討してみてはいかがでしょうか。
適性検査には、複数の企業が提供するサービスがあり、それぞれ測定できる内容や目的が異なります。一般的に適性検査の性格診断では、転職希望者の性格や行動特性を数値化することで、組織に対する適応性を測定できます。これらの結果が、自社が求める人材かどうかを見極める判断材料となり、採用の精度を高めることに役立つでしょう。
採用面接で人柄を見極める方法
ここからは、面接時に転職希望者の人柄や性格を見極めるにあたって、有効な3つの方法をご紹介します。
求める人物像を明確にする
人柄重視の採用面接を行う前に、採用したい人物像を含めた採用要件を明確に定めておきましょう。自社が求める人物像を明らかにすることで、その基準に沿って採用すべき人材かどうかを、面接時に的確に見極められます。
採用要件が定まっていないと、採用面接で見極めるべき基準の一貫性がなくなり、結果的に採用の精度が下がり、ミスマッチにつながるリスクが高まります。自社の理念や価値観、採用活動の目的などを踏まえて、自社が求める人物像を具体的に決めておく事前準備が重要です。
(参考:『採用ペルソナとは?設定ノウハウや手順・具体例をまとめて紹介【テンプレート付】』)
構造化面接を行う
構造化面接は、事前に決めた質問や評価基準を基に行う面接のことです。この方法であれば、質問内容が統一されるため、転職希望者ごとの判断基準があいまいになるリスクを防止できます。面接官にとっても、転職希望者の比較が容易になるため、自社が求める人柄の人材を見極めやすくなります。
人柄重視の面接では、カジュアルな会話から、その人材の中身を探ろうとしてしまうものです。しかし、行き当たりばったりの質問を繰り返していては、複数の転職希望者に対して一定の基準での評価ができません。
採用計画を立てる段階で適切な質問内容や評価基準を設け、公平かつ客観的な評価で、自社に合う人材の採用を目指しましょう。
(参考:『構造化面接とは?どんな質問をすべき?半構造化面接との違いやメリット・デメリットを解説』)
人柄がわかる質問を用意する
採用面接で人柄を見極めるためには、オープンクエスチョンの質問を用意した上で傾聴の姿勢にも気を配る必要があります。オープンクエスチョンとは、「はい」「いいえ」で答えられる質問ではなく、相手が自分の考えを自由に話せる形式の質問を指します。
以下に、実際に採用面接で使えるオープンクエスチョンの例文をまとめました。
採用面接で人柄を見極める際に役立つ質問内容
| 性格 | ●長所と短所を教えてください。 ●周りの人からどのような性格だと言われますか? |
|---|---|
| 価値観 | ●仕事で最も大切にしていることを教えてください。 ●モチベーションを維持する方法を教えてください。 |
| 熱量・意欲 | ●この会社で挑戦したいことはありますか? ●今後のキャリアプランを教えてください。 |
| 協調性 | ●チームでの仕事では、何が重要だと考えますか? ●チーム内で意見が衝突した場合、どのように行動しますか? |
| 責任感 | ●これまでに経験した大きな失敗と、そのときの対処法を教えてください。 ●学生時代や前職で、粘り強く取り組んだ経験を教えてください。 |
このようなオープンクエスチョンを活用して採用面接を進めることで、転職希望者の考え方や言葉遣い、態度といった側面を多角的に見極める手立てとなります。
(参考:『【質問例付】第二新卒・中途も“人柄重視”採用が拡大。採用候補者の“人柄を引き出す”面接官とは』、『面接官の質問55選!本音を引き出すポイントと注意点【面接質問シート付】』)
人柄重視の採用での注意点
最後に、人柄重視の採用を行うにあたって、注意しておきたい3つのポイントをご紹介します。
転職希望者が不満に感じる可能性がある
人柄重視の採用を掲げているにもかかわらず、「人柄重視ではない」と少しでも思われてしまうと、転職希望者に不信感を抱かれるかもしれません。
例えば、先述の構造化面接を取り入れる際には「本当に人柄を重視した質問になっているか」という視点で、内容を精査する必要があります。採用面接の質問と求人情報に乖離があると、「人柄重視の求人内容だったのに、面接でスキルや経験のことばかりを聞かれた」という違和感や不満につながります。
もし、採用要件にスキルや資格が含まれるのであれば、「経験者優遇」という文言を求人情報に明記しておくと安心です。人柄重視の姿勢が崩れないように注意した上で、採用計画を立てましょう。
企業イメージを下げる恐れがある
「人柄重視」や「人柄採用」と求人情報に載せると、企業イメージが下がる可能性がある点も、把握しておきたい注意点の一つです。これは、人柄での採用でなければ人が集まらない、あるいは定着しないなど、ネガティブな印象を与えてしまうためです。
さらに、スキルや経験を持つ人材からの応募を、遠ざけてしまうリスクもあります。特に能力の高い人材は、「人柄よりも、自分のスキルや経験を活かしたい」と考える傾向があるためです。
人柄重視の採用は、自社が求める人材を採用できる可能性を高められるメリットがある一方、イメージ低下につながるリスクがある点は押さえておくべきポイントです。
面接で演技をする可能性がある
採用面接で人柄を見極められるよう思考を重ねた質問を投げかけても、転職希望者が面接で自分を良く見せようと演技する可能性は否定できません。転職希望者が、うそをついたり演技をしたりしていた場合に、真の人柄を見抜けなければ、採用しても入社後のミスマッチを避けることは困難です。
例えば「当社の理念に共感できますか」という質問に対して、転職希望者が「いいえ」と答えることは考えにくいでしょう。面接では、人柄を引き出せるように質問の仕方を工夫するだけでなく、適性検査を取り入れるなど、多角的に評価できる環境の整備が大切です。
(参考:『【弁護士監修】裁判でも使われる、採用面接時に応募者の嘘を見抜く方法』)
人柄重視の採用では面接内容を工夫して、転職希望者の人となりを本質的に見極めることが大切
本記事では、人柄重視の採用手法について解説しました。
人柄を重視して人材を採用すると、熱量や意欲の高い人材が長期間にわたって定着しやすくなり、組織力強化につながります。一方で、その人柄を見極めることは簡単ではなく、多面的な視点で採用計画を立てる必要があります。
(制作協力/株式会社eclore、編集/d’s JOURNAL編集部)
面接で採用候補者の「人柄を引き出す」質問例
資料をダウンロード