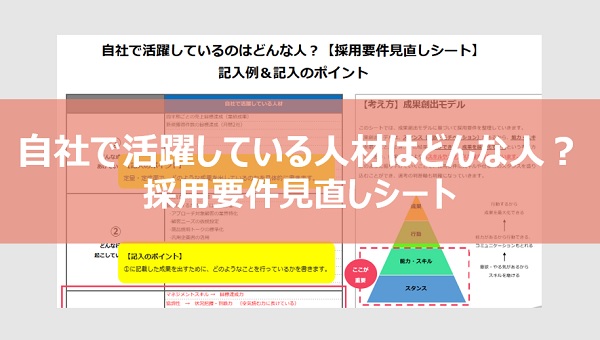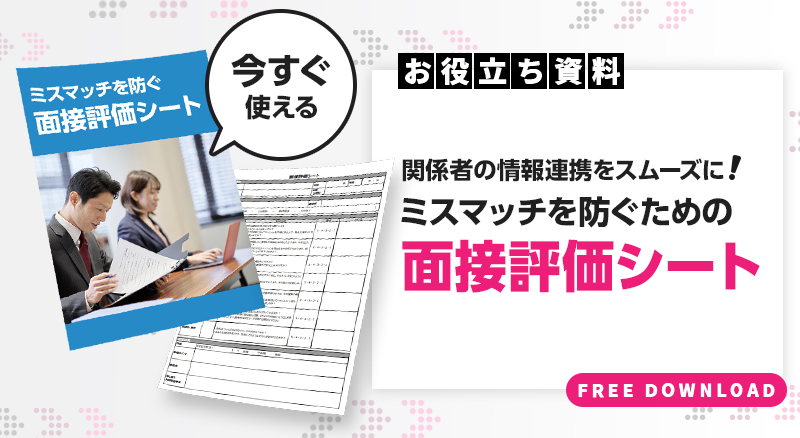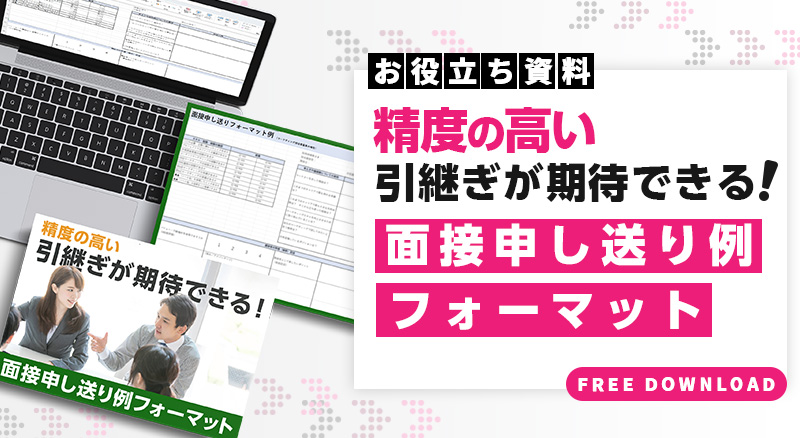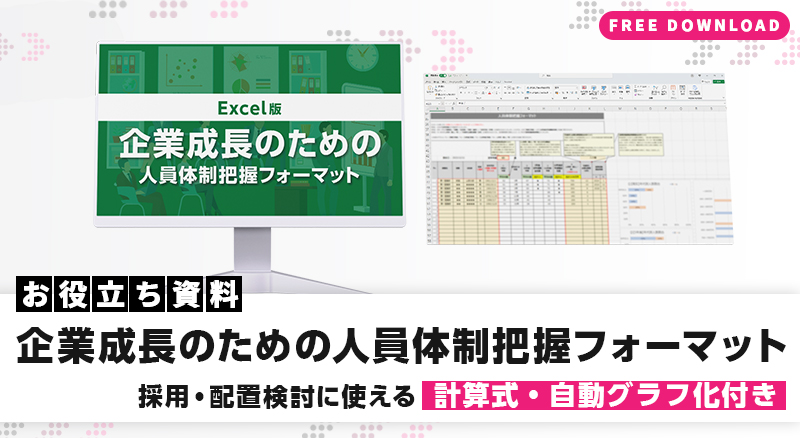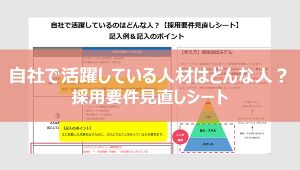採用強化とは?採用力を強化する方法や注意点、事例を解説


d’s JOURNAL編集部
人手不足が叫ばれる今の日本では、採用活動の成否が企業の将来を左右するといっても過言ではありません。そこで重要となることが、「採用強化」に対する取り組みです。
本記事では、採用強化の概要や重要性とともに、具体的な実践方法も解説します。採用活動が難航しており、根本的な対策が必要であるとお考えであれば、ぜひご覧ください。
自社で活躍している方を分析し、採用力を強化するためのシートを下記から無料ダウンロードできますので、ぜひご活用ください。
採用強化とは?
採用強化とは、企業の発展に不可欠な人材を採用するための戦略のことです。
企業を発展させていく上では、売上の拡大や新規事業への挑戦などが欠かせません。そして、上記を実現するために必要となることが、自社の要望に合致した経験やスキルを持つ人材の採用です。そのような人材を採用するために、企業の採用戦略や判断力、実行力を強化していく試みが採用強化です。
一点、採用強化は「採用する人数を増やす」「採用エリアを広める」などの試みだけを指すものではないことに注意しましょう。採用人数の増加や規模の拡大などは手段の一種であり、主たる目的ではありません。「自社が本当に求める人材を採用できるかどうか」という点が最も重要であり、そのための多角的な取り組みが採用強化の軸となります。
採用強化の重要性
採用強化の重要性が高まっている背景にあるのは、現代の日本が抱える「人手不足」の問題です。
少子化による労働人口の減少の影響から、日本ではここ数年採用の売り手市場が続いています。そのため採用力の乏しい企業では、自社に合った人材どころか、そもそも十分な数の人材を採用できない可能性すらあります。また働き方の多様化が進む昨今では、柔軟に働ける労働環境を提供する企業が数多く存在するため、転職希望者に興味を持ってもらうことも容易ではありません。
このような状況では、従来的な方法で求める人材を採用することは困難を極めるでしょう。だからこそ、採用力の強化によって採用活動の確度を上げる必要があるのです。
企業の採用力を強化する方法
「採用強化の重要性は理解したが、どのように実践すればよいのか…」とお悩みの人事・採用担当者のために、ここからは採用強化の具体的な実践方法をお伝えします。
採用基準や求める人材像の見直し
採用強化を実施する上では、まず採用基準および求める人材像の見直しが必要です。
採用基準があまりにも高い場合、自社によほどの優位性がない限りは競合他社へと転職希望者が流れてしまい、十分な数の人材を採用できません。しかし、安易に採用基準を引き下げると、求める人材像に合致しない転職希望者も増えてしまいます。妥協できる要件とそうでない要件を取捨選択し、最適な採用基準を設定することが大切です。
また、上記に並行して求める人材像の見直しも行いましょう。「自社が必要としているのは、どのような人材か?」を改めて明確化することで、採用活動の方針が定まります。その上、自社内での認識も統一できるため、全社での採用活動がより効率よく進められます。
(参考:『採用基準とは?具体的な設定手順や自社にマッチした人材の見極め方|テンプレ付』、『採用ペルソナとは?設定ノウハウや手順・具体例をまとめて紹介【テンプレート付】』)
採用手法の見直し
採用基準や求める人材像とともに、採用手法についても再検討する必要があります。求める人材の属性とマッチする採用手法でなければ、効果的な採用活動の実現にはつながらないためです。
例えば、採用人数の多さを重視するのであれば、不特定多数が利用する求人サイトを用いた採用活動をおすすめします。反対に、特定の経験・スキルを持つ人材を採用したい場合には、人材紹介サービスの活用が有用です。このほか、転職希望者のスキルや業種・業界によっても最適な採用手法は異なります。それぞれの利点を理解した上で利用する手法を選択しましょう。
(参考:『【2025年版】採用手法16選を徹底比較|メリット・デメリット・最新の注目トレンド』)
採用ブランディングを行う
採用強化を実現する方法としては、採用ブランディングの実践も挙げられます。
採用ブランディングとは、経営理念や社風、企業文化などを積極的に発信し、自社の魅力やブランド力を高める活動のことです。転職希望者の自社に対するイメージアップにつながるだけではなく、競合他社との差別化も図れます。
採用ブランディングを実践する際は、自社の業界での立ち位置や強みなどを最初に分析しましょう。魅力を正確に伝えることができれば、長期的な活躍が見込める人材の採用につながる可能性が高まります。
(参考:『採用ブランディングとは?目的や方法、メリット、進める際のポイントなどを紹介』)
採用CXを行う
採用力を強化するためには、まず転職希望者に良い印象を持ってもらわなければなりません。そこで必要となる施策が、採用CXです。
採用CXとは、採用活動を通じて転職希望者に「この企業に入りたい」と感じてもらえるような体験を提供する、という試みのことを指します。具体的な取り組み方は以下の通りです。
採用CXの実践方法の一例
●応募があった場合に迅速に返信する
●面接の際に誠実な対応を心掛ける
●入社の承諾を得られたあともフォローする
採用CXによって自社の評判が高まれば採用力も強化される上に、転職希望者が入社したあとのモチベーション維持にもつながります。
(参考:『採用CX(候補者体験)とは?注目される理由や実施する4つのメリット』)
選考スピードを早める
転職の際に複数社に応募することが多い昨今では、選考に時間がかかると、それだけで選考を辞退される可能性もあります。実際「面接の日程は決まったがその前に辞退されてしまった…」というケースは少なくありません。よって、採用力を強化するためには選考スピードも早めなくてはならないのです。
書類選考を3日以内で終わらせる、または転職希望者からの連絡には早めに返信するなどが、具体的な対策として挙げられます。面接の日程調整に時間がかかっているのであれば、関係者の日程を早い段階から押さえておくことも一案です。
(参考:『今、選考スピードアップは必須。どう現場を巻き込む?他社事例やデータを活用して社内協力を得る方法』、『中途採用“早期化”のススメ 採用活動を早めて行うべき4つのワケとは?』)
労働条件の見直し
労働条件を改善することも採用強化の一環に含まれます。近年は、「労働環境が良く福利厚生が充実している企業に転職しよう」という傾向が強く表れているためです。しかし、給与額や休日数の突然の変更は、対応が難しいこともあるでしょう。そのような場合には、リモートワークやフレックスタイム制の導入といった、制度面での改善を図りましょう。
労働条件が改善されれば、転職希望者へのアピールにもなるほか、在籍中の社員の定着率、さらには生産性の向上が実現するかもしれません。そうなれば会社の業績も好転し、結果としてより大々的に自社の魅力を伝えられるようになります。
(参考:『働き方改革の専門家が提言。採用・定着に悩む中小企業こそ労働環境改善で企業成長へ』、『応募数は年1件程度。高知県の建設企業が4カ月半で応募22名、採用10名、女性比率51%を実現した変革とは』)
キャリアパスの明確化
「この会社に入ればこんな風にステップアップできるだろう」というイメージを転職希望者に持ってもらうことも、採用強化には欠かせません。よって、自社内でのキャリアパスを明確化することも、非常に重要な取り組みとなります。
また、キャリアパスを伝える際は、採用CX、特に入社承諾後のフォローを欠かさずに行いましょう。キャリアパスに関する転職希望者の懸念点を解消できれば、入社の辞退や早期退職などを予防できる可能性があります。
(参考:『キャリア開発とは?メリットや具体的な手法・企業の実施例を紹介』)
自社で活躍している方を分析し、採用力を強化するためのシートを下記から無料ダウンロードできますので、ぜひご活用ください。
採用課題の見つけ方
採用強化の取り組みをより実りあるものにするためには、まず自社の採用課題を見つけなくてはなりません。そこでここからは、採用活動のフェーズに区切って、発生し得る採用課題を解説いたします。
母集団形成フェーズ
母集団形成フェーズで起こり得ることが、「転職希望者が集まらない」という課題です。転職希望者からの応募がなくては、活躍が見込める人材も採用できないため、早急に対処する必要があります。
応募数が少ないときに考えられる主な原因が「自社の訴求が不十分」「求める人材像と転職市場との乖離」の2点です。前者は、転職希望者が企業に何を求めているのかを分析し、それに合致する自社の強みをアピールすることで、解決できる可能性があります。後者に関しては、転職市場の動向と自社の求める要件を突き合わせた上で、最適なラインを再設定することで対応可能です。
これらを解決してもまだ転職希望者が集まらないのであれば、アプローチ方法から見直す必要があるかもしれません。複数の採用手法を比較する、また別のサービスの利用も検討するなどして、最適なアプローチ方法を模索しましょう。
面接前フェーズ
転職希望者からの応募が集まったあとの面接前フェーズでは、面接の辞退という課題に直面することが考えられます。
面接を辞退されてしまう大きな要因の一つが、選考スケジュールの長期化です。志望度や労働条件に大きな差がなければ、転職希望者としては、先に選考が進んだ企業に入社を決めたくなるものです。このような理由での面接辞退を減らすためにも、選考プロセスを一度見直して、スピーディーに転職希望者との接点が持てるように努めましょう。
また、自社への興味・関心が損なわれないように、面接前から定期的に情報を訴求することも重要です。転職希望者は、企業のホームページや採用サイトの情報もしっかりとチェックしています。そのため、掲載する内容には気を配りつつ、可能な限り高頻度で更新しておきたいところです。
面接後フェーズ
面接後フェーズの課題としてまず挙げられるものが、選考不合格の多発による採用の停滞です。特に、最終面接まで通過していた転職希望者の不合格が続いている場合には、関係者間で採用基準を再度すり合わせる必要があるでしょう。人事・採用担当者と現場の社員の間で求める人材像に乖離があっては、採用活動を円滑に進められません。
上記のほか、選考は通過したものの、入社の承諾を得られなかった、ということも起こり得ます。このケースに関しては、可能であれば辞退した理由を転職希望者に直接確認したいところです。自社のどこに不足があったのかを把握し、その内容に合った対策を講じれば、それ以降の転職希望者が入社を辞退する可能性を減らせます。
年収などが理由の場合には対応が難しいかもしれませんが、ほかの方法で自社の魅力をアピールすることは可能です。面接後のフォローを手厚くするなどして、自社の志望順位が少しでも上がるように努めましょう。
(参考:『採用活動がうまくいかないのはなぜ?母集団形成・面接前・面接後の各フェーズにある「採用課題の見つけ方」と「対策」』)
採用強化に成功している企業の特徴
採用強化に関してのノウハウがないのであれば、取り組みが成功している企業を参考にすることがおすすめです。該当する企業の具体的な特徴としては、以下の6つが挙げられます。
採用の目的や目標が明確に定められている
採用活動の目的や目標が確実に定まっている企業は、採用強化に成功している傾向があります。目的・目標が明確であれば、自社に必要な人材の条件も自然と決まり、採用強化の活動方針にも軸ができるためです。
なお、採用の目的を決める際は、可能な限り具体的な数値を設定しましょう。採用活動のゴールが漠然としていては、打ち出すべき施策を検討することもままなりません。具体的な目的を定めるためにも、まずは自社の現状を一度整理して、検討材料を集めることをおすすめします。
求める人材が明確である
繰り返しにはなりますが、求める人材像を明確にすることも採用強化には欠かせません。実際、採用力を順調に強化できている企業の多くは、自社が求める人材の要件を詳細に設定しています。
求める人材像が明らかとなれば適した採用手法が決まり、採用活動を滞りなく進められます。ミスマッチも減らせるため、入社辞退や早期退職の発生を防ぐ上でも効果的です。また採用力のある企業は、人材像を検討する際に、現場の意見も積極的に取り入れている傾向にあります。現場の目線が加わることで、即戦力を採用できる可能性を高められるためです。
人事・採用担当者と現場の認識が統一されている
人事・採用担当者と現場との間で、採用活動の方針や採用基準の認識が統一されていることも、非常に重要です。社内の認識が統一されていなければ、最終選考で不合格となるケースが増えて、活躍が見込める人材を採用できる機会が減ってしまいます。
認識を統一する上で必要となるものが、申し送り事項を共有する際のフォーマットです。フォーマットによって共有できる内容が定められていれば、担当者ごとの観点の違いによるばらつきが減り、以降のフェーズでも同じ目線で転職希望者を評価できます。とは言え、担当者個人の解釈などを、全て定量的な項目に落とし込むことは容易ではありません。そのため、別途自由記入欄を設けておくこともおすすめします。
また、このフォーマットを利用する際は、担当者側も「事実と解釈」を混ぜて記載しないように注意しましょう。転職希望者のそのときの発言や態度といった事実と、それに対する担当者の解釈をそれぞれ分けて伝えることが大切です。
(参考:『面接官同士をつなぐ、精度の高い「面接申し送り」ノウハウとは -申し送り例フォーマット付-』、『パーソルキャリアも苦戦!?「本部人事×現場」連携。採用成功への取り組み事例』)
自社の魅力を発信できている
採用力の高い企業の共通点としては、さまざまな方法で自社の魅力をしっかりと発信していることも挙げられます。採用強化を実現するためには、転職希望者に「この企業で働いてみたい」と思ってもらわなくてはなりません。よって、発信力が必要になるのは必然だといえるでしょう。
自社の魅力を効果的に伝えられる手段として考えられる手法が、SNSや自社採用サイトなどの活用です。親しみやすいかたちで訴求するならSNSを、自社に関する定量データをしっかりとアピールしたいなら自社採用サイトを、と使い分けられると理想的です。
(参考:『求人票で「アットホームな社風」はNG?求職者が知りたい社風を伝えるコツとは』)
最適な採用手法を用いている
先ほど少し触れましたが、最適な採用手法を選んでいることも、採用強化に成功している企業の共通点です。
採用手法にはさまざまな種類があり、それぞれ適した使用場面が異なります。例えば、特定の経験・スキルを持つ人材を採用したいのであれば、人材紹介サービスやダイレクト・ソーシングが有効です。特に、ITエンジニアなどの専門職や管理職は引く手あまたであるため、これらのサービスを利用して効果的に人材を採用したいところです。
最適な採用手法は転職市場の動向とともに移り変わるものなので、最新の情報を常にキャッチアップして、都度見直しを図りましょう。
(参考:『【今の採用手法や予算は最適!?】よくある5つの課題をデータを基に解説(無料調査データ付)』)
入社後の定着率が高く活躍できる環境が整備されている
採用力が高い企業では、入社後すぐに転職希望者が辞めるケースが少ない傾向にあります。これは、採用活動の軸がぶれておらず、採用した人材と自社の風土でミスマッチが生じていないためだと考えられます。
「定着率が向上しない…」とお悩みであれば、一度求める人材像の見直しを行いましょう。その上でまだ改善が見られないなら、評価システムの刷新や、福利厚生の再構築などに取り組む必要性も生じます。また、入社した人材のフォローを教育担当者や上司にだけ任せるのではなく、会社全体でサポートすることも大切です。
(参考:『定着率とは?計算方法や低い企業の特徴・向上させるための方法』、『“あの人がいるから辞めない”関係性をつくる!横のつながり「ピアコーチング」で実現する離職防止』)
採用強化に失敗している企業の特徴
採用強化がうまくいっていない企業の特徴も把握しておけば、自社で取り組む際の反面教師として活用できるでしょう。具体的には以下の4点が挙げられます。
採用基準が高すぎる
採用基準があまりにも高い企業は、採用強化に失敗してしまう可能性が高いといえます。応募数、あるいは選考に通過する転職希望者の数が少なくなり、活躍が期待できる人材を採用する機会が減ってしまうためです。
このような事態を避けるためにも、採用基準は転職市場の動向も踏まえながら、適切なラインで設定しましょう。また、一律で基準を設けるのではなく、理想的なラインと最低限クリアすべきラインの2つを用意する、というのも一つの手です。
人事・採用担当者と現場が連携できていない
社内で連携できていないことも、採用力の乏しい企業の特徴の一つです。このような企業では、現場の社員が本当に求める人材を採用できず、最終選考での不合格や入社後の早期退職が頻発してしまいます。
自社にとっての理想的な人材像を把握するためには、現場の意見を取り入れることが必要不可欠です。採用活動の前に担当者同士ですり合わせをしっかりと行い、求める人材像の認識を社内で統一することが、採用の強化につながります。また、採用活動中もこまめに情報を共有し合えば、PDCAが回り、自社に合った人材を採用できる可能性が高まります。
採用後の定着率が低い
先ほど少し触れましたが、採用強化に失敗している企業では人材の定着が見込めません。
早期退職にもさまざまな理由があるため、全てに対応することは不可能です。しかし、「想像していた会社の雰囲気と違った」「業務内容が事前に知らされていた内容と異なる」などのミスマッチが理由なのであれば、対策することで改善できる余地があります。ここまでに述べた、採用基準の見直しや部門間での連携強化によって自社の採用活動の方針を定め、ミスマッチが生じる可能性を減らしましょう。また、入社が決まったあとのフォローによって、転職希望者の不安や懸念を払拭することも非常に重要です。
採用活動のリソースが不足している
採用活動のリソースが確保できていない企業では、採用力を強化することは難しいでしょう。特に中小企業では、人事・採用担当者がほかの業務を兼務している場合が多いため、この傾向が顕著に表れます。
この問題を解決するためには、採用活動の中で少しでも業務を効率化していかなくてはなりません。例えば、求人票やメールのテンプレートをつくって使い回せるようにすれば、連絡業務の負担を軽減できます。また、面接の日程調整に時間がかかるのであれば、関係者の日程をあらかじめ確保しておくことがおすすめです。
(参考:『採用だけに時間をかけられない!これさえあれば採用業務の時間短縮につながるノウハウ・テンプレートまとめ』)
採用強化を実践する場合の注意点
採用強化の実践では、求める人材像の見直し、そして社内での認識の統一が重要である、ということはここまでに説明してきた通りです。しかし、何をもって「自社に合っている」とするのかについては、入念に検討しなくてはなりません。
例えば、営業職の経験者を採用したい企業に、他社で何年も営業に携わってきた転職希望者からの応募があったとします。「経験の豊富さ」だけを考慮すれば、まさしく求めていた人材だと思えるかもしれません。しかし実際に採用してみると、自社の風土や雰囲気になじめず、期待していたような活躍が見られなかった、ということが起こり得るのです。
このような事態を避けるためにも、「経験・スキルの有無」と「人柄・雰囲気の相性」は、それぞれを別軸で評価する必要があります。どちらかの要素に偏っていないかどうかをチェックし、総合的な視点から求める人材像を決めることが、採用強化の成功につながります。
採用後に人材を定着させるための方法
自社の要望に合った人材を採用できたとしても、その人材が定着しなければ採用強化が成功したとはいえません。採用した人材が定着するだけでなく、長期にわたって活躍してもらうことが、採用強化の最終的な目標です。
上記を踏まえて、ここでは人材の定着率を上げる4つの方法を解説します。
採用計画を見直す
定着率の向上を図る上では、やはり採用のミスマッチが発生しないように努めることが重要です。この点を考えると、採用計画の見直しは優先して実施すべき施策だといえます。
採用計画を練り直す際は、まず人材に求める経験やスキル、特性、人柄などを定義します。その際は、現場の社員とともに認識のすり合わせを行って、求める人材像にずれが出ないように努めましょう。ただし、要望ばかりを重視して実現性が損なわれては元も子もありません。関係各所と調整しつつ、要望と実現性のバランスが取れた採用計画を立てたいところです。
「採用計画を見直したいが、そもそも現状の体制把握ができていない…」とお悩みなら、ぜひ以下のテンプレートをご活用ください。定年年齢や生年月日などを入力するだけで、定年までの年数や定年退職の該当者を自動で整理できるため、採用計画を見直す前の準備作業の大幅な短縮となります。
(参考:『人員計画とは?立てる目的とメリット、策定方法や注意点をまとめて解説』、『採用戦略を立てる5つのフロー|企業事例やフレームワークも解説』)
社内環境の見直し
社内の雰囲気や労働環境に問題がある状況で、定着率を上げるのは困難でしょう。よって、社員が働く環境についても見直していく必要があります。そこで万が一労働基準法に違反するような問題が見つかったのであれば、早急に対処しなくてはなりません。そのほかには、業務の偏りや制度の不備などの有無も確認しましょう。
なお、明らかとなった問題の内容次第では、ルールを制定するだけでは対応できないことも少なくありません。そのような場合には、システムや制度を抜本的に見直して、そもそも問題が発生しないように工夫する試みも求められます。
(参考:『定着率とは?計算方法や低い企業の特徴・向上させるための方法』)
コミュニケーションの促進
社内でのコミュニケーションが活発になることも、定着率の向上には欠かせません。
コミュニケーションを促進する具体的な方法としては、フリーアドレス制度の導入や、社員同士で語り合える専用スペースの設置などが挙げられます。また、感情をマネジメントするためのツールを導入すれば、お互いに本音を話しやすくなり、組織全体の心理的安全性も高められます。
(参照:『成功する組織の秘策は“感情”にあった。成果を出すリーダーが実践する「感情マネジメント」と「EQの鍛え方」』)
キャリアサポートを充実させる
キャリアサポートを充実させることでも、社員が安心して働けるようになり、定着率の向上が見込めます。
まずは社員一人ひとりのキャリアプランを把握するためにも、キャリア面談を実施しましょう。その上で、自身の将来について具体的なイメージがない社員に関しては、キャリアデザイン研修を実施して個別にサポートできると理想的です。
また、キャリアプランについて考えてもらう際は、企業としてのビジョンも理解してもらう必要があります。そのためには、先述したようにコミュニケーションを促進し、経営陣から社員へと考えがきちんと伝わる環境をつくりあげることが大切です。
採用強化の事例
最後に、採用強化に取り組んでいる企業の事例をご紹介します。自社で採用強化に取り組む際は、ぜひ以下の例を参考にしてください。
社内連携を重視した採用活動によりキャリア採用の数が倍増|BIPROGY株式会社
IT業界の大手であるBIPROGY株式会社では、既存のビジネスモデルからの脱却を目指して採用強化への取り組みを始めました。
即戦力となるIT人材の採用を目標に、人事・採用担当者と各事業部門が密に連携を取りながら、さまざまな手法を駆使した多角的な採用活動を実施。また、採用プロセスでは同社ならではの強みをアピールし、転職希望者の興味・関心を引くように努めたとのこと。その結果、キャリア採用の実績が倍増するという大きな成果を出すことに成功しました。
(参照:『苦戦しがちなIT業界でキャリア採用数を倍増。即戦力となるハイクラス層のエンジニアも継続採用』)
時代の変化に対応するために採用体制の根本的な見直しを実施|トヨタ自動車株式会社
日本を代表する自動車メーカーであるトヨタ自動車株式会社も、採用強化を積極的に行っている企業の一つです。
かつて同社は新卒中心の採用体制を敷いていましたが、時代の変化に対応するため、キャリア・第二新卒も重視する採用体制へシフトすることに決定します。選考方法や面接のシステムなどを根底から見直し、多種多様な人材を採用するための環境づくりを実施しました。また、人材の定着率を向上させるために、入社後の研修や配属後のフォローなども実施し、社員が安心して働けるように手厚くサポートを行っています。
(参照:『なぜトヨタは新卒採用一辺倒からキャリア・第二新卒採用に注力したのか。大変革した人事・採用戦略とは』)
人材のサポートに注力するための専門組織を設置|株式会社サイバーエージェント
株式会社サイバーエージェントは、多様化していく転職市場の変化に対応するため、採用強化に取り組み始めます。具体的には、「採用育成本部」という専門組織をつくり、入社した人材を一気通貫でサポートできる体制を整備しました。
また、携わった事業が失敗してしまった社員に対しても、同社はしっかりとフォローを行っています。実際、事業の失敗を理由に退職する社員はほとんどいないそうです。
(参照:『「社員の才能を開花させたい」サイバーエージェント流、採用力強化のキーワード』)
求める人材像や採用方法の見直しによって採用強化を図ることが、売り手市場が続く日本では重要となる
今回は、採用強化の指す内容やその重要性、そして実践する際のポイントなどを解説しました。
採用強化とは、企業が本当に求める人材を採用するための、さまざまな戦略を総括したものです。採用の売り手市場が続く今の日本では、この採用強化に取り組むことが企業の発展には欠かせないといえます。また実践に際しては、求める人材像の社内での統一や、採用基準の見直し、入社後の定着率の改善などが必要となります。
(制作協力/株式会社eclore、編集/d’s JOURNAL編集部)
自社で活躍している人材はどんな人?採用要件見直しシート
資料をダウンロード